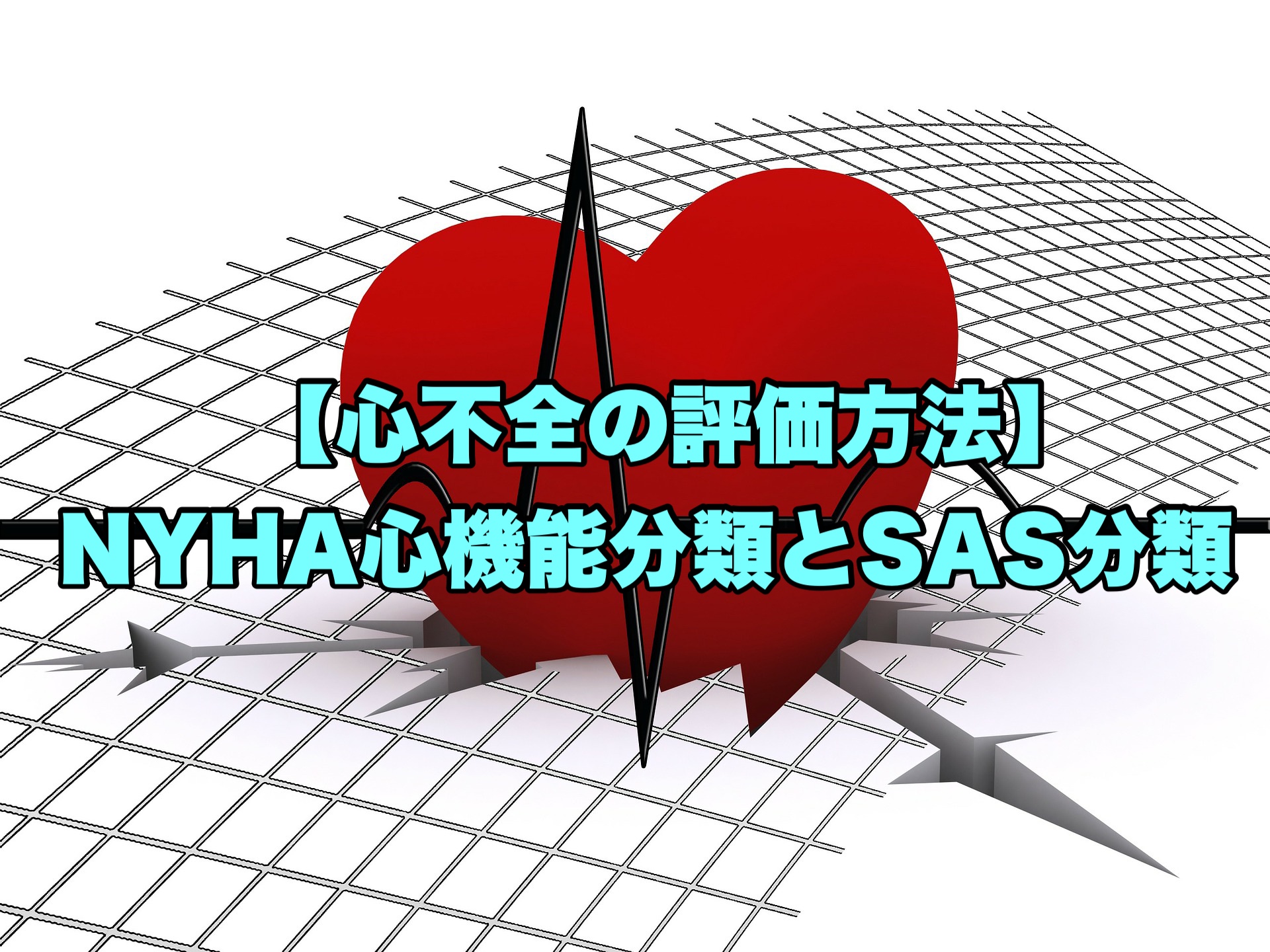NYHA と SAS の違い(結論):心不全評価の使い分け
結論:カンファや経過の要約で “重症度を共有” したいなら NYHA、生活動作のレベルを “できる/できない” で具体化して運動処方に落としたいなら SAS が向きます。両者は競合ではなく、NYHA で全体像 → SAS で行動レベルに落とすと、評価と指導がつながります。
心不全リハ全体の「評価 → 運動処方 → モニタリング → 再評価」の流れは、心不全リハ実務ハブ(総論)で整理しています。まずは “違い” を 1 画面で理解し、必要なら単体プロトコル( NYHA / SAS )へ進む設計です。
NYHA と SAS の違い(早見表:10 秒まとめ)
結局どっち?:NYHA=症状ベースで重症度を共有/SAS=活動例と METs で “動ける範囲” を半定量化。
| 指標 | 主目的 | 判定軸 | 取得方法 | 想定場面 | 強み | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYHA | 症状に基づく重症度の共有 | 自覚症状 × 身体活動の制限( I〜IV ) | 問診中心(安静時症状/日常活動での症状) | 初回評価・経過観察・患者説明 | 世界的に最も普及/比較が容易 | 主観度が高く評価者間でぶれやすい |
| SAS | 活動可否の半定量化 | 活動例と METs(不可になった最小 MET ) | 活動リストの可否チェック | 運動処方前の足切り/外来問診の定量化 | 具体的な生活動作に落としやすい | 活動例のローカライズが必要 |
背景:心不全パンデミックと評価の重要性
日本では超高齢化や基礎疾患の増加を背景に、慢性 心不全 患者が増え続け、いわゆる「心不全パンデミック」が課題となっています。限られた診療時間で再現性高く機能を把握するため、本記事では NYHA 心機能分類とSAS( Specific Activity Scale )の役割と使い分けを “要点だけ” で整理し、詳細は個別プロトコルに委ねます。
心不全 リハビリ の方針決定では、「心不全 × NYHA 分類 × SAS 分類」をどの場面でどう組み合わせるかを意識しておくと、ゴール設定と運動処方がスムーズになります。
心不全ステージ分類との違い
「心不全 ステージ分類」は、ACC / AHA の A〜D のように病態の進行段階(リスク〜難治性)を示す枠組みで、病歴や構造心疾患の有無に着目します。一方 NYHA 分類は、症状と身体活動制限をもとにした機能的重症度の分類であり、同じ慢性 心不全 でも日によって変動し得る指標です。
臨床では「ステージ分類で長期リスクを把握しつつ、NYHA 分類 × SAS 分類 で “いまどのくらい動けるか” を評価する」という役割分担を意識すると、運動処方と患者説明に落とし込みやすくなります。
NYHA 心機能分類の概要(覚え方つきで 1 分)
NYHA は I〜IV 度で機能的重症度を示します。ざっくりした覚え方は、I:制限なし/II:通常の活動で息切れ/III:軽い活動でも息切れ/IV:安静時にも症状と “息切れが出る活動レベル” で並べることです。慢性 心不全 の外来フォローや入退院時の比較に向いており、心不全 リハビリ の共通言語としても重要です。
評価時は、安静時症状(夜間発作性呼吸困難、起坐呼吸、下腿浮腫など)を先に確認し、そのうえで「その人にとっての通常の活動」を具体例(通勤・買い物・洗濯・階段昇降など)で固定して聴取すると、判定が安定しやすくなります。
臨床記録では「NYHA II(通常の歩行で労作時呼吸困難)」のように、クラス+具体的な活動レベルや症状をセットで残すと、解釈のずれが減ります。
SAS 分類の概要(心不全 × METs 評価)
SAS 分類は、階段昇降・速歩・洗濯物の運搬などの活動例と METs を手がかりに「できる/できない/つらい」を問診し、「できなくなった中で最も低い MET 値」を記録する方法です。NYHA の主観性を補い、活動量の足切りや運動処方の安全域設定に役立ちます。
心臓リハビリテーションの初期評価では、既往歴・検査所見・投薬状況を確認したうえで、SAS による METs レベルと NYHA を組み合わせ、「この患者さんは日常生活で何 METs まで安定してこなせているか」を把握しておくと、運動処方の上限設定と教育(ペース配分・自覚症状の見方)が具体的になります。
臨床ワークフロー(外来・心リハでの回し方)
- 主訴・既往・治療歴の整理(バイタル・安静時症状・体重増加・浮腫を必ず確認)
- NYHA で機能的重症度の目安を共有( I〜IV )
- 必要に応じて SAS で活動可否を半定量化(最低不可 MET を記録)
- 運動処方・教育では、METs と日常活動の具体例を紐づけて説明(例:3 METs=平地歩行、4 METs=やや速歩 など)
- 経過再評価は、同一条件・同一説明で NYHA × SAS を再測し、変化量を把握(主観的な印象だけに頼らない)
判定の落とし穴・中止基準(チェック表)
| テーマ | NG | OK(対策) |
|---|---|---|
| 安静時症状 | 「活動時だけ」を前提に聴取してしまう | 安静時の息切れ・夜間発作性呼吸困難・浮腫の有無から開始 |
| 活動例 | 海外の活動例をそのまま使用 | 施設・患者の生活様式に合わせて例示(買い物・洗濯・階段など) |
| 評価タイミング | 治療変更直後すぐに比較 | 薬剤調整後は安定期を待ち、同一条件で再測 |
| 安全管理 | 胸痛・めまい・動悸の訴えを軽視 | 増悪徴候があれば即時中止・医師共有(バイタル・ SpO2 ・体重) |
現場の詰まりどころ(どこで悩みやすいか)
実務では、NYHA と SAS の理屈は理解していても、「どの程度なら II / III にするか」「SAS の活動例をどう日本の生活に合わせるか」で悩みやすくなります。特に、同じ患者でも評価者によってクラスが分かれたり、「今日は体調がよい/悪い」の影響をどこまで許容するかが現場の詰まりどころです。
対策としては、①施設でよくある生活動作のリストをあらかじめ共有しておく、②「この症状があれば少なくとも III 以上」といったカットポイントをチームで決めておく、③評価日ごとの体重・バイタル・自覚症状をセットで記録する、の 3 点を徹底すると迷いが減ります。細かな疑問や判断の揺れは、下記「よくある質問」で代表的なパターンを押さえておくと整理しやすくなります。
関連する単体プロトコル(必要なときに深掘り)
評価票ダウンロード( A4 ・印刷対応)
PDF 化したい場合は、各ページを開いて印刷 → PDF で保存を選択してください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
NYHA II と III の違いは?
「通常の身体活動」で症状が出るのが II、「通常未満の軽い活動」でも出るのが III です。患者さんにとっての “通常の活動”(通勤・買い物・家事など)を具体的な例で固定し、その活動での息切れの有無を確認すると、境界が分かりやすくなります。
SAS の METs はどこまで厳密に見るべきですか?
日常診療では目安で十分です。施設標準の活動例をあらかじめ決めておき、「できなくなった中で最も低い MET 」の経時変化を追う運用にすると、再現性を保ちやすくなります。
外来 5 分で NYHA と SAS をどう回すのが現実的ですか?
ショート版テンプレ(安静時症状 → 日常活動レベル → 代表的な活動例の可否)の順で問診し、まず NYHA を決め、それを踏まえて 2〜3 個の代表動作で SAS の MET レベルを押さえると、慢性 心不全 フォローでも負担なく継続できます。
おわりに
心不全 評価のリズムは、安全確認(安静時症状・バイタル)→ NYHA・ SAS で機能を言語化 → 運動処方とセルフモニタリングへ具体化 → 同じ指標で再評価のサイクルをどれだけ安定して回せるかがポイントになります。指標そのものを覚えるだけでなく、「誰が見ても同じクラス・同じ METs にたどり着く運用」をチームで整えることが、急変予防と生活再構築の両立に直結します。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えるので、「いまの職場で心不全 リハビリ にどこまで関われているか」「次の職場では何を大事にしたいか」を整理するツールとして、ぜひ一度確認してみてください。面談準備チェック&職場評価シートはこちら。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下