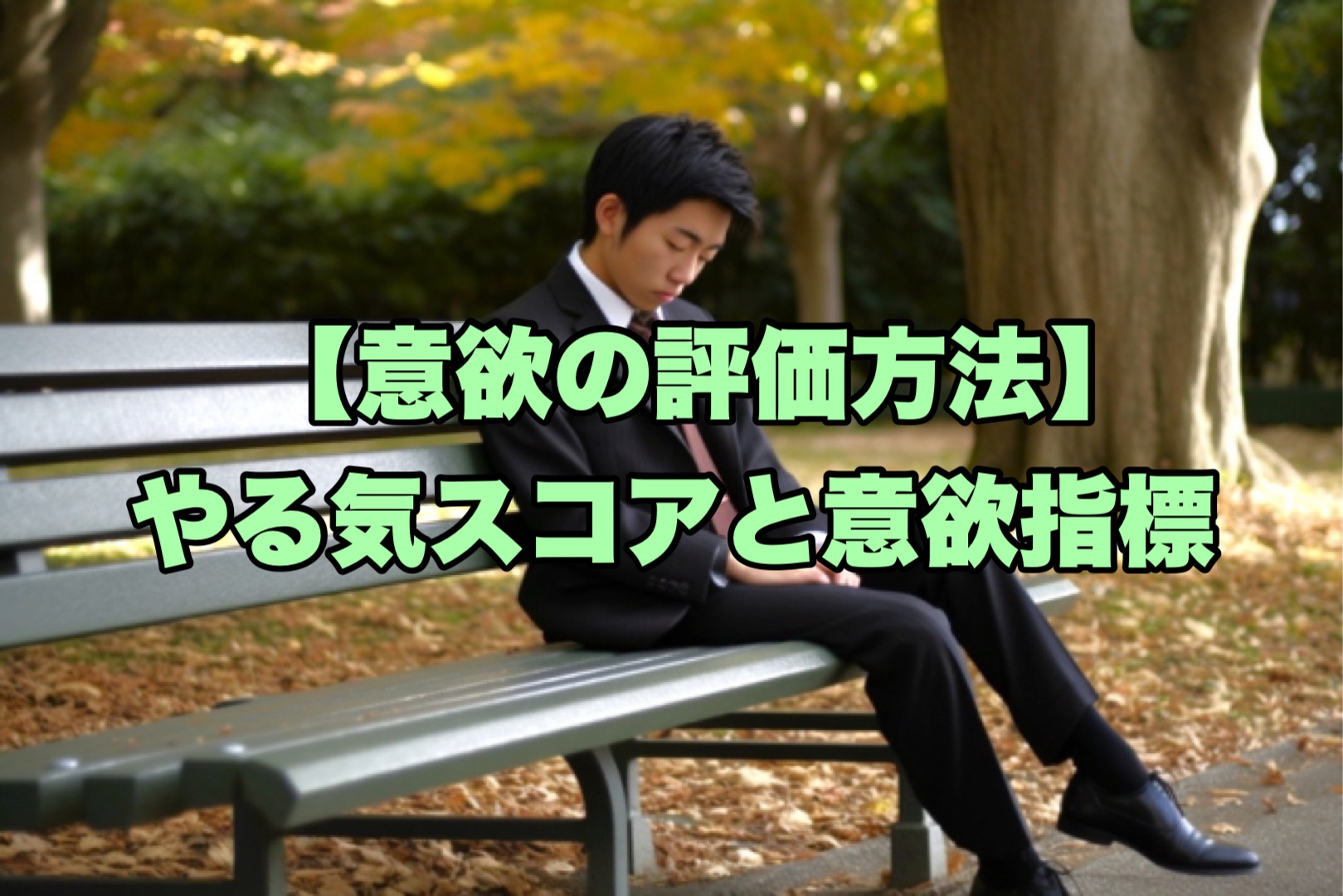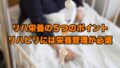意欲の評価は「やる気」だけでなく“参加度”まで分けると迷わない
意欲(やる気)の評価で詰まりやすいのは、「本人の主観(やる気)」「行動としての自発性(観察できる意欲)」「リハ参加の質(参加度)」が混ざってしまう点です。ここを分けて捉えると、評価スケールの選択とカルテ記載が一気に整理できます。
本記事では、代表的な 3 系統(①やる気スコア=アパシー、② Vitality Index=観察でみる意欲、③ PRPS=参加度)を、使いどころ・判定の軸・運用のコツでまとめます。設問本文の転載はせず、現場で再現できる判断基準と言い換えで解説します。
意欲を測る 3 つの軸(主観・観察・参加度)
「やる気」を 1 つの指標で表そうとすると、うつ・せん妄・疼痛・環境不適合などが混ざり、解釈が不安定になります。まずは、主観(本人のやる気)/観察(自発性)/参加度(リハ場面での関わり)のどれを見たいのかを先に決めるのが近道です。
観察主体で使いやすい代表が Vitality Index です。採点・カットオフ・運用の細部は、別記事の Vitality Index の評価方法とカットオフ にまとめています(本記事は「選び方・読み方」に集中します)。
| スケール | 主に見る軸 | 評価方法 | 強み | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| やる気スコア(Apathy Scale) | 主観(アパシー) | 自己記入が基本(状況により代理) | 「やる気低下」の自覚を数値化しやすい | うつ・せん妄・認知で回答が揺れやすい(点数だけで鑑別しない) |
| Vitality Index | 観察(自発性) | 行動観察( 5 項目を 0–2 点) | 認知症や重度障害でも使いやすい/短時間 | 環境・疼痛・介助量の影響が混ざりやすい(理由を併記) |
| PRPS | 参加度(リハ場面) | 療法士の臨床評価(参加の質を段階化) | 「参加の良し悪し」をチーム共有しやすい | 評定者間の基準合わせが必須(事前に例示で統一) |
※表は横スクロールできます(スマホ対応)。
使い分けの結論|最初に 3 つの質問を決める
結論から言うと、「何が問題か」を切り分けたい場面ほど、軸を決めてスケールを選ぶのが安全です。意欲低下に見えても、実際は疼痛・便秘・睡眠・薬剤・環境不適合・指示の出し方で「動けない/動きたくない」が起きているケースが多いからです。
迷ったら次の 3 問で決めます。①本人は「やる気が出ない」と感じているか(主観) ②日常行動として自発性が落ちているか(観察) ③リハ場面で参加の質が落ちているか(参加度)。それぞれに対応して、やる気スコア/Vitality Index/PRPS を当てると、記録も介入もブレにくくなります。
運用の 5 分フロー|測る前に“条件”をそろえる
意欲系スケールは、同じ人でも「時間帯・疼痛・眠気・せん妄・薬剤変更」で点数が動きます。再評価で意味のある比較をするには、評価条件の固定(いつ・どこで・誰が・どんな声かけで)を先に決めることが最重要です。
現場の運用は、①当日の急性イベント(発熱・せん妄・疼痛・不眠)を一言メモ ②スケール実施 ③点数だけでなく“そう判断した根拠”を 1 行で記録 ④介入(環境調整・目標設定・負荷調整) ⑤次回再評価日を決める、の順が回しやすいです。
解釈のコツ|点数より「下がった理由」を言語化する
意欲評価を“判定”で終えると、リハの次アクションが止まりがちです。スコアはあくまでシグナルなので、「なぜ今そう見えるのか」を身体・環境・心理社会で分解して、介入仮説に変換します。
例えば、Vitality Index が低い場合でも、便秘や疼痛コントロール、離床導線(椅子・靴・補装具)、声かけの順序(先に目的→次に行動)を整えるだけで改善することがあります。逆に、やる気スコアが高い(悪い)場合でも、うつ・せん妄・認知の影響が強いと「意欲低下」とは別の対応が必要になるため、医師・看護師・家族と情報を合わせて解釈します。
現場の詰まりどころ|「意欲」か「できなさ」かが混ざる
最も多い詰まりは、意欲の低下と身体能力の低下が混ざることです。たとえば起床や活動が少ないのは「やる気」ではなく、疼痛・呼吸苦・起立性低血圧・不安で避けているだけ、というケースが少なくありません。意欲評価は、原因探索の入口として使うのがコツです。
もう 1 つは、点数だけで介入の可否を決めてしまうことです。意欲が低いほど、短時間・高頻度・成功体験の設計が必要になります。スコアは「縮小の根拠」ではなく、「介入の設計図」に変換して活用すると、チームの足並みがそろいやすくなります。
よくある誤りと対策(OK / NG 早見)
| 場面 | NG(起きやすいミス) | OK(対策) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 評価条件 | 時間帯・担当者・声かけが毎回バラバラ | 条件を固定し、例外時は「参考値」と明記 | 実施日・時刻・場所・担当者 |
| 解釈 | 点数だけで「意欲低下」と結論づける | 疼痛・睡眠・便秘・せん妄・薬剤を同時チェック | 下がった理由の仮説を 1 行 |
| 介入 | 意欲が低い=訓練量を減らすだけ | 短時間・高頻度、成功体験、目標の具体化 | 次回までの小目標(行動) |
| 共有 | 職種で評価の言葉がズレる | 「何ができて/何が出ていないか」を共通語化 | チーム共有メモ(誰に伝えたか) |
※表は横スクロールできます(スマホ対応)。
カルテ記載テンプレ(コピペ用)
意欲系の記録は「点数+理由+次アクション」がセットだと、再評価とカンファレンスが回りやすくなります。下のテンプレは、どのスケールでも流用できる形にしています(数値は各施設の運用に合わせて置換してください)。
最初は“文章を短くする”より、“条件と理由が残る”ことを優先すると、後で振り返りやすくなります。
【意欲評価】スケール:____ 実施:__年__月__日 __:__(場所:__/担当:__) 点数:__点(前回:__点) 判定:__(※施設基準) 条件:疼痛__/眠気__/便秘__/せん妄__/薬剤変更__ 理由(観察・発言):________________________ 次アクション:____(環境調整/声かけ/目標設定/負荷調整 など) 再評価予定:__年__月__日
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1.意欲評価は、どのタイミングで入れるのが効果的ですか?
おすすめは「リハの伸びが鈍い/参加が安定しない」と感じた時点です。初期評価から入れてもよいですが、まずは疼痛・睡眠・せん妄など急性要因を確認し、条件をそろえたうえで実施すると、点数の変化が“介入の効果”として読み取りやすくなります。
Q2.意欲が低いとき、リハは中止すべきですか?
中止の判断は意欲スコア単独では行いません。意欲が低いほど、短時間・高頻度、成功体験、選択肢の提示(本人が選べる形)など、設計の工夫が必要になります。急性イベント(発熱・せん妄・強い疼痛)など、医学的リスクがある場合は主治医・看護師と連携して安全を優先します。
Q3.「うつ」と「アパシー(意欲低下)」は同じですか?
同じではありません。アパシーは自発性の低下が中心で、強い抑うつ気分を伴わないこともあります。一方で両者は重なりやすく、スケールだけで鑑別はできません。点数は重症度や経時変化の把握に使い、診断や治療方針は医師を中心にチームで検討します。
おわりに|安全の確保→条件統一→数値化→理由の言語化→再評価
意欲の評価は、点数を付けること自体が目的ではなく、「なぜ今動き出しにくいのか」をチームで共有し、介入へ落とし込むための道具です。安全の確保→条件統一→数値化→理由の言語化→再評価のリズムで回すと、スケールが“評価で終わる”状態を避けやすくなります。
一方で、評価やカンファレンスの工夫だけでは限界を感じる職場も少なくありません。面談準備チェックと職場評価シートを使いながら、学びやすい環境づくりも含めて整理したい方は こちら(面談準備チェック&職場評価シート) も活用してみてください。
参考文献(外部リンクは新規タブで開きます)
- Starkstein SE, Fedoroff JP, Price TR, et al. Apathy and depression following stroke. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1992;4(2):134-139. DOI:10.1176/jnp.4.2.134 / PubMed
- Lenze EJ, Munin MC, Quear T, et al. The Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale: reliability and validity of a clinician-rated measure of participation in acute rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(3):380-384. DOI:10.1016/j.apmr.2003.06.001 / PubMed
- Ito T, Takebayashi T, Hanada K, et al. Apathy after stroke is associated with poor participation in rehabilitation. Disabil Rehabil. 2021;43(7):955-961. DOI:10.1080/01616412.2020.1831301 / PubMed
- Fujita A, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the Apathy Scale in stroke patients. Medicine (Baltimore). 2024;103(2):e41042. DOI:10.1097/MD.0000000000041042 / PubMed
- Kawagoe Y, et al. Cut-off point of the Vitality Index for predicting walking independence on discharge in patients with proximal femoral fracture: a retrospective study. Psychiatry Clin Neurosci. 2020;74(8):429-436. DOI:10.1111/pcn.13009 / PubMed
- Toba K, Nakai R, Akishita M, et al. Vitality Index as a useful tool to assess elderly with dementia. Geriatr Gerontol Int. 2002;2(1):23-29. DOI:10.1046/j.1444-1586.2002.00016.x
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下