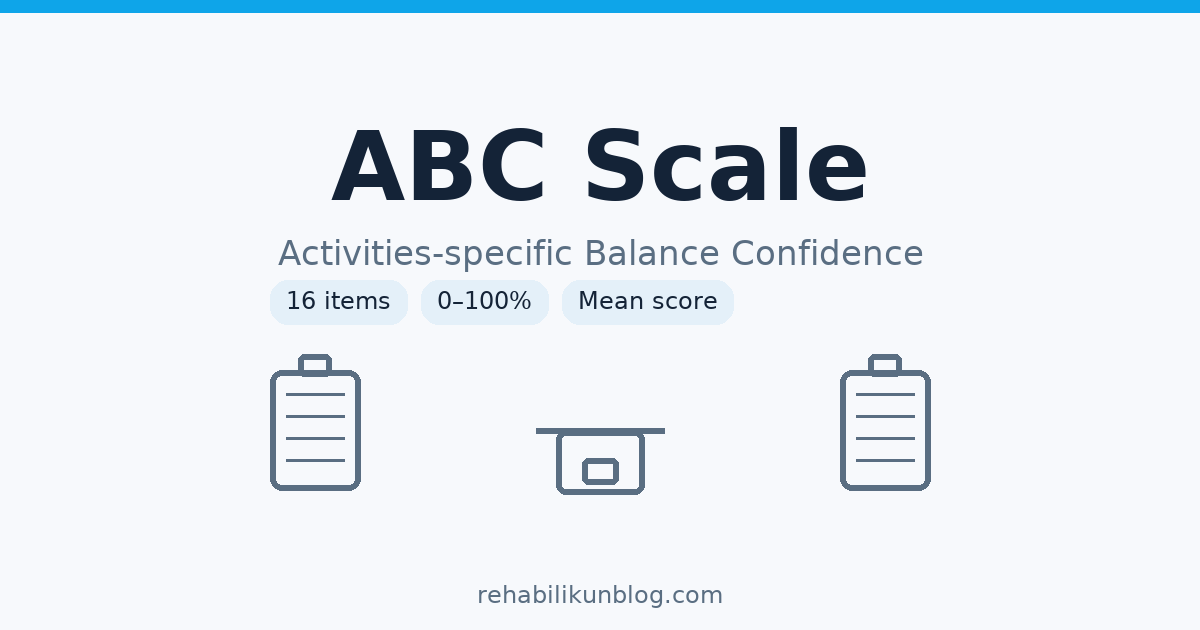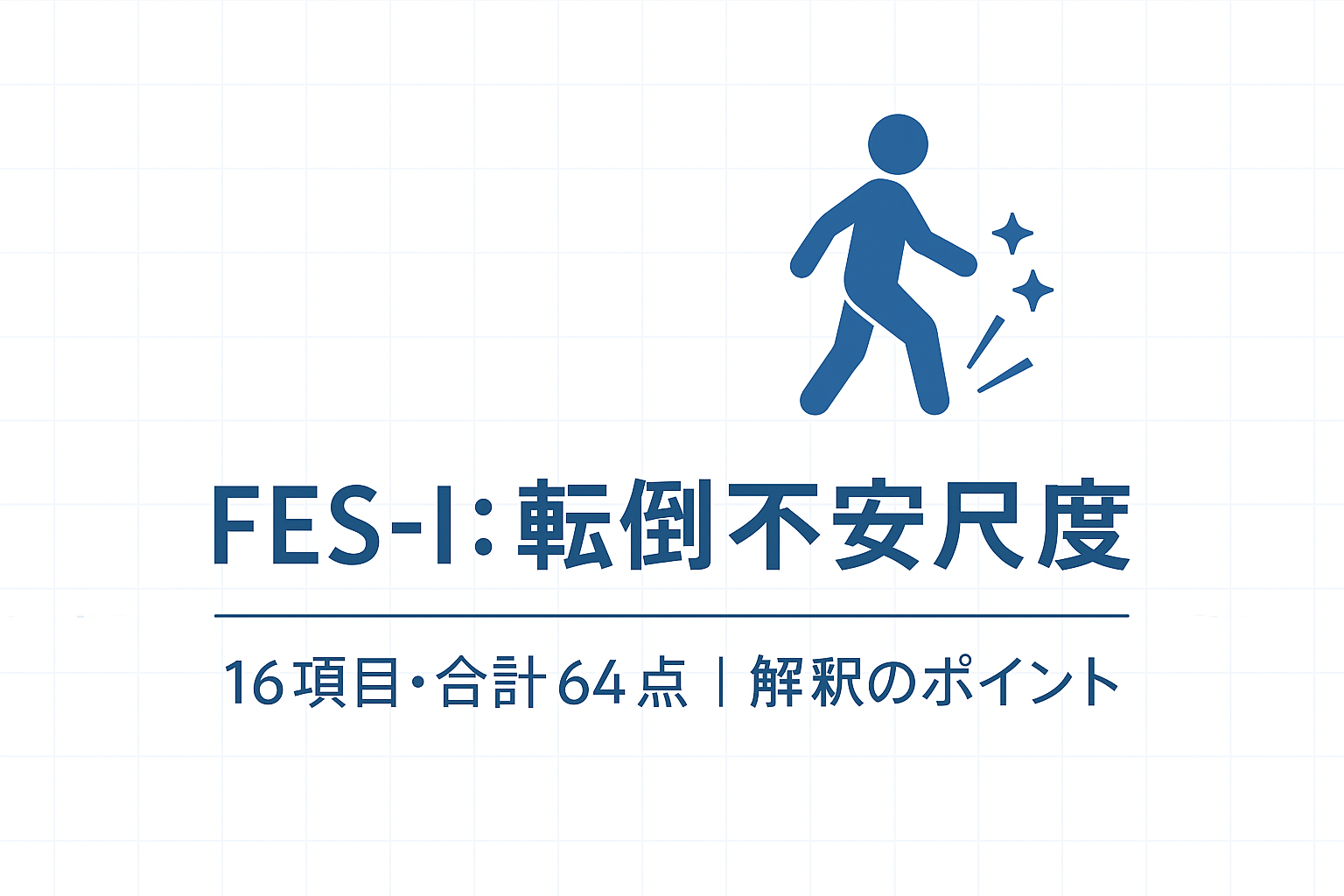ABCスケールとは?(バランスの「自信度」を数値化)
ABC スケール(Activities-specific Balance Confidence Scale/活動特異的バランス自信度スケール)は、日常 16 場面について「転倒せずにできる自信」を 0〜100 %で自己評価し、その平均値からバランスに対する自信度を数値化する患者報告アウトカムです。Falls Efficacy Scale-International(FES-I)が「不安の強さ」を問うのに対し、ABC は「できる自信」を扱うため、両者を併せてみることで“身体機能”と“認知・感情”のギャップを整理しやすくなります。
構成・採点(16 項目 × 0〜100 %)
ABC スケールは 16 項目の自己記入式質問票で、各項目の「転倒せずにその活動ができる自信」を 0〜100 %で答えてもらい、平均値で総合スコアを算出します。いわば「バランス自信度」の定量化であり、やり方自体はシンプルですが、説明と集計ルールを標準化しておくことが重要です。
- 各項目は0 %=まったく自信がない〜100 %=完全に自信があるの連続尺度で評価します(10 %刻みなど、施設内で目盛りを統一)。
- 最終スコアは全回答項目の平均(%)とし、小数第 1 位までで十分です(例:
78.1 %)。 - 回答不能(N/A)は母数から除外し、「78.1 %(15/16)」のように母数と併記して記録方法を標準化します。
| 平均スコア(%) | 解釈の目安 | 臨床メモ |
|---|---|---|
| < 67 % | 転倒リスク増の一つのカットオフ | 地域高齢者研究で示唆される範囲。既往歴・転倒歴・身体機能とあわせて要精査。 |
| 67〜80 % | 中等度の自信 | 状況や環境によって回避行動が残りやすいゾーン。曝露設計と環境調整で行動範囲を広げる。 |
| > 80 % | 概ね十分な自信 | ピンポイントな苦手場面(階段・人混みなど)を抽出し、実場面での練習に結びつける。 |
※カットオフはあくまで集団データからの目安です。疾患・既往・補助具・転倒歴・歩行速度などと組み合わせて総合的に判断してください。
実施手順(自記/面接のやり方)
ABC スケールのやり方自体は難しくありませんが、「何を聞いている検査なのか」を共有したうえで、説明と質問の仕方をそろえることがポイントです。ここでは基本的な実施手順を 3 ステップで整理します。
- 説明:「できるかどうか」ではなく「転倒せずにできる自信の程度」を評価する検査であることを最初に共有します。見本の 1 問を一緒に読んで、0・50・100 %のイメージを確認します。
- 回答方法:自記の場合は、視力や読み書きの問題がないかを確認します。面接の場合は問い直しや誘導を避け、患者さんの第一印象に近い数字を尊重します。
- スコアリング:16 項目の合計を回答数で割り、平均%を算出します。N/A がある場合は母数とセットで記録します(例:
78.1 %(15/16 項目回答))。
所見の読み方と次のアクション
ABC スコアは単独で「安全か危険か」を決める値ではなく、「自覚的な自信」と「客観的なバランス能力」の関係を見るためのものです。次のようなパターンを意識すると、目標設定や説明が組み立てやすくなります。
- ABC 低値 + 客観的バランス低下:身体機能訓練(筋力・バランス)、住宅環境調整、転倒予防教育を組み合わせて、まずは実際のリスク低減を優先します。
- ABC 低値だが身体機能は保たれる:「恐怖 > 能力」のパターンが疑われます。不安評価や行動活性化を意識し、段階的曝露や成功体験の積み上げで自己効力感を高めます。
- 特定場面のみ低値:階段・段差・人混み・バス乗降などの「場面依存の苦手」が見えたら、その状況を模したドリルや実地練習を計画します。
記録テンプレ(そのままコピペ)
電子カルテやサマリーに残すときのひな形です。施設のフォーマットに合わせて調整して使ってください。
【ABC】平均 __.__ %(母数 __ / 16) 方式:自記・面接(担当:____) 低値項目:____(例:外出先での歩行、階段下降、人混み) 併用評価:FES-I __ 点、Mini-BESTest __ / 28、FGA __ / 30、5xSTS __.__ 秒 対応:曝露の段階化(場面:____)、バランス訓練、家族・環境調整
よくあるミスと対策
ABC スケールは“自覚的な自信”を扱うため、実施の仕方によって結果がぶれやすい検査です。次のポイントをチーム内で共有しておくと、再現性が高まりやすくなります。
- 能力と自信の混同:「できますか?」と聞くと実能力の話になりがちです。「転倒せずにできる自信は何パーセントくらいですか?」と問い直すクセをつけましょう。
- 誘導的な聞き方:「このくらいなら 80 %くらいですかね?」など数値を提案しないよう注意します。迷ってもらう時間も評価の一部です。
- 手順・環境の不統一:初回と再評価で説明の言い回しや評価者、環境(歩行補助具の有無など)が大きく違うと変化の解釈が難しくなります。マニュアル化しておきましょう。
バランス評価全体の中での位置づけ
ABC スケールは「どれくらい自信があるか」を、Mini-BESTest や FGA、5xSTS などは「どれくらいできるか」をそれぞれ示します。日常生活での活動範囲や転倒回避行動を検討するときは、客観的バランス能力と自覚的自信のギャップを見ることで、目標設定や説明が具体的になります。
歩行・バランス評価全体の整理や、他の代表的アウトカムとの組み合わせ方は、評価ハブ(歩行・バランス評価のまとめ)もあわせて参照してください。
現場の詰まりどころ
実際の現場では、ABC スケールを「とりあえず全部配っているけれど、その後の介入にうまくつながらない」という声がよく聞かれます。スコアだけを眺めて終わると、「なんとなく低い/高い」で止まってしまい、行動変容やプログラム設計に結びつきにくいことが詰まりどころです。
ポイントは、①低値の“場面”を具体的な訓練課題に落とし込む、②客観評価とのギャップをチームで共有する、③経時変化を同じ条件で追う、の 3 点です。特に「自覚は低いが機能は保たれる」ケースでは、家族への説明や活動目標のすり合わせに ABC スコアが役立ちます。評価票をカルテにスキャンしておき、カンファレンスで実物を見ながら話し合う運用もおすすめです。
おわりに
ABC スケールは、「安全の確保 → 自覚的なバランス自信の評価 → 苦手場面の抽出 → 段階的な曝露と訓練 → 再評価」という一連の流れの中で力を発揮します。16 項目の平均%というシンプルな指標だからこそ、他のバランス評価や歩行テストとセットで捉えることで、患者さんにも説明しやすいアウトカムになります。
まずは数名のケースで、ABC と歩行・バランス指標を一緒に追ってみてください。自覚と能力のズレが見えてくると、「どのタイミングで何を伝えるか」「どの場面から練習するか」がクリアになり、チームで共有しやすい評価ツールとして定着していくはずです。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップすると閉じます。
ABC スケールは何を測る検査ですか?
ABC スケールは、日常 16 場面について「転倒せずにできる自信」を 0〜100 %で自己評価し、その平均値からバランスに対する自信度を数値化する検査です。能力そのものではなく“自信の程度”を扱う点がポイントです。
ABC スケールのやり方・実施時間はどれくらいですか?
自記式であれば、多くの方で 5〜10 分程度が目安です。見本の 1 問を一緒に確認し、「転倒せずにできる自信」を 0〜100 %で答えてもらいます。読み書きが難しい場合は面接法でも構いませんが、誘導的な聞き方は避け、第一印象に近い数字を尊重します。
カットオフはどのように解釈すれば良いですか?
地域高齢者研究などから、67 %未満は転倒リスク増の一つのカットオフとされています。ただし単独で“転倒する/しない”を決めるものではなく、歩行速度やバランス検査、転倒歴、環境要因などと組み合わせて総合的に判断することが推奨されます。
参考文献
- Powell LE, Myers AM. The Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1995;50A(1):M28–M34. doi:10.1093/gerona/50a.1.m28. PubMed
- Shirley Ryan AbilityLab. Activities-Specific Balance Confidence Scale(ABC). Rehabilitation Measures Database. https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/activities-specific-balance-confidence-scale
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下