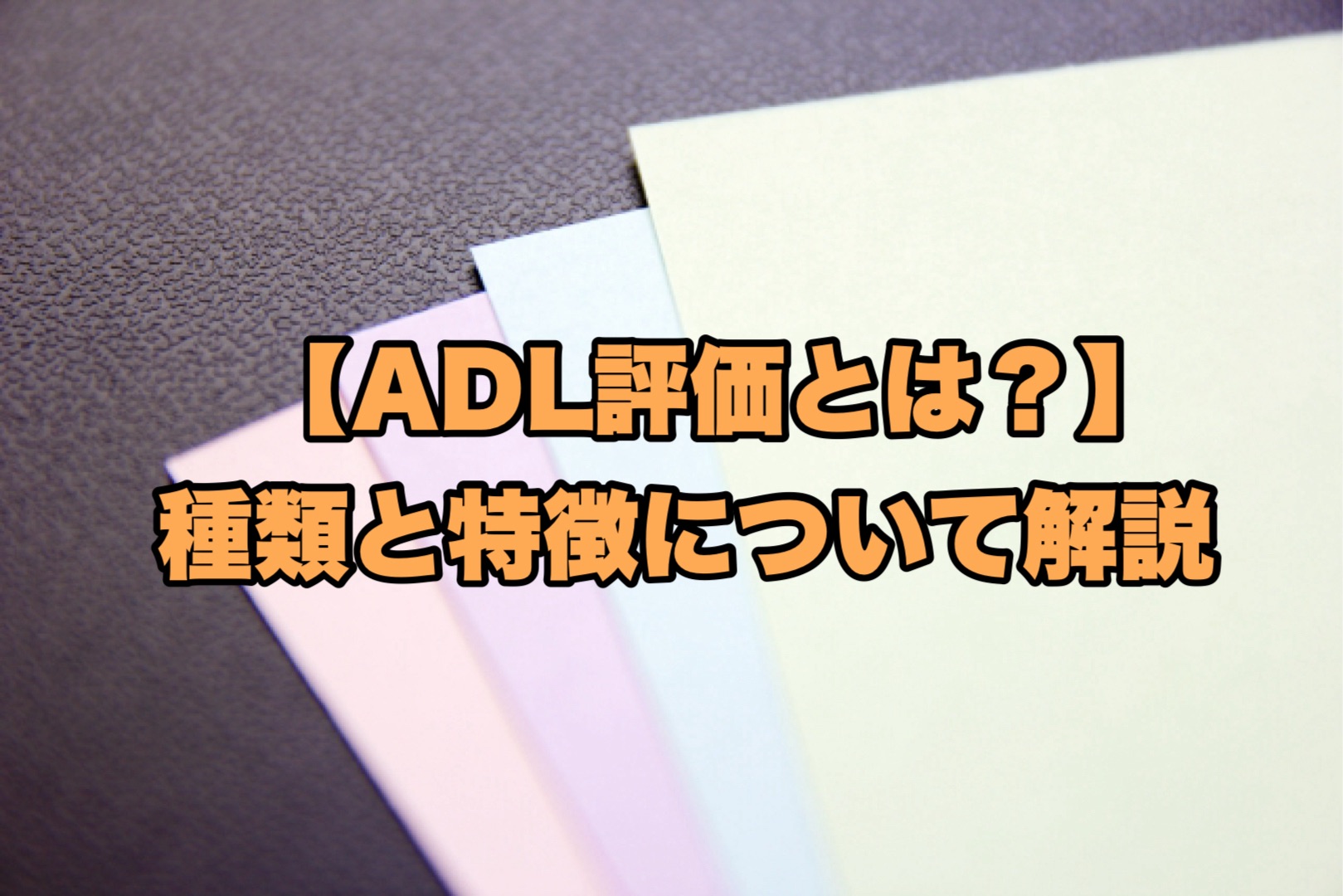ADL 評価スケールの種類と使い分け【理学療法士( PT )向け比較表】
結論:理学療法士( PT )が使う ADL 評価スケールは、目的(介助量の段階化/自立度の把握/在宅での活動性)と病期、所要時間で選ぶと迷いません。本記事では、 Barthel Index( BI )・ FIM ・ Katz ・ Lawton IADL ・ FAI などを、現場で使い分けられる形に整理します。
ADL は「できる ADL 」と「している ADL 」がズレやすく、スケール選びを誤ると介入の優先順位もぶれます。比較表で “ まず 1 本 ” を決め、記録ポイント(観察条件/介助量の定義/再評価タイミング)までセットで揃えるのがコツです。関連:評価の全体像(評価ハブ)も合わせて確認すると、尺度の選択と運用が一気に安定します。
ADL 尺度の比較表(目的・所要時間・使いどころ)
| 領域 | 代表テスト | 所要 | スコア範囲 | 主な使いどころ |
|---|---|---|---|---|
| 基本 ADL(介助量) | Barthel Index( BI ) | 5–10 分 | 0–100 | 急性〜回復期の介助量、退院調整の初期指標 |
| 基本 ADL+認知要素 | FIM( Motor / Cognitive ) | 15–30 分 | 18–126 | 入退院判定、経過比較、チーム間の共通言語 |
| 基本 ADL(簡便) | Katz Index | 3–5 分 | A–G | 高齢者スクリーニング、短時間の層別化 |
| IADL(生活行為) | Lawton IADL | 5–10 分 | 0–8(原著) | 在宅の自立度、家事・買物・服薬管理 |
| IADL / 活動性 | FAI( Frenchay Activities Index ) | 10 分 | 15–60 | 生活期の社会参加・活動性の評価 |
疾患特異的 ADL/生活機能 尺度(代表例)
| 疾患/領域 | 代表尺度 | 所要 | 主な評価対象 | 使いどころ |
|---|---|---|---|---|
| 脊髄損傷 | SCIM( Spinal Cord Independence Measure ) | 15–30 分 | 自己管理、排泄、移乗・移動 | SCI の生活自立度を詳細に把握(入退院・追跡) |
| パーキンソン病 | MDS-UPDRS Part II( ADL ) | 10–15 分 | 食事・書字・歩行など日常動作 | 薬効 ON / OFF を含む生活機能の追跡 |
| COPD・呼吸器 | LCADL( London Chest ADL ) | 5–10 分 | 呼吸困難に伴う生活活動制限 | 在宅復帰・呼吸リハでの活動制限評価 |
| 認知症 | DAD( Disability Assessment for Dementia ) | 15–20 分 | IADL の遂行・発動 | 介入効果・進行度、家族支援の設計 |
| ALS | ALSFRS-R | 10 分 | 四肢/体幹・嚥下・呼吸の生活影響 | 病期の追跡、補助具・呼吸管理の検討 |
どれを選ぶ?(症例像ごとの第一選択)
| 症例像/目的 | まず取るテスト | 補助/代替 |
|---|---|---|
| 急性〜回復期・介助量の把握 | BI または FIM | Katz(短時間)、FAI(生活期の活動性) |
| 在宅復帰の生活自立 | Lawton IADL | FAI、DAD(認知症合併時) |
| SCI の詳細な自立度 | SCIM | BI(横並び比較用) |
| PD の生活機能( ON / OFF 含む) | MDS-UPDRS Part II | 歩行/バランス系( TUG / Berg ) |
| COPD の活動制限 | LCADL | 6 MWT、mMRC、Borg |
| ALS の経過追跡 | ALSFRS-R | 呼吸機能( ABG / SpO2 等) |
専用記事(配布物なしの内部リンク)
- Barthel Index( BI ) — 10 項目・0–100 点、介助量の全体把握と初期スクリーニングに
- Lawton IADL — 在宅の自立度(買物・金銭・服薬など)の評価と介入設計
- FAI( Frenchay Activities Index ) — 15 項目の活動頻度で生活期の活動性を追跡
- SCIM( Spinal Cord Independence Measure ) — SCI のセルフケア・排泄管理・移動を詳細に把握
- MDS-UPDRS Part II( Parkinson ) — 日常動作( ADL )の変化と ON / OFF 条件の把握
- ALSFRS-R( ALS ) — 四肢・嚥下・呼吸を含めた生活機能の縦断評価
ダウンロード(記録シート/クイックリファレンス)
配布物はいずれも記録用テンプレート/要点メモです(項目本文は掲載していません)。
Katz Index
LCADL( COPD )
DAD(認知症)
FAQ
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
BI と FIM の違いは?
BI は短時間で介助量の全体像を把握するのに適し、FIM は Motor / Cognitive を含めた自立度の精密な追跡に向きます。病期・所要時間・目的で使い分けます。
IADL は誰に向いている?( Lawton / FAI の使い分け)
在宅や生活期の自立度評価に有用です。家事・買物・金銭・服薬などの複雑な活動は Lawton、活動性・社会参加の広がりは FAI が得意です。
疾患特異的尺度はいつ併用する?
まず BI / FIM / IADL で土台を押さえ、疾患特有の制限を詳しくみたいときに併用します(例:SCI → SCIM、PD → MDS-UPDRS Part II、COPD → LCADL、認知症 → DAD、ALS → ALSFRS-R )。
参考文献
- Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61–65. PubMed
- Keith RA, Granger CV, Hamilton BB, Sherwin FS. The functional independence measure: a new tool for rehabilitation. Adv Clin Rehabil. 1987;1:6–18. PubMed
- Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The Index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA. 1963;185:914–919. doi: 10.1001/jama.1963.03060120024016. PubMed
- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179–186. PubMed
- Catz A, Itzkovich M, Agranov E, Ring H, Tamir A. SCIM–spinal cord independence measure: a new disability scale for patients with spinal cord lesions. Spinal Cord. 1997;35(12):850–856. doi: 10.1038/sj.sc.3100504. PubMed
- Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR, et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord. 2008;23(15):2129–2170. doi: 10.1002/mds.22340. PubMed
- Garrod R, Bestall JC, Paul EA, Wedzicha JA, Jones PW. Development and validation of a standardized measure of activity of daily living in patients with severe COPD: the London Chest Activity of Daily Living scale (LCADL). Respir Med. 2000;94(6):589–596. doi: 10.1053/rmed.2000.0786. PubMed
- Gélinas I, Gauthier L, McIntyre M, Gauthier S. Development of a functional measure for persons with Alzheimer’s disease: the Disability Assessment for Dementia (DAD). Am J Occup Ther. 1999;53(5):471–481. doi: 10.5014/ajot.53.5.471. PubMed
- Cedarbaum JM, Stambler N, Malta E, et al. The ALSFRS-R: a revised ALS functional rating scale that incorporates assessments of respiratory function. J Neurol Sci. 1999;169(1–2):13–21. doi: 10.1016/S0022-510X(99)00210-5. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下