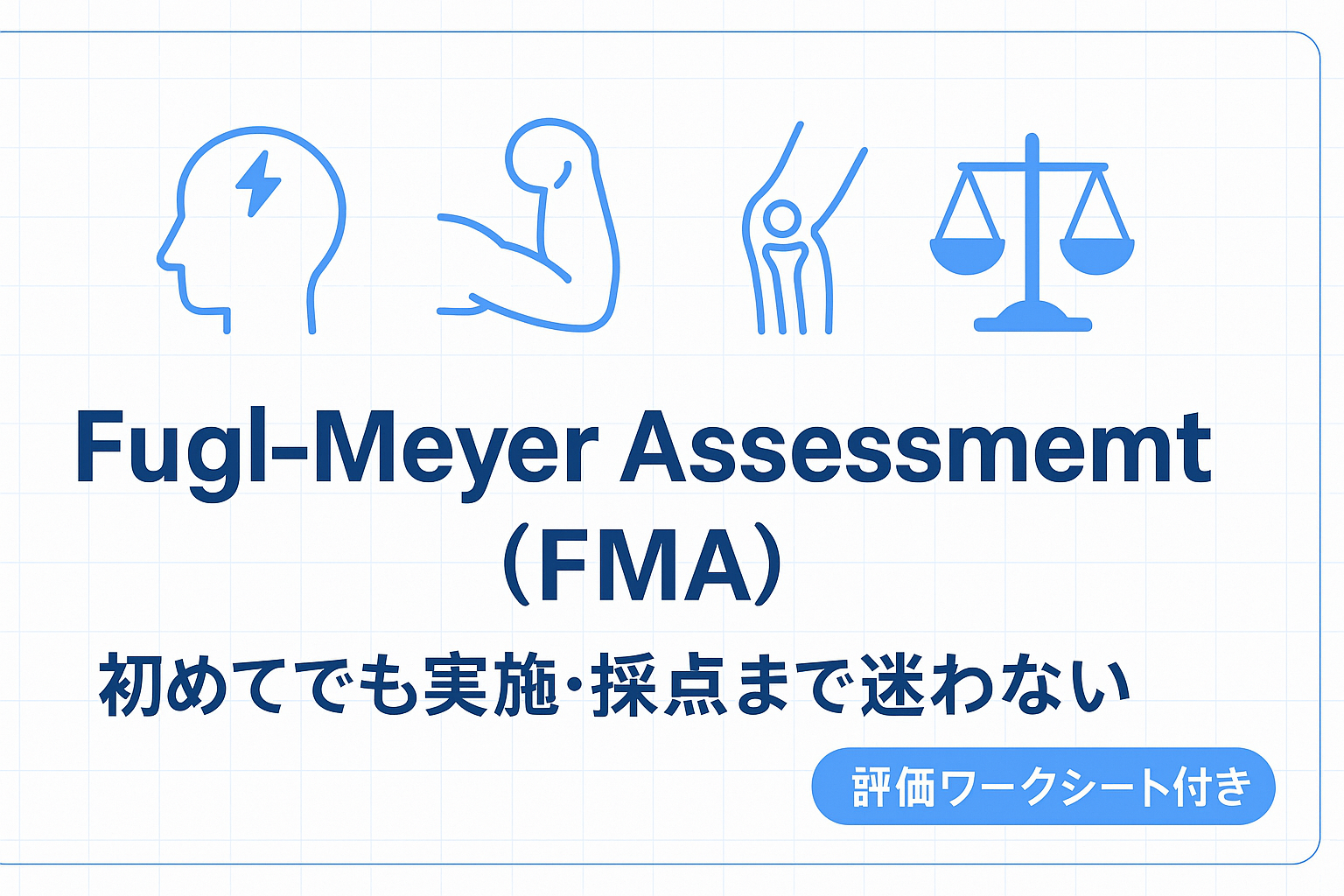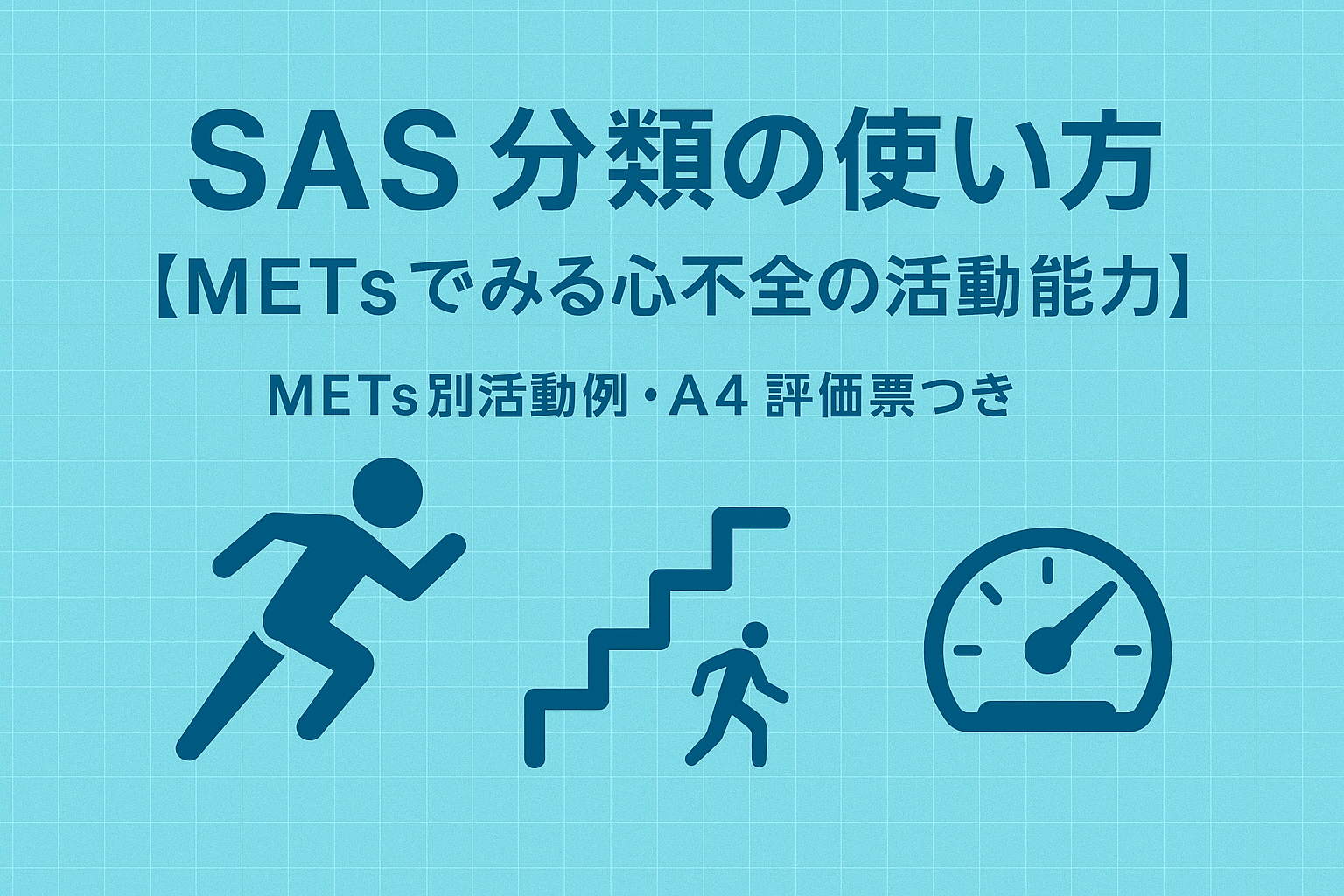Fugl-Meyer Assessment( FMA )とは?(目的と使いどころ)
Fugl-Meyer Assessment( FMA )は、脳卒中後の感覚運動障害を モーター(上肢 66 点・下肢 34 点)、感覚、バランス、関節可動域、関節痛の複数ドメインで定量化する評価です。各課題は 0(不能)/ 1(部分的)/ 2(完全)の 3 段階で採点し、経時変化とボトルネック(どこが止まっているか)を整理します。
本記事は、初めて FMA を扱う方が 準備 → 実施 → 採点 → 解釈 → チーム導入までを 1 本で組み立てられることをゴールにします。項目文の掲載はせず、運用は公式マニュアル参照を前提に、配点構造と集計欄のみの A4 スコア記録シート( PDF )で記録を完結できる形に整えます。
評価構成と配点の概要
| ドメイン | 主な内容 | 最大点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上肢運動( FMA-UE ) | 反射、シナジー内/混合/外、手関節・手指、協調/速度 | 66 | 33 項目 × 0 / 1 / 2 |
| 下肢運動( FMA-LE ) | 反射、シナジー内/外、立位課題、協調/速度 | 34 | 0 / 1 / 2 採点 |
| 感覚 | 触覚・位置覚(閉眼・左右比較) | 24 | 上肢・下肢 |
| バランス | 座位/立位の保持と姿勢反応 | 14 | 転倒予防に配慮 |
| 関節可動域 | 主要関節の自/他動可動域 | 44 | 疼痛と別採点 |
| 関節痛 | ROM 実施時の疼痛反応 | 44 | 項目内基準で採点 |
| 合計 | フル版(全ドメイン) | 226 | モーター合計は 100( UE 66 + LE 34 ) |
所要時間の目安は、フル版で約 30〜45 分、モーターのみなら 約 20〜30 分です。臨床では「 UE / LE を中心に経時変化を追う」「研究や詳細評価ではフル版」のように、目的でスコープを固定すると運用が安定します。
実施前チェックと採点ルール
| 観点 | 要点 | 運用メモ |
|---|---|---|
| 環境 | 静かで安全なスペース、覚醒が良い時間帯 | 評価時間帯を固定すると再現性が上がります |
| 説明 | 指示は短く、必要なら非麻痺側で模倣デモ | 複数課題を同時に提示しない |
| 試行回数 | 原則 各課題 最大 3 回、最良成績を採点(協調/速度は 1 回) | 疲労が出やすい症例は途中で区切ります |
| 介助 | 誘導するハンドリングは不可。安全確保の接触のみ | 接触の有無・介助量は記録欄に残す |
| スコア | 0=不能/ 1=部分的/ 2=完全 | 疼痛や ROM 制限で実施不能でも 0 として扱う運用が多いです |
| 安全管理 | 立位・バランスでは転倒対策、肩痛・亜脱臼の確認 | 評価のために痛みを悪化させない |
準備物(最小構成)
- 安定した椅子・ベッド、テーブル
- ストップウォッチ、反射ハンマー、綿球/小物(触覚・位置覚)
- 遮蔽用アイマスク等、筆記具
- 本記事の FMA スコア記録シート( A4 ・ PDF )(後半で配布)
FMA-UE(上肢)実施のコア手順
- 反射:上腕二頭筋・三頭筋などを誘発し、左右差と有無を 0 / 1 / 2 で評価します。
- シナジー内:屈曲/伸展シナジー内の随意運動を確認し、代償とパターン崩れを観察します。
- シナジー混合/外:分離の程度を評価し、開始位と終末位を丁寧にそろえます。
- 手関節・手指:背屈保持、把持課題、指の屈伸などを実施します。
- 協調/速度:拮抗運動の滑らかさ・正確性・時間内反復を見ます。
詳細な姿勢・開始位・減点基準は、公式の資料で確認してください。Fugl-Meyer Assessment( University of Gothenburg )
FMA-LE(下肢)実施のコア手順
- 反射:膝蓋腱・アキレス腱反射を評価し、左右差・亢進/低下を確認します。
- シナジー内:股・膝・足の屈曲/伸展パターン内の随意運動を評価します。
- シナジー外:分離運動(立位課題を含む)の程度を評価します。
- 協調/速度:下肢の拮抗運動で、リズム・正確性・分離を確認します。
感覚・バランス・関節可動域/疼痛
- 感覚( 24 点 ):触覚・位置覚を閉眼で左右比較し、正常/軽度低下/高度低下を 0 / 1 / 2 で評価します。
- バランス( 14 点 ):座位/立位の保持と姿勢反応を評価し、保持時間・介助量・代償を記録します。
- 関節可動域( 44 点 )/疼痛( 44 点 ):主要関節の ROM と、その際の疼痛反応を別ドメインとして採点します。
解釈:重症度の目安と経時変化の見方
| 重症度 | FMA-UE 目安 | 臨床メモ |
|---|---|---|
| 重度 | 0〜19(〜22) | クラスタ分析等で提案された範囲。臨床像と合わせて解釈します。 |
| 中等度 | 20〜46( 23〜47 ) | 境界域は重なりやすく、一律に線引きしません。 |
| 軽度 | 47 以上( 48〜66 ) | 上位域は ARAT など能力評価と併用すると見落としが減ります。 |
MCID は対象や病期で差があり、報告も幅があります。実務では、同一検者・同一条件での再評価を徹底し、「変化量」+「どの領域が変わったか」をセットで読み取る運用が安全です。
よくあるミス/中止基準( OK / NG 早見表 )
| 場面 | OK(推奨) | NG(避ける) | 中止・再評価 |
|---|---|---|---|
| 指示・デモ | 短い口頭指示/非麻痺側での模倣デモ | 長い説明・複数課題の同時提示 | 理解が難しい場合は別日に再設定 |
| 試行回数 | 各課題 最大 3 回で最良成績を採点 | 無制限の反復・片側だけの練習 | 疲労・痛み増悪時は中止し別日再開 |
| 安全管理 | 見守り配置・動線確保・転倒対策 | 立位課題での無監視・環境調整なし | バイタル逸脱・失神前駆で即中止 |
| 肩の扱い | 痛み・亜脱臼の有無を確認し、必要なら支持 | 抵抗を無視した他動運動の強要 | 痛み増悪なら ROM/ Pain 項目は見送り |
| 採点の一貫性 | 開始位・終末位・減点基準をチームで統一 | 担当者ごとに判断がバラバラ | 不一致が多いなら二重採点で再確認 |
FMA スコア記録シート( A4 ・ PDF )
本記事の配布は PDF 1 本に統一しました。項目文は掲載せず、配点構造と集計欄のみで記録できるスコアシートです(採点基準は公式マニュアル参照)。院内の記録用紙・回診用フォーマットとして使いやすい形にしてあります。
印刷は A4/余白 10〜12 mm 前後/ヘッダ・フッタ非表示を推奨します。再評価は同一条件(体位、開始位、指示、見守り、補装具)で比較してください。
運用プロトコル(チーム導入の最短ルート)
- 対象と目的を明確化します(例:回復期での FMA-UE 改善の追跡、下肢運動と歩行の関係を見る)。
- 本記事の手順+スコアシートで 1 例パイロット評価を行い、二重採点で解釈をすり合わせます。
- 評価タイミング(入棟時/ 2 週ごと/退棟時など)をルーチン化し、カルテ・カンファへ組み込みます。
- 「どの程度の変化を意味のある改善として扱うか」をチームで共有し、判断のばらつきを減らします。
- 結果を BI ・ FIM や歩行速度、上肢能力(例: ARAT )などと関連づけ、次の介入に落とし込みます。
現場の詰まりどころ(よくある失敗と対処)
| 詰まりどころ | 起きやすい状況 | 対処 | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| 時間がかかりすぎる | フル版を全員に実施して破綻 | まずは UE のみ/ UE + LE など、対象と時期でスコープを固定 | 「今回みた範囲( UE のみ等)」を条件メモに残す |
| 0 / 1 / 2 の判断がばらつく | 開始位・終末位が人で違う | 開始位・代償の扱い・減点の考え方をチームで統一(必要なら動画で擦り合わせ) | 迷った課題は「何が足りず 1 点か」を一言で残す |
| 肩痛・亜脱臼が強く進めにくい | 疼痛で UE が止まる | 評価のために痛みを悪化させない。 ROM/ Pain は見送りも含めて安全優先 | 「痛みで中止」「支持の有無」を必ず明記 |
| スコアは出るが、次の一手が決まらない | カンファが短い/情報が散る | 「止まった領域 → 原因仮説 → 次の 1 手」を 1 行でセット化。整理の型は 面談準備チェック&職場評価シートの書き方を流用すると早いです。 | 例:「 UE 手指で停滞 → 分離+巧緻 → 物品操作を段階化」 |
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. FMA の読み方は?
A. Fugl-Meyer Assessment は、一般的に「フーグルマイヤー評価」と呼ばれます。院内資料では「 Fugl-Meyer Assessment( FMA )」のように正式名称+略称で併記すると伝わりやすいです。
Q2. まず UE と LE のどちらから導入すべきですか?
A. 迷ったら、対象が多い方(例:上肢の課題が主目的なら UE )から固定して導入すると回ります。まずは 範囲を固定し、二重採点で基準をそろえるのが最優先です。
Q3. 0 / 1 / 2 の判断のブレを減らすコツは?
A. 「開始位」「代償の扱い」「終末位の基準」を先に決め、チーム内で 1 回は動画や同時評価で擦り合わせるのが効果的です。スコアだけでなく、迷った理由を 1 行残すと次回の一致率が上がります。
Q4. スコアシートに項目文がないのはなぜですか?
A. 本記事では、運用は公式マニュアル参照を前提にし、配布物は配点構造と集計欄のみに整理しています。採点基準や詳細手順は、必ず公式資料で確認してください。
次の一手(評価→介入へつなぐ)
- 評価の全体像を整理する:評価ハブ
- 同じ脳卒中の姿勢・起居を整理する:PASS 運用プロトコル
参考文献
- Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient: I. A method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31. PubMed
- University of Gothenburg. Fugl-Meyer Assessment – Protocols & Manuals. Link
- Sullivan KJ, et al. Fugl-Meyer assessment of sensorimotor function after stroke: standardized training procedure. Stroke. 2011;42(2):427-432. doi:10.1161/STROKEAHA.110.592766
- Gladstone DJ, et al. The Fugl-Meyer Assessment of motor recovery after stroke: a critical review. Neurorehabil Neural Repair. 2002;16(3):232-240. doi:10.1177/154596802401105171
- Pandian S, et al. Minimal clinically important difference of the lower-extremity Fugl-Meyer Assessment in chronic stroke. J Neurol Phys Ther. 2016;40(3):186-193. doi:10.1097/NPT.0000000000000134
- Woytowicz EJ, et al. Determining levels of upper-extremity movement impairment by cluster analysis of the Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity. Arch Phys Med Rehabil. 2017;98(3):456-462. doi:10.1016/j.apmr.2016.06.023
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下