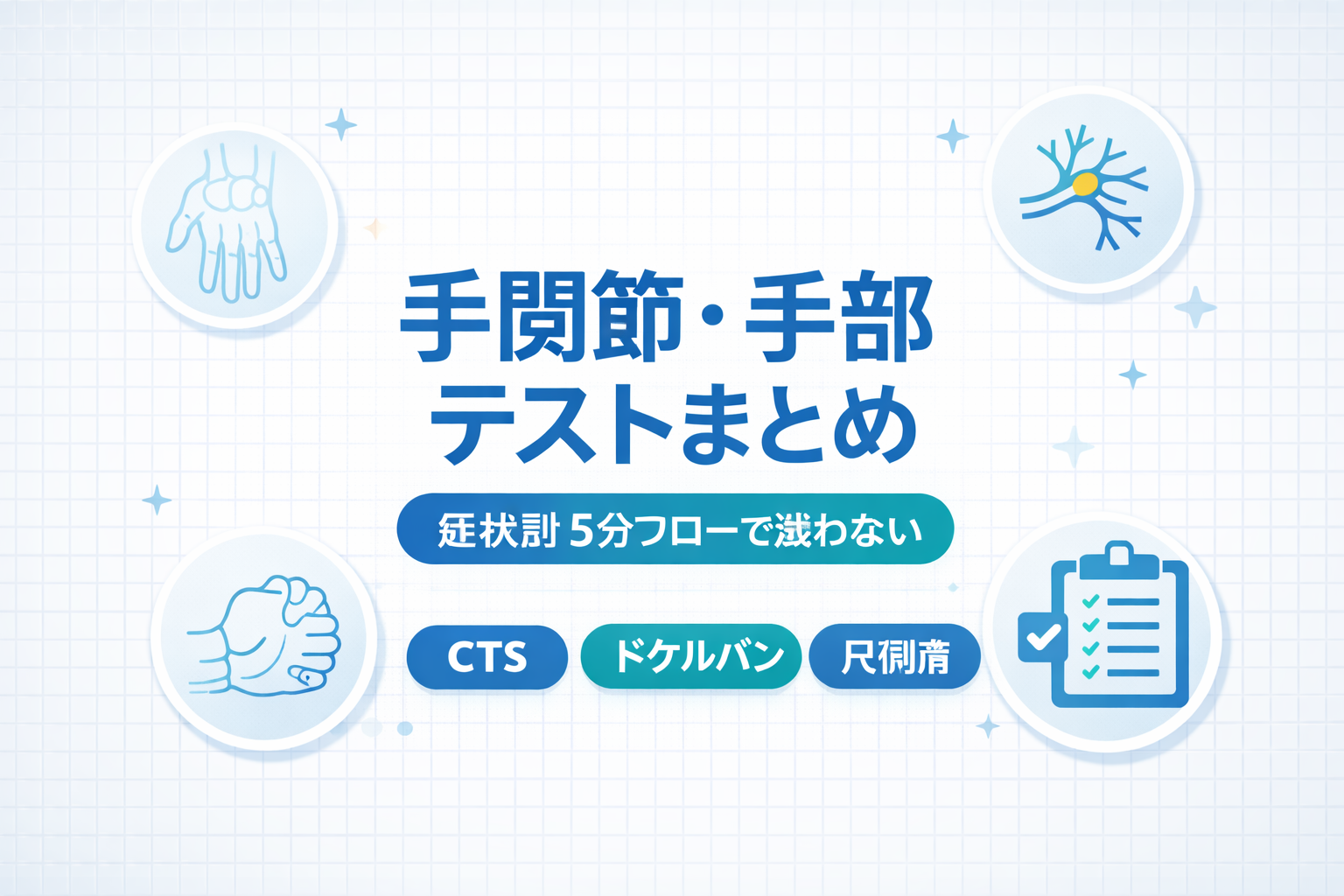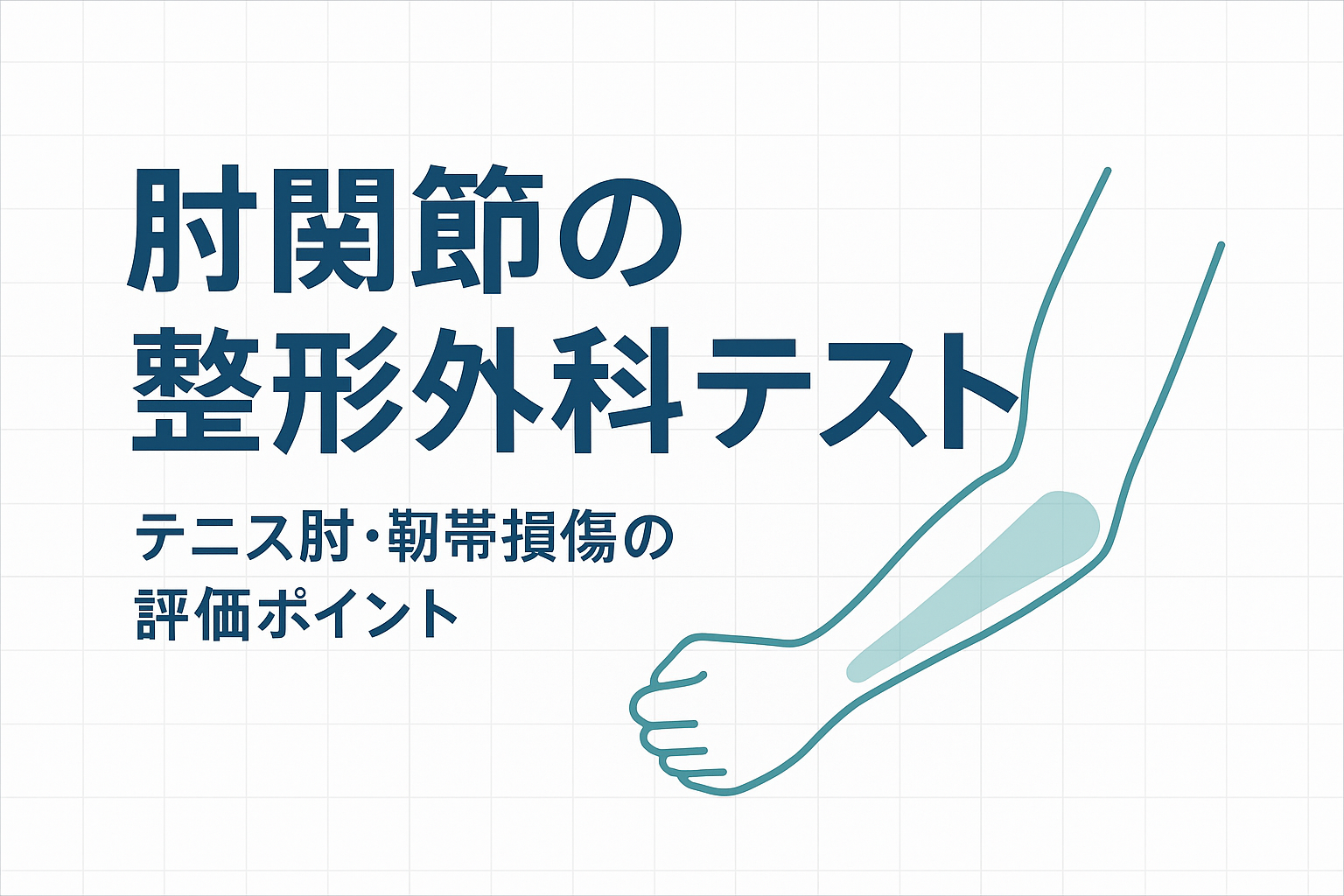- 手関節・手部の整形外科テストまとめ|症状別に “迷わず選べる” 運用へ
- まずは 5 分フロー| “症状” からテストを迷わず決める
- しびれ(正中神経領域)| CTS は “Phalen → Durkan で確認” が迷いにくい
- 母指側(橈骨茎状突起)痛|ドケルバンは Finkelstein の “混同” を潰す
- 尺側手関節痛| TFCC などは “部位+負荷” の再現で絞る
- 外傷+舟状骨周囲| “舟状骨窩圧痛” を最初に拾う
- 現場の詰まりどころ| “迷い” を 3 本で戻す
- よくある失敗| “増やす前に揃える” が最短で効く
- 回避の手順/チェック| 5 分で “増やさず決める”
- よくある質問
- 次の一手|運用を整える→共有の型→環境も点検する
- 参考文献
- 著者情報
手関節・手部の整形外科テストまとめ|症状別に “迷わず選べる” 運用へ
手関節・手部の疼痛やしびれは、腱鞘炎(ドケルバン)、手根管症候群( CTS )、靱帯損傷( TFCC など)、骨折(舟状骨)など鑑別の幅が広く、「知っているのに、どれを先にやるか迷う」場面が起きやすい領域です。本記事は、テストを羅列するのではなく、症状の出方(分布・部位・増悪動作)→テスト選択→記録の型までを “運用” として固定し、現場でブレない形にまとめます。
結論はシンプルで、まず①しびれ(分布)と②母指側痛(橈骨茎状突起)を最短で押さえ、必要に応じて③尺側痛( TFCC )と④舟状骨へ広げます。とくに本サイトでは、手根管( CTS )とドケルバンについては、子記事で “記録の型” まで固定しています(下の回遊リンクからすぐ行けます)。
このページの使い方(回遊の三段)
標準化(総論):評価の全体像(ハブ)
代表の子記事:Phalen テスト( CTS ) / Durkan テスト( CTS ) / Finkelstein テスト(ドケルバン)
まずは 5 分フロー| “症状” からテストを迷わず決める
手関節・手部は、最初に「痛みの場所」と「しびれの分布」を 1 行で固定するだけで、テスト選択がほぼ決まります。以下の順に “上から埋める” と、増やさずに判断が揃います。
| 順番 | まず聞く/見る | 次にやる | 代表のテスト |
|---|---|---|---|
| 1 | しびれの分布(正中/尺骨)+夜間増悪 | CTS を “確認 1 本” で固める | Phalen / Durkan |
| 2 | 母指側(橈骨茎状突起)痛+把持で増悪 | ドケルバンを “痛くしすぎず” 確認 | Finkelstein |
| 3 | 尺側手関節痛(回内外・荷重で増悪) | TFCC/尺側の構造物を疑い拡張 | 尺側圧痛+負荷の再現(本記事内に整理) |
| 4 | 外傷歴+舟状骨周囲の圧痛 | 舟状骨を “見逃さない” 方向へ | 舟状骨窩圧痛(本記事内に整理) |
しびれ(正中神経領域)| CTS は “Phalen → Durkan で確認” が迷いにくい
母指〜中指中心のしびれ、夜間〜起床時の増悪、把持で悪化が揃うときは、まず CTS を疑います。ここで大事なのは、テストの “数” より条件を揃えて再現できることです。現場運用としては、入口に Phalen テスト、確認 1 本に Durkan テストを置くと、結果が揃いやすくなります。
詳しい手順・保持時間・偽陽性回避・記録の型は、子記事で “運用” として固定しています:Phalen テスト / Durkan テスト
母指側(橈骨茎状突起)痛|ドケルバンは Finkelstein の “混同” を潰す
母指側の手関節痛が主役で、つまみ動作・把持・母指使用で増悪する場合は、ドケルバン病( APL / EPB )を疑います。ここで最も多い詰まりは、Finkelstein と Eichhoff の混同により痛みを出しすぎて解釈不能になることです。まずは “受動で段階的” を標準に固定して、痛む場所が一致するかで判断します。
混同しやすい Finkelstein と Eichhoff の違い、痛くしすぎない運用、記録の型は:Finkelstein テストにまとめています。
尺側手関節痛| TFCC などは “部位+負荷” の再現で絞る
尺側手関節痛は、 TFCC を含む尺側の構造物(尺側手根伸筋腱・尺側側副靱帯など)が絡みやすく、テスト名を追うより痛みの部位と増悪する負荷を揃えて再現性を取るのが近道です。まずは、①尺側の限局圧痛(どこか)②回内外・尺屈・荷重での増悪(どの動作か)を固定し、同条件で左右差を比較します。
| 見るポイント | 確認する内容 | 記録の型 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 部位 | 尺側の “一点” を特定(広い痛みは分割) | 尺側限局圧痛(部位:__) | 部位が定まらないなら動作から戻る |
| 負荷 | 回内外/尺屈/荷重のどれで増悪するか | 増悪動作:__(条件:__) | 同条件で左右差を取る |
| 再現 | 同じ条件で痛みが再現するか | 同条件で再現(+/−) | 負荷量・角度・速度を固定する |
外傷+舟状骨周囲| “舟状骨窩圧痛” を最初に拾う
転倒(手をつく)など外傷歴があり、橈骨遠位〜手根部の痛みがある場合は、舟状骨を見逃さない方針が重要です。現場の初動としては、舟状骨窩(解剖学的スナッフボックス)付近の圧痛を確認し、疼痛が強い/腫脹が目立つ場合は無理に誘発テストを増やさず、医師共有・画像評価へ繋ぐ判断が安全です。
| 項目 | 見る/聞く | 記録の型 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 外傷歴 | 手をついた/捻った/衝撃の有無 | 外傷機転:__ | 不明でも疑いは残る |
| 圧痛 | 舟状骨窩の限局圧痛 | 舟状骨窩圧痛(+/−) | 強い痛みは無理に誘発しない |
| 腫脹 | 手根部の腫脹・熱感 | 腫脹(+/−) | 腫脹が強い場合は共有優先 |
現場の詰まりどころ| “迷い” を 3 本で戻す
この領域で詰まりやすいのは、①テストを増やしすぎて解釈不能 ②陽性の主語が “痛み” だけで分布が曖昧 ③記録が手技名だけで条件が残らない、の 3 つです。ここはボタン無しで、戻り道だけ用意します。
よくある失敗| “増やす前に揃える” が最短で効く
手関節・手部は、テストを増やすほど精度が上がるわけではありません。むしろ、痛みの主語が曖昧になりやすい領域です。まずは「部位」「分布」「条件」を揃えてから、必要最小限のテストで再現性を取りましょう。
| NG | なぜ起きる | まず直す 1 点 | OK 記録の型 |
|---|---|---|---|
| テストを次々追加して混乱 | 症状要約がない | 部位/分布を 1 行で固定 | 母指〜中指しびれ+夜間増悪(例) |
| 局所痛だけで陽性扱い | 痛みとしびれの混同 | “分布” を主語にする | 正中神経領域のしびれ再現(+) |
| 手技名だけ残して条件がない | 共有できない | 保持時間・条件を書く | 保持 30 秒、 12 秒で再現(例) |
回避の手順/チェック| 5 分で “増やさず決める”
- 症状を 1 行で要約:部位(どこ)+分布(正中/尺骨)+増悪動作(何で)
- しびれが主役なら CTS へ:Phalen → Durkan で確認
- 母指側痛が主役ならドケルバンへ:Finkelstein で混同を潰す
- 尺側痛は “部位+負荷” を固定し、同条件で左右差
- 外傷+舟状骨周囲は “拾う” を優先し、無理に誘発を増やさない
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
まず何からやると迷いませんか?
最初に「痛みの場所」と「しびれの分布」を 1 行で固定してください。しびれが主役なら CTS を疑い、Phalen → Durkanで確認する流れが迷いにくいです。母指側(橈骨茎状突起)痛が主役なら、Finkelsteinでドケルバンの混同を潰すのが近道です。
テストをたくさんやるほど精度は上がりますか?
上がりません。手関節・手部は痛みの混入が起きやすいので、まず “条件を揃えて再現性を取る” 方が精度が上がります。保持時間、負荷量、部位・分布など、結果の主語が残る形で運用してください。
記録は何を書けば共有しやすいですか?
手技名より、条件(保持時間・負荷・位置)と主語(分布/部位)を残すのが一番強いです。例: “保持 30 秒で 12 秒に母指〜中指しびれ再現(+)” のように、再現条件が残る形にすると引き継ぎが楽になります。
次の一手|運用を整える→共有の型→環境も点検する
この領域は、テストの暗記より “運用(条件固定・記録の型)” を整える方が、再現性と回遊が伸びます。次の 3 段で整えると、現場でもサイト内でも迷いが減ります。
- 運用を整える:評価の全体像(ハブ)
- 共有の型を作る:整形外科的テスト一覧(部位別)
教育体制・人員・記録文化など “環境要因” を一度見える化すると、次の打ち手が決めやすくなります。
チェック後に「続ける/変える」の選択肢も整理したい方は、PT キャリアナビで進め方を確認しておくと迷いが減ります。
参考文献
- Phalen GS. The carpal-tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1966;48(2):211-228.
- Durkan JA. A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1991;73(4):535-538.
- Wu F, Rajpura A, Sandher D. Finkelstein's Test Is Superior to Eichhoff's Test in the Investigation of de Quervain's Disease. J Hand Microsurg. 2018;10(2):116-118.
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下