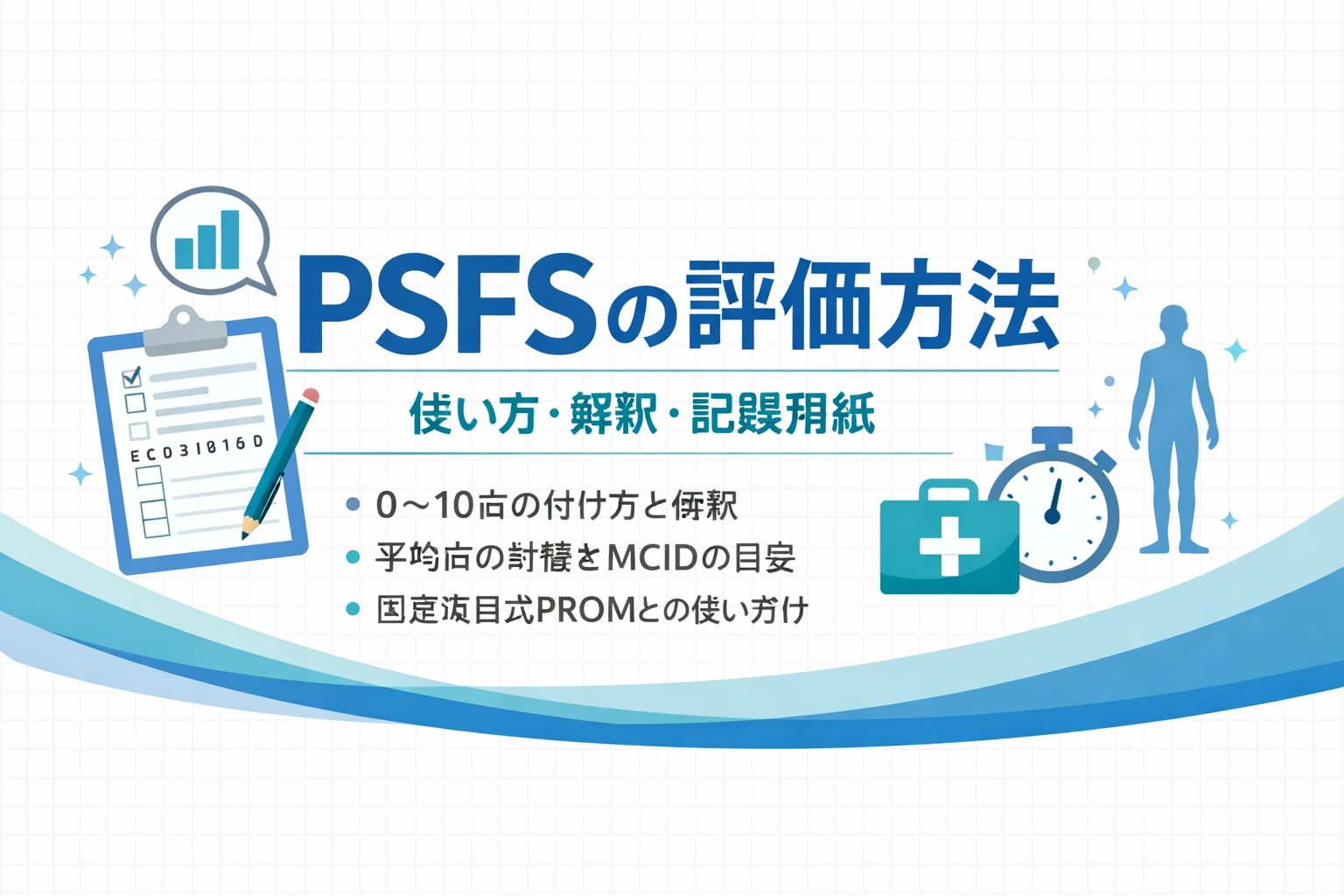- PSFS(患者特異的機能評価)の使い方|活動の挙げ方・0〜10 の説明・変化量の読み方
- 記録シート PDF(印刷してそのまま使える)
- PSFS とは?|「困りごと」を活動レベルで可視化する
- いつ使う?|初回・中間・退院前の「同じ条件」で追う
- 実施手順 1:活動の挙げ方|抽象→行動→条件(距離/時間/環境)
- 実施手順 2:0〜10 の説明テンプレ|“痛み”ではなく“できる度”でそろえる
- スコアのまとめ方|各活動スコア+平均値(まずはこの 2 つだけ)
- 解釈のコツ|平均点だけで結論を出さない( MID / MCID の読み方)
- 固定項目式 PROM との使い分け|PSFS は「最重要課題」を拾う役
- 現場の詰まりどころ/よくある失敗|PSFS が崩れる 5 パターン
- PSFS 2.0 と日本語運用|「想起が難しい」人では質問の出し方を工夫する
- よくある質問(FAQ)
- 次の一手|PSFS を「記録 → 再評価」まで回すために
- 参考文献
- 著者情報
PSFS(患者特異的機能評価)の使い方|活動の挙げ方・0〜10 の説明・変化量の読み方
PSFS は「本人がいちばん困る活動」を数値化できるので、目標設定と再評価が一気に揃います。 評価 → 記録 → 再評価の流れを 3 分で確認する
PSFS( Patient-Specific Functional Scale )は、患者さん自身が「今いちばん困っている活動」を 3〜5 個あげ、各活動を 0〜10 で評価して変化を追う PROM(患者報告アウトカム)です。固定項目式( NDI / ODI / RDQ など)と違い、設問が決まっていないぶん、個別性の高い目標(生活の困りごと)をそのままモニタリングできます。
本記事は「PSFS を現場で迷わず回す」ために、①活動の挙げ方(抽象→行動→条件)、② 0〜10 の説明テンプレ、③変化量( MID / MCID )の読み方までを 1 ページに整理します。運動器 PROM の全体像(どれを選ぶか)は 運動器 PROM の使い分け にまとめています。
記録シート PDF(印刷してそのまま使える)
記事の内容に合わせた PSFS 記録シートです。印刷してそのまま運用できます。
PDF をページ内でプレビューする(タップで開く)
PSFS とは?|「困りごと」を活動レベルで可視化する
PSFS の強みは、痛みの強さや疾患名ではなく「生活の行動」を直接追えることです。たとえば「腰が痛い」ではなく「駅まで 10 分歩けない」「洗濯物を干すと痛くて途中で休む」のように、本人の優先度が高い活動がそのまま評価項目になります。
固定項目式 PROM は、集団比較や標準化に強い一方で、個別目標が取りこぼれやすいことがあります。PSFS はそこを補い、説明と合意形成(何を良くするか)を助ける役割で使うと整理しやすいです。
いつ使う?|初回・中間・退院前の「同じ条件」で追う
PSFS は、初回評価で「優先課題」を確定し、2〜4 週など施設の再評価周期に合わせて同条件で追うと運用が安定します。ポイントは「測る頻度」より条件を固定して比較できる形にすることです(補装具・介助量・環境・距離・時間など)。
入院・外来・訪問のいずれでも、初回=課題の確定、中間=介入の方向性が合っているか、退院前=生活で再現できるかという目的で使うと、PSFS が単なる点数ではなく「次の一手」につながります。
実施手順 1:活動の挙げ方|抽象→行動→条件(距離/時間/環境)
PSFS がうまく回らない最大の原因は、活動が「大きすぎる(抽象的)」ことです。患者さんにお願いするのは、カテゴリではなく行動と条件まで落とした活動です。
| 抽象(避けたい) | 行動(良い) | 条件(さらに良い) |
|---|---|---|
| 歩く | 駅まで歩く | 駅まで 10 分、杖なし、途中休憩なし |
| 家事 | 洗濯物を干す | ベランダまで往復、立位 10 分、痛みで中断しない |
| 仕事 | デスクワーク | 座位 30 分、立ち上がり回数、症状増悪の有無 |
活動は 3〜5 個が基本です。迷う場合は「生活の中心(仕事/家事/移動/趣味)」から 1 つずつ拾うと偏りが減ります。
実施手順 2:0〜10 の説明テンプレ|“痛み”ではなく“できる度”でそろえる
PSFS は 0〜10 の 11 段階です。説明が毎回ブレると再評価が崩れるので、施設内では言い方を固定するのがおすすめです。
| スコア | 状態のイメージ | 説明の一言(例) |
|---|---|---|
| 0 | まったくできない | その活動が不可能です |
| 1〜3 | ほとんどできない | 人の助けや大きな工夫が必要です |
| 4〜6 | 何とかできる | 時間や休憩が必要で、負担が大きいです |
| 7〜9 | だいたいできる | 少し気になるが、大きな問題なくこなせます |
| 10 | 問題なくできる | 症状が出る前と同じレベルです |
患者さんが迷うときは、「最近 1 週間の平均」で答えてもらい、良い日・悪い日が極端な場合は「最頻値(いちばん多い状態)」でそろえると再評価が安定します。
スコアのまとめ方|各活動スコア+平均値(まずはこの 2 つだけ)
PSFS の基本は、①各活動スコア、②平均値です。最初から複雑にせず、この 2 つだけ固定するとチーム共有がラクになります。
記録の最小セット(おすすめ):
PSFS:①活動 A( 3→7 )、②活動 B( 2→6 )、③活動 C( 1→5 )(平均 2.0→6.0 )
解釈のコツ|平均点だけで結論を出さない( MID / MCID の読み方)
PSFS は「何点以上で改善」と一律に決めにくい指標です。解釈は、①各活動の変化、②平均点の変化、③本人の回復実感(グローバル評価)を合わせて判断します。
- 目安:平均点で 1.3〜2.7 点程度の変化が「小〜大の意味ある変化( MID )」として報告されています(病態・部位でばらつきあり)。
- 実地の考え方:平均が動かなくても、本人の最優先の活動が改善していれば価値があります(平均は“全体の空気”、各項目は“本丸”)。
- 要注意:再評価で活動そのものが入れ替わると、点数の比較が難しくなります。次章の「詰まりどころ」を先にルール化すると崩れにくいです。
固定項目式 PROM との使い分け|PSFS は「最重要課題」を拾う役
PSFS は「本人の最重要課題」に強く、固定項目式 PROM は「標準化された全体像」に強い、という役割分担で考えると迷いません。腰痛領域の整理は 腰痛 PROM の選び方 にまとめています。
| 観点 | PSFS | 固定項目式 PROM(例: NDI / ODI / RDQ ) |
|---|---|---|
| 強い場面 | 個別目標、優先課題の可視化、介入の合意形成 | 標準化、集団比較、重症度の説明、研究 |
| 弱い場面 | 症例間比較、重症度の一律分類 | 本人の“この生活課題”を拾いにくいことがある |
| 運用の型 | 各活動+平均、条件固定で再評価 | 採点・欠損処理・%換算・重症度で共有 |
現場の詰まりどころ/よくある失敗|PSFS が崩れる 5 パターン
PSFS はシンプルですが、運用が崩れるポイントはだいたい決まっています。先に「失敗パターン」を共有しておくと、再評価が安定します。
- 活動が抽象的すぎる:歩く・家事・仕事、で終わる → 行動+条件(距離/時間/環境)まで落とす。
- “痛み”を点数化してしまう:できる度ではなく痛みの強さで答える → 「できる度」を強調し、痛みは別指標で追う。
- 毎回ちがう活動を挙げて比較不能:再評価時は「継続 2〜3 個+新規 0〜1 個」のようにルール化する。
- 条件が変わっているのに点数だけ比較:杖・介助・靴・環境が変わる → 条件を 1 行で固定して残す。
- 記録フォーマットがなく共有が止まる:忙しいと残せない → まずは「活動名+各点+平均」だけ固定し、必要なら本ページの PDF 記録シートで運用の型をそろえる。
PSFS 2.0 と日本語運用|「想起が難しい」人では質問の出し方を工夫する
PSFS は「障害前の状態」を想起しにくい場合に回答が難しくなることがあります。臨床では、活動を思い出しにくい人ほど「最近の生活の中で困る場面」から具体例を引き出し、行動と条件に落とす支援が重要です。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
PSFS は何点くらい変化したら「効果あり」と考えますか?
一律のカットオフより、「意味のある変化( MID / MCID )」の考え方で捉えるのが現実的です。平均点だけでなく、最優先活動の変化と本人の回復実感も合わせて判断します。
活動は 3 個と 5 個、どちらがいいですか?
運用が崩れやすい施設では 3 個が回りやすいです。外来で生活課題が多い場合や、回復期で家事・移動・余暇を押さえたい場合は 5 個まで広げてもよいですが、再評価で比較できることを優先します。
再評価で「困りごと」が変わったらどうしますか?
自然な変化なので否定しません。比較のために「継続課題(前回から続く 2〜3 個)」と「新規課題(今回追加 0〜1 個)」に分け、継続課題で変化量を追い、新規課題は次の介入計画に反映します。
口頭でも実施できますか?
可能です。口頭のときほど「活動名をそのまま記録に残す」ことが重要です。活動が抽象化しやすいので、行動+条件(距離/時間/環境)まで具体化してから点数をつけます。
次の一手|PSFS を「記録 → 再評価」まで回すために
- 評価ハブ:目的別に「どれを使うか」を最短で整理する
- 運動器 PROM の使い分け:PSFS と固定項目式を迷わず選ぶ
- 腰痛 PROM の選び方:ODI / RDQ / PSFS の役割分担を確認する
運用を整えて共有の型ができたら、最後に「環境の詰まり」も点検しておくとスムーズです(職場の状況チェックシート:こちら)。
参考文献
- Stratford P, Gill C, Westaway M, Binkley J. Assessing disability and change on individual patients: a report of a patient-specific measure. Physiother Can. 1995;47(4):258–263. doi:10.3138/ptc.47.4.258
- Westaway MD, Stratford PW, Binkley JM. The Patient-Specific Functional Scale: validation of its use in persons with neck dysfunction. J Orthop Sports Phys Ther. 1998;27(5):331–338. doi:10.2519/jospt.1998.27.5.331
- Horn KK, Jennings S, Richardson G, et al. The Patient-Specific Functional Scale: psychometrics, clinimetrics, and application as a clinical outcome measure. J Orthop Sports Phys Ther. 2012;42(1):30–42. doi:10.2519/jospt.2012.3727
- Abbott JH, Schmitt J. Minimum important differences for the Patient-Specific Functional Scale, 4 regions of the body. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(8):551–558. doi:10.2519/jospt.2014.5248
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下