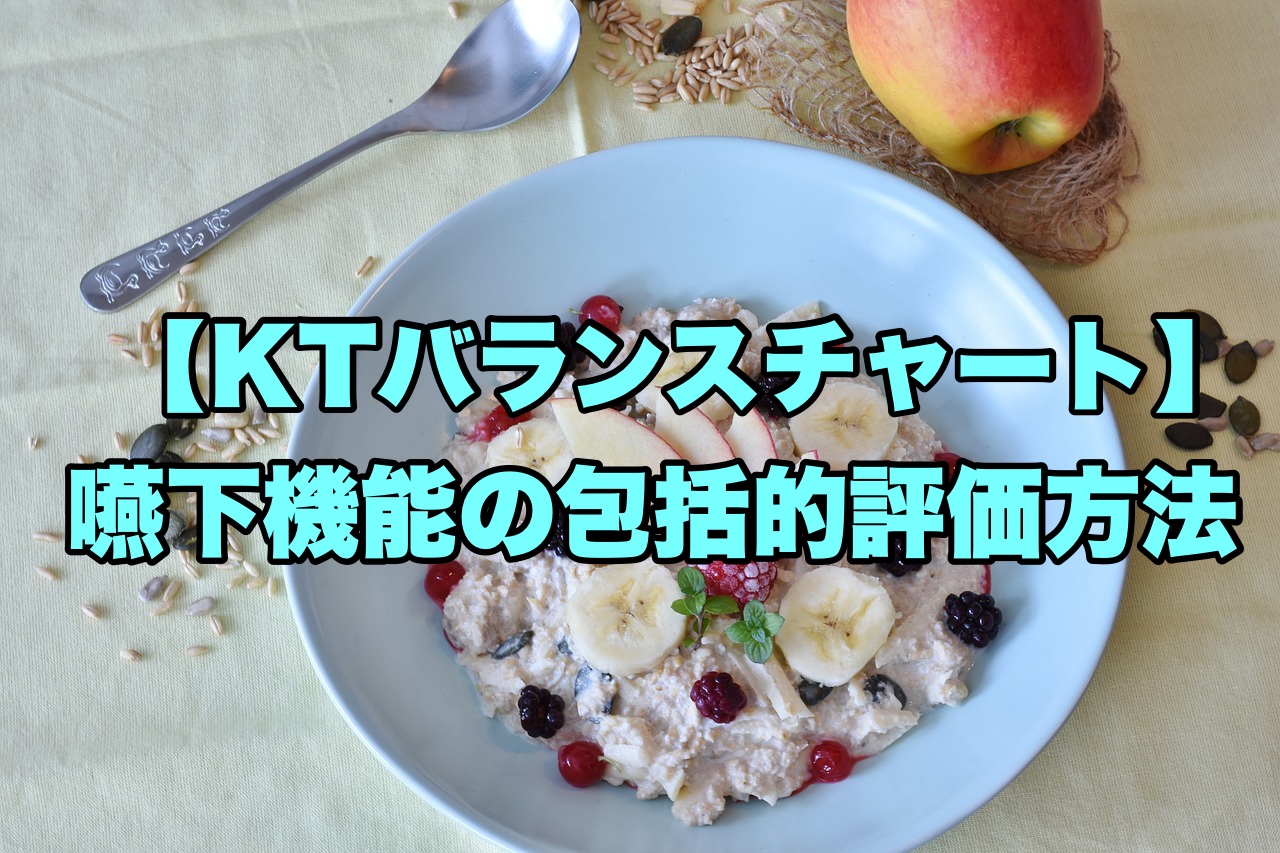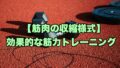KT バランスチャート( KTBC )とは?( 13 項目で“食べる”を多職種で見える化 )
嚥下評価を「手順」で学ぶ流れを見る( ST キャリアガイド )
KT バランスチャート( KTBC )は、摂食・嚥下機能だけに絞らず、全身状態/呼吸/口腔/活動/食形態/栄養まで含めて「口から食べる」を支える条件を 13 項目で整理し、レーダーチャートで可視化する包括的ツールです。項目の“弱いところ” を起点にケアを組み立て、介入後の変化を同じ枠で追えるため、多職種カンファレンスでの共通言語として使いやすいのが強みです。 [oai_citation:0‡J-STAGE](https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/58/4/58_58.561/_pdf)
なお、嚥下評価の全体像(安全確認 → スクリーニング → CSE → 必要なら FEES / VF → 介入設計 → 再評価)は、別記事「嚥下評価の実務フロー」にまとめています。KTBC は、その中でも介入設計と共有の段で真価を発揮します。
KTBC が効く場面(“評価が計画に落ちない” を防ぐ)
KTBC は「点数を付けること」自体が目的ではなく、次の一手(優先順位)を決めて、チームで同じ方向を向くための道具です。特に次の場面で使い勝手が良くなります。
- むせ・湿性嗄声・食事量低下などがあり、食形態や介助条件を決め直したいとき
- 座位が崩れる/疲労で後半に悪化するなど、嚥下以外の条件(姿勢・耐久性・活動)が絡むとき
- 介入は入っているのに改善が鈍く、ボトルネックを再特定したいとき
- 退院・転院・在宅移行で、情報提供を 1 枚にまとめたいとき
KTBC の構造( 4 視点 × 13 項目 )
KTBC は、( 1 )心身の医学的視点、( 2 )摂食・嚥下の機能的視点、( 3 )姿勢・活動的視点、( 4 )摂食状況・食物形態・栄養的視点の 4 つで構成されます。13 項目を同じ尺度で並べることで、「嚥下だけ」では見えにくい条件依存の問題が浮かび上がります。 [oai_citation:1‡J-STAGE](https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/58/4/58_58.561/_pdf)
| 視点 | 項目(例:要約) | 臨床での読み替え |
|---|---|---|
| 心身の医学的視点 | 食べる意欲/全身状態/呼吸状態/口腔状態 | 「食べられる土台」が整っているか |
| 摂食・嚥下の機能的視点 | 食事中の認知/咀嚼・送り込み/嚥下 | 口腔準備〜咽頭期のどこで詰まるか |
| 姿勢・活動的視点 | 姿勢・耐久性/食事動作/活動 | 姿勢保持と“食べ続ける体力” が足りているか |
| 摂食状況・食形態・栄養的視点 | 摂食状況レベル/食物形態/栄養 | 安全域(形態・量・介助)と摂取の確保 |
実施の手順(カンファで“回る形” にする)
現場で KTBC を “回る仕組み” にするコツは、評価 → 共有 → 介入 → 再評価を同じ会議体(または同じ記録様式)で繰り返すことです。KTBC は、時間経過で弱点の変化を追う運用と相性が良いとされています。 [oai_citation:2‡シュプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1447-x)
- 前提条件を固定:覚醒・座位・口腔ケアの有無・食事時間帯など、比較に必要な条件をそろえます。
- 13 項目を評価:多職種で分担し、根拠(観察事実)を添えて入力します。
- レーダーチャートで可視化:低い項目=介入の優先候補、高い項目=強み(維持・活用)として扱います。 [oai_citation:3‡シュプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1447-x)
- 介入を “束ねて” 決める:姿勢・口腔・呼吸・形態・介助・活動配分をセットで設計します。
- 再評価のタイミングを決める:食形態変更、義歯調整、発熱・肺炎の前後、ADL 変化など “条件が変わるとき” を合図にします。
スコアを “計画” に落とすコツ(低い所だけを直さない)
KTBC は “弱点を上げる” だけでなく、強みで弱点をカバーする発想を取り入れると、現実的な計画になります。たとえば、嚥下の項目が低いときでも、姿勢・耐久性や口腔状態が整うだけで安全域が広がるケースがあります。
| 見えた課題 | 起きやすい落とし穴 | 束ねる介入(例) | 再評価の観点 |
|---|---|---|---|
| 呼吸状態が不安定 | 水分や形態の変更だけで押し切る | 呼吸介入+休息挿入+食事ペース調整+座位安定 | 食後の呼吸数/湿性嗄声/ SpO_{2} 変化 |
| 姿勢・耐久性が低い | 訓練だけ増やして食事条件は固定のまま | 座位再建(骨盤・体幹・頭頸部)+食事時間の再設計 | 後半で崩れるか/むせ・残留が増えるか |
| 口腔状態が悪い | 嚥下訓練のみで進める | 食前口腔ケア+保湿+義歯適合の確認 | 声の湿り/口腔内残留/食事のしやすさ |
| 栄養が不足 | 安全優先で量が確保できない | 形態・一口量・回数を調整し摂取量の底上げ(栄養連携) | 摂取量/体重変化/食事時間の負担 |
記録のポイント(“条件” と “次の一手” を残す)
KTBC の運用で差が出るのは、点数より記録の粒度です。「できる/できない」ではなく、何がそろえばできるかを残すと、次回の再現性が上がります。
- 成立条件:座位(骨盤・頭頸部)、覚醒、食前口腔ケア、食具、一口量、食事時間帯
- 観察事実:むせ、湿性嗄声、反復嚥下、呼吸変化、食後の疲労、口腔内残留
- 担当と期限:誰が・何を・いつまでに(例: 1 週で再評価)
現場の詰まりどころ・よくある失敗
KTBC は便利ですが、運用が雑だと “作って終わり” になります。失敗パターンはほぼ決まっているので、先に潰しておくと回り始めます。
| 失敗 | 原因 | 対策 | 一言テンプレ(例) |
|---|---|---|---|
| 点数は付いたが計画が変わらない | 低い項目の “次の一手” が決まっていない | 低い項目は必ず「介入 1 つ+再評価条件 1 つ」をセット化 | 「低値:姿勢・耐久性 → 座位再建+食事時間短縮、 1 週で再評価」 |
| 担当が不明で進まない | 多職種ツールなのに “誰がやるか” が抜ける | 項目ごとに主担当を決め、会議で合意する | 「口腔:看護主、形態:栄養・ ST、座位: PT/OT」 |
| 前回と比較できない | 座位・覚醒・口腔など条件が毎回違う | 成立条件を記録し、比較するときは条件をそろえる | 「骨盤前傾保持+頸部中間位、食前口腔ケア後に実施」 |
| 弱点ばかり直して疲弊する | 強み(高い項目)を活用できていない | 高い項目は “維持戦略” を置き、弱点を補う設計にする | 「強み:食べる意欲は高い → ペース調整で量を確保」 |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. KTBC と KT index は同じものですか?
A. 近い概念ですが、運用のされ方が異なる文脈で語られることがあります。KT index は 13 項目で包括的に評価し、低い項目を中心に介入計画と再評価を回す枠組みとして報告されています。 [oai_citation:4‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27996109/?utm_source=chatgpt.com)
Q2. いつ評価すればいいですか?(頻度の目安)
A. “日付で固定” より、条件が変わったときが合図です。食形態変更、義歯調整、発熱・肺炎の前後、ADL 変化、薬剤変更などで再評価すると、介入の当たり外れが見えやすくなります。 [oai_citation:5‡シュプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1447-x)
Q3. 点数が低い項目が多すぎて、何からやればいいですか?
A. まずは呼吸・覚醒・姿勢・口腔など「食べる土台」を優先し、次に一口量・ペース・形態など “条件調整” を入れるのが現実的です。その上で訓練要素(耐久性、協調性)を積み上げると転びにくいです。
Q4. VE / VF があるのに KTBC は必要ですか?
A. 必要性は目的次第です。VE / VF は誤嚥や残留などを直接確認できますが、KTBC は介入設計と共有(姿勢・活動・栄養を含めた優先順位づけ)に強みがあります。検査所見を “チームで回る計画” に落とす補助線として使うと効果が出やすいです。 [oai_citation:6‡シュプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1447-x)
参考文献
- Maeda K, Shamoto H, Wakabayashi H, et al. Reliability and Validity of a Simplified Comprehensive Assessment Tool for Feeding Support: Kuchi-Kara Taberu Index. J Am Geriatr Soc. 2016;64(12):e248-e252. doi: 10.1111/jgs.14508 / PubMed: 27996109 [oai_citation:7‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27996109/?utm_source=chatgpt.com)
- Aruga Y, et al. Nursing care using KT (Kuchi-kara Taberu) index radar chart for dysphagia: (article). Jpn J Nurs Sci (SAGE platform). doi: 10.1177/2010105817740374 [oai_citation:8‡SAGE Journals](https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2010105817740374?utm_source=chatgpt.com)
- Shamoto H, et al. The effects of promoting oral intake using the Kuchi-kara Taberu index in older pneumonia patients: a cluster randomized controlled trial. BMC Geriatrics. 2020. doi: 10.1186/s12877-020-1447-x [oai_citation:9‡シュプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-020-1447-x)
- Hidaka Y, et al. A Comprehensive Oral Intake Evaluation Tool (the Kuchi-kara Taberu Index): (article). Gerontol Geriatr Med. 2022. doi: 10.1177/23337214221090284 [oai_citation:10‡SAGE Journals](https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/23337214221090284?utm_source=chatgpt.com)
- Dziewas R, Michou E, Trapl-Grundschober M, et al. European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia. Eur Stroke J. 2021. PubMed: 34746431
- DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water swallow test for aspiration following stroke. Arch Neurol. 1992;49(12):1259-1261. doi: 10.1001/archneur.1992.00530360057018
- 小口和代, 才藤栄一, 水野雅康, 他. 機能的嚥下障害スクリーニングテスト「反復唾液嚥下テスト」( RSST )の検討( 1 )正常値の検討. リハビリテーション医学. 2000;37(6):375-382. doi: 10.2490/jjrm1963.37.375
著者情報
 rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
おわりに
KTBC は、条件確認 → 13 項目の見える化 → 弱点に合わせた“束ね介入” → 再評価のリズムで回すほど、チームの意思決定が速くなります。面談準備チェックと職場評価シートで学びを実装に落とし込めるので、必要なら /mynavi-medical/#download もあわせて活用してみてください。