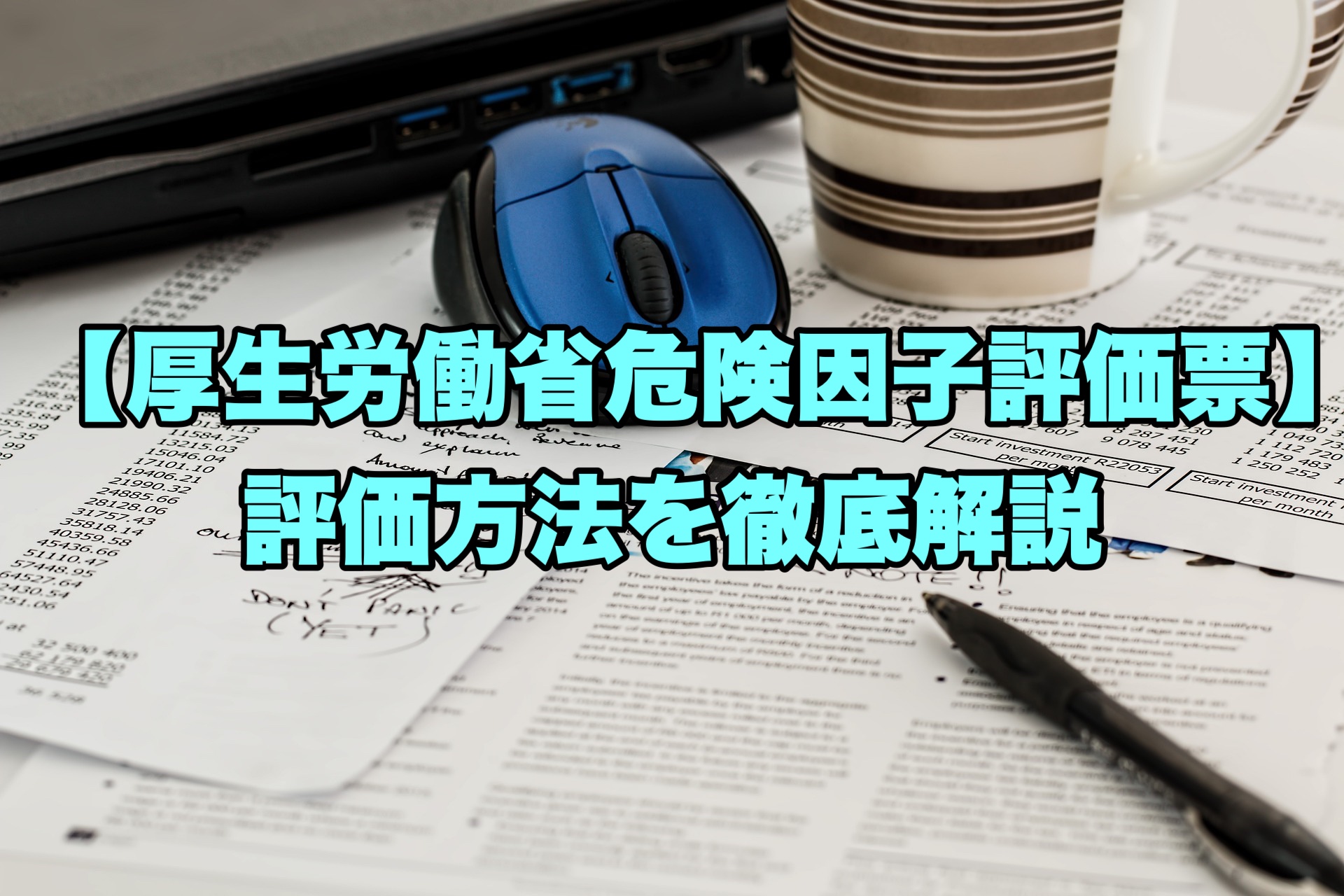危険因子評価票の位置づけ(結論)
厚生労働省が示す「褥瘡に関する危険因子評価票」(いわゆる 褥瘡 危険因子評価表)は、ADL 自立度 B/C の患者さんを対象に、褥瘡発生リスクを 二者択一(あり/できない)で素早くふるい分けするスクリーニングです。 1 項目でも該当 したら褥瘡予防の計画立案へ直結します。本稿では「 8 項目 」の要点、実施タイミング、評価後の運用までを PT 視点で整理します。
本票(厚生労働省 危険因子評価)は「誰に」「いつ」「どう判定し」「次に何をするか」を明確にする院内標準です。対象は ADL 自立度 B/C、判定は 8 項目の二者択一で、 1 項目でも該当なら看護計画や診療計画書の作成に進みます。点数合算は不要で、迅速に介入へ橋渡しできるのが最大の強みです。
関連:褥瘡予防の全体像(皮膚観察→リスク評価→除圧/体位変換→寝具→栄養→再評価)は 褥瘡予防の基本フロー(総論) にまとめています。
危険因子評価票とは?(厚生労働省の公式様式)
「危険因子評価票」は、厚生労働省が提示する「褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書」一式の中で、褥瘡発生リスクの有無をチェックするための 1 枚です。ベースラインのリスクを確認し、必要に応じて褥瘡予防計画・診療計画書・看護計画へつなぐトリガーとなる位置づけです。
ブレーデンスケールのように詳細なスコアリングを行うツールとは異なり、危険因子評価票は 「高リスク群(ADL 自立度 B/C)」に絞って二者択一で確認するシンプルな様式です。そのため、新人スタッフでも運用しやすく、病棟全体で標準化したい場面に向いています。
対象と評価タイミング
対象は原則として ADL 自立度 B/C です。入院時・術後・全身状態の変化時・長期臥床化の兆候・失禁管理の変更時など、リスクが動きやすい局面で実施します。観察と同時に体位変換の可否・除圧の自立度・皮膚所見をセットでまとめると、その後の計画立案が速くなります。
頻度は病棟の標準手順に合わせます。急性期では短い間隔(例: 48 時間ごと)、慢性期・療養では週 1 回程度の見直しが実務的です。スクリーニング結果は電子カルテで即共有し、多職種のタスクリストへ反映します。
危険因子評価票の「点数」と判定の考え方
褥瘡危険因子評価表 点数を知りたくて検索された方も多いと思いますが、厚生労働省の 危険因子評価票は点数合算を行わない設計です。各項目は「あり/できない」で判定し、 1 項目でも該当すればハイリスクとして扱い、褥瘡予防計画や診療計画書の作成に進む、というルールになっています。
ブレーデンのように合計点でリスクを段階づける方式と異なり、危険因子評価票はそもそも対象を ADL 自立度 B/C に絞ったうえで、「迷わず介入へ進めること」を優先した トリガー型のスクリーニングです。「何点なら安全か」を議論するより、該当項目ごとに体圧分散・離床・栄養・失禁ケアなどの具体的対策へ落とし込むことが重要になります。
よくある間違い(点数化/対象/“あり”の解釈)
危険因子評価票は「点数で段階づける評価」ではなく、該当項目を見つけたら迷わず対策へ進む“トリガー型”です。下の OK/NG をチームで共有しておくと、評価者が変わってもブレにくくなります。
| NG(ありがち) | なぜ危険? | OK(正しい整理) | 記録フレーズ例(短く) | 次アクション |
|---|---|---|---|---|
| 「合計何点?」を探して点数化する | 点数に意識が向き、該当項目ごとの対策が遅れる | 点数合算はしない。 1 項目でも該当=ハイリスク として計画へ | 危険因子:体位変換×/湿潤○ → 計画へ反映 | 褥瘡予防計画・診療計画書の作成/更新 |
| 対象(寝たきり度)を外して、全患者に漫然と実施 | 対象外が混ざると、病棟の優先順位付けが崩れる | 原則は ADL 自立度 B/C でスクリーニング | 対象:B(寝返り・座位除圧に介助) | 対象・タイミングを病棟手順で明文化 |
| 「あり」でも“チェックしただけ”で終わる | 評価が計画につながらず、褥瘡予防が属人化する | 該当項目を問題・目標・ケア内容・期限に翻訳する | 問題:殿部湿潤/対策:交換頻度を統一 | 担当割り振り+ 48 時間以内に効果判定 |
| “あり”の根拠が書かれていない(申し送りで再現できない) | 次の担当が状況をイメージできず、介入が続かない | 「観察事実+意味づけ」を 1 行で残す | 仙骨の圧集中+座り直し不可 → 除圧頻度を上げる | 観察指標(皮膚所見・疼痛・活動量)をセットで記録 |
判定がぶれやすい項目:判断の具体例(院内標準のたたき台)
危険因子評価票は二者択一のため、判定基準が曖昧だと「人によって○×が変わる」状態になります。まずは迷いやすい項目だけ、病棟で“判断の言葉”を揃えておくのがおすすめです。
| 項目 | 迷いどころ | 観察のそろえ方(例) | 記録フレーズ例 |
|---|---|---|---|
| 基本的動作能力 | 「できる/できない」の境目が人で変わる | 寝返り・座り直し・端坐位保持を“介助量と頻度”で表現して揃える | 寝返り:全介助/座り直し:自力不可、 30 分毎に介助 |
| 栄養状態低下 | 「低栄養っぽい」の主観で割れる | 摂取量低下・体重減少・検査値など、根拠を 1 つ以上セットで残す | 摂取 5 割以下が継続+体重減少 → 低栄養疑い |
| 皮膚湿潤 | 失禁があっても「皮膚は大丈夫」に見える | 湿潤は“現時点の皮膚所見”だけでなく、持続時間・交換間隔で判断を揃える | 失禁あり、殿部湿潤が持続 → 交換間隔を短縮 |
| 皮膚の脆弱性(浮腫) | 浮腫の程度が曖昧 | 浮腫による皮膚緊張+ずれ/摩擦の起点(移乗・更衣・端坐位)をセットで確認 | 下肢浮腫+皮膚緊張あり、移乗でずれやすい |
| 皮膚の脆弱性(スキンテア) | 既往の扱い、保護が必要な場面が曖昧 | 保有/既往に加えて、発生場面(更衣・移乗・シーツずれ)を 1 つ特定して対策へ | スキンテア既往あり、更衣で牽引 → 滑走面+保護材 |
8 項目の判定と PT 視点のポイント
| 項目 | 判定のめやす(あり/できない) | PT 視点の補足 |
|---|---|---|
| 基本的動作能力 | 寝返り・座り直し・端坐位保持などに自立不可 | 座り直しの 頻度 と 手がかり を観察。座面・足台・背支持の調整で自力除圧を促進。 |
| 病的骨突出 | 仙骨・腸骨・踵などの突出で圧集中が懸念 | 接触面の圧集中部を同定し、クッション配置と体位バリエーションを即日指示。 |
| 関節拘縮 | 体位変換・座位保持を制限する拘縮あり | 短期:ポジショニング固定/中長期:伸張・駆動域確保とハンドリング教育。 |
| 栄養状態低下 | 食思不振・摂取不足・体重減少・低栄養疑い | 栄養士と連携し、摂取記録・補助食品・蛋白摂取の最適化を提案。 |
| 皮膚湿潤 | 多汗・尿失禁・便失禁で皮膚が持続的に湿潤 | 吸収パッド・通気・シート素材の選択と交換頻度の標準化を支援。 |
| 皮膚の脆弱性(浮腫) | 浮腫により皮膚張力が高く損傷リスク高い | 下肢挙上・弾性着衣・離床頻度増で循環改善。ずれ・摩擦の最小化を指導。 |
| 皮膚の脆弱性(スキンテア) | スキンテアの保有・既往あり | 移乗・更衣時の牽引回避、滑走面活用、保護材の使用を標準手順に組み込む。 |
| その他の危険因子 | せん妄・発熱・鎮静・麻痺などで除圧困難 | 看護・医師と共同で一時的な体圧分散強化(マットレス選定・体位計画)。 |
評価後の計画立案フロー
二者択一の結果はゴールではなくスタートです。該当項目を介入方針・担当・期限に落とし、日次でモニタリングします。体位変換表・離床スケジュール・皮膚観察記録・マットレス選定を 1 枚の計画に束ねると、属人性が下がり実行率が上がります。
PT は「体位変換ができる身体づくり」と「座面環境の規格化」を両輪で進めます。評価票は“チェック”で止めず、該当した危険因子を具体的なケア手順(除圧・離床・寝具・失禁ケア・栄養)へ変換して運用します。
診療計画書・褥瘡予防計画への落とし込み例
「厚生労働省 危険因子評価票」は単独で完結せず、診療計画書・褥瘡予防計画書・看護計画の各欄にどう反映するかが重要です。該当した危険因子を「問題」「目標」「ケア内容」「評価期間」にマッピングすると、多職種で共有しやすくなります。
| 危険因子の例 | 診療計画書の「問題」記載例 | 代表的なケア・リハ介入 |
|---|---|---|
| 基本的動作能力低下 | 自力による体位変換・座り直しが困難で、長時間同一体位となる | 2 時間ごとの体位変換、離床スケジュール、座位保持訓練、自力除圧動作の練習 |
| 皮膚湿潤(失禁) | 尿失禁により殿部皮膚が持続的に湿潤し、褥瘡リスクが高い | 失禁ケアの見直し、パッド選択と交換頻度の標準化、皮膚保護剤の使用 |
| 皮膚の脆弱性(浮腫) | 下肢浮腫と皮膚脆弱性により、ずれ・摩擦で損傷しやすい | 下肢挙上、弾性ストッキング、移乗時のスライディングシート使用、体圧分散マットレス導入 |
| その他の危険因子(せん妄) | せん妄により安静保持が困難で、除圧指示の自己管理ができない | 環境調整、体圧分散の強化、多職種での観察強化 |
このように、危険因子評価票の結果を 診療計画書の文章とケア内容に翻訳しておくことで、褥瘡予防の具体的なタスクが明確になり、看護・リハ・栄養など多職種での実行率が高まります。
PT の関与ポイント
( 1 )座位保持・座り直しの自立化、( 2 )関節可動域の維持と短時間反復、( 3 )ポジショニングとクッション配置の標準化、( 4 )移乗・寝返りの手順教育、( 5 )リスク変動の早期検知。この 5 本柱で「自力除圧能力」を底上げします。
実施例: 1 日 3 回の座り直し訓練+クッション再配置点検を 1 セットとして病棟と共通言語化。 48 時間で効果が乏しければプランを更新します。
他スケールとの使い分け
ブレーデンは包括的で点数式、OH は個体要因に特化、本票は二者択一で 行動決定 を加速します。病棟の人員・用具配分では併用が合理的なケースもあります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 厚生労働省の危険因子評価票は「合計点」で判定しますか?
A. 合計点での段階づけは行いません。各項目を「あり/できない」で判定し、 1 項目でも該当すればハイリスク として褥瘡予防計画や診療計画書の作成・更新へ進む整理が実務的です。
Q2. 対象は誰ですか?(寝たきり度 A や J もやりますか?)
A. 原則の対象は ADL 自立度 B/C です。対象外まで広げると病棟内の優先順位が崩れやすいので、対象と実施タイミングは病棟手順として明文化しておくのがおすすめです。
Q3. いつ再評価すればいいですか?
A. 病棟の標準手順に合わせつつ、急性期は短い間隔(例: 48 時間ごと)で見直し、慢性期・療養では週 1 回程度の見直しが実務的です。介入後は「皮膚所見・疼痛・活動量」などの観察指標を決め、少なくとも 48 時間以内に効果判定の期限を置くと回りやすくなります。
Q4. 判定がブレるのが不安です。最低限そろえるなら何を統一しますか?
A. まずは「基本的動作能力(寝返り・座り直し・端坐位)」「皮膚湿潤」「栄養状態低下」の 3 つを、介助量・頻度/持続時間・交換間隔/根拠(摂取・体重など)で書くルールにすると、病棟内でブレが減りやすいです。