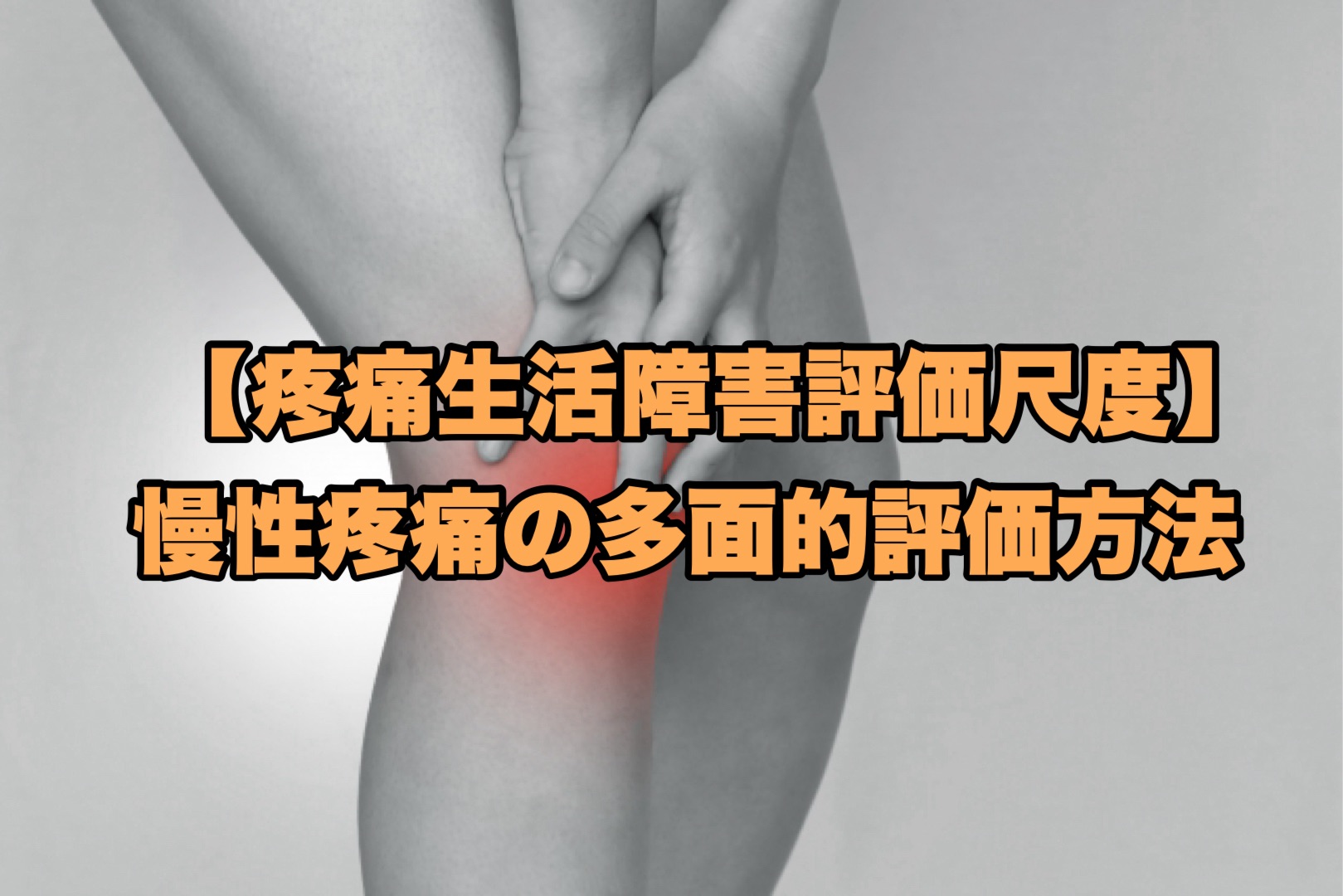PDAS(疼痛生活障害評価尺度)とは?
結論:PDAS( Pain Disability Assessment Scale /疼痛生活障害評価尺度)は、慢性疼痛が日常生活にどの程度の支障をきたしているかを 20 項目で評価する、日本発の患者報告式尺度です。過去 1 週間の生活を振り返り、各項目を 0〜3 点で回答し、合計 0〜60 点で生活障害の重症度を把握します。
関連:疼痛の評価|NRS・VAS・VRS・FPS-R・BPI の実践ガイド
なお、PDAS は痛みそのものの「強さ」ではなく「生活障害(痛みによる活動・参加の低下)」を測る尺度です。痛み強度( NRS / VAS )や心理社会的要因(例: PCS 、 PHQ-4 )と組み合わせると、慢性疼痛の評価を多面的に整理しやすくなります。
PDAS の評価方法(やり方)と基本仕様
PDAS は自己記入式で、外来フォローアップの経時変化モニタリングにも向きます。まずは「評価の条件」と「採点ルール」をそろえるのがコツです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 項目数 | 20 項目(生活動作・移動・家事・社会生活など) |
| 評価期間 | 主に「過去 1 週間」の日常生活を振り返って回答 |
| 採点 | 各 0〜3 点( 0 :困難なし〜 3 :実施不能) |
| 合計点 | 0〜60 点(高得点ほど生活障害が大きい) |
| 実施時間 | おおよそ 2〜3 分(自己記入式) |
| 点数の扱い方 | 単回の合計点+「どの項目が高いか」をセットで読む(目標設定に直結) |
臨床報告では、スクリーニング上の実務目安として 「 10 点以上」を生活障害ありの目安として扱う記述がみられます。ただし、対象の重症度や目的により、単純な閾値よりも「再評価での推移」や他尺度との整合性を重視した方が妥当な場面も少なくありません。
構成項目とカバーする生活機能
PDAS は、慢性疼痛患者の「身体活動と移動能力」を中心に開発された尺度です。20 項目はおおまかに次のような生活領域をカバーします。
- 腰や下肢を使う動作:しゃがむ・持ち上げる・立ち上がるなど
- 基本的な ADL :身の回り動作、入浴、衣服の着脱など
- 移動・外出:歩行、階段昇降、公共交通機関の利用など
- 家事・役割:掃除、買い物、家事全般といった家庭内役割
- 社会生活・余暇:仕事、余暇活動、対人場面での参加度
このように PDAS は「痛みの部位」には依存せず、部位を問わず共通する生活障害(活動・参加)の程度を測れるのが特徴です。腰痛や頚部痛だけでなく、広範な慢性痛に横断的に使えるため、集学的治療やリハビリテーションプログラムのアウトカムにも適しています。
採点と解釈:合計点より「困りごと項目」を読む
PDAS は 0〜60 点で、高いほど生活障害が強いと解釈します。実務では「合計点」だけでなく、高得点の項目がどれかを読み解いて、目標設定に落とし込むのがポイントです。
- 合計点:生活障害の全体量(介入の必要度や負荷調整の目安)
- 高得点項目:優先課題の候補(例:通勤、家事、階段、余暇)
- 同点の並び:「動作」中心か「参加」中心か(介入の軸の選択)
たとえば「 NRS は高いが PDAS は低い」場合、痛みは強いものの生活全体の制限はまだ軽い可能性があります。逆に「 NRS は軽めでも PDAS が高い」場合は、回避行動、活動量低下、生活背景の負荷など、生活障害を増やす要因の見直しが必要になることがあります。
再評価の見方:点数の推移を“生活の変化”に翻訳する
PDAS は単回の点数よりも、同じ条件で繰り返し測って推移を見ることで価値が上がります。再評価では、合計点の増減に加えて、次の 3 つをセットで確認すると解釈がぶれにくくなります。
- 高得点項目が入れ替わったか:困りごとの焦点が移動していないか
- 目標行動が増えたか:できる活動が広がったか(頻度/時間/距離)
- NRS や情動尺度と整合するか:痛み強度だけで説明できない変化がないか
慢性疼痛では「痛みが少し残っても生活が広がる」ことが重要なアウトカムになります。PDAS の推移を、そのまま患者さんの行動目標(何を、どれくらい、いつまでに)に結びつけて共有できると、介入の納得感が高まりやすくなります。
他尺度との組み合わせ(推奨バンドル)
PDAS 単体では「生活障害」の側面が中心になります。実務では、次のような組み合わせで評価すると、介入の方針が立てやすくなります。
- 痛み強度:NRS( 0〜10 )や VAS で主観的な痛みの強さを把握
- 破局化思考:PCS で「痛みに対する考え方」の偏りを把握
- 情動:PHQ-4 など短縮版で不安・抑うつをスクリーニング
- 部位特異的尺度:腰痛なら RDQ などを補助的に使用
たとえば「 NRS は大きく変わらないが PDAS が改善」している場合、「痛みは残るが生活は広がっている」を説明できます。一方「 NRS は改善しているのに PDAS が下がらない」場合は、回避行動や生活背景がボトルネックになっている可能性があり、教育・曝露・環境調整などアプローチの軸を切り替える判断材料になります。
臨床ワークフロー(初診〜フォロー)
外来で PDAS を使うときの流れを、理学療法の視点で 4 ステップに整理します。
- 初診評価:PDAS + NRS + PHQ-4(必要に応じ PCS )を実施し、「戻したい活動」を 1〜3 個の行動目標として共有します。
- 介入デザイン:教育(痛みの捉え方・回避行動の整理)+運動(有酸素・筋力)+動作練習を組み合わせ、PDAS で高得点だった場面から課題設定します。
- フォローアップ:2〜4 週ごとに PDAS と NRS を再測定し、生活障害が続く場合は睡眠、活動量、仕事の負担、ストレスなども含めて再分析します。
- 連携:PDAS の推移をもとに、多職種で目標と課題を共有し、必要に応じて支援を組み合わせます。
理学療法での使いどころと患者説明のコツ
理学療法士の立場では、PDAS を単なるスコアではなく「会話のきっかけ」として活用すると有用です。得点が高かった項目を一緒に眺めながら、「どの場面が一番困っていますか?」「どこから改善していけると良さそうですか?」と問いかけると、価値観や優先順位が見えやすくなります。
また「今日は痛みの強さだけでなく、痛みのせいで生活がどこまで制限されているかも確認しましょう」と前置きして PDAS を使うと、「痛みがゼロでなくても生活が広がれば前進」というゴールを共有しやすくなります。
実務での注意点(回答条件・欠損・読み違いの防止)
- 条件をそろえる:評価期間(過去 1 週間)と回答の前提(普段の生活/最近の特別な出来事)をそろえ、再評価も同じ説明で行います。
- 欠損の扱い:未回答がある場合は合計点だけで判断せず、未回答理由(実施機会がない/理解が難しい/別の支援が必要)を確認します。
- 点数だけで結論を出さない:同じ合計点でも「困りごと項目」が違えば介入の優先順位は変わります。
- 自己記入が難しい場合:視力、認知、疲労などで回答が難しいときは、負担の少ない尺度や面接中心の評価へ切り替えます。
おわりに:PDAS で慢性痛リハの“焦点”をそろえる
PDAS は、慢性疼痛が「どの場面の生活をどれくらい妨げているか」を共通言語で確認できる、コンパクトで実用的な尺度です。説明を統一 → 条件をそろえて記録 → 推移を見て再評価の流れを回すと、教育・運動・環境調整の優先順位がはっきりし、チーム内での目標共有もしやすくなります。
評価の“型”が整うほど、学び続けやすい職場かどうかの見極めもスムーズになります。見学や面談で使える「面談準備チェック( A4 ・ 5 分)」と「職場評価シート( A4 )」を公開しているので、必要なタイミングで印刷して活用してみてください。ダウンロードページを見る。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
PDAS はどのような慢性疼痛患者さんに使うと効果的ですか?
主な対象は、 3 か月以上続く慢性腰痛・頚部痛・肩痛・線維筋痛症などの運動器慢性痛ですが、部位を限定せず「痛みが生活にどれだけ影響しているか」を幅広く把握したいときに使えます。一方で、急性期の鋭い痛みや、自己記入が難しい場合には、他の評価法を優先した方がよい場面もあります。
PDAS が高かったとき、どのように対応を考えればよいですか?
まずは「どの項目が高いか」を確認し、患者さんの優先度が高い活動(例:通勤、家事、趣味)を 1〜3 個に絞って行動目標にします。点数だけで判断せず、 NRS や PCS 、 PHQ-4 などと組み合わせて、目標達成を妨げている要因(回避行動、活動量低下、睡眠、ストレス)も整理すると介入の方向性が定まりやすくなります。
PDAS と PDI や RDQ などの生活障害尺度はどう使い分ければよいですか?
PDAS は慢性疼痛全般に使える汎用的な生活障害尺度です。PDI は国際的に広く用いられる尺度、RDQ は腰痛に特化した尺度です。国内の外来ではまず PDAS で全体像をつかみ、研究や国際比較が必要な場面では PDI 、腰痛に焦点を絞る場合は RDQ を併用する、といった使い分けが実務的です。
参考文献
- 有村達之, 小宮山博朗, 細井昌子. 疼痛生活障害評価尺度の開発. 行動療法研究. 1997;23(1):7–15. DOI
- Yamashiro K, Arimura T, Iwaki R, et al. A multidimensional measure of pain interference: reliability and validity of the Pain Disability Assessment Scale. Clin J Pain. 2011;27(4):338–343. DOI
- Takahashi N, et al. Multidisciplinary pain management program for patients with chronic pain. J Pain Res. 2019;12:2563–2576. DOI
- 阿瀬千咲, 他. 慢性痛の治療効果における疼痛生活障害度尺度( PDAS )の変化量の検討. 日本ペインクリニック学会誌. 2024;31(6):99–105. DOI
- Yamada K, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the Pain Disability Assessment Scale in patients with chronic pain. PLOS ONE. 2022;17(9):e0274445. DOI