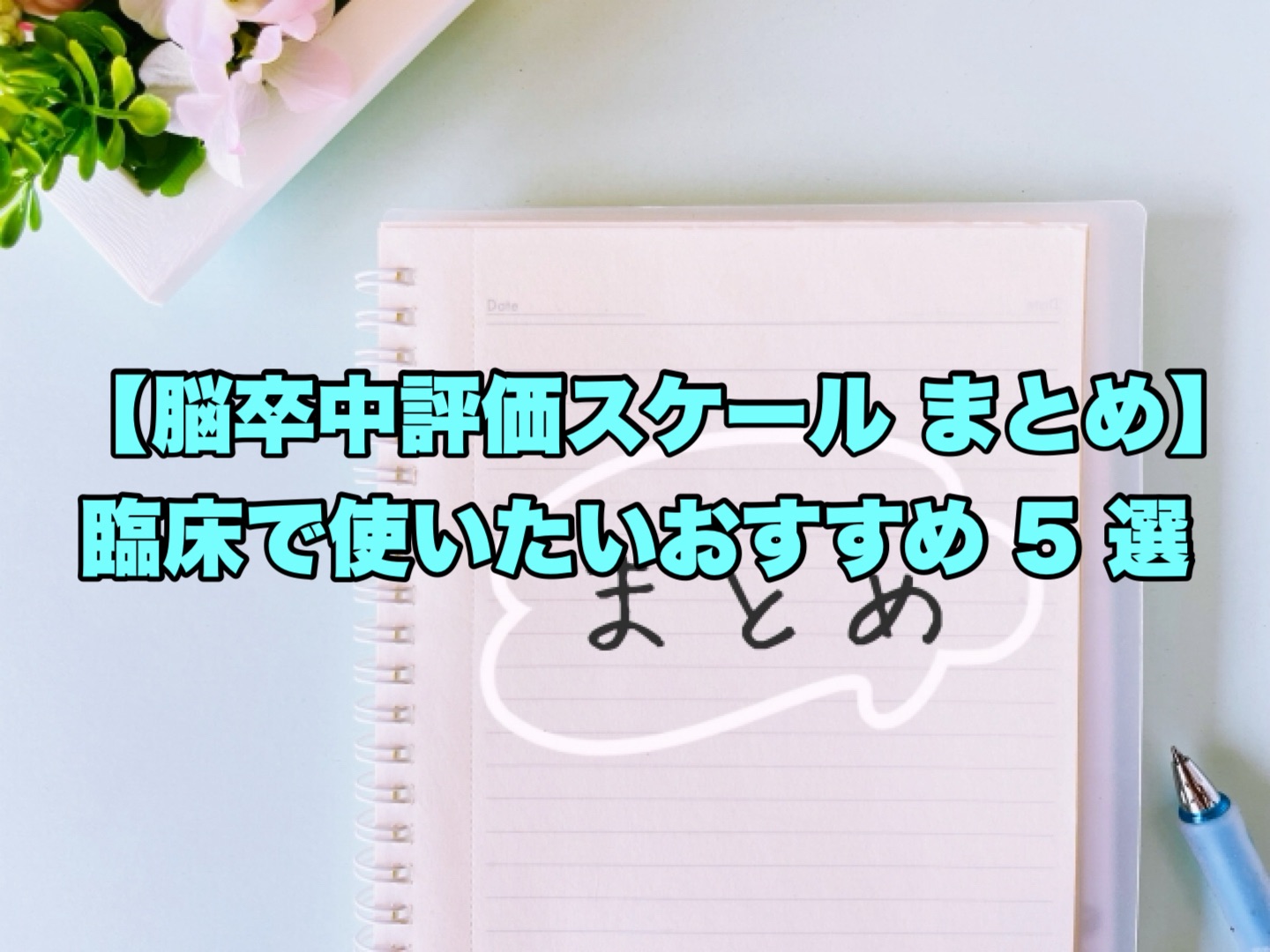この記事でわかること(結論)
脳卒中の評価スケールは「どれが有名か」ではなく、いま判断したいこと(重症度/麻痺・運動/体幹/機能)から選ぶと迷いません。本記事では、臨床で使いやすい代表的スケールを 5 つに絞り、使いどころ・取り方のコツ・組み合わせ例までをまとめます。
結論としては、入院早期は “重症度+体幹”、回復期以降は “麻痺・運動+体幹+機能” を軸に、同じセットで繰り返し(再評価)できる形にしておくと、記録がそのまま介入設計に直結します。
脳卒中評価は「病期の目的」から逆算するとブレません
急性期〜入院直後は、まず 全身状態と神経学的な重症度を把握し、「どれくらい危ないか」「どれくらい変化しやすいか」を共有するのが優先です。そのうえで、移乗・座位が安全に回るかを左右する 体幹機能を早期に押さえると、離床計画が立ちやすくなります。
回復期〜生活期では、麻痺・運動機能の質(回復段階・分離運動・協調)と、ADL・移動などの 機能をセットで追うと、介入の焦点(筋力/協調/課題指向/環境調整)が明確になります。
選び方の結論:スケールは「判断したいこと」で 3 群に分けます
おすすめの考え方はシンプルで、①重症度(全体像)、②麻痺・運動(質と回復段階)、③体幹・機能(移乗・歩行の土台)の 3 群に分けて “主役を 1 つずつ” 決めることです。闇雲に数を増やすより、少数を定点観測した方が、チーム内の共通言語になります。
本記事の 5 選は、上の 3 群をできるだけ偏りなくカバーしつつ、臨床で “取り切れる” 現実感を優先して選びました。
現場の詰まりどころ:点数が「記録で終わる」ときに起きていること
評価が活きない最大の原因は、点数の変化を “次の介入” に翻訳できていないことです。下の表のどれかに当てはまる場合、セットの再設計(主役の整理・測定条件の統一)だけで、評価の価値が一気に上がります。
| よくある詰まり | 起きていること | その場での修正 |
|---|---|---|
| 毎回スケールが違う | 比較できず、介入の意思決定が “感覚” に寄る | 主役を 3 群で 1 つずつ固定(重症度/運動/体幹・機能) |
| 条件がバラバラ | 介助量・装具・薬効で点が揺れる | 測定条件(装具・杖・介助)を記録して統一 |
| 点数だけ書いて終わる | 次の練習課題が決まらない | “どこで落ちたか” を 1 行で言語化(例:座位保持/選択運動/協調) |
脳卒中評価スケールおすすめ 5 選(使いどころとコツ)
1)JSS( Japan Stroke Scale ):急性期の “全体像” を短時間で共有
JSS は、脳卒中の重症度を定量化して共有するためのスケールです。急性期のカンファレンスで「どれくらい重いか」「変化が起きていないか」を把握するのに向きます。“同じタイミング”(例:朝の診察前/リハ介入前)に取り、変動要因(鎮静・疼痛・発熱など)を併記すると、経時比較が安定します。
コツは、JSS の値そのものよりも、前回からの変化を “臨床判断” に繋げることです。数値が悪化していれば、離床の負荷設定や観察項目(呼吸循環・意識・再発兆候)を強める根拠になります。
2)SIAS( Stroke Impairment Assessment Set ):障害像を “抜けなく” 押さえる総合セット
SIAS は、運動・感覚・体幹・視空間・言語など、脳卒中の障害(impairment)を広くカバーする評価セットです。新人が「何を見落としやすいか」を学ぶ枠組みとしても優秀で、チームの共通フォーマットとして運用しやすいのが強みです。
運用のポイントは、“全部を毎回フルでやる” のではなく、初回で全体像を取り、以後は介入に直結する項目(例:体幹・下肢運動・視空間など)を主に追うことです。目的が “移乗の自立” なら体幹と下肢、目的が “上肢実用” なら上肢運動と感覚の変化を軸に追うと、記録が戦略になります。
3)FMA( Fugl-Meyer Assessment ):分離運動・協調など “運動の質” を段階的に見える化
FMA は、脳卒中後の運動麻痺を中心に、反射・共同運動・分離運動・協調などを段階的に評価できる代表的スケールです。「なぜ ADL が伸びないのか」を、筋力だけでなく運動制御の観点から説明しやすく、介入目標(共同運動から分離へ、協調の質の改善へ)を作りやすいのがメリットです。
注意点は、項目数が多く測定負荷が高いことです。現場では、上肢/下肢のどちらを主軸にするかを決め、測定日を固定(例:週 1 回)するだけでも回しやすくなります。
4)Brunnstrom 回復段階( BRS ):回復の “段階” を手早く共有するショートカット
BRS は、麻痺の回復過程を段階として把握する考え方で、短時間で “いまどの段階か” を共有しやすいのが利点です。ベッドサイドや家屋調査など、時間が限られる場面でも使いやすく、チーム内の共通言語になりやすい評価です。
ただし、段階が同じでもできる動きの質は個人差があります。BRS を主役にする場合ほど、どの課題で詰まっているか(例:体幹固定/分離運動/スピード)を、別の観察(課題動作・動画)で補うと解像度が上がります。関連:Brunnstrom と FMA の違い(比較・使い分け) にも整理しています。
5)FACT( Functional Assessment for Control of Trunk ):座位〜移乗の “土台” を早期から定点観測
FACT は、脳卒中後の体幹機能を評価するツールです。座位保持・体幹のコントロールが崩れていると、立ち上がりや歩行だけでなく、上肢のリーチや更衣にも波及します。急性期〜回復期の早い段階から追うことで、離床のリスク管理と、体幹介入の優先順位づけがしやすくなります。
運用のコツは、測定条件(足底接地・ベッド高さ・介助の入れ方)を揃えることです。条件が揃うと、点数の変化がそのまま “次に上げる負荷” の根拠になります。
5 スケールの早見表(どれを「主役」にするか)
※横にスクロールできます。
| スケール | 主に見る領域 | おすすめ病期 | 強み | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| JSS | 重症度(全体像) | 急性期 | 短時間で共有しやすい | 測定タイミングを固定しないと揺れやすい |
| SIAS | 障害像(運動・感覚・体幹など) | 急性期〜回復期 | 抜け漏れ防止・チーム運用に強い | 目的に合わせて “追う項目” を絞る |
| FMA | 運動麻痺(質・分離運動) | 回復期〜生活期 | 介入目標が立てやすい | 負荷が高いので頻度・範囲の設計が必要 |
| BRS | 回復段階(麻痺のステージ) | 全病期 | 手早く共有できる | 同じ段階でも “質” の差が出やすい |
| FACT | 体幹機能 | 急性期〜回復期 | 離床・移乗の土台を追える | 足底接地など条件を揃える |
病期別の「組み合わせ」例:最小セットで回す
現場で回しやすいのは、“ 3 群(重症度/運動/体幹・機能)” から 1 つずつ選ぶ形です。以下は一例なので、病棟の運用(カンファ頻度・担当制)に合わせて調整してください。
| 病期 | 重症度(全体像) | 運動(質・段階) | 体幹・機能(離床の土台) | 回す頻度の例 |
|---|---|---|---|---|
| 急性期 | JSS | BRS(手早く) | FACT | 週 2〜3 回(状態変動が大きい間) |
| 回復期 | (必要時)JSS or SIAS | FMA(上肢 or 下肢を主軸) | FACT | 週 1 回(同じ曜日・同条件) |
| 生活期 | (初回)SIAS | FMA or BRS | FACT(必要に応じて) | 月 1 回〜(目標更新のタイミング) |
よくある失敗(OK / NG 早見)
評価を “回す” ための要点は、主役を絞る/条件を揃える/次の介入に翻訳するの 3 つです。ここが揃うだけで、記録が一気に武器になります。
| 観点 | NG | OK |
|---|---|---|
| スケール選択 | 毎回その場で選ぶ | 3 群から主役を固定(重症度/運動/体幹・機能) |
| 測定条件 | 装具・介助が毎回違う | 条件(装具・杖・介助)を記録して揃える |
| 記録の書き方 | 点数だけ | 「どこで落ちたか」を 1 行で言語化(次の課題に直結) |
| 再評価 | タイミングが不定 | 週 1 回など “曜日固定” にして比較可能にする |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
どのスケールを “最優先” にすべきですか?
最優先は「いま何を決めたいか」で変わります。急性期なら 重症度(JSS)+体幹(FACT) を先に揃えると、離床計画とリスク管理が安定します。回復期で上肢の改善を狙うなら、運動の質を追える FMA を主軸にすると、介入の焦点が明確になります。
時間がないとき、最低限のセットは?
“定点観測” を優先して、短時間でブレにくいものを選びます。例として、急性期は JSS+BRS+FACT のように「全体像+段階+体幹」にすると、短時間でも離床の意思決定に直結します。
点数が良くても ADL が伸びないのはなぜ?
スケールが見ているのが「障害(impairment)」なのか「活動(activity)」なのかでギャップが出ます。点数が上がっているのに ADL が伸びないときは、体幹・姿勢制御や、課題動作の条件(環境・速度・注意配分)にボトルネックが隠れていることが多いです。評価は “点” ではなく、課題動作へ翻訳して確認します。
評価結果を介入計画に落とすコツは?
コツは 1 行で言い切ることです。たとえば「座位保持が崩れるので、立ち上がりは体幹固定と足底接地を優先」「共同運動が強いので、分離運動に入る前に姿勢と近位の制御を整える」など、評価→優先課題→練習内容の順で短く結びます。
おわりに
脳卒中の評価は、安全の確保 → 段階刺激 → スケール記録 → 再評価のリズムで回すほど、チームの意思決定が速くなります。現場で “回し切れる” 主役を決めて、同じ条件で取り続けるところから始めてみてください。
面談準備チェックと「職場評価シート」をまとめて使いたい方は、/mynavi-medical/#download から確認できます。
参考文献
- Gotoh F, Terayama Y, Amano T, et al. Development of a novel, weighted, quantifiable stroke scale: Japan Stroke Scale. Stroke. 2001;32(8):1800-1807. doi: 10.1161/01.STR.32.8.1800 / PubMed: 11486108
- Liu M, Chino N, Tuji T, et al. Psychometric properties of the Stroke Impairment Assessment Set (SIAS). Neurorehabil Neural Repair. 2002;16(4):339-351. doi: 10.1177/0888439002239279 / PubMed: 12462765
- Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient. 1. A method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31. doi: 10.2340/1650197771331 / PubMed: 1135616
- Gladstone DJ, Danells CJ, Black SE. The Fugl-Meyer Assessment of motor recovery after stroke: a critical review of its measurement properties. Neurorehabil Neural Repair. 2002;16(3):232-240. PubMed: 12234086
- Huang CY, Lin GH, Huang YJ, et al. Improving the utility of the Brunnstrom recovery stages in patients with stroke: Validation and quantification. Medicine (Baltimore). 2016;95(31):e4508. doi: 10.1097/MD.0000000000004508 / PubMed: 27495103
- Perry J. Motor development in hemiplegia. Phys Ther. 1967;47(5):451-462. PubMed: 6023294
- Sato K, Maeda K, Ogawa T, et al. The functional assessment for control of trunk (FACT): An assessment tool for trunk function in stroke patients. NeuroRehabilitation. 2021;48(1):59-66. doi: 10.3233/NRE-201533 / PubMed: 33386820
- Granger CV, Hamilton BB, Keith RA, Zielezny M, Sherwin FS. Performance profiles of the functional independence measure. Am J Phys Med Rehabil. 1993;72(2):84-89. PubMed: 8476548
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下