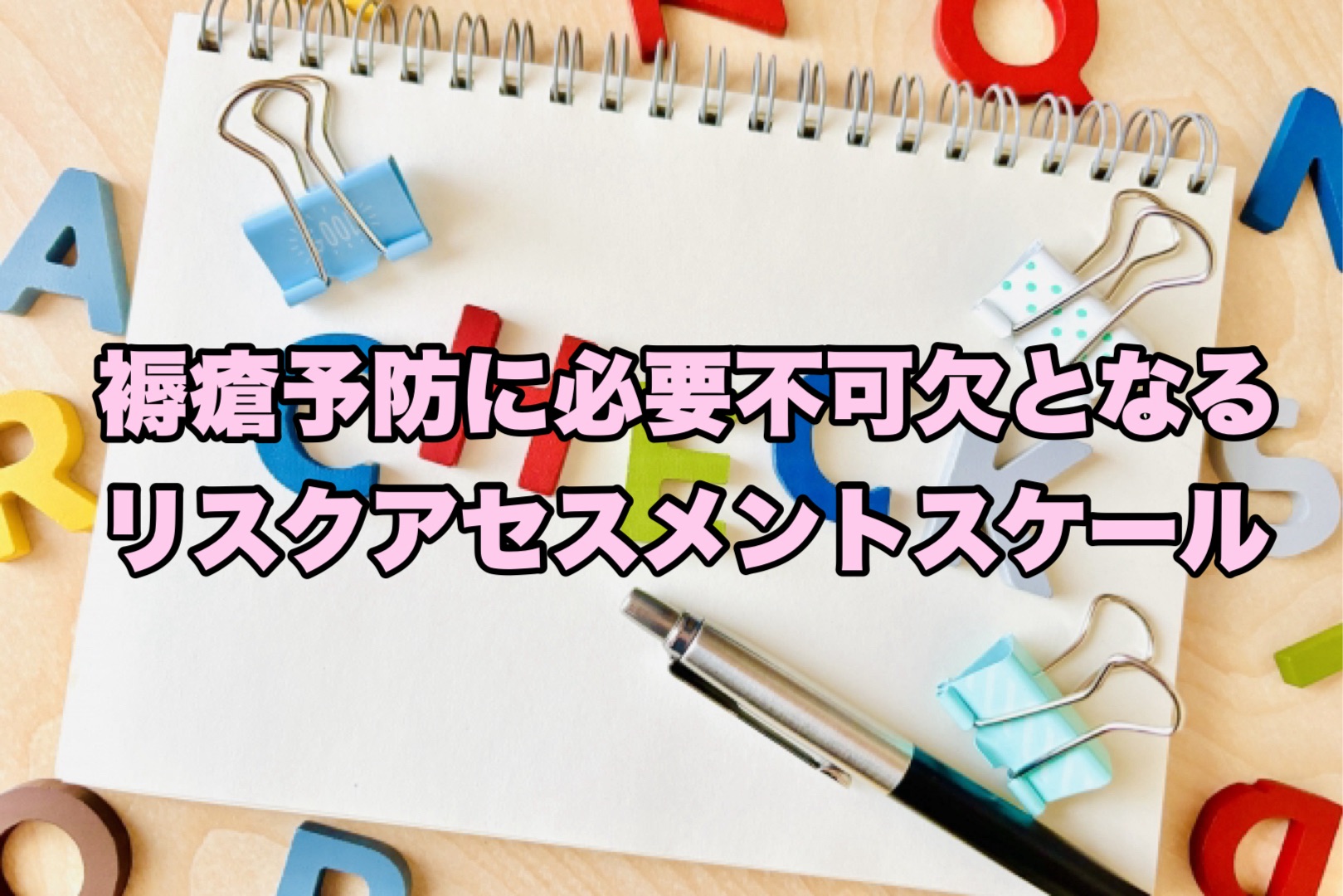褥瘡リスクアセスメントスケールの比較・使い分け【早見表+共通記録+体位変換計画】
入退院時・術後・状態変化時に標準化された褥瘡リスクアセスメントスケールで危険度を層別化し、体位変換・寝具・皮膚ケア・栄養などの具体介入へつなげることが重要です。本ページでは Braden・Norton・Waterlow に加え、K 式・OH スケール・厚労省危険因子評価表・在宅向けツールなどの特徴を横並びで整理し、「どれを・いつ・どう使うか」を 1 ページで確認できるようにまとめます。
関連:褥瘡予防の基本フロー(観察 → リスク評価 → 除圧 → 再評価)も合わせて読むと、評価から介入までの流れが途切れません。
ページ冒頭にA4 配布物(使い分け早見表/共通記録シート/体位変換・除圧計画)を用意しました。スコアの数値だけでなく「どの危険因子が強いか」「どの介入をいつまで続けるか」をチームで揃える共通フォーマットとしてご活用ください。
使い分け早見表(A4・印刷) 共通記録シート(A4) 体位変換・除圧計画(A4)
まず何を使う?(場面別ファーストチョイス)
結論:まずは施設の標準スケールを 1 つ決め、必要時に「補助ツール」を足す形にすると運用が崩れにくいです。ここでは、現場で迷いやすい「初回」「継続」「局所リスク」「要件確認」「在宅」の観点で整理します。
| 場面 | まず使う | 次に足す(必要時) | 見落としやすいポイント |
|---|---|---|---|
| 急性期入院・術後早期 | Norton など簡便スクリーニング | Braden/K 式で詳細層別 | 湿潤(失禁・発汗)と短時間の ADL 低下 |
| 回復期・療養 | Braden(週 1–2 回など) | OH/厚労省評価表(局所・要件確認) | スコア変化より先に「皮膚所見」が悪化する |
| 拘縮・骨突出が強い | Braden(全身) | OH(局所リスクの可視化) | ベッド上だけでなく座位姿勢のずれ・疼痛 |
| 病棟の運用・要件確認 | 厚労省 危険因子評価表 | Braden で危険因子を再整理 | 該当確認だけで介入に落ちない |
| 在宅・施設 | 在宅向け簡易チェック/在宅版 K 式 等 | Braden(必要時に詳細化) | 介護力・寝具・座位時間がリスクを左右する |
代表的スケールの比較(使い分けの要点)
ここでは、よく用いられる褥瘡リスクアセスメントツールの一般的な特徴を比較します。自施設の基準を前提に、「どの場面でどれを使うか」と「陽性時に何をするか」をセットで揃えると、運用がスムーズです。
| スケール | 主な対象 / 場面 | 所要 | 評価軸(概略) | 強み | 注意 | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden | 入院全般 / 回復期・療養 | 3–5 分 | 感覚・湿潤・活動・可動・栄養・摩擦 / ずれ | 危険因子ごとに介入へ落とし込みやすい | 評価者でばらつきが出やすい | 層別 → 体位変換頻度・寝具・栄養・モビライゼーションを具体化 |
| Norton | 急性期〜慢性期の簡便スクリーニング | 1–3 分 | 身体状態・精神状態・活動・可動性・失禁 | 導入しやすく初期スクリーニング向き | 施設特性で陽性率がぶれやすい | 陽性例 → Braden や K 式で詳細化し、介入パスへ接続 |
| Waterlow | 看護現場での包括的評価 | 3–6 分 | 体格・皮膚・年齢・失禁・食事・可動性・全身状態など | 危険因子を網羅的に拾いやすい | 項目が多く習熟に時間がかかる | 高リスク例 → 自施設の褥瘡予防パス(体位変換・寝具・ケア)へ自動接続 |
| K 式スケール | 高齢入院患者・介護保険領域 | 3–5 分 | 前段階要因(活動性・栄養など)と引き金要因(発熱・手術など) | 高齢者の危険因子を日本の実情で整理しやすい | 引き金要因は多職種の情報共有が必要 | 高リスク例 → 体位変換・離床・水分 / 栄養を早期に強化 |
| OH スケール | 拘縮や骨突出が強い症例・長期療養 | 3–5 分 | 骨突出・拘縮・体位変換能力・疼痛など局所リスク | 「部位ごとの危険度」を整理しやすい | 姿勢観察が必要で評価負荷がやや高い | 高リスク部位 → クッション選定・ポジショニングへ直結 |
| 厚労省 危険因子評価表 | 急性期〜回復期病棟・要件の確認 | 3–5 分 | 年齢・活動性・栄養・失禁・既往褥瘡など | 院内運用の共通言語として揃えやすい | 層別に満足して介入が曖昧になりやすい | 該当確認と合わせて、Braden 等で危険因子を再整理 |
| 在宅版 K 式 / PPRA-Home 等 | 在宅・施設・訪問リハ | 2–4 分 | 活動性・介護力・環境整備・栄養状態など | 在宅特有の要素(介護体制・環境)を組み込める | ツール差が大きく、研修がないと統一しづらい | 陽性例 → 寝具・車いす・介護指導をセットで計画 |
層別 → 具体アクション(例)
結論:スケールは「測る」だけでは意味が薄く、層別に応じて介入レベルが自動で決まる状態にすると現場の迷いが減ります。以下はあくまで例として、チーム運用のイメージを示します。
| 層 | 体位変換・除圧 | 寝具・シーティング | 皮膚・湿潤 | 栄養・活動 | 再評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高リスク | 1–2 時間ごと(夜間含む) | 高機能マットレス/クッション | 失禁ケアをプロトコル化 | 高たんぱく・高エネルギー+離床計画 | 24–48 時間以内に見直し |
| 中リスク | 2–3 時間ごと | 中等度体圧分散寝具 | 重点部位を観察し保湿強化 | 水分摂取・活動量を底上げ | 週 1–2 回+状態変化時 |
| 低リスク | 日常ケア範囲での調整 | 現状維持+座位時間の確認 | 定期観察 | ADL 低下・食事量低下に注意 | 状態変化時に臨時評価 |
再評価のタイミング
結論:褥瘡リスクは「一度測って終わり」ではなく、状態変化に合わせて更新します。特に急性期の数日は変動が大きいため、初回評価のあとに短い間隔で見直すと、見落としが減ります。
- 入院初期: 入院時スクリーニング後、24–48 時間以内に 1 回目の再評価。
- 入院中: 回復期・療養病棟では週 1–2 回を目安に継続評価し、スコアや所見の変化で介入を調整。
- 在宅・施設: 発熱・寝たきり化・体重減少・介護力低下など、リスクが変化したタイミングで臨時再評価。
現場の詰まりどころ(よくある失敗と対策)
| よくある失敗 | 起きること | 対策(チームで揃える) | 記録のポイント |
|---|---|---|---|
| スコアだけ記録して終わる | 介入の濃淡が決まらず、担当者ごとにバラつく | 層別ごとに「体位変換頻度・寝具・湿潤・栄養」の最小セットを決める | 層別(高/中/低)+介入レベルを同じ欄に残す |
| 局所リスクが埋もれる | 骨突出・拘縮の部位がケアに反映されない | 全身スケール+局所観察(座位含む)をセット化 | 「部位」「姿勢」「疼痛」「ずれ」を短文で残す |
| 再評価の契機が曖昧 | 状態変化に追従できず、手遅れになる | 「24–48 時間」「週 1–2 回」「状態変化時」をルール化 | 再評価日と、変更した介入だけを追記する |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
スケールはどれか 1 つに固定すべき?
運用を崩さないコツは、「標準スケールを 1 つ」+「補助ツールを必要時に足す」です。たとえば、初期の見落とし防止に簡便スクリーニングを使い、継続モニタリングは標準スケールで統一、拘縮や骨突出が強い症例では局所リスクを補うツールを併用、という整理にすると現場が回りやすくなります。
Braden の点数は、何点から要注意と考える?
一般に「合計点が低いほどリスクが高い」という前提で運用します。要注意の目安は現場や病期で変わるため、病棟特性(急性期・回復期・療養・在宅)を踏まえて「どの点数帯から、どの介入レベルに上げるか」を褥瘡対策チームで揃えるのが実務的です。
K 式や OH スケールはどんな症例に向いている?
K 式は、高齢者の危険因子を整理しつつ、状態変化(発熱・手術など)を契機に介入を強めたいときに扱いやすいです。OH は骨突出や拘縮が強い長期療養者で、「どの部位が危ないか」をチームで共有し、クッションやポジショニングへ直結させたいときに役立ちます。
PT・OT・ST はスコア以外に何を残すとチームが動きやすい?
スコアに加えて、体位変換の自立度、座位耐久性、寝具・車いすの種類、痛みが出る部位、姿勢で生じるずれ(滑り)を短文で残すと、寝具選定やポジショニングの議論が速くなります。共通記録シートに 1 枚で集約すると申し送りが楽です。
おわりに
褥瘡予防は「皮膚の観察 → リスク層別 → 段階的な除圧(体位変換・寝具) → 記録 → 再評価」というリズムを崩さないことが要点です。スケールは 1 つに決めて回しつつ、場面に応じて補助ツールを足す “使い分け” にすると、現場の迷いとやり直しが減ります。
見学や情報収集の段階で抜け漏れが起きやすい方は、「面談準備チェック( A4 )」と「職場評価シート( A4 )」を手元に置いておくと整理が速くなります。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下