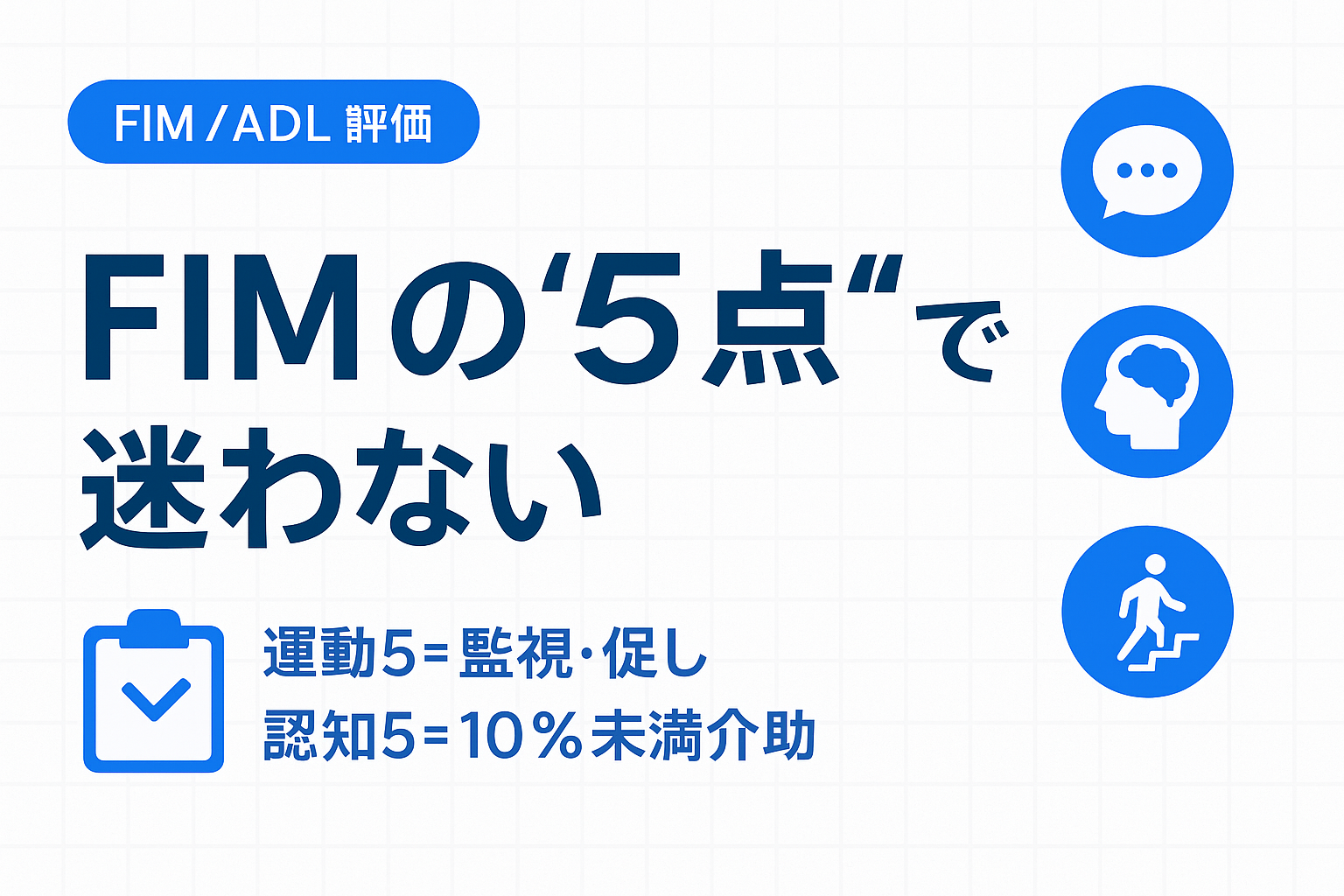FIM 5 点とは?運動項目と認知項目 5 点の違い
FIM は 18 項目を 7 段階で判定し、実際に「している ADL(普段必要な介助量)」を数値化する指標です。その中でも FIM 5 点 は、運動項目と認知項目で “根拠の置き方” が異なるため、評価者間でブレやすいポイントです。本稿では 運動 5 点/認知 5 点の定義を整理し、つまずきやすい代表例と 4〜1 点の介助割合の考え方までを 1 ページにまとめます。
結論:5 点は「他者の関与が残る」ゾーン
FIM 5 点は「ほぼ自立だが、他者の関与が残る」状態です。ここで重要なのは、運動 5 点と認知 5 点は “同じ 5 点” でも根拠が違うことです。運動では「監視・口頭指示・促し(身体介助なし)」、認知では「介助量が 10 % 未満(時々の助言やヒント)」を軸に整理すると、判断が揃いやすくなります。
| 領域 | 5 点の定義(要点) | 境界の見方 | よくある臨床例 |
|---|---|---|---|
| 運動 | 監視・口頭指示・促しのみ(身体介助なし) | 手が出たら 4 点以下を検討 | 病棟内歩行の常時見守り/更衣の声かけ/階段での言語指示 |
| 認知 | 介助量 10 % 未満(時々の助言・ヒント) | 助言が “頻回” なら 4 点以下を検討 | 段取りのヒント提示で自己修正/会話の軽微な軌道修正 |
FIM 5 点の全体像と 6 点との違い
まず 6 点との違いを 1 行で固定すると迷いが減ります。
| 点 | 合言葉 | 実務での判断 |
|---|---|---|
| 6 | 他者の関与なし(補助具のみ) | 見守り・口頭指示が “一貫して不要” なら 6 |
| 5 | 他者の関与が残る(監視・助言) | 手は出ないが、促し・安全見守りが “一貫して必要” なら 5 |
つまり、6 点は「条件付きの自立」、5 点は「軽い介入が残る状態」として切り分けると、評価者間の解釈が揃いやすくなります。
FIM 運動項目 5 点:意味と臨床例
運動 5 点は「監視・促し・口頭指示のみで、身体介助は不要」な状態です。歩行や移乗、更衣で “安全のための見守り” は必要でも、体を支える・持ち上げる・誘導するなどの物理的介助が入らなければ運動 5 点の候補になります。
| 観察ポイント | 見方 | 記録の残し方(例) |
|---|---|---|
| 関与の種類 | 監視・声かけ・準備のみか | 「見守り+ 2 回の声かけで完遂」 |
| 接触の有無 | 一瞬でも “体を支える” が入ったか | 「接触介助なし」/「一瞬の支持あり」 |
| 安全配慮 | 転倒リスクのため近接監視が必須か | 「段差・方向転換で近接監視」 |
逆に、一瞬でも接触介助が反復して入る、あるいは “手が出る前提” での介助体制が必要なら、介助割合を見積もって 4 点以下を検討します。
FIM 認知項目 5 点:意味と臨床例
認知 5 点は「介助量 10 % 未満」が目安です。理解・表出・社会的交流・問題解決・記憶に対して、ときどき助言やヒントを提示すれば、本人が自分で軌道修正できる状態を想定します。
| 場面 | 5 点に寄せやすい状況 | 4 点以下を検討する状況 |
|---|---|---|
| 理解/表出 | 言い直しの誘導が時々あるが、内容は概ね成立 | 内容が成立しない場面が頻回、代行や反復が多い |
| 問題解決 | 最初のヒントで自己修正できる | 段取り提示が頻回、危険行動の抑制が必要 |
| 記憶 | 時々のリマインドで遂行可能 | 常時プロンプトが必要、遂行できない場面が多い |
同じ 5 点でも 運動=監視・促し(身体介助なし)/認知= 10 % 未満の介助 と根拠が違うため、まずここを混同しないことが迷いを減らす第一歩になります。
4〜1 点の介助割合:見積もり方(ブレを減らす)
介助割合は “感覚” で決めるとブレやすいので、工程分解 → 介助が入った工程を特定 → 合計 % の順で揃えると安定します。食事なら〈道具操作・口に運ぶ・嚥下〉、整容なら〈口腔ケア・整髪・手洗い・洗顔・髭剃り/化粧〉のように、工程を固定しておくのがコツです。
| 点 | 介助割合の目安 | 現場での言い換え |
|---|---|---|
| 4 | < 25 % | 最小介助(少し手が出る) |
| 3 | 25–49 % | 中等度介助(半分弱) |
| 2 | 50–74 % | 最大介助(半分以上) |
| 1 | ≧ 75 %/ 2 名介助・機械介助 | 全介助 |
判定は次の順番にすると迷いにくくなります。① 身体介助の有無で 6–7 か ≤5 を決める → ② 運動/認知を区別して 5 点の定義を当てる → ③ 工程分解で介助 % を見積もる → ④ 記録は「工程・ %・根拠・安全配慮(促し内容)」をセットで残す。
つまずきやすい 10 ケース(判定と根拠)
新人が迷いやすい代表例を “根拠つき” で整理します。施設内の合議では、点数だけでなく「どの工程に、どんな関与が入ったか」を短く統一すると再現性が上がります。
- シャワー温度の設定のみ介助 → 準備介入に相当 → 運動 5。
- 歩行は自立だが常時見守りが必要 → 身体介助なし/関与あり → 運動 5。
- 立ち上がりで一瞬の接触介助が反復 → 身体介助あり → 4(割合で根拠化)。
- 整容 5 工程中 2 工程が全介助 → 実施 60 % → 3。
- 表出は概ね成立、時折言い直し誘導 → 介助量 10 % 未満 → 認知 5。
- 階段は手すり併用+言語指示で完遂 → 身体介助なし → 運動 5。
- 食事で「口に運ぶ」が全介助、他は自立 → 工程分解で ≈ 67 % 実施 → 3。
- 浴槽またぎで部分介助が 2 回入る → 身体介助あり → 4(割合で根拠化)。
- 問題解決は “最初のヒント” で自己修正 → 介助量 10 % 未満 → 認知 5。
- 記憶で常時プロンプトが必要 → 介助が頻回 → 3〜2(割合で決定)。
迷わない判定フロー(チーム共有用)
下の 4 ステップをチームで共有すると、判定速度と再現性が上がります。カンファレンスでは「どの工程に介助が入ったか」「監視・促しの内容」を 1 行で残す運用が効果的です。
① 身体介助の有無:なし= 6/7 または(運動) 5 /あり= 4〜1
② 5 点の定義を分ける:運動 5=監視・促し(身体介助なし)/認知 5= 10 % 未満
③ 工程分解で介助 %: 4(< 25 %)/ 3(25–49 %)/ 2(50–74 %)/ 1(≧ 75 %)
④ 記録の型:「工程 × %・根拠・安全配慮・促し内容」をセットで残す
現場の詰まりどころ:5 点がブレる “ 3 つの原因”
| 原因 | 起きやすいズレ | 対策(チームで揃える) |
|---|---|---|
| 運動と認知の定義混同 | 「助言がある= 5」だけで決めてしまう | 運動=監視・促し、認知= 10 % 未満を合言葉にする |
| 接触介助の扱いが曖昧 | 一瞬の支持を “見守り” と同一視 | 接触が入ったら 4 以下を検討し、割合で根拠化 |
| 記録が「点数のみ」 | 後から根拠が追えず、測定者で変わる | 促し内容/工程/ % を 1 行で残し、再評価を安定させる |
よくある失敗:5 点を “便利札” にしない
- 失敗 1:迷ったら 5 点に寄せる → 「関与の種類(監視/助言)」と「頻度」を書かずに終わる。
- 失敗 2:接触介助が入ったのに 5 点 → “手が出た” 事実を見落とす。
- 失敗 3:認知の 10 % 未満を確認しない → 助言が頻回でも 5 点にしてしまう。
評価の抜け漏れを減らすために、面談準備チェック( A4 )と職場評価シート( A4 )を無料で置いています。ダウンロードページを見る。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
FIM 5 点とはどんな状態ですか?
FIM 5 点は、運動項目では「監視・促し・口頭指示のみで身体介助は不要」、認知項目では「介助量 10 % 未満」を意味します。いずれも「ほぼ自立だが、ごく軽度の介入が必要」なゾーンで、運動/認知で定義を分けて共有しておくことが重要です。
運動 5 点の具体例は?
病棟内の常時見守り歩行、整容での声かけ 1〜2 回、階段での言語指示のみなどです。実際に体を支える・持ち上げるなどの接触介助が入る場合は 4 点以下を検討し、介助割合で根拠化します。
認知 5 点の具体例は?
会話の軽微な軌道修正、最初の段取りヒントで自己修正できるケースなどです。「助言が時々」か「頻回」かで 5 点と 4 点以下の検討が変わります。
4〜1 点の介助割合はどう見積もる?
工程を配点化して(例:食事=道具・口に運ぶ・嚥下)介助が入った工程を特定し、合計 % を出します。< 25 %= 4 点、25–49 %= 3 点、50–74 %= 2 点、≧ 75 %= 1 点を目安に、工程・ %・根拠・安全配慮をセットで記録します。
次の一手:点数別に迷いどころを潰す
参考文献
- Granger CV, Hamilton BB, et al. Performance profiles of the Functional Independence Measure. Am J Phys Med Rehabil. 1993;72(2):84–89. PubMed / DOI.
- Keith RA, Granger CV, Hamilton BB, Sherwin FS. The Functional Independence Measure: a new tool for rehabilitation. Adv Clin Rehabil. 1987;1:6–18. PubMed.
- Ottenbacher KJ, et al. The reliability of the Functional Independence Measure. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77(12):1226–1232. DOI:10.1016/S0003-9993(96)90184-7 PubMed / DOI.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下