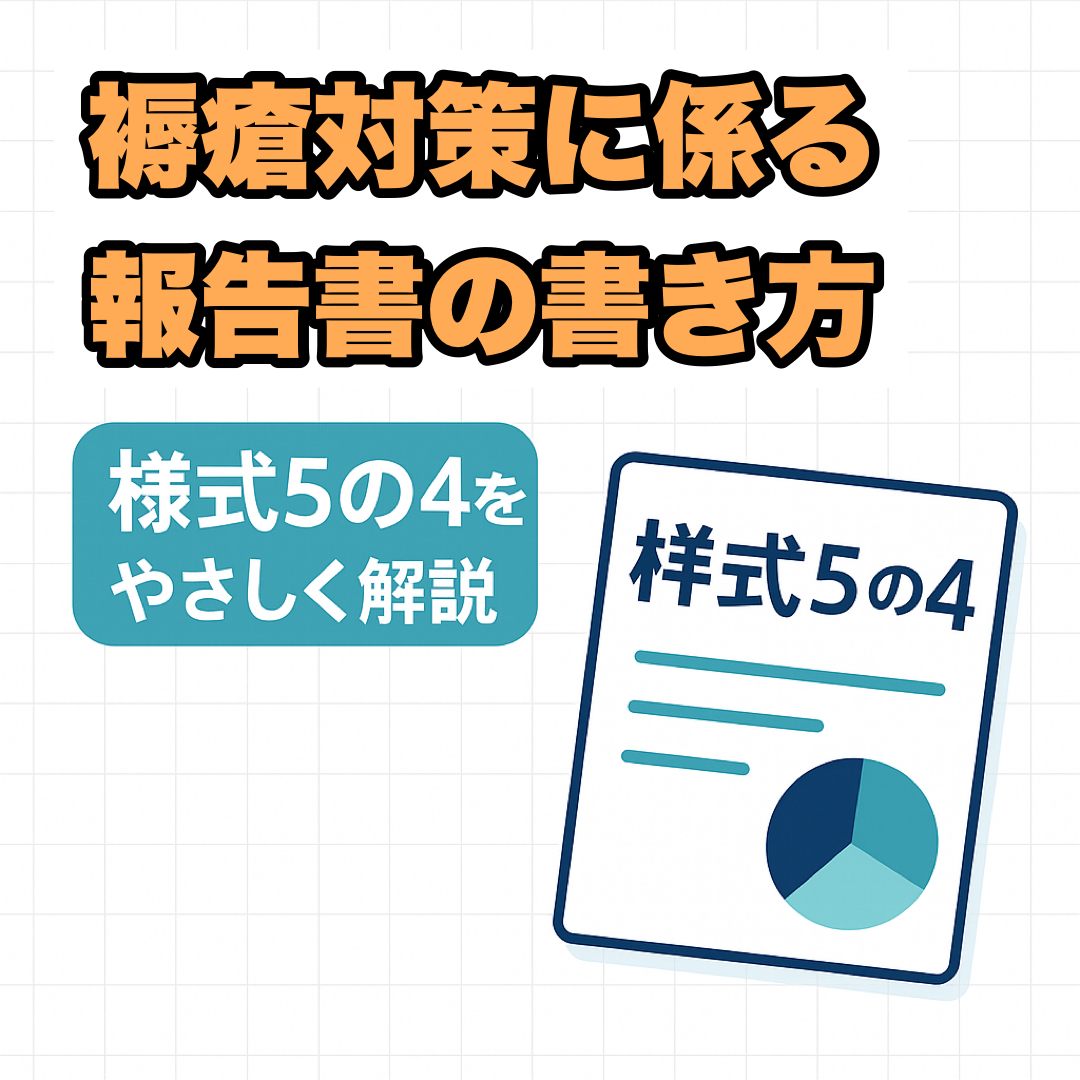褥瘡対策に係る報告書(様式 5 の 4)の書き方|数字が合わない時の最短ルート
様式 5 の 4 は、①〜⑥ を “きれいに数える” だけで作業時間が大きく変わります。結論から言うと、数字が合わない時は「集計表」ではなく患者単位の一覧(褥瘡の有無/入院時か院内発生か/最重グレード)に戻して、②→③→④→⑥ の順で復元するのが最短です。
本記事では、①〜⑥ の数え方のルールと、現場でズレやすいポイント(どこで崩れるか)を “拾う場所” まで落として整理します。提出用の公式様式は各厚生局のページから取得し、ここでは集計の考え方に絞って解説します。
書類作成がラクになるのは、「評価 → 記録 → 共有」を同じ型で回せた時です。 現場の型づくりを 3 分で確認する
①〜⑥ 早見表|「何を」「どこから」拾うか(OK/NG 付き)
様式 5 の 4 が崩れる原因の多くは、「患者数」と「褥瘡数(部位数)」が混ざることです。②〜④ と⑥ は患者数で数え、複数部位があっても1 人は 1 人として扱います。
まずは下の表で、各欄の “拾う場所” を固定してください。院内の集計者が変わっても再現できるようになります。
| 欄 | 何を数える | 拾う場所(例) | よくある NG | 対策(最短) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 対象日の入院患者数 | 病棟入院一覧(対象日) | 当日入院(予定)を入れる/当日退院(予定)を外す | 対象日の定義を院内で統一(一覧抽出条件を固定) |
| ② | ①のうち d1 以上の褥瘡を有する患者数(褥瘡保有者数) | 患者単位一覧(褥瘡あり/なし) | 部位ごとに数える(延べ数になる) | 「患者 1 行」へ戻し、複数部位は 1 人にまとめる |
| ③ | ②のうち入院時から d1 以上を有する患者数 | 入院時評価(初回 DESIGN-R) | 入院後の発生を混ぜる | 入院時点で d1 以上だったかだけで振り分ける |
| ④ | ②のうち入院中に新たに発生した患者数 | インシデント/創傷記録(発生日) | ③と重複計上する | ④ は “② − ③” で必ず整合を取る |
| ⑤ | 体圧分散マットレス等の体制(保有/レンタル等) | 物品台帳・レンタル契約・病棟配備表 | 現場運用と台帳がズレる | 「実際に出せる物品」を基準に年 1 回棚卸し |
| ⑥ | 重症度(d1〜 DU)を、③(入院時)と④(院内発生)に分けて患者数で集計 | 患者単位一覧(最重グレード) | 複数褥瘡を延べで数える/最重でないグレードに入れる | 「最も重症な区分に 1 名」で固定し、③・④ と合計が一致するか確認 |
数字が合わない時の 5 分フロー|②→③→④→⑥ の順で復元する
集計表をいじる前に、いったん “患者単位” に戻す方が早いです。やることは 3 ステップで、最後に整合チェックをかけます。
ポイントは、⑥ を先に埋めないことです。先に③・④ の母集団(患者)が確定すると、⑥ は自然にそろいます。
- 患者単位一覧を作る(対象日の入院患者を 1 行ずつ:褥瘡あり/なし、入院時から/院内発生、最重グレード)
- ②→③→④ を確定する:②=褥瘡ありの人数、③=入院時からの人数、④=②−③
- ⑥ を埋める:③ の患者は「入院時の最重」、④ の患者は「発見時の最重」で d1〜 DU に 1 人 1 カウント
- 整合チェック 1:③(合計)+④(合計)=②
- 整合チェック 2:⑥(入院時側の合計)=③、⑥(院内発生側の合計)=④
現場の詰まりどころ/よくある失敗|ズレる原因はだいたい 4 つ
様式 5 の 4 が毎年しんどい施設は、「集計の技術」より運用の前提が揺れていることが多いです。下の 4 つを直すと、翌年以降の作業が一気に軽くなります。
特に “患者数と部位数の混在” と “③・④ の重複” が最頻出です。ここだけでも、病棟に共有しておく価値があります。
| 失敗パターン | 何が起きる | 現場での対策 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 患者数と部位数が混ざる | ②や⑥が延べ数になり、合計が合わない | 「患者 1 行」の一覧に戻し、複数部位は最重で 1 人にまとめる | ②・③・④・⑥は “人数” だけ |
| ③と④の重複計上 | ③+④が②を超える | ④は必ず “②−③” で確定し、後から発生例だけを④側に置く | ③+④=②が崩れない |
| 評価タイミングが病棟でバラバラ | ⑥の最重グレードが揺れて集計不能になる | 入院時/定期/発生時の “評価タイミング” を院内で固定 | 「いつの評価を⑥に使うか」を明文化 |
| 体制(⑤)が台帳と一致しない | 監査・適時調査で説明が詰まる | 年 1 回、物品棚卸し(保有/レンタル/配備場所)を短時間で回す | 「今この瞬間に出せるか」で整理 |
もし「そもそも運用が回っていない」「標準化する時間が取れない」と感じる場合は、職場の詰まり(人員・教育・記録文化)を先に棚卸しして、改善の優先順位を決める方が結果的に早いです。関連:無料チェックシート(環境の詰まりどころ)
集計補助シート(A4)の構成と使い方
rehabilikun blog では、様式 5 の 4 を作る時に使える「集計補助シート」を用意しています。1 ページで「①〜⑤ の転記サマリー」「 d1〜 DU × 入院時/院内発生の重症度別集計」「対象日時点の入院患者一覧」をまとめる想定です。
公式様式そのものではなく院内集計用の自作シートなので、提出用の様式は必ず各厚生局のサイトから取得してください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
褥瘡が 0 名でも、報告は必要ですか?
はい。褥瘡を有する患者がいない場合でも報告が必要で、②〜⑥ は「0 名」として記載します。対象の要件(報告対象かどうか)は、管轄の厚生局の案内・FAQ を確認してください。
1 名の患者が複数の褥瘡を有している場合、⑥ はどう数えますか?
⑥ は延べ数ではなく患者数です。複数褥瘡がある場合でも、最も重症な区分に「患者 1 名」として数える運用にすると整合が取りやすくなります。
①〜④ と⑥ の数字が合いません。どこから確認すればよいですか?
最初に「患者単位の一覧」に戻してください(対象日の入院患者を 1 行ずつ)。②→③→④ を確定し、最後に⑥ を “最重で 1 名” で集計すると、③=⑥(入院時側合計)、④=⑥(院内発生側合計)を作りやすくなります。
次の一手(同ジャンルで理解をつなげる)
参考文献
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下