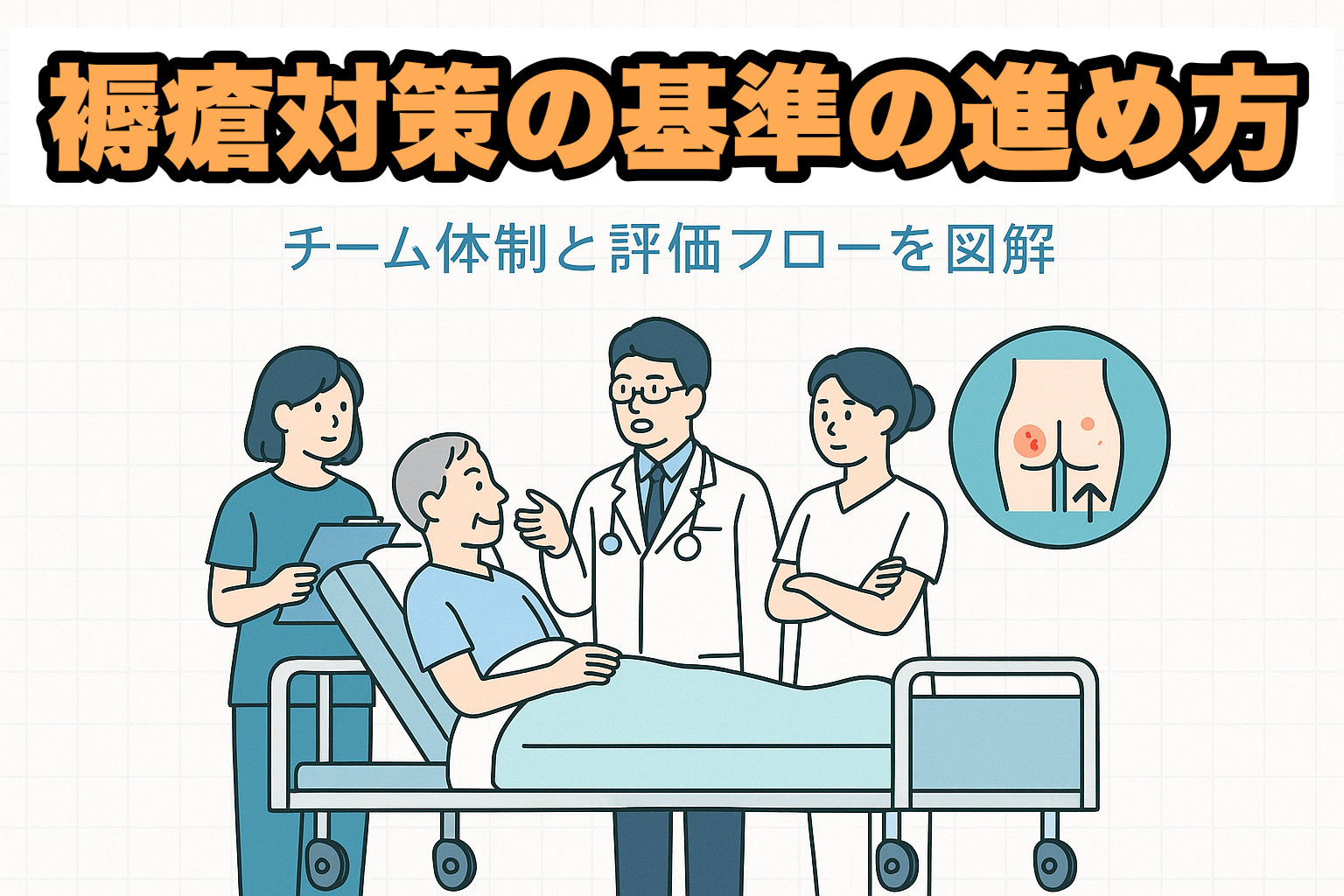「褥瘡対策の基準」の進め方|入院基本料の施設基準を“運用フロー”で回す
褥瘡対策の基準は、条文を読んで終わりではなく「対象患者を拾う → 計画を回す → 記録を残す」を病棟とチームで“同じリズム”にそろえる仕組みです。本記事では、PT が現場で説明・監査対応まで通るように、施設基準(体制)と患者単位(フロー)を 1 枚でつなげます。
先に結論だけ押さえるなら、①危険因子評価の対象を固定、②危険因子あり/褥瘡ありは診療計画へ接続、③委員会・ラウンド・研修・物品体制を「出せる資料」にしておく、の 3 点です。
施設基準の“運用”は、覚えるより「説明の型」を先に持つ方がラクです。 評価→記録→監査対応の流れを 3 分で整理する
褥瘡対策の基準とは?(PT向けに一言で)
褥瘡対策の基準は、入院基本料を算定するうえで求められる「院内体制+プロセス(評価・計画・実施・評価)」の要件です。ポイントは、褥瘡が“できたら対応”ではなく、入院早期から危険因子を拾い、計画と記録で再現性を担保する点にあります。
実務では「誰に危険因子評価をするか」と「危険因子あり/褥瘡ありをどう計画書へつなぐか」で詰まりやすいので、本記事ではその分岐をフロー化し、監査で出しやすい資料の形まで落とします。
施設として先にそろえるもの(体制・会議・記録)
施設基準は、個々の症例の上手さよりも「院内として回る仕組み」が問われます。まずは褥瘡対策チームの設置根拠(要綱・メンバー表)を明文化し、委員会・ラウンド・職員研修の実績が追える形で保管します。
加えて、体圧分散マットレス等の体制は“現場の肌感”ではなく、台数・配置・レンタル状況と使用基準を資料化して説明できる状態にします(ここが適時調査で詰まりやすい論点です)。
入院患者 1 人あたりの褥瘡対策フロー(最小の全体像)
運用は「入院時の危険因子評価」から始め、結果で分岐させると理解が早くなります。危険因子なし(低リスク)は標準的スキンケアと体位変換を基本に、状態変化で再評価します。
危険因子あり/既存褥瘡あり(高リスク)は、褥瘡対策チームの関与した診療計画へ接続し、支持面(マットレス等)・ポジショニング・栄養・リハを含めた重点ケアを回します。そのうえで、要件を満たす症例のみ加算や報告書へ接続します。
- 入院時:危険因子評価を実施(対象の拾い漏れを防ぐ)
- 分岐:危険因子なし → 標準ケア / 危険因子あり・褥瘡あり → 診療計画へ
- 重点ケア:支持面・体位・栄養・リハを“同じ条件で記録”し、見直しを回す
- 必要時:加算要件の確認 → 報告書(集計)へ接続
褥瘡対策加算・ハイリスク加算との関係(混乱を防ぐ整理)
褥瘡対策加算やハイリスク患者ケア加算は、施設として褥瘡対策の基準を満たしたうえで、特定の症例に対して一定水準以上のケアを実施した場合に上乗せされる仕組みです。現場では「施設の要件」と「症例の要件」を分けて考えると迷いにくくなります。
前者は体制・実施率・ラウンド・研修など院内資料で担保し、後者は診療計画書や報告書などでエビデンスを残します。算定の詳細や集計の詰まりは、次の一手で個別記事に分けて確認してください。
適時調査で見られるポイントとセルフチェック(最短で直す)
適時調査では「やっている」より「出せる資料」と「運用の一貫性」が見られます。特に、危険因子評価の対象が病棟で揺れている、計画書が空欄のまま、活動記録が口頭説明だけ、物品体制が資料化できていない、の 4 つは指摘につながりやすいので先に潰します。
下の表をそのまま院内の“セルフ監査”に使い、NG が出た行だけを優先的に整えると、負荷を増やさずに通る確率が上がります。
| チェック項目 | ありがちな NG | 確認ポイント | 最短で直す一手 |
|---|---|---|---|
| 危険因子評価の対象 | 特定病棟だけ/寝たきり患者だけ | 日常生活自立度の低い入院患者を入院早期から拾えているか | 対象定義を 1 行で院内共有(誰が・いつ・どの画面で) |
| 診療計画書の運用 | テンプレはあるが実施・評価欄が空欄 | 作成→見直しが“循環”しているか | 見直しタイミングを固定(週○回/ラウンド後など) |
| チーム活動・研修の記録 | 口頭説明のみで資料が残っていない | 議事録/ラウンド記録/研修記録が出せるか | 保存場所を 1 つに統一(年度フォルダ+命名規則) |
| 体圧分散マットレス体制 | 台数・配置・レンタル状況が不明 | 「今この瞬間に出せる物品」を説明できるか | 年 1 回棚卸し(台帳と現場を一致させる) |
| 栄養・リハとの連携 | 悪化時だけスポット介入 | 高リスクに継続関与できる仕組みがあるか | チーム介入のトリガーを固定(評価で「あり」なら自動依頼) |
現場の詰まりどころ/よくある失敗(ここだけ先に直す)
褥瘡対策の基準は、真面目にやっていても「対象の拾い漏れ」と「記録の置き場所」で崩れます。特に多いのは、病棟によって危険因子評価の対象が違う、計画書は作るが見直しが回らない、物品体制が“説明できる資料”になっていない、の 3 パターンです。
もし「運用を整える時間が取れない」「標準化が進まない」と感じる場合は、個人の努力より先に“環境の詰まり”(教育体制・記録文化・人員・標準化の仕組み)を棚卸しすると、改善の優先順位が決めやすくなります。関連:無料チェックシート(環境の詰まりどころ)。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
自院が「褥瘡対策の基準」を満たしているか、ざっくり確認するには?
厳密には通知本文と施設基準を照合しますが、現場ではまず ①危険因子評価、②診療計画書、③チーム活動・研修、④体圧分散マットレス体制 の 4 点が回っているかを確認すると全体像がつかみやすいです。
本記事の「セルフチェック表」で NG が出た行だけを優先的に整えると、負荷を増やさずに改善が進みます。
適時調査で「褥瘡対策の基準」を聞かれたとき、最低限そろえておきたい資料は?
最低限そろえておきたいのは、①チームの設置根拠(要綱・メンバー表)、②危険因子評価の実施状況、③診療計画書と報告書のサンプル、④ラウンド・研修実績の一覧、⑤体圧分散マットレス等の台数・配置リスト、の 5 つです。
「評価 → 計画 → 実施 → 評価・見直し → 集計」の流れが追える症例を数例ピックアップしておくと、説明が通りやすくなります。
診療計画書の「薬学的管理」「栄養管理」は毎回ぜんぶ書くべきですか?
実務では“必要な場合に記載する”整理が基本です。空欄が問題というより、患者の状態に応じて必要項目が落ちていないか(必要時に書ける運用か)を見られます。
院内で「どの条件なら記載するか」を短いルールにしておくと、病棟間のブレが減ります。
次の一手(関連リンク)
このページは「全体設計」を押さえる場所です。実務を一気に進めるなら、次は “書類(報告・加算)” と “ケア(支持面・体位)” をそれぞれ 1 本ずつ確認すると、院内の標準化が進みます。
- 施設基準を横断で整理:施設基準ハブ
- 報告(様式 5 の 4)をズレなく集計:様式 5 の 4 の書き方|褥瘡報告の数え方・集計
- 加算の実務(療養病棟):療養病棟の褥瘡対策加算|算定要件・実務ガイド
- 支持面の運用を回す:体圧分散マットレス導入・モニタリングプロトコル
- ポジショニングの具体:褥瘡予防のポジショニング実務
参考文献
- 厚生労働省.基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)関連資料.(参照:褥瘡対策の基準).https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/5-2-1.pdf
- 厚生労働省.褥瘡対策に関する診療計画書(別紙).https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038911.pdf
- 社会保険研究所.施設基準Q&A(疑義解釈等).(褥瘡対策:薬学的管理・栄養管理の記載).https://www.shaho.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/130516_060725_1.pdf
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下