フレイル対策実践ガイド|J-CHS|運動・栄養・口腔の多面的介入
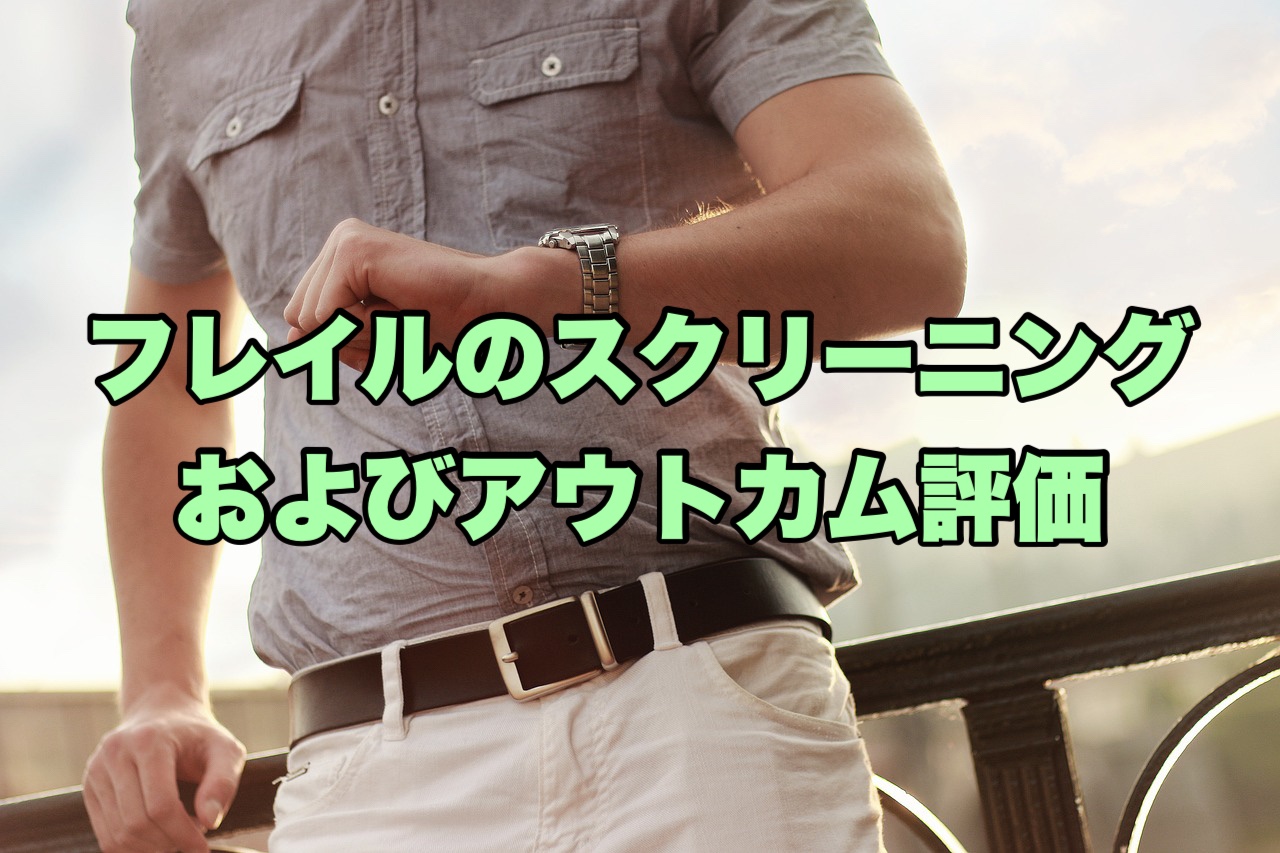 疾患別
疾患別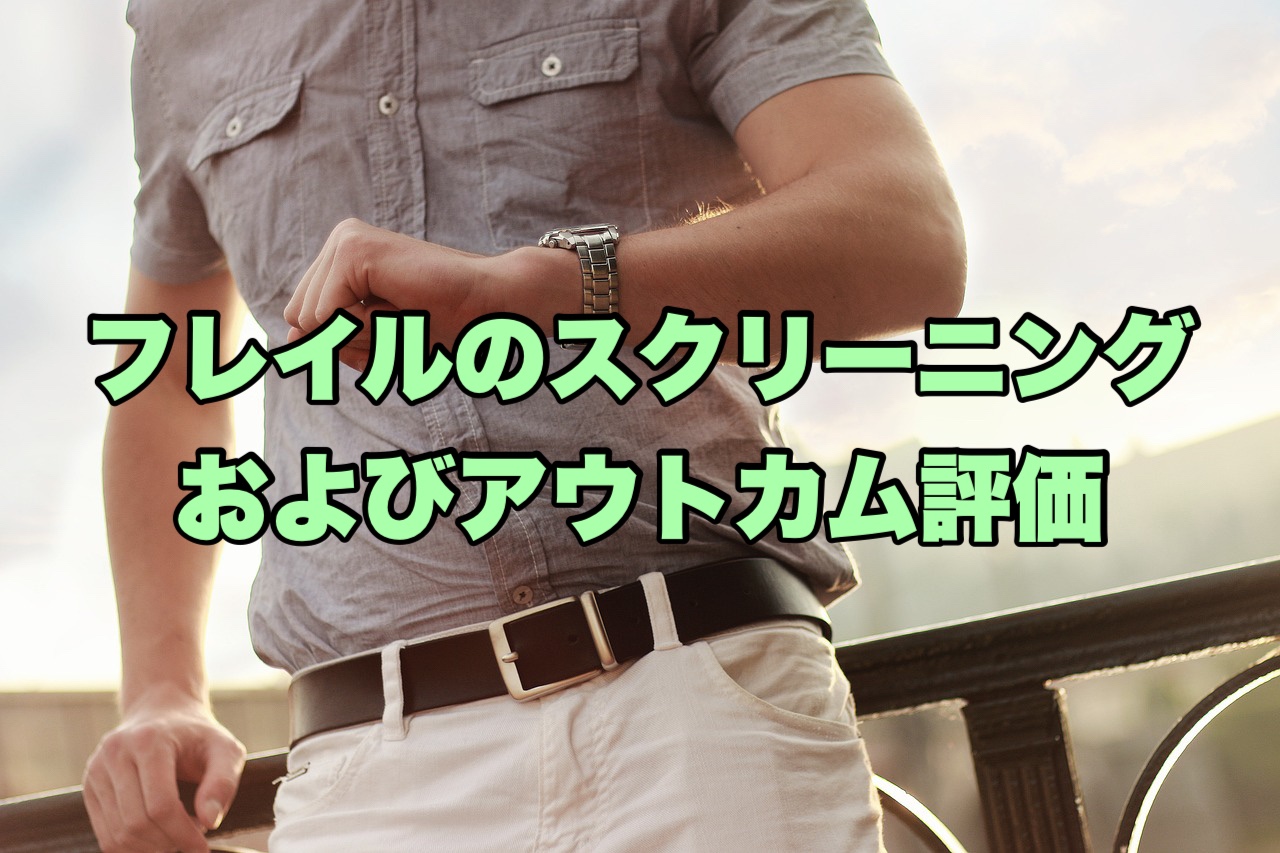 疾患別
疾患別本記事は、フレイルの実践的マネジメントを①スクリーニング(J-CHS中心)→②多面的介入(運動・栄養・口腔・薬剤・社会)→③モニタリングの3段で整理します。現場で即使えるよう、J-CHSのA4評価用紙(印刷・自動スコア付き)を埋め込み、フォロー時の指標(SPPB、握力、5回椅子立ち上がり、6分間歩行など)もセットで提示します。
結論としては、“まず測る → 小さく始める → 短サイクルで見直す”の運用が最短距離です。プレフレイルなら歩行+下肢レジスタンス+たんぱく質摂取の3点セットを少量・高頻度で着手し、1〜2週間ごとに再評価していきます。
臨床で迷わない評価→介入の流れを5分で確認(PTキャリアガイド)
J-CHS(日本版CHS)は、体重減少・易疲労感・身体活動量低下・歩行速度低下・握力低下の5項目でプレフレイル/フレイルを判定する簡便な方法です。数値基準(例:歩行速度おおむね 1.0 m/s 未満、握力 男性<26 kg・女性<18 kg)を目安に、施設の標準手順に沿って評価してください。
本記事では、評価後の介入へスムーズに繋げるため、印刷・自動スコア付きのJ-CHSフォームをそのまま使える形で掲載しています。別タブで開けば配布・印刷も容易です。
| 指標 | 主目的 | 所要 | 判定の目安 | 使いどころ |
|---|---|---|---|---|
| J-CHS | 表現型(体力・活動)に基づく判定 | 3–5分 | 0=健常/1–2=プレフレイル/3–5=フレイル | 標準的な一次スクリーニング |
| CFS | 臨床的フレイルの重症度スケール | 1–2分 | 9段階(上位ほど脆弱) | 病棟・在宅での迅速な重症度把握 |
| FRAIL | 5問の自己申告式 | 1–2分 | 0=健常/1–2=プレ/3–5=フレイル | 外来・集団での素早いふるい分け |
| 基本チェックリスト | 生活機能の幅広い把握 | 5–10分 | 8点以上でフレイル該当 | 包括的な生活機能評価 |
関連記事:評価ハブ
フレイルは一領域だけでは改善しづらく、運動(レジスタンス・バランス・歩行/二重課題)+栄養(十分なたんぱく質・エネルギー)+口腔機能+薬剤適正化+社会参加を同時に回す方が効果的です。院内フローはこちらの流れを参考に、評価→目標→介入→再評価の周期を短く設計しましょう。
運動:レジスタンスは週2–3回・主要筋群をRPE 13程度から段階的に。バランスは反応的/予測的課題や支持基底面の縮小、二重課題化。歩行は通常歩行と速歩を交互に2–3セット、方向転換・段差を課題化します。
栄養:目安はたんぱく質 1.0–1.2 g/kg/日(必要に応じ 1.2–1.5 g)。低栄養・サルコペニアの併発に注意し、食事記録と体重変化を追跡。
口腔:咀嚼・嚥下・口腔清掃、口腔乾燥の是正。
薬剤:鎮静・起立性低血圧・食欲低下などを招く薬剤を見直し。
社会参加:役割・交流・外出機会の創出で日常活動に落とし込み。
関連記事:SPPBのやり方と判定
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
まずは歩行+下肢レジスタンス+たんぱく質摂取の3点セットを少量・高頻度で始めます。歩行は通常と速歩を交互に2〜3セット、下肢は椅子立ち上がりやカーフレイズを10回×2セット程度。食事は主菜を「手のひら1枚分」を毎食で確保するところから。
体重の週1回記録と、4 m 歩行のストップウォッチ計測は自宅でも実施しやすいです。助走1〜2 mの後に4 mのみを計測し、4秒を超える場合は「歩行速度低下」の可能性。握力計があれば左右1〜3回の最大値を記録しましょう。
運動と栄養介入を始めたら1〜2週間ごとにミニ再評価を推奨します。体重、主観的疲労、活動量(歩数や実施回数)、4 m 歩行時間、握力のうち2つ以上を追うと変化が掴みやすいです。4週間で小目標を見直すと定着しやすくなります。
個人差はありますが、歩行や立ち上がりなどの機能面は2〜4週間で体感的な改善が出ることが多いです。体重・筋量は長めのスパンで。数値だけでなく「外出が増えた」「疲れにくい」など行動変化も重要な成果指標です。
胸痛・強い息切れ・めまい・失神感・冷汗・発熱・著しい血圧変動などがあれば即中止し医療者へ相談してください。運動前後の水分補給、薬剤(降圧薬・睡眠薬など)の影響、起立性低血圧への配慮も重要です。