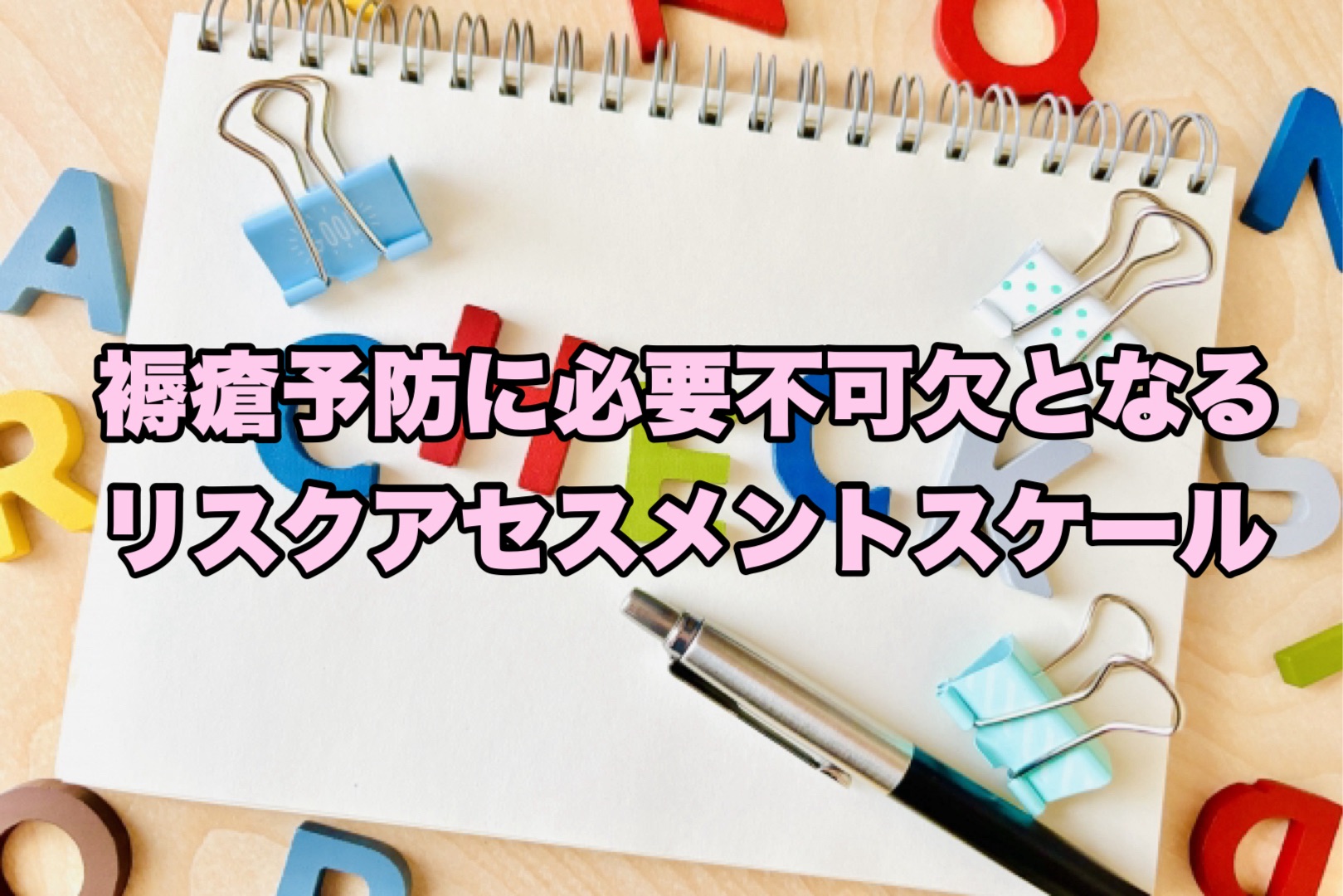褥瘡リスクスクリーニング【使い分け表+共通記録+体位変換計画】
入退院時・術後・状態変化時に標準化された褥瘡リスクアセスメントスケール/ツールを用いて層別化し、体位変換・寝具・皮膚ケア・栄養などの具体的な褥瘡予防介入へつなげることが重要です。本ページでは Braden・Norton・Waterlow に加え、 K 式・ OH スケール・厚労省危険因子評価表・在宅向けツールなどの特徴と使い分けを 1 ページに整理します。
ページ冒頭にA4 配布物(使い分け早見表/共通記録シート/体位変換・除圧計画)を用意しました。スコアの数値だけでなく、「どの危険因子が強いのか」「どの介入をいつまで続けるのか」をチームで共有する共通フォーマットとしてご活用ください。
使い分け早見表(A4・印刷) 共通記録シート(A4) 体位変換・除圧計画(A4)
まず何を使う?(場面別ファーストチョイス)
- 急性期入院・術後早期: 緊急入院や術後すぐは、まず Norton などの簡便なスクリーニングで「見落としがないか」を確認し、陽性やハイリスク例は Braden や K 式で詳しく層別化します。
- 回復期・療養: Braden を週 1–2 回の定期評価に用い、スコアのトレンドと個々の危険因子(湿潤・活動性・栄養など)を追います。骨突出や拘縮が強い症例では OH スケールや厚労省危険因子評価表を併用すると、局所リスクが整理しやすくなります。
- 在宅・施設: 訪問リハや介護施設では、簡易チェックや在宅版 K 式・ PPRA-Home などを起点にし、必要時に Braden で詳細評価を行います。ベッド・車いす・介護体制・栄養状態を一体として評価することがポイントです。
※本ページは褥瘡リスクアセスメントスケールの公式設問を転載しません。実施・採点は必ず正規様式・マニュアルに従ってください。
代表的スケールの使い分け(要点)
ここでは、よく用いられる褥瘡リスクアセスメントツールの一般的な特徴を比較します。自施設の基準・ガイドラインを前提としたうえで、「どの場面でどれを使うか」をチームで統一しておくことが重要です。
| スケール | 主な対象 / 場面 | 所要 | 評価軸(概略) | 強み | 注意 | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden | 入院全般 / 回復期・療養 | 3–5 分 | 感覚・湿潤・活動・可動・栄養・摩擦 / ずれ | 普及度が高く、危険因子ごとに介入へ落とし込みやすい | 評価者教育が不十分だとばらつきや過小評価が起きやすい | リスク層別 → 体位変換頻度・マットレス・栄養・モビライゼーションを具体化 |
| Norton | 急性期〜慢性期の簡便スクリーニング | 1–3 分 | 身体状態・精神状態・活動・可動性・失禁 | 項目数が少なく導入しやすい・初期スクリーニング向き | 感度・特異度が施設特性に左右される | 陽性例 → Braden や K 式などで詳細評価し、介入パスを作成 |
| Waterlow | 看護現場での包括的評価 | 3–6 分 | 体格・皮膚・年齢・性別・失禁・食事・可動性・全身状態など | 要素が多く、褥瘡関連の危険因子を網羅的に拾いやすい | 項目・配点が多く、習熟まで評価負荷が高い | 高リスク例 → 自施設の褥瘡予防パス(体位変換・寝具・ケア)に自動的に接続 |
| K 式スケール | 高齢入院患者・介護保険領域 | 3–5 分 | 前段階要因(活動性・栄養など)と引き金要因(発熱・手術など) | 高齢者の褥瘡危険因子を日本の実情に合わせて整理しやすい | 「引き金要因」の把握には医師・看護・リハの情報共有が必須 | 高リスク例 → 体位変換・離床・水分 / 栄養管理を早期に強化 |
| OH スケール | 拘縮や骨突出が強い症例・長期療養 | 3–5 分 | 骨突出・拘縮・体位変換能力・疼痛など局所リスク | 「どの部位がどれくらい危険か」を局所的に把握しやすい | ベッド上姿勢・座位姿勢の観察を伴うため、やや手間がかかる | 高リスク部位 → 体圧分散マットレスやクッション選定・ポジショニングに直結 |
| 厚労省 危険因子評価表 | 急性期〜回復期病棟・診療報酬要件の確認 | 3–5 分 | 年齢・活動性・栄養・失禁・既往褥瘡などの危険因子 | 診療報酬上の褥瘡ハイリスク患者の判定に用いられる | スコアだけに頼ると個別要因が見えにくい | 褥瘡対策加算の該当確認と合わせて、Braden 等で危険因子を詳細に再整理 |
| 在宅版 K 式 / PPRA-Home | 在宅・施設・訪問リハビリテーション | 2–4 分 | 活動性・介護力・環境整備・栄養状態など | 在宅特有の要素(介護体制・住宅環境)を評価に組み込める | ツールごとに採点方法が異なるため、統一した研修が必要 | 陽性例 → ベッド・車いす・ポジショニングと介護指導をセットで計画 |
層別→具体アクション(例)
スケールでリスク層別したあとは、「どの層に何をするか」をあらかじめ決めておくと現場運用がスムーズです。以下は一例であり、自施設の褥瘡対策チームでの合意形成が前提です。
- 高リスク: 1–2 時間ごとの体位変換(夜間も含む)/高機能体圧分散マットレス・車いすクッションの導入/失禁ケアプロトコル(皮膚洗浄・保護剤)/栄養評価と高カロリー・高たんぱく介入/除圧姿勢でも呼吸・循環を悪化させないポジショニング。
- 中リスク: 2–3 時間ごとの体位変換/中等度の体圧分散寝具への変更/踵などの高リスク部位へのピローリング/皮膚観察と保湿ケアの強化/活動量や水分摂取の促進。
- 低リスク: 日常ケアの範囲での体位変換・離床/定期的な皮膚観察と評価スケールの再評価/状態変化(発熱・ADL 低下・栄養低下)時の早期再スクリーニング。
再評価のタイミング
褥瘡リスクは「一度測って終わり」ではなく、状態変化に応じて見直すことが重要です。
- 入院初期: 入院時スクリーニング後、24–48 時間以内に 1 回目の再評価(急性期の状態変化を反映させる)。
- 以降の入院中: 回復期・療養病棟では週 1–2 回を目安に継続評価し、スコアのトレンド変化があれば体位変換頻度・寝具・栄養介入を見直します。
- 在宅・施設: 寝たきりへの移行・急性疾患の罹患・体重減少・介護力低下など、リスクが変化したタイミングで臨時再評価を行います。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
スケールはどれか 1 つに固定すべき?
まずは自施設で「標準スケール」を 1 つ決めることが大切です。そのうえで、急性期の初期スクリーニングには Norton、継続モニタリングには Braden、高齢・拘縮が強い症例には K 式や OH スケール、在宅では在宅版 K 式 / PPRA-Home を補助的に使うなど、場面ごとにサブツールを位置付けると運用しやすくなります。
Braden スケールのカットオフはどのくらい?
文献やガイドラインでは、概ね「合計点が低いほどリスクが高い」とされ、18 点未満をリスクありとみなす報告が多いです。ただし、急性期・回復期・在宅など場面によって最適なカットオフは異なります。自施設の患者特性・褥瘡発生率を踏まえ、褥瘡対策チームでカットオフと対応する介入レベルを決めておくことが重要です。
K 式や OH スケールはどんな症例に向いている?
K 式は高齢入院患者の前段階要因(活動性や栄養)と引き金要因(手術・発熱など)を整理したいときに有用です。OH スケールは骨突出や拘縮が強い長期療養者で、「どの部位にどれくらい局所リスクがあるか」を可視化したいときに役立ちます。Braden など全身的なスケールでは見えにくい部分を補完する役割と考えると整理しやすくなります。
PT・OT・ST はスコア以外に何を記録しておくべき?
スコアに加えて、体位変換自立度・座位耐久性・車いすやベッドの種類・ポジショニングで痛みが出る部位・栄養リスク(食思不振・サルコペニア疑いなど)をメモしておくと、体位変換計画・寝具選定・栄養介入をチームで検討しやすくなります。本ページの共通記録シートを使えば、これらの情報を 1 枚に集約できます。
おわりに
実地では「リスクスクリーニング → 危険度の層別化 → 体位変換・寝具・皮膚ケア・栄養などの介入 → 再評価」というリズムを崩さないことが褥瘡予防の基本になります。複数のリスクアセスメントツールの強みと限界を理解し、病棟・在宅・施設それぞれの場面で「いつ・誰が・どのスケールを使うか」をチームで揃えておくことが、現場の負担を減らしつつアウトカムを改善する近道です。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック(A4・5分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下