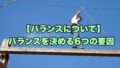METs とは?(目的と使いどころ)
METs( metabolic equivalents /メッツ)は、安静時代謝量を 1 とした相対的な運動強度の単位です。ざっくり言うと「同じ活動をしたとき、安静の何倍くらいの負荷か」を表し、運動処方・教育・リスク管理の“共通言語”として使えます。
一方で、年齢・体格・疾患・薬剤・環境で実際の代謝量はズレるため、数値は目安です。強度設定の全体像( METs → RPE → 症状で合わせる流れ)は、関連:運動強度の決め方( METs・ Borg・心拍の使い分け)でまとめています。
METs 自動計算(消費 kcal )
入力すると、概算の消費エネルギー( kcal )を自動計算します(目安)。式は kcal = METs × 体重( kg )× 時間( h )です。
METs の求め方と計算式(まずここだけ)
臨床で最優先の式は、消費エネルギーの概算です。時間は h(時間)に直して計算します。
- kcal = METs × 体重( kg )× 時間( h )
- 分で計算:kcal = METs × 体重( kg )× 分 ÷ 60
- 酸素摂取量から METs:METs = VO2( mL/kg/min )÷ 3.5
- VO2 から kcal(概算):kcal/min = VO2( mL/kg/min )× 体重( kg )÷ 200
計算例:体重 60 kg の方が 4 METs で 30 分活動した場合
4 × 60 × 30 ÷ 60 = 120 kcal
kcal 換算早見( 60 kg )
スマホでは横スクロールでご覧ください。数値は四捨五入の目安です。
| METs | 10 分 | 30 分 | 60 分 |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 kcal | 90 kcal | 180 kcal |
| 4 | 40 kcal | 120 kcal | 240 kcal |
| 5 | 50 kcal | 150 kcal | 300 kcal |
| 6 | 60 kcal | 180 kcal | 360 kcal |
| 8 | 80 kcal | 240 kcal | 480 kcal |
他の体重は「kcal = METs × 体重 × 時間」で計算します。概算として、50 kg は上表の値 × 0.83、70 kg は × 1.17 が目安です。
体重別の換算係数( 60 kg を 1.00 とした目安)
スマホでは横スクロールでご覧ください。
| 体重 | 係数 | 体重 | 係数 | 体重 | 係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 0.75 | 60 kg | 1.00 | 75 kg | 1.25 |
| 50 kg | 0.83 | 65 kg | 1.08 | 80 kg | 1.33 |
| 55 kg | 0.92 | 70 kg | 1.17 | 90 kg | 1.50 |
代表的な活動の METs(抜粋・代表値)
活動の METs は、速度・路面・斜度・気温・技術で変動します。ここでは「当たりを付ける」ための抜粋を示し、最終判断は RPE( Borg )と症状で補正します。
スマホでは横スクロールでご覧ください。
| 活動 | 具体例 | METs |
|---|---|---|
| 歩行 | 普通(約 3.0 mph ) | 3.0–3.5 |
| 歩行 | 早歩き(約 3.5–4.0 mph ) | 4.3–5.0 |
| 階段昇り | 手すり併用含む | 6.0–8.8 |
| 家事 | 掃除機・床掃き | 3.0–3.5 |
| ジョギング | 約 5 mph(時速 8 km ) | 8 |
METs と RPE・%HRR のブリッジ(目安)
METs は絶対強度、 RPE は相対強度です。成人一般を想定した便宜的な対応表を示しますが、β 遮断薬、心疾患、自律神経障害、暑熱環境では乖離しやすいため、必ず症状観察とセットで判断します。
スマホでは横スクロールでご覧ください。
| 区分 | METs | %HRR | RPE( 6–20 ) | 会話テスト |
|---|---|---|---|---|
| 軽度 | 1.6–2.9 | 20–39% | 9–11 | 楽に会話できる |
| 中等度 | 3.0–5.9 | 40–59% | 12–13 | やや息が上がるが会話可 |
| 高強度 | ≥ 6 | 60–84% | 14–16 | 会話は途切れがち |
| 非常に高い | ≥ 9 | ≥ 85% | 17 以上 | 会話困難 |
現場の詰まりどころ(よくある間違い→対策)
METs 計算はシンプルですが、臨床では「単位」「条件」「相対強度」の 3 つでつまずきやすいです。下の表で、迷いをそのまま“次アクション”に落とし込みます。
| よくあるミス | なぜ起きる? | 対策 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 体重を掛け忘れる | 式の “ kg ” が抜ける | kcal = METs × 体重 × 時間 を口に出して確認 | 体重( kg )を明記 |
| 分のまま掛けてしまう | 時間を h に直していない | 分 ÷ 60 を必ず入れる( 30 分= 0.5 h ) | 単位(分/ h )を併記 |
| METs と体感が合わない | 個体差・疾患・環境でズレる | RPE と症状で補正し、安全側に 1 段階弱く始める | RPE、症状、条件 |
| ウェアラブルの値を鵜呑みにする | 推定アルゴリズムが不明 | 「アプリ推定」など推定方法を併記して解釈 | 機種、装着条件 |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 1 MET は人によって違いますか?
A.実際の安静時代謝量には個体差があります。実務では便宜的に「 1 MET = 1 kcal/kg/時(目安)」として扱い、強度の最終判断は RPE( Borg )や症状と組み合わせて安全側に調整します。
Q2. 10 分など短時間でも kcal を計算する意味はありますか?
A.あります。短時間でも「強度 × 時間」を数値化すると、週単位の積み上げ(総量)を説明しやすくなります。まずは無理のない時間で開始し、体調・症状を見ながら段階的に増やします。
Q3. VO2 から METs を出す式は臨床で使いますか?
A.呼気ガス分析がある環境では有用です。一般臨床では、患者説明や運動処方の“共通言語”として METs を使い、最終は RPE と症状で合わせる運用が現実的です。
Q4.「同じ 4 METs 」でも日によってきつさが違うのはなぜ?
A.睡眠、脱水、暑熱、感染後、疼痛、薬剤などで相対強度が変動します。活動条件(速度・坂・休憩)と RPE・症状をセットで記録し、その日の状態に合わせて微調整します。
参考文献
- Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, et al. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(8):1575–1581. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31821ece12 / PubMed: 21681120
- Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, et al. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334–1359. DOI: 10.1249/MSS.0b013e318213fefb / PubMed: 21694556
- Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. PubMed: 7154893
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
おわりに
METs の計算は、安全の確認→段階介入→条件をそろえて記録→再評価のリズムに入れると、現場で“使える知識”になります。まずは自動計算で当たりを付け、体感( RPE )と症状で微調整する運用が最短です。
数値は便利ですが、ズレる場面は必ずあります。体調変動や暑熱、薬剤の影響があるときほど、短時間から始めて、条件と反応を残しながら積み上げていきましょう。