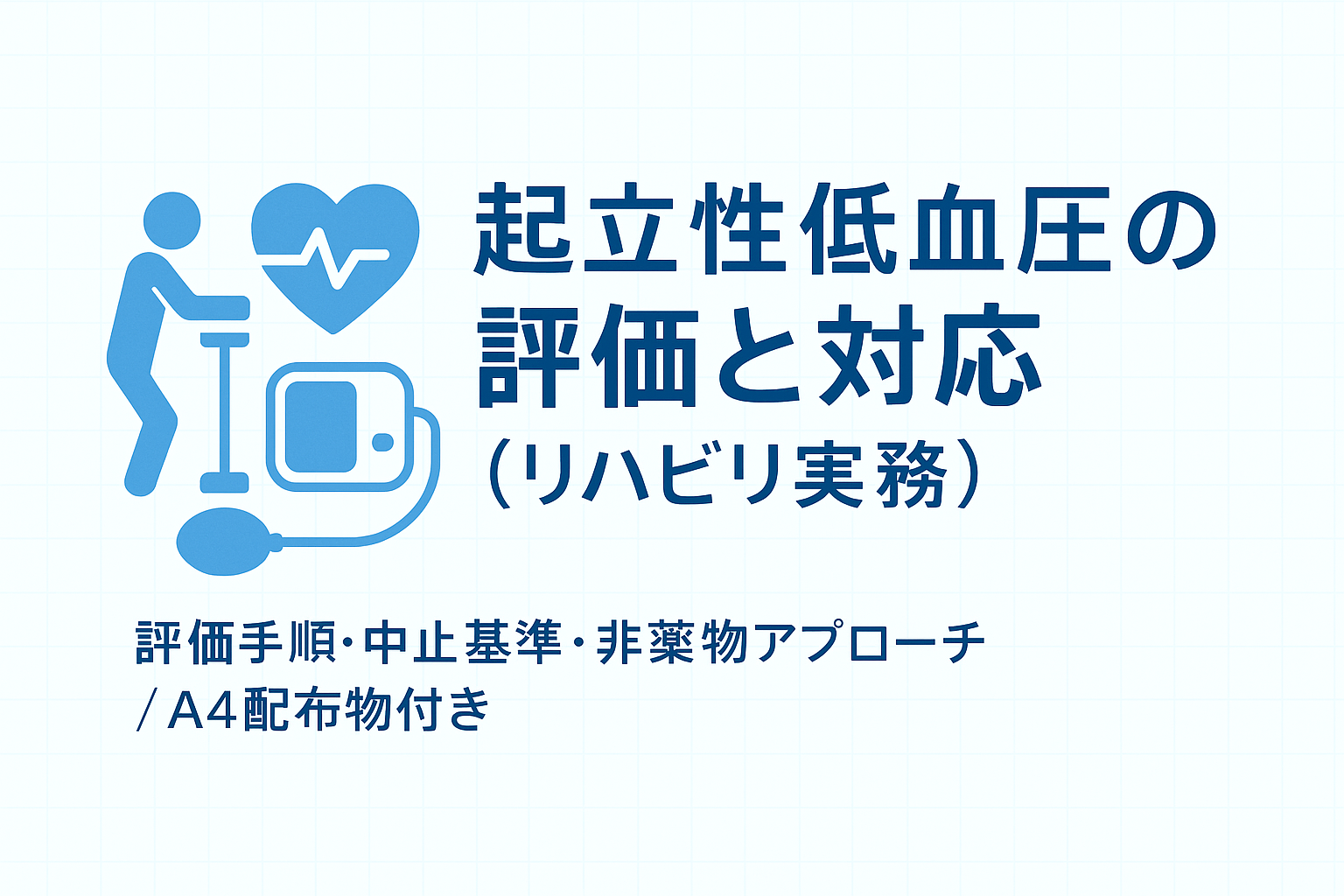起立性低血圧の評価と対応(リハビリ実務)|チェックリスト&患者指導プリント
本ページは、起立性低血圧( orthostatic hypotension / 体位変換性低血圧・OH )の評価とリハビリでの対応を 1 ページで完結できるよう再編集しました。測定条件、禁忌・中止基準、非薬物療法のコツ、家族配布用プリントまでを網羅します。
まずは A4 評価チェックリスト と 患者指導プリント をダウンロードしてから読み進めてください(当サイト既定運用)。
関連:位置づけや関連指標は 呼吸・運動耐容能の評価ハブ にまとめています。
- ✔ 起立性低血圧の 評価プロトコル(所要 7 分) と判定のコツ
- ✔ リハビリでの 対応(非薬物アプローチ)早見表:弾性ストッキング・腹帯・段階的起立 等
- ✔ A4 配布物:評価チェックリスト/患者指導プリント(朝の起立手順)
- ✔ 症例ミニケース 3 本(結果 → 解釈 → 次アクション)
- ✔ よくある質問(FAQ)と中止基準
評価チェックリスト(A4・印刷) 患者指導プリント:朝の起立手順(A4)
起立性低血圧の評価(要点まとめ)
- 臥位 5 分安静 → 起立 1 分・3 分で BP/HR を測定(同一条件)
- 判定の目安:SBP −20 mmHg 以上、または DBP −10 mmHg 以上の低下+症状
- 主観(めまい NRS 等)と客観(BP・HR・SpO2)を同時記録
- 危険サイン:失神前駆・蒼白・冷汗・SBP < 90・SpO2 低下 → 中止
起立性低血圧の評価プロトコル(リハビリ導入前の標準手順)
目的:体位変換時の血圧低下と症状の出現を再現性高く確認し、安全に次アクションへつなげます。
- 前準備(2 分):禁忌チェック(中止基準)、カフサイズ確認、利き腕の反対で測定、利尿薬・食後すぐ等の影響因子をメモ。
- 臥位 5 分安静:臥位血圧・脈拍を測定。
- 起立直後〜 1 分:安全確保しつつ起立。起立 1 分の血圧・脈拍、症状(めまい・失神前)をメモ。
- 起立 3 分:起立 3 分の血圧・脈拍、症状有無。必要に応じて 5 分まで継続。
- 判定の目安:収縮期 −20 / 拡張期 −10 低下を主指標とし、症状の出現と併せて判断。
記録は 臥位 → 1 分 → 3 分(→ 5 分) の順に、BP(SBP/DBP)、HR、症状(有/無・具体)を 1 行で残します。院内共有のため、評価チェックリストの利用を推奨します。
起立性低血圧の対応(リハビリ)早見表|評価結果からの使い分け
| 状況 | よくある要因 | 最初の一手(対応) | フォロー |
|---|---|---|---|
| 食後や朝に症状が強い | 脱水・夜間利尿・食後低血圧 | 段階的起立(座位 → 端座位 → 立位)/朝のコップ 1 杯の水 | 朝の手順プリント配布、食後の前屈姿勢回避 |
| 神経因性を疑う | 自律神経障害、パーキンソン関連 | 弾性ストッキング・腹帯、分割起立訓練、薬剤整理を主治医へ情報提供 | 転倒歴・失神前駆の聴取、夜間トイレ動線の安全化 |
| 薬剤影響が濃厚 | 降圧薬、利尿薬、α 遮断薬 等 | 服薬タイミング・用量の情報整理 → 主治医へ共有 | 再評価スケジュール(7〜14 日目安) |
リハビリでの対応(非薬物アプローチ)
- 段階的起立:臥位 → 30° 座位 → 端座位 → 立位、それぞれ 30〜60 秒で症状確認。
- 水分・塩分:医師の方針に従う前提で、朝のコップ 1 杯の水など簡便策を検討。
- 下肢・腹部圧迫:弾性ストッキング・腹帯は装着手順と再評価をセットで。
- カウンターマニューバ:大腿・殿筋の等尺性収縮、下肢交差など(症状前駆で実施)。
- 環境調整:夜間動線、トイレ照明、立ち座り手すり、座面高の是正。
| デバイス | 主目的 | 適応の目安 | 注意/禁忌の目安 | 装着手順(要点) | 観察ポイント | 再評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性ストッキング(下腿〜大腿) | 静脈還流の促進・下肢血液プールの抑制 | 起床時のふらつき、起立 1〜3 分での BP 低下が持続する例 | 重度末梢動脈疾患、皮膚潰瘍の活動期、著明な浮腫の急性増悪 |
① 朝の起立前に装着/座位で足関節背屈 ② 皺・ロールを作らない(膝窩・足関節) ③ 適正サイズ(ふくらはぎ・大腿周径計測) ④ 日中活動時は継続、就寝時は原則外す |
しびれ・痛み・蒼白、皮膚発赤/水疱、末梢冷感 | 初回は装着直後と 30 分後に BP/症状確認 → 以後は毎日朝と午後で比較。効果不十分ならサイズ・長さ・圧を再検討 |
| 腹帯(腹部コンプレッション) | 腹腔内圧の上昇による静脈還流の補助 | 神経因性 OH(パーキンソン関連、自律神経障害)での立位耐性低下 | 術後創部・腹部疼痛の増悪、呼吸困難の誘発、胃食道逆流の悪化 |
① 立ち上がる前に下腹部を中心に装着 ② 苦痛のない圧で固定(会話と深呼吸が可能な範囲) ③ 食後すぐは強圧を避ける/体位変換時は苦痛の有無を確認 |
圧迫感・悪心、呼吸のしづらさ、食後の胃部不快、皮膚トラブル | 装着前後・立位 1 分・3 分の BP/HR と症状を比較。2〜3 日で効果を判定し、運用(時間帯・圧)を最適化 |
※ 施設の SOP と主治医の方針を最優先。皮膚観察と末梢循環の確認を必ずセットにしてください。
装着の流れ(図解テキスト:弾性ストッキング/腹帯)
- 準備:サイズ計測(周径・長さ)/皮膚チェック/起床前に座位で足関節を動かす
- 弾性ストッキング:つま先 → 踵 → ふくらはぎ → 大腿の順に皺なしで装着/膝窩の食い込み禁止
- 腹帯:下腹部中心に装着 → 呼吸・会話が楽にできる圧に調整(食後は弱め)
- 評価:臥位 → 立位 1 分 → 3 分で BP/HR・症状を記録(同一条件)
- 運用:日中は継続、就寝時は原則解除/皮膚・循環トラブル時は中止して再評価
薬物療法は医師判断です(例:ミドドリン、ドロキシドパ 等)。療法士は評価所見・発症状況・服薬情報・転倒歴を簡潔に整理し共有します。
症例ミニケース(評価 → 解釈 → 対応)
- 回復期・脳卒中後:臥位 138/76 → 1 分 110/64(めまい)→ 3 分 106/62。解釈:SBP −28、症状あり。対応:段階的起立+弾性ストッキング、服薬整理を主治医に情報提供。
- パーキンソン関連:起床時にふらつき。臥位 130/70 → 3 分 100/60。対応:朝のコップ 1 杯、腹帯、起立訓練、夜間動線の安全化。
- 整形周術期:疼痛薬・利尿薬使用。起立 1 分で SBP −18、3 分 −22。対応:服薬タイミングの情報整理 → 主治医相談、短期再評価。
禁忌・中止基準(レッドフラッグ)
- 前失神・意識消失、胸痛、冷汗・蒼白などショック兆候
- SBP < 90 mmHg が持続、脈拍の著明な不整
- 頸動脈洞過敏症が疑われる場合の過度な頸部伸展
いずれか出現時は即座に座位・臥位へ戻し、必要に応じて医療者へ連絡します。
よくある質問(FAQ)|評価とリハビリの実務
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
起立性低血圧の評価は 1 分と 3 分のどちらが重要?
どちらも重要です。起立直後〜 1 分で急峻な低下を捉え、3 分時点で持続性を確認します。症状の出現有無も併記してください。
弾性ストッキングはリハビリのどのタイミングで対応に組み込む?
朝の起立前に装着し、日中活動時に継続するのが一般的です。就寝時は原則外し、翌朝再装着します(皮膚観察を忘れずに)。
水分・塩分対応の一般的な考え方は?
心不全や腎機能などの併存疾患により指示が異なります。必ず主治医の方針に従ってください。
どの数値ならリハビリを中止・中断すべき?
失神前駆・蒼白・冷汗、SBP < 90、SBP −20 / DBP −10 低下+症状、SpO2 の持続低下などは中断して安全確保します。測定は臥位 → 1 分 → 3 分で再評価します。
関連記事
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下