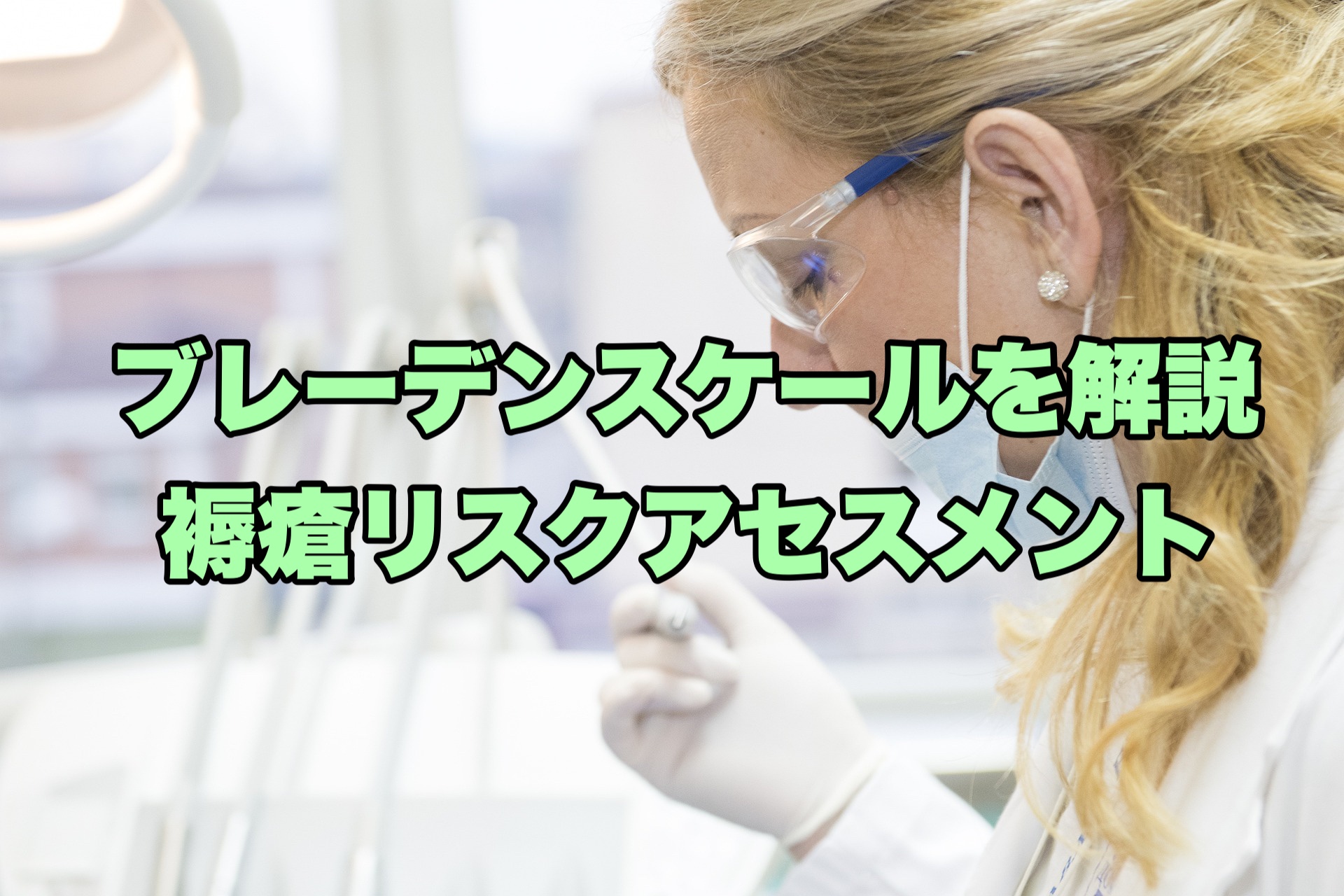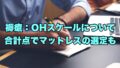ブレーデンスケールの使い方|評価方法と点数の見方
結論:ブレーデンスケール( Braden Scale )の「使い方」は、① 6 項目を “最も低い水準” で採点 → ② 総点より先に弱点項目を特定 → ③ 弱点(湿潤/摩擦・ずれ/活動・移動/栄養)に直結する介入をセット化の順に回すと迷いが減ります。
ブレーデンスケールは、感覚知覚・湿潤・活動・移動・栄養・摩擦・ずれの 6 項目で褥瘡リスクを 6–23 点のスコアで評価するツールです。一般的には総合点 ≤ 18 を「褥瘡リスクあり」の目安としますが、最終判断は病棟特性や院内規定、対象者の臨床像を優先します。褥瘡予防の全体像( PT が介入で変えやすいポイントの整理)は 褥瘡予防 × 理学療法士|基本フロー にまとめています。
重要なのは総合点だけでなく、「どの項目の点数が低いか」を可視化し、褥瘡予防ケア(体位変換・寝具・栄養・スキンケア)の優先順位に直結させることです。たとえば湿潤が弱い人なら失禁対策やスキンケアを、活動・移動が弱い人ならポジショニングや離床、体圧分散マットレスの見直しへと結びつけます。
ブレーデンスケールの使い方( 5 分手順 )
「採点する」だけだとケアが動きません。採点 → 翻訳(弱点の言語化)→ 介入 → 再評価までを 1 セットで回すのがコツです。
- いつ評価するか:入院・入所時/転棟・転院時/状態変化( ADL 低下、鎮静、発熱、下痢、摂取低下など)をトリガーに実施
- 6 項目を採点:原則は「直近 24 時間の実態」。迷ったら安全側(低得点)に倒す
- 弱点項目を 1 行化:例)「主因は湿潤+ずれ」/「踵の底つきが主因」
- 介入をセット化:除圧(体位変換)+ずれ対策(引き上げ/介助法)+支持面(寝具)+湿潤対策+栄養連携
- 再評価を予定にする:総点だけでなく項目別の変化(例:湿潤 2 → 3 )で効果を確認し、強化/緩和を決める
ブレーデンスケールの 6 項目と着眼点
ブレーデンスケールの 6 項目は、外力(圧・ずれ・摩擦)と組織耐久性に関わる因子をカバーしています。評価は原則として「直近 24 時間の実態」を基準に、最も当てはまるレベルで採点します。判断に迷うときは安全側(低得点)に倒し、「弱点項目=優先的に介入するポイント」としてチームで共有すると、褥瘡予防のケア計画がぶれにくくなります。
摩擦・ずれのみ 1–3 点評価(他の因子は 1–4 点)で、ベッド上でのずり上がりや頭高位固定などの影響を強く受けます。移乗・離床の方法、スライディングシートやリフトの使用、寝具の選択を合わせて見直すことで、ブレーデンスケールの点数改善だけでなく実際の褥瘡リスク低減につながります。
| 総合点 | リスク区分(目安) | 介入の例 |
|---|---|---|
| ≤ 9 | 非常に高い | 高度な体圧分散マットレス、自動体位変換の活用、2–3 時間毎の体位変換、皮膚保護材、栄養評価の即時実施 |
| 10–12 | 高い | エアマット導入、ずれ対策(スライディングシート/リフト)、排泄ケアの標準化、スキンケアの強化 |
| 13–14 | 中等度 | 静止型または交互圧マットレス、2–4 時間毎の体位変換、離床拡大とポジショニング再検討 |
| 15–18 | 軽度 | 標準マットレスの見直し、セルフ体位変換の促進、患者・家族への教育 |
| ≥ 19 | リスク低 | 基本ケアの継続、状態変化時に再評価 |
ブレーデンスケールの評価方法と点数の見方
ブレーデンスケールの評価方法は「患者の最も低い機能水準」に合わせて点数をつけることが原則です。たとえば、日中は車いす座位でも夜間はベッド上全介助であれば、活動レベルは低い方に合わせて評価します。留置カテーテル中で失禁はなくても、皮膚湿潤リスクが残る場合は「湿潤」を過大評価しないよう注意が必要です。
活動は「ベッド外への離床レベル」、移動は「ベッド上で体位を変えたり、ずり上がりできるか」といった軸で考えると迷いにくくなります。点数評価と同時に、「なぜその点数になったのか」を短いコメントで残しておくと、多職種カンファレンスでの共有がスムーズです。ブレーデンスケールの結果を、体位変換・寝具・栄養など具体的なケアにどう落とし込むかをセットで考えることが重要です。
再評価のタイミングは、「入院・入所時/状態変化時/転棟・転院時」を原則とし、急性期病棟では 48 時間ごとの評価を運用例として設定する施設もあります。総合点の推移だけでなく、弱点項目の改善度(例:湿潤 2 → 3、活動 1 → 2)を追うことで、介入効果を客観的に振り返りやすくなります。
よくある採点ミス:ここを直すと “使い方” が安定する
「点数が合わない」「毎回ブレる」は、観察軸が混ざっていることが多いです。下表を“チーム内の共通ルール”として使うと、採点が介入につながりやすくなります。
| つまずき | 起きやすい誤解 | 防ぎ方(判断軸) | 記録の一言例 |
|---|---|---|---|
| 活動と移動の混同 | 離床できる=ベッド上でも動ける、と判断してしまう | 活動=ベッド外(座位・立位・歩行)/移動=ベッド上の体位変換・ずり上がり | 離床は可だが夜間の寝返りは不可 |
| 湿潤の過小評価 | 失禁がないと湿潤リスクなし、と判断しがち | 発汗・浸軟・滲出・おむつ内環境など “皮膚が湿る要因” で判断 | 会陰部に浸軟あり/スキンケア強化 |
| 摩擦・ずれの見落とし | 圧(体圧)だけで考えてしまう | 頭側挙上・ずり落ち・移乗介助の剪断をセットで観察(姿勢・介助法・支持面も含める) | 背上げで前滑り大/引き上げを標準化 |
| 日中だけで採点する | 昼は動けるから高得点にしがち | 原則は “最も低い機能水準” に合わせる(夜間・疲労・鎮静を含む) | 夜間は全介助で同一体位が長い |
評価表( PDF ダウンロード )
ブレーデンスケールの評価表は、スコアリングの抜け漏れを防ぐチェックリストとして利用できます。床頭台やラウンド用ファイルに挟み、褥瘡リスクの高い症例では看護師・リハビリ・栄養士が同じシートを見ながら話し合うと、ケア方針の共有が容易になります。
カットオフ値と運用の考え方
一般的な運用では、ブレーデンスケールの総合点 ≤ 18 を「褥瘡リスクあり」とみなし、体圧分散マットレス導入や体位変換頻度の見直しなどを検討します。ただし、 ICU や高度急性期など患者背景が大きく異なる環境では、最適なカットオフ値が 12–16 程度に変動することも報告されています。
本記事では、「標準的な目安は ≤ 18 /しかし運用は各施設の規定と病棟特性を最優先」という二層構造で説明することを推奨します。カットオフ値はあくまでスタートラインであり、「スコアが低いから終わり」ではなく、「なぜ低いのか」「どの項目から介入するか」を考えるためのトリガーとして活用します。特に体圧分散・ずれ対策・栄養の 3 本柱は、弱い項目に合わせてセットで実装することが重要です。
褥瘡評価における他スケールとの使い分け
褥瘡評価に用いられるスケールには、ブレーデンスケール以外にも OH スケールや K 式スケールなどがあり、介護力や生活環境を反映しやすい特徴があります。在宅や介護施設では、介護者の負担や環境調整の視点を含めやすいこれらのスケールが有用な場面も多くあります。
一方で、ブレーデンスケールは 6 項目が明確で、点数と評価項目がそのままケアプランに落とし込みやすいのが利点です。「どの褥瘡リスク要因が弱いのか」を因子別に特定しやすいため、多職種での共有や対策の優先順位付けに向いています。小児では Braden Q/QD などの小児版スケールの使用が推奨されており、新生児・小児 ICU や医療デバイス関連褥瘡のリスク評価に対応しています。
まとめ
・ブレーデンスケールの「使い方」は、採点 → 弱点項目の特定 → 介入セット化 → 再評価までを 1 セットで回すと迷いが減ります。
・評価では総合点だけでなく、「どの項目が低いか=どこから介入するか」を明確にすることが重要です。
・カットオフの標準的な目安は総合点 ≤ 18 ですが、最終的な判断は院内規定と病棟特性、対象者の臨床像を優先します。
・体圧分散・ずれ対策・栄養介入を、ブレーデンスケールの弱点項目に合わせてセットで実装し、入院時・状態変化時・転棟時に再評価していきましょう。
おわりに
実地では「スクリーニング → リスクの見える化 → ケア計画 → 再評価」というリズムを途切れさせないことが、褥瘡予防の要となります。ブレーデンスケールの点数や評価方法をチームで共有し、弱い項目に応じた体位変換・寝具・栄養介入を日々のラウンドに織り込むことで、褥瘡リスクの高い症例でも安心して在院・在宅を支えられます。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止には、見学や情報収集中から使える面談準備チェックと職場評価シートが役立ちます。転職を具体的に考える前の段階でも、面談準備チェックと職場評価シート( A4 )を印刷しておけば、療法士として大切にしたい褥瘡ケアの体制や教育環境を整理しやすくなります。
参考文献
- Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, Holman V. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk. Nurs Res. 1987;36(4):205–210. PubMed / DOI
- Agency for Healthcare Research and Quality. Preventing Pressure Ulcers in Hospitals: Braden Scale. AHRQ
- Huang C, et al. Predictive validity of the Braden Scale for pressure injury risk: systematic review and meta-analysis. Nurs Open. 2021;8(5):2194–2207. PubMed / DOI
- 日本褥瘡学会. 褥瘡の予防(一般向け). JSPU
- Indiana Dept. of Health. Braden Scale(スコア帯を含む配布版). PDF
- Braden Q / QD(小児)教育モジュール. Children’s Hospital of Philadelphia. CHOP
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、褥瘡予防や体圧管理、栄養(リハ栄養)などの領域を中心に、臨床で明日から使える評価・プロトコルを発信しています。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下