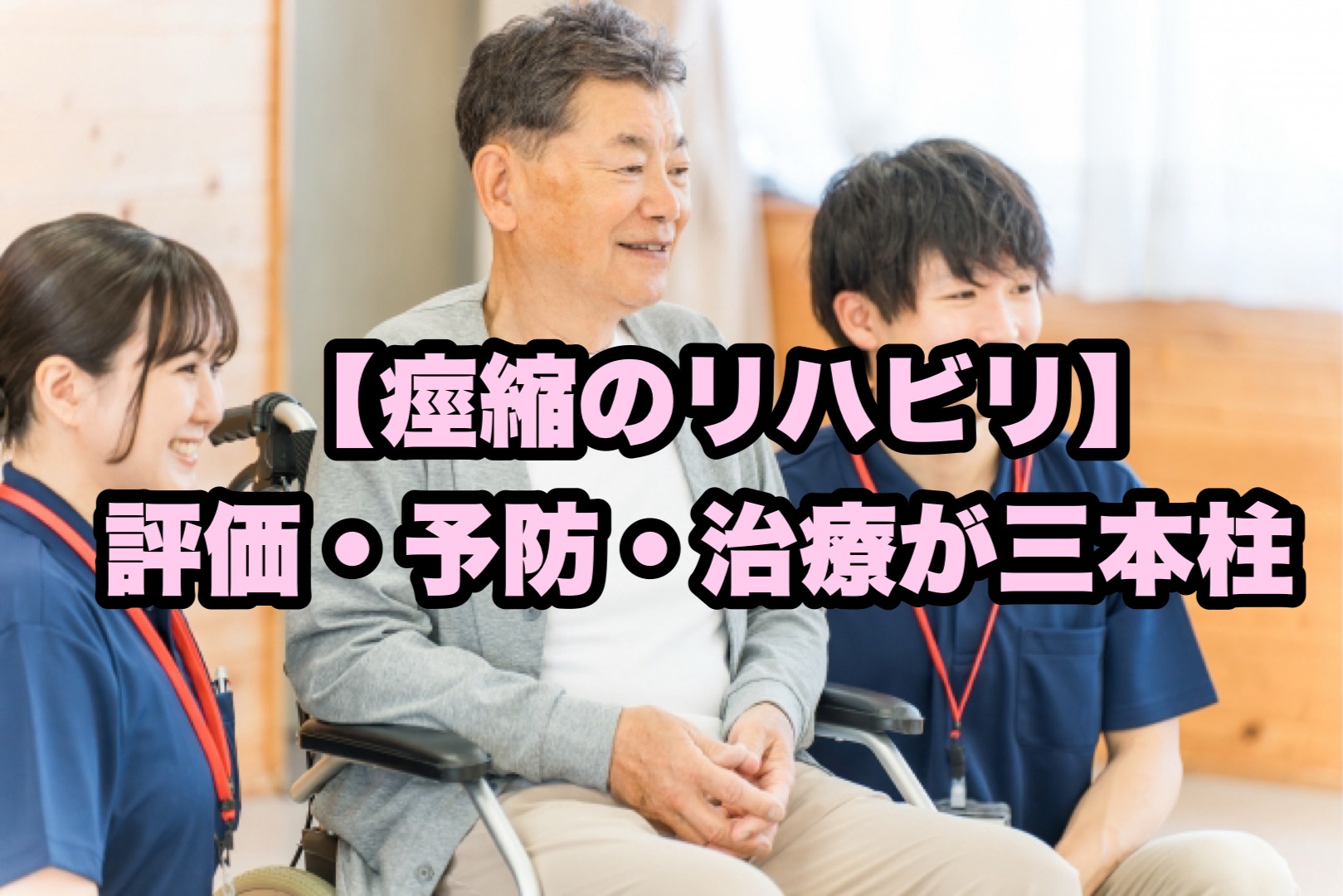痙縮リハビリの基本(総論)
痙縮は上位運動ニューロン障害に伴う 伸張反射の速度依存性亢進で、 ADL ・ QOL を阻害し、拘縮や疼痛を招きます。本稿は「評価・予防・治療」の全体像を 総論として整理し、詳細は専門記事へつなげます。関連:脳卒中ハブ(保存版)
現場では「測る → 用量を決める → 再評価」を週次で回し、薬物・注射療法と理学療法を統合して運用することが要点です。評価は 鑑別(痙縮・固縮・拘縮)と 定量化( MAS / MTS )を分けて考えると迷いにくく、さらに歩行・セルフケアなどの 生活アウトカムで効果を確かめると、チームの方向性が揃いやすくなります。
痙縮の典型パターン
痙縮は パターンで捉えると臨床判断が整理しやすくなります。上肢は「肩内転・内旋、肘屈曲、前腕回内、手関節屈曲、母指内転」、下肢は「内転歩行、反張膝、尖足 / 内反尖足」が典型です。まずは立位・歩行・座位での姿勢パターンを押さえ、どの関節群が生活上の困りごとに直結しているかを明確にします。
そのうえで、 ADL 影響(更衣・整容・排泄・歩行)と二次障害(筋短縮・皮膚トラブル・疼痛)を動作観察と併せて必ず記録します。筋トーヌスだけでなく「手が袖に入らない」「靴を履くときに足が内反してしまう」など、患者さんや家族の言葉もカルテに残すと、治療ターゲットと介入効果が共有しやすくなります。
評価:鑑別 → 定量化 → 生活アウトカム
痙縮は 速度依存で他動抵抗として現れます。まずは他動運動で「痙縮(速度依存)」「固縮(速度非依存)」「拘縮(関節 / 軟部の構造変化)」を切り分け、過緊張が “主因” か “付随所見” かを整理します。鑑別が曖昧なまま介入すると、伸張や装具が痛みを増やしたり、逆に歩行の安定を崩すことがあります。
次に、痙縮が主要因なら MAS / MTS で定量化し、注射や装具導入前後の変化を比較しやすくします。ただし、スコアは「抵抗感」の評価であり、機能改善や生活動作の変化をそのまま反映するものではありません。したがって、再評価は同一肢位・同一速度・できれば同一時刻で揃えつつ、 10 m 歩行、 TUG 、 5 回椅子立ち上がりなどの機能指標もセットで記録し、「スコア変化が生活にどう効いたか」を確認します。
予防: ROM ・離床・ポジショニングの基本
ROM 運動と持続伸張は拘縮予防を第一目的に行い、効果判定は関節角度(能動・他動)と ADL 指標で行います。長期臥床を避け、早期からの離床と座位・立位の安定化を進めることで、痙縮パターンの固定化を遅らせることができます。特に肩外転・股外転位の確保や、ベッド上でのポジショニングは「毎日続けられる最小単位のバンドル」として設計します。
ただし、伸張は万能ではなく、慢性期の痙縮そのものを単独で大きく軽減することは難しいとされています。そのため、単独介入に過度な期待をせず、運動学習・装具・電気刺激・薬物療法と束で設計することが大切です。記録上も「どの組み合わせが、どのタイミングで効いたか」を残しておくと、次の患者さんにも活かしやすくなります。
治療:段階的アプローチ(理学療法 → 装具 → 注射 / ITB → 外科)
治療選択は「何のために痙縮を落とすのか」を起点に、段階的に組み立てます。たとえば「手を広げて手指衛生をしやすくする」「尖足を抑えて装具歩行を安定させる」など、 ADL ・介護負担・二次障害予防のいずれかに紐づけて目標を設定します。そのうえで、理学療法・装具・注射 / ITB ・外科を、タイミングと役割を意識して組み合わせます。
下表は成人痙縮に対するマネジメントの概略です。実際には、主治医・看護・リハビリ・義肢装具士・薬剤師など多職種でのカンファレンスを通じて、「どの部位に」「どの治療を」「いつまでに」行うかを共有することが重要です。注射や ITB 導入後は、少なくとも 2 週間程度の集中的な理学療法フェーズを設け、目標達成度を再評価します。
| 手段 | 主目的 | 適応 / 注意 | 運用のコツ |
|---|---|---|---|
| 理学療法( ROM ・持続伸張・課題特異的練習) | 拘縮予防・機能最大化 | 慢性期は単独効果が限定的 | 目標関節を決めて姿勢時間 × 週次再評価 |
| 装具 / キャスティング | 矯正位保持・伸張時間の確保 | 皮膚トラブル・疼痛に注意 | 段階矯正+ ADL への一般化を並走 |
| 電気刺激( TENS / FES 等) | 筋活動調整・歩行 / 上肢機能の補助 | 単独より併用で効果が出やすい | 課題練習と同時適用で学習を強化 |
| 薬物・注射(ボツリヌス、経口、 ITB ) | 局所 / 全身の過活動抑制 | 目標筋・用量・副作用を管理 | 目標動作と再評価セットを事前に合意 |
| 外科 | 変形是正・機能向上 | 保存療法の不十分例 | 術後の装具・再学習を計画 |
いずれの段階でも「痙縮スコアを下げること」自体が目的化しないよう注意が必要です。ゴールは、疼痛や介護負担の軽減、転倒リスク低減、生活範囲の拡大など、患者さんにとって意味のあるアウトカムです。評価指標も、 MAS / MTS のみでなく、歩行・セルフケア・介護時間などの記録とセットで残していきましょう。
臨床の運用ポイント
日々のリハビリ場面では、痙縮評価と治療プロセスを「ルーチン化」しておくと、属人的なばらつきを減らしやすくなります。特に、導入期と注射療法期は、評価・介入・再評価のテンポを意識して回すことが重要です。
| タイミング | 見るもの | 記録の型 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 週 1 回 | 鑑別(痙縮 / 固縮 / 拘縮)+ MAS / MTS + 機能( 10 m / TUG 等) | 同一肢位・同一速度・同一時刻で再現 | 目標動作の難易度を 1 段だけ更新 |
| 毎日 | 姿勢時間(スプリント / ポジショニング)と疼痛 | 「実施できた最小単位」を残す | 継続不能の理由(痛み / 皮膚 / 介護負担)を先に潰す |
| 注射 / ITB 後 | ベースライン → 2 週間の集中的 PT → 再評価 | 「目標動作」「評価日」「用いた手段」をセット | 薬効期間に課題特異的練習を集中配置 |
現場の詰まりどころとよくある失敗
現場でよく詰まるのは、「痙縮の強さ」ばかりに目が行き、生活上の困りごとと結びつけて評価できていないケースです。 MAS スコアだけをカルテに残し、どの動作で困っているか、介護者がどこで苦労しているかの記述が乏しいと、治療方針がチームで共有しにくくなります。また、夜間ポジショニングやスプリント装着など、時間のかかる介入がマンパワー不足で継続できないことも大きなボトルネックです。
よくある失敗としては、①伸張や装具のみで「何となく続けている」状態が長期化し、再評価が形骸化する、②ボツリヌス治療後に十分な課題特異的練習を行えず、薬効期間を活かしきれない、③痛みや皮膚トラブルのモニタリングが不十分で、介入継続が難しくなる、などが挙げられます。これらを避けるために、「目標動作」「評価日」「用いた手段」「次の一手」をセットで記録し、週ごとにチームで振り返る仕組みを作っておくとスムーズです。
関連記事(内部リンク)
- 痙縮の評価| MAS と MTS ( R1 / R2 早見)
- 被動性検査(筋緊張の鑑別)
- 深部腱反射の手順(上肢・下肢)
- 反射検査 完全ガイド( UMN / LMN 鑑別)
- 脳卒中 GL 2025 : PT 実務アップデート
- 筋緊張低下と筋力低下の見極め
おわりに
痙縮リハビリは「安全の確保 → 目標動作の設定 → 段階的な介入 → 観察記録 → 再評価」のリズムを絶やさず、姿勢時間と課題特異的練習を組み合わせていく地道な仕事です。痙縮の強さそのものよりも、疼痛・介護負担・転倒リスク・動作の質といったアウトカムに目を向けることで、チームの方向性が揃いやすくなります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。マイナビコメディカルの活用ポイントとチェックシートはこちらから確認できます。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
痙縮の評価は、何をどの順番で見ればいいですか?
まずは他動運動で「痙縮(速度依存)」「固縮(速度非依存)」「拘縮(構造的制限)」の鑑別を行い、痙縮が主因なら MAS / MTS で定量化します。そのうえで、 10 m 歩行や TUG 、セルフケアなどの機能・生活アウトカムをセットで取り、「スコア変化が生活に効いたか」を確認します。評価は条件(肢位・速度・時刻)を揃えるほど、介入効果が読み取りやすくなります。
ストレッチや ROM だけで痙縮は改善しますか?
ROM と持続伸張は拘縮予防に有用ですが、慢性期の痙縮そのものを単独で大きく下げる効果は限定的とされます。目的を「拘縮予防」や「姿勢時間の確保」に置きつつ、課題特異的練習、装具、電気刺激、薬物・注射療法などを組み合わせて設計する方が、生活アウトカムにつながりやすくなります。
装具は、痙縮を “落とす” ために使うものですか?
装具の主目的は「矯正位保持」「伸張時間の確保」「歩行・立位の安定化」です。痙縮を直接下げるよりも、姿勢と課題練習の土台を整え、 ADL に一般化させる役割が中心になります。疼痛や皮膚トラブルが出ると継続できないため、装着時間は段階的に調整し、毎週の定点再評価で合う・合わないを早めに判断します。
ボツリヌス治療後に “やりがちな失敗” は何ですか?
よくあるのは、注射で筋緊張が下がったのに、課題特異的練習(歩行・更衣など)を十分に行えず、薬効期間を生活改善に変換しきれないパターンです。術前に「目標動作」と「評価セット」を決め、術後は 2 週間ほど集中的に練習量を確保し、再評価で目標達成度を判定すると、効果を活かしやすくなります。
参考文献
- Harvey LA, et al. Stretch for the treatment and prevention of contractures. Cochrane Database Syst Rev. 2017;CD007455. DOI / PMC
- Royal College of Physicians. Spasticity in adults: management using botulinum toxin. 2018 / 2019 update. RCP
- AAPM&R Spasticity TEP. Consensus guidance on spasticity assessment & treatment. PM&R. 2024. DOI
- Marcolino MAZ, et al. TENS for post-stroke spasticity: systematic review. Top Stroke Rehabil. 2020. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下