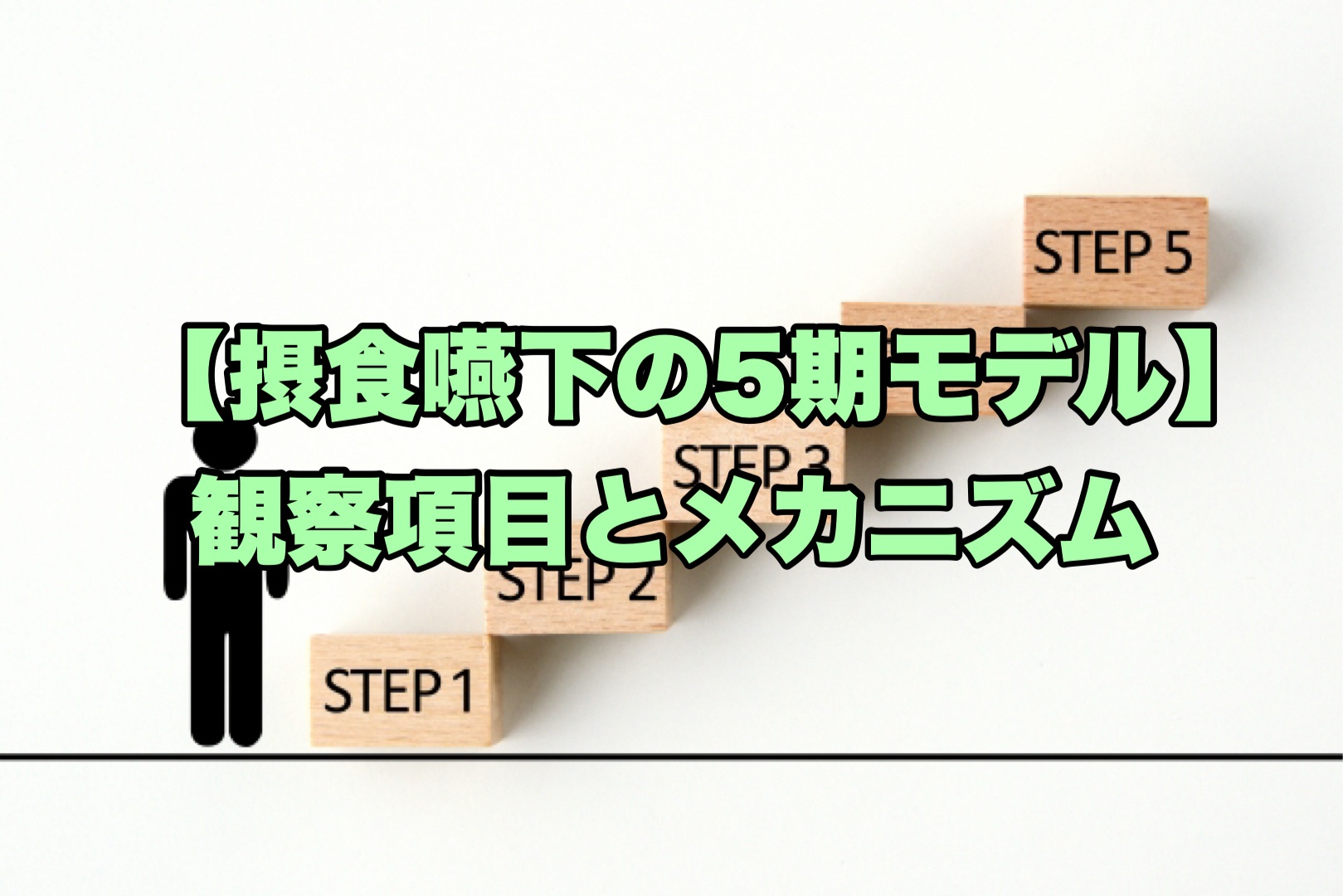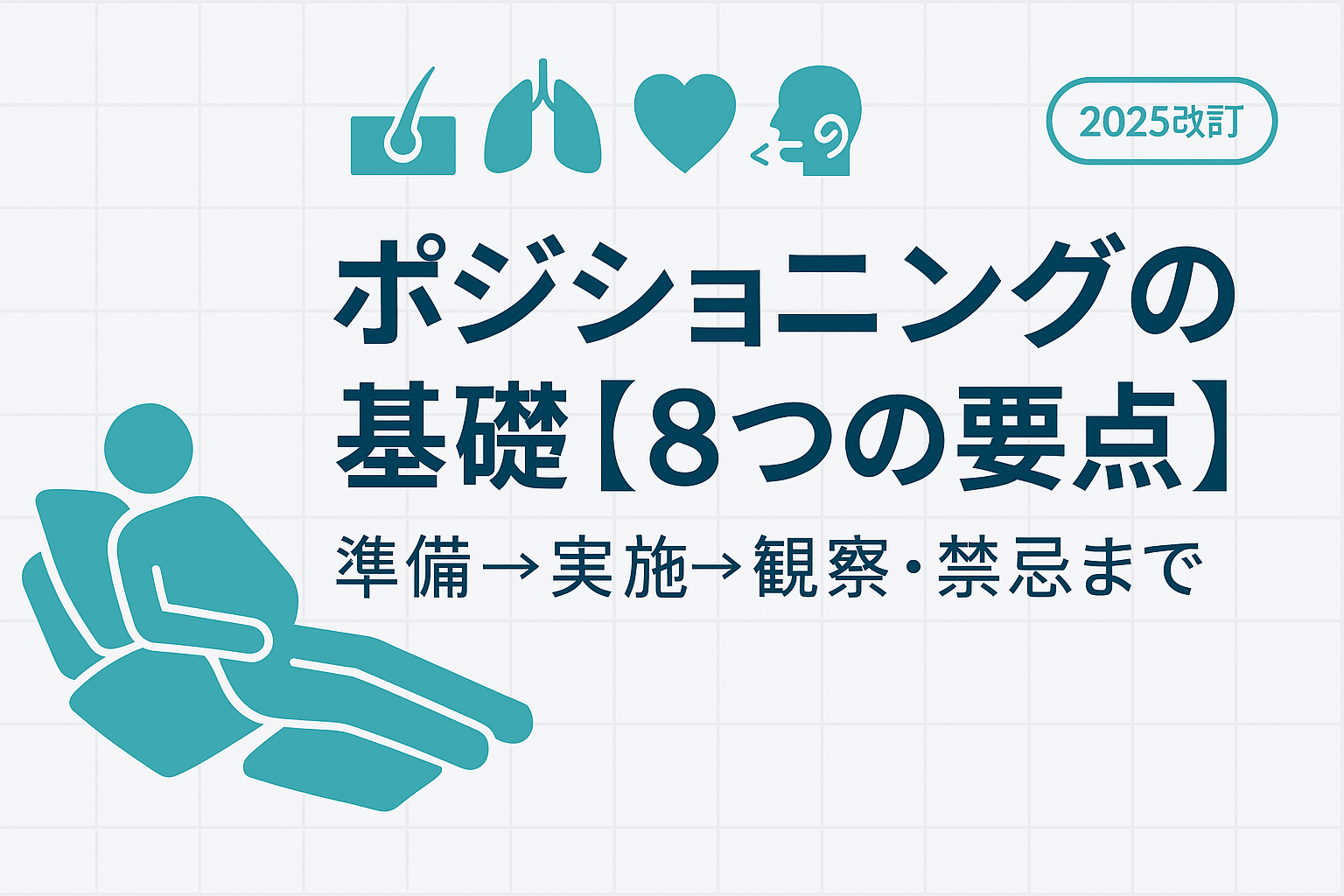摂食嚥下の 5 期モデル|リハビリでの見分け方と次アクション【クイック表+観察チェック+家族向けポイント】
摂食嚥下を 先行期→準備期→口腔期→咽頭期→食道期 の 5 期で整理すると、「どこで・なぜ・どの程度つまずいているのか」を言語化しやすくなります。リハビリでは、所見を 5 期にマッピングして介入の優先順位を決めると、粘度や一口量の調整、姿勢づくり、多職種共有までが一つの流れになります。
冒頭に A4 配布物( 5 期クイック表/ベッドサイド観察チェックリスト/家族向けポイント)を用意しました。評価だけで終わらせず、カンファレンスや家族説明、スタッフ勉強会などにもそのまま使える構成です。関連として、摂食嚥下評価の全体像(基本フロー)は 摂食嚥下評価の基本|ベッドサイドのフローと使い分け に整理しています。
5 期モデル クイックリファレンス( A4 ) ベッドサイド観察チェック( A4 ) 家族・介護者向けポイント( A4 )
5 期の要点(要約)
まずは各期の「役割・サイン・見落としやすい所見・次アクション・相談の目安」を一覧でつかみます。どの期に主な負荷がかかっていそうかを仮説立てしてから観察すると、記録の焦点が絞りやすくなります。
| 期 | 主な役割 | 典型サイン | 見落としやすい所見 | その場の次アクション(リハ) | 相談・精査の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先行期 | 気づき・認知・意欲 | 無関心・注意散漫・食事開始までが遅い | 覚醒のムラ、指示理解のズレ、食具操作の混乱 | 環境調整、声かけ手順の固定、開始合図の統一、時間帯調整 | 覚醒低下が強い/拒否が続く→医師・看護・ ST と方針共有 |
| 準備期 | 取り込み・咀嚼・食塊形成 | 口腔内ポケット・咀嚼遅延・片側だけで噛む | 疲労で後半に崩れる、義歯不適合、頬の保持低下 | 姿勢・支持(体幹/頸部)、一口量調整、食形態調整、休憩の入れ方 | 口腔内環境不良・義歯問題→歯科/口腔ケア連携 |
| 口腔期 | 後方送球・移送 | 口腔残留・反復嚥下・なかなか飲み込まない | 舌の左右差、送り込みのタイミング遅れ | 一口量と粘度の最適化、舌運動の促通、ペース調整 | 残留が強い/食事時間が極端に延長→ ST へ共有 |
| 咽頭期 | 嚥下反射・気道閉鎖 | むせ・湿性嗄声・嚥下後のゴロゴロ音 | むせがないのに声が変わる、呼吸数増、食後に痰が増える | 姿勢(軽度前屈など)、少量から、休憩、呼吸状態のモニタ | サイレント疑い/呼吸不安定→試験を中止し精査( VE / VF )相談 |
| 食道期 | 蠕動・胃搬送 | 胸部つかえ感・逆流感・食後のむせ | 食後の咳、胸焼け、臥位で悪化 | 食後 30 分の座位保持、摂取量/時間帯の見直し、前屈しすぎ回避 | つかえ/逆流が持続→医師と共有し評価方針を検討 |
ベッドサイドでの観察→次アクション
ベッドサイドでは「安全の確認」と「どの期が怪しいかの仮説づくり」を同時に進めます。観察した所見を 5 期に対応づけてメモし、当日の中止基準と今後の評価・訓練方針を決めるイメージです。
この所見はどの期?( 30 秒で当たりをつける)
- 食事に気づかない/開始できない → 先行期
- 咀嚼が遅い/ポケットが残る → 準備期
- 口腔残留/送り込みが遅い/反復嚥下が多い → 口腔期
- むせ/湿性嗄声/嚥下後のゴロゴロ → 咽頭期
- つかえ・逆流感/食後にむせる → 食道期
ポイントは「むせ=咽頭期」と決め打ちしないことです。準備期・口腔期の負担(残留や疲労)が先に破綻していると、粘度変更が逆効果になることがあります。
- 姿勢・環境:90–90–90 座位、頭頸部は軽度前屈、足底接地、トレー高さやテレビ・雑音を調整する。
- 一口量と粘度:最小量・安全側の粘度から開始し、嚥下ごとの反応を確認しながら段階的に調整する。
- 観察の視点:取り込みの様子、咀嚼リズム、送り込みのタイミング、嚥下後の表情や呼吸音を 5 期に対応させてメモする。
- 多職種連携:看護・栄養・リハ・医師へ、期ごとの気づきと具体的な場面(食形態・姿勢・時間帯)を添えて共有する。
| サイン | その場の対応 | 次の一手 |
|---|---|---|
| むせが連続する/増える | 中断・休憩、量とペースを最小へ | 期の仮説を見直し、必要なら ST /医師へ相談 |
| 湿性嗄声が持続する | 中断、咳払い・排痰を促す | サイレント疑いを含め精査( VE / VF )の相談 |
| 息切れ/呼吸数増/ SpO₂ 低下 | 中断、呼吸が整うまで待つ | 呼吸と嚥下の同期・全身耐久性を再評価 |
現場の詰まりどころとよくある失敗
摂食嚥下の評価では「むせの有無」だけに注目してしまいがちです。 5 期のどこで負荷がかかっているかを意識しないと、誤った粘度変更や不必要な経口中止につながることがあります。
4 期 / 5 期 / 6 期 / プロセスモデルの違い(混線しないために)
- 4 期モデル:口腔準備期・口腔期・咽頭期・食道期(「飲み込み」中心)
- 5 期モデル:4 期に 先行期(認知〜取り込み)を足し、「食べ始め」から整理できる
- 6 期モデル:先行期をさらに分け、導入〜取り込みの詰まりをより細かく言語化できる
- プロセスモデル:咀嚼しながら食塊が段階的に咽頭へ送られる“重なり”を説明しやすい
本記事はまず 5 期で地図を作り、必要なときだけ 6 期やプロセスモデルの観点で解像度を上げる方針です。
- よくある失敗 1:いきなりトロミを強くしすぎる
咽頭期の問題と決めつけて粘度を上げすぎると、準備期・口腔期の負担が増え、かえって残留や疲労を招きます。 - よくある失敗 2:一口量が多いまま評価する
一口量が大きいと、先行期・準備期・口腔期が一気にオーバーロードされます。まずは「安全な最小量」から始めるのが鉄則です。 - よくある失敗 3:姿勢調整を後回しにする
座位や頸部位置が崩れたまま評価しても、本来の能力が測れません。 5 期の前に「ポジショニング」を 0 期として必ず整えます。 - よくある間違い:むせのない誤嚥を見逃す
むせの有無だけでは サイレント誤嚥 を拾いきれません。声の変化や呼吸数、食後の状態変化もあわせてチェックすることが重要です。
ご家族・介護者に伝えるポイント
ご家族・介護者には、専門用語ではなく「やること」ベースで具体的に伝えることが大切です。 5 期の全てを説明する必要はなく、「安全のための約束事」としてシンプルにまとめます。
- 食前・食後の口腔ケアを習慣化し、食後は少なくとも 30 分は座位を保つ。
- 焦らせず、ひと口ごとに飲み込みを確認してから次のひと口へ進む。食事中の会話は少なめにする。
- むせが続く・声が急に変わる・発熱や呼吸が荒いなどの変化があれば、早めにスタッフへ相談する。
- 無理に食べさせず、「今日はここまでにしましょう」と切り上げる判断も大事な支援であることを共有する。
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップすると閉じます。
5 期はすべて同時に評価する?
粘度や一口量の決め方は?
むせがないのに怪しい(サイレント疑い)ときは?
おわりに
摂食嚥下の評価は「ポジショニング→先行期の意欲確認→安全な一口量の試験→ 5 期ごとの観察・記録→多職種共有→再評価」というリズムで回すと、抜け漏れが減りやすくなります。 5 期モデルを頭の中の地図として持っておくと、ベッドサイドでの小さな違和感も言語化しやすくなり、誤嚥性肺炎の予防や経口維持の判断にもつながります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える「面談準備チェック( A4 ・ 5 分)」と「職場評価シート( A4 )」を無料公開しています。将来のキャリアや今の職場環境が気になったときに、印刷して手元に置いておくと便利です(当サイト内「マイナビコメディカル」ページのダウンロード欄に掲載)。
参考文献
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会.摂食嚥下障害の評価 2019( PDF ).資料を見る
- 藤島一郎.摂食嚥下障害に対するリハビリテーションの進歩.Jpn J Rehabil Med.2017;54(9):648-657.PDF
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下