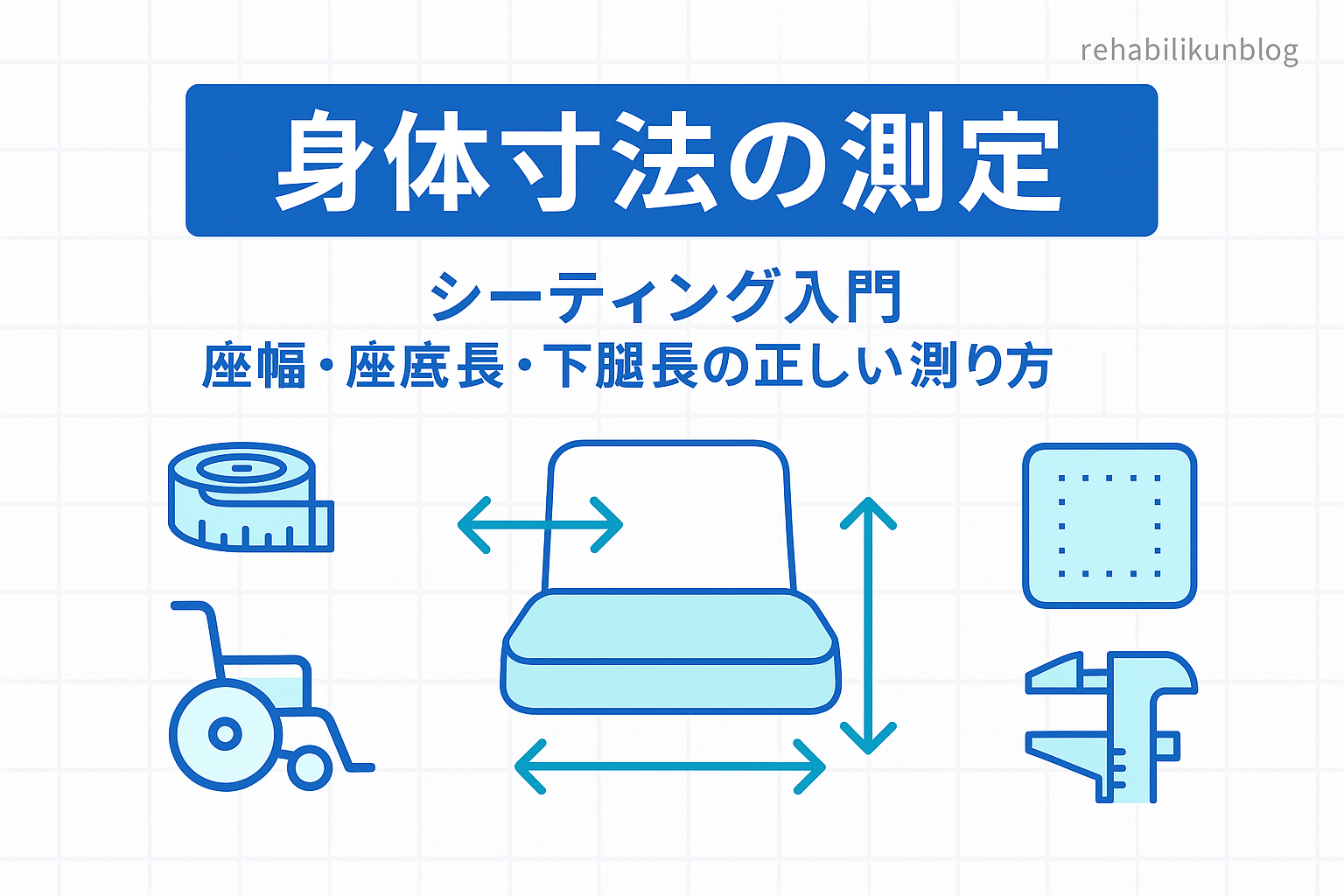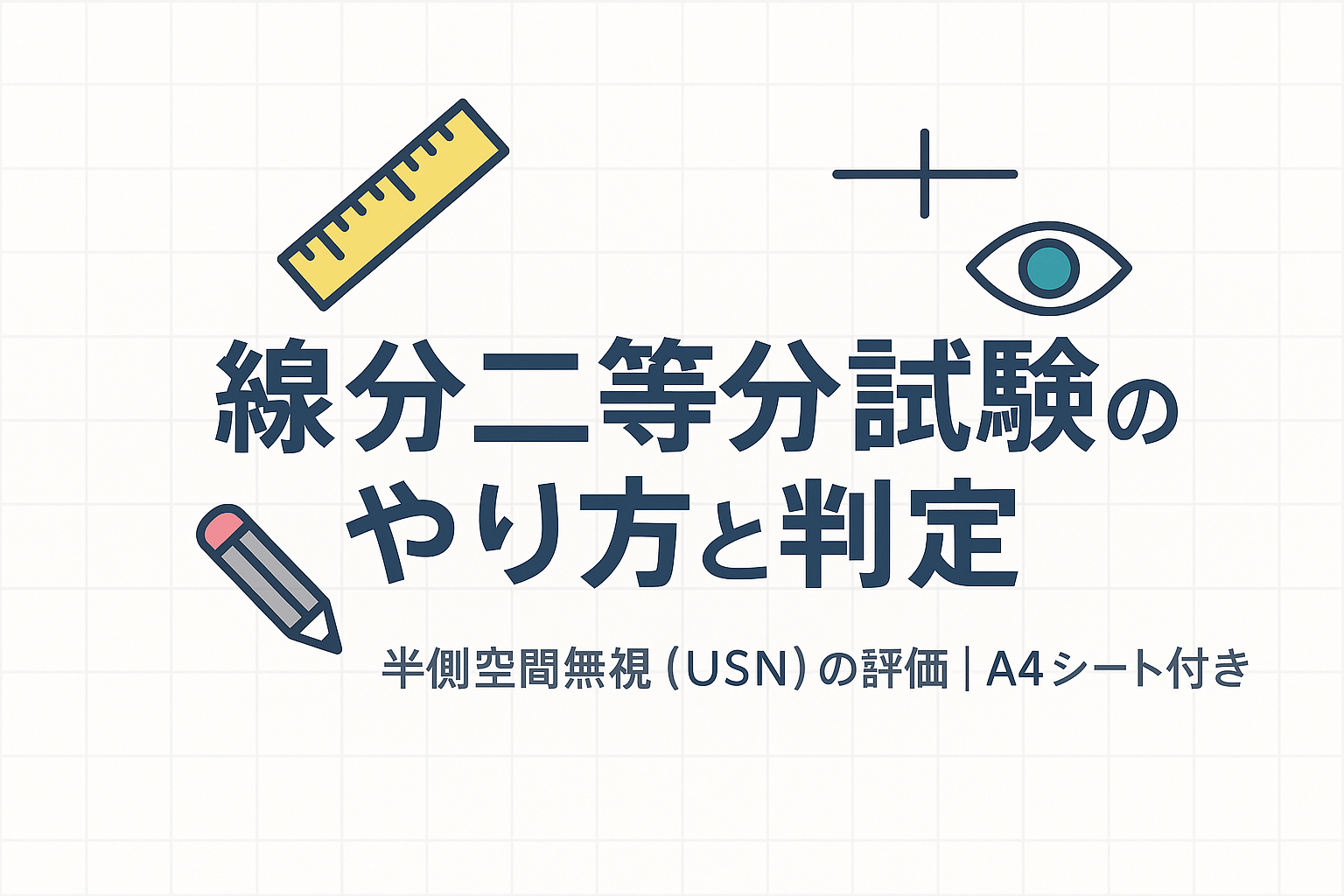身体寸法の測り方(座幅・座底長・下腿長)のゴール
シーティングの採寸は「測定 → 寸法の仮決定 → 試座で微調整 → 記録」の流れを揃えるだけで、再現性が一気に上がります。本記事は、座位が取れる場面を基本に、座位が難しい場合の代替も含めて、誰が測っても同じ結論に近づく“型”を整理します。
結論として、まずは 座位臀幅(座幅)・座底長(座面奥行き)・下腿長(座面高)の 3 点を“同じ基準点”で測り、余裕(クリアランス)を足し引きして仮決定します。最後は必ず試座で、骨盤位置・膝窩圧・足底条件を見て微調整します。
臨床の詰まりを減らす:5 分で“転職の選択肢”も整えておく
体制や教育が合わないと、良いシーティングほど現場で回らなくなります。働き方の選択肢は早めに整理しておくと安心です。
PT 転職の全体像を 5 分で確認する用語と基準点の確認(“同じもの”を測る)
シーティングで迷う原因の多くは、測り方そのものより「何を測ったか(基準点)」が揃っていないことです。まず用語を定義して、記録欄に残せる形にします。
- 座位臀幅:両大転子の最外側の左右幅(衣服の厚みは最小化。側方パッド有無も記録)。
- 座底長:坐骨結節(座位基準点)から膝窩手前までの水平距離。
- 下腿長:膝窩(目安)から踵底面まで(靴底厚は別に mm で記録)。
測定姿勢は可能な範囲で 骨盤中間位・股関節 約 90°・膝関節 約 90°・足底接地を目安に統一します。クッションを使う場合は、沈み込み量や条件(衣服・装具)をメモし、再現性を担保します。
準備する道具とセットアップ
“測れる環境”を先に作ると、採寸が一気に安定します。おすすめは、道具と記録様式を 1 セット化して持ち回れる状態にしておくことです。
- メジャー(硬め・幅広タイプ推奨)
- 直角定規( L 尺)
- 記録用紙(本記事の PDF)
- 写真記録用スマホ(基準点が写る正面・側面)
- 補助者 1 名(メジャー水平保持・姿勢保持)
座位での測定手順(基本)
座位で測れるなら、まずはこの手順を“固定手順”にします。ポイントは 水平・垂直を崩さないことです。
- 骨盤・体幹を整える:骨盤中間位を目標。胸郭が過度に後方へ倒れないようにする。
- 座位臀幅:両大転子の最外側を触診し、床と水平にメジャーを張って測る(斜行に注意)。
- 座底長:坐骨結節(基準点)〜膝窩手前まで水平に測る(左右で大きい側を採用)。
- 下腿長:膝窩〜踵底面を、直角定規で垂直に測る。靴底厚は別に mm で記録。
- 写真記録:前後・側面から 2〜3 枚。衣服・装具などの条件も一緒に残す。
仰臥位での代替計測(座位困難時)
痙縮・疼痛・易疲労などで座位保持が難しい場合は、仰臥位で“座位を仮想”して置換計測します。目安として、股関節屈曲 約 90°を想定し、基準点がずれないように注意します。
ただし仰臥位は坐骨位置の推定誤差が出やすく、測定値どおりが最適とは限りません。最終決定は試座で微調整し、背張り・座面傾斜・フットサポートまで含めて総合的に合わせます。
座面幅の決め方(座位 臀幅 → 座幅)
基本式は 座幅 = 座位臀幅 + 余裕(クリアランス)です。余裕は一律ではなく、保持と駆動の優先度で決めます。
- 標準:+ 20〜50 mm(衣服と体動スペース)
- 小さめ:側方保持が必要/上肢駆動を優先/スリム衣類
- 大きめ:厚着・体重変動/皮膚トラブル予防を優先
広すぎると骨盤が流れやすくなり安定性が落ち、狭すぎると大転子部の圧・摩擦が増えます。仮決定後は試座で、左右差と皮膚反応を確認します。
座面奥行きの決め方(座底長 → 座面奥行き)
基本式は 座面奥行き = 座底長 − 膝窩前クリアランスです。
- 膝窩前クリアランス: 20〜30 mm を目安(軟部圧迫を避ける)
- 骨盤後傾/円背:実効奥行き不足が生じやすいので、試座で 10〜20 mm の追加短縮を検討
座底長が長いからといって奥行きを最大にすると、円背・骨盤後傾がある方では前滑りを助長します。測定値はスタートラインとして、試座で膝窩圧と骨盤位置を見ながら調整します。
座面高の決め方(下腿長 → 座面高)
基本式は 座面高 = 下腿長 − 靴底厚 ± 調整値です。足部条件と移動環境で最適値が変わります。
- 足置きクリアランス:地面〜フットプレート下端 40〜60 mm を目安(段差・屋内外走行を想定)
- 膝角度:おおむね 90°を目標(拘縮がある場合は連動を見て最適化)
尖足や下腿浮腫がある場合、測定値どおりに合わせると痛みやスキントラブルにつながることがあります。必要に応じて傾斜やフットサポートで逃がし、両下肢の荷重バランスも確認します。
その他寸法(併せて決める)
- 座位肘頭高:アームレスト高の基準。肩をすくめず、肘が軽く支持される高さを目標。
- 背もたれ高:体幹コントロールに応じて、肩甲下角下〜肩峰下を基準に段階設定。
- フットサポート長:下腿長・靴底厚・拘縮の有無を反映し、足底条件とクリアランスを両立。
ケース別補正の要点
- 片麻痺:麻痺側の殿部沈み込み/体幹側屈を考慮。左右差が残る前提で、試座で微調整。
- 肥満:軟部のはみ出しで見かけの臀幅が増えやすい。圧分散と駆動性のバランスで設定。
- 円背・胸腰椎後弯:骨盤後傾が出やすい。奥行きは短め、背支持は局所支持を意識。
- 拘縮(尖足/膝屈曲):座面高は関節角度に合わせ、フットサポート・ウェッジで逃がす。
現場の詰まりどころ/よくある失敗(ここだけ直すと再現性が上がる)
採寸が安定しないときは、測り方の工夫より先に「条件固定(体位・肢位・衣服・装具・クッション)」が抜けていることがほとんどです。記録様式を 1 枚に統一して、誰が測っても同じ条件が再現できるようにしましょう。
新人指導や運用づくりで詰まりやすい場合は、現場の“標準化”を進める前に、教育・働き方の選択肢も整理しておくと進めやすいです(関連:面談準備・チェックリストをまとめてダウンロード)。
| 項目 | ありがちミス | すぐ直せる対策 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 座位臀幅 | メジャーが斜行/厚着で + 値 | 水平を保ち、薄着にして再測 | 衣服・側方パッド有無を明記 |
| 座底長 | 膝窩に食い込ませて過大評価 | 膝窩手前で止める( 2〜3 cm 余裕) | 骨盤角度/背張り条件を併記 |
| 下腿長 | 靴底厚を差し引き忘れ | 靴・中敷きの厚みを mm で計測 | フットプレート地上高も記録 |
| 最終決定 | 試座なしで発注 | 試座 → 微調整 → 記録(理由も残す) | 最終寸法・変更理由を残す |
測定→試座→処方のワークフロー
- 座位保持レベルを把握し、どこまで“座位で測れるか”を判断する。
- 本記事の手順で身体寸法を測定(座位/仰臥位)。
- 座幅・奥行き・座面高を仮決定し、候補サイズを絞る。
- 試座で、骨盤位置・膝窩圧・足底条件・駆動/移乗の干渉を確認し、微調整する。
- 最終記録を残し、次回も同条件で再現できる状態にする。
ダウンロード(記録・運用にそのまま使えます)
現場でそのまま使える A4 記録シートを用意しました。印刷設定は A4 /余白 10〜12 mm /ヘッダ・フッタ非表示が目安です。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
余裕寸法は一律何 mm にすべきですか?
一律ではなく条件依存です。標準は + 20〜50 mm。厚着・体重変動が予想される場合は広め、側方保持や駆動性重視では狭めに設定し、必ず試座で皮膚と姿勢の両面を確認します。
仰臥位計測でも正確に決められますか?
置換は可能ですが誤差が出やすい領域です。坐骨位置の推定が難しいため、最終は試座で微調整し、背張り・座面傾斜・フットサポートまで含めて総合決定してください。
試座では何を必ず確認しますか?
骨盤位置(左右差・後傾)、大転子・膝窩・踵の圧、上肢駆動の干渉、足置きクリアランス、移乗のしやすさ、安定性のバランスを最低限チェックします。
座面奥行きが合っていないサインは?
膝窩前の圧迫感、前滑り、骨盤後傾の増悪、背もたれへ“もたれすぎ”が増える、などが代表的です。座底長の測定値は目安にしつつ、試座で膝窩圧と骨盤位置を見て調整します。
左右差がある場合、どちらの値を採用しますか?
原則は「皮膚・姿勢の安全側」を優先し、左右差が出る理由(沈み込み、側屈、麻痺側の崩れ)を併記して、試座で最終調整します。数値だけで決めず、所見とセットで記録してください。
次の一手(最短で上達する進め方)
- 次回からは、測定条件(姿勢・衣服・装具・クッション)を 1 行で固定し、同じ様式で回します。
- 座位保持レベルが揺れる症例は、まず Hoffer 座位能力分類で“どこまで座位で測れるか”を揃えると進めやすいです。
- 身体計測の条件固定そのものを整理したい場合は、形態測定(四肢長・周径)の測り方もあわせて確認してください。
参考文献
- ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks. ISO
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下