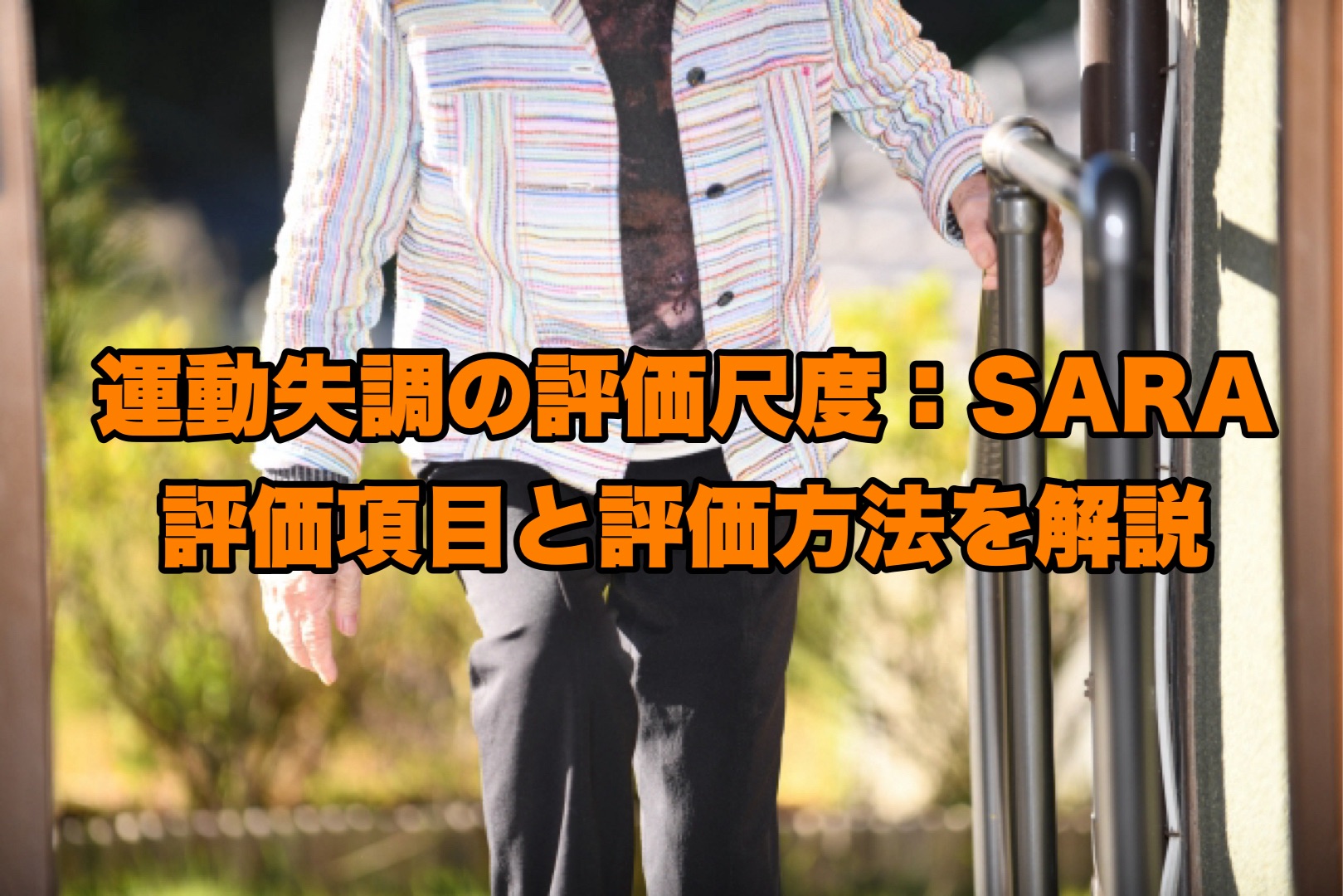SARA とは?(目的と使いどころ)
SARA(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia)は、運動失調の重症度を 8 項目で評価する臨床スケールです。総点は 0–40(数値が大きいほど重い)。評価のねらいは、初期評価・経過観察・介入効果の把握を共通の物差しで行うことにあります。診断名を付ける検査ではなく、機能障害の重症度指標として活用します。
最終更新:2025-10-09
要点早見表(構成とスコア範囲)
| 項目番号 | 上限 |
|---|---|
| SARA-1 | 8 |
| SARA-2 | 6 |
| SARA-3 | 4 |
| SARA-4 | 6 |
| SARA-5 | 4 |
| SARA-6 | 4 |
| SARA-7 | 4 |
| SARA-8 | 4 |
※ 元の項目記述・採点基準の原文は著作権保護のため掲載しません。実施時は正規資料をご参照ください。
スコア記録シートのダウンロード
項目本文は含みません(著作権保護)。下のプレビューで内容を確認できます。
PDFが必要な場合は、別タブで開く → 印刷 → PDFに保存で作成してください。
準備・安全チェック(チェックリスト)
- 環境:十分なスペース、滑りにくい床。必要に応じて平行棒・手すり。
- 安全管理:転倒リスク評価を事前確認。歩行・立位は見守り/補助者を配置。
- 装具・杖:ふだんの用具は原則そのまま。再評価時も条件を統一。
- 疲労・痛み:休憩を適宜挿入。実施時間の目安は10–15分。
- 説明:目的と手順を簡潔に説明し、中断の合図を共有。
評価フロー(手順の全体像)
- 前準備:上記チェック完了、同意取得。
- 実施:各項目を標準化した順で実施(詳細基準は正規資料)。
- 得点記録:各項目 0〜上限を記録シートに転記。
- 合計:8項目の合計(0–40)。
- 所見:姿勢・協調・代償動作・疲労など自由記載にメモ。
- フィードバック:患者・家族へ概要を伝え、再評価計画を共有。
スコアの読み方(臨床での使い分け)
- 縦比較:同一個人の経時変化を見る用途が主(入退院、介入前後、外来フォロー)。
- 同条件原則:靴・装具・環境・実施順・休憩などをできるだけ揃える。
- 報告書:総点だけでなく、バランス系 / 上肢協調 / 歩行など臨床的クラスターで所見を補足。
- “カットオフ”より文脈:疾患や研究ごとに基準が異なるため、固定の重症度区分は置かない前提で記述。
評価導線の設計は 臨床導線の作り方(#flow) も参考にしてください。
スコアリングの考え方(共通)
- 同条件の徹底:靴・装具・補助具・場所・説明文言・実施順・休憩の入れ方を固定。
- 観察語彙で所見化:「軌跡のぶれ/リズムの乱れ/反復回数のばらつき/過大・過小運動/代償動作」などで記録。
- 練習→本番:学習効果を避けるため、短い練習→本番。再評価も同手順。
- 左右差・疲労:左右別の差、前半⇔後半の質の変化をメモ欄に。
- 安全最優先:歩行・立位では見守り/補助者を配置し、中断の合図を事前に共有。
各領域の「観察ポイント」と「解釈のコツ」
歩行(観察項目)
- 観察:速度、ステップ均等性、歩幅、接地安定、方向転換のふらつき。
- 代償例:広い歩隔、上肢の過度な振り、視線の落ち込み。
- 解釈:速度上昇やターンで不安定さが増すかを比較。補助具の有無は明記。
立位保持(観察項目)
- 観察:静止時の体幹揺れ、足圧移動、閉眼の影響、狭い足位での耐性。
- 安全:壁/手すり近くで実施、補助者配置。
- 解釈:感覚入力の差(開眼安定・閉眼不安定など)を所見化。
座位バランス(観察項目)
- 観察:体幹揺れ、自己修正の速さ、微小ずれからの復帰。
- 解釈:上肢協調課題追加で体幹が崩れるか。
発話の明瞭さ(観察項目)
- 観察:リズム、強弱、分節、言い直し頻度。
- 記録例:「モノトーン傾向/語の切れ目不明瞭/長文で乱れ増加」など。
上肢ターゲット追従(観察項目)
- 観察:過大/過小運動、減速の仕方、到達直前の震え。
- 記録:左右差、試行間ばらつき、視覚注視の使い方。
指先—鼻先の協調(観察項目)
- 観察:往路/復路の軌跡、終末振戦、リズムの一定性。
- 解釈:速度変化や疲労で質が落ちるか。
交互反復運動(観察項目)
- 観察:切り替えの速さ・規則性・持続性。
- 記録:「開始良好→20秒で失速」「左右でリズム差」など時間経過の変化。
下肢協調(踵—脛滑走など)(観察項目)
- 観察:軌跡の直線性、目標からの逸脱、速度と正確性のトレードオフ。
- 安全:臥位・座位で実施し、転落リスク回避。
記録・レポートの書き方テンプレ
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 実施条件 | 平行棒内、靴あり、補助具なし。説明統一、練習後に本番。 |
| SARA 総点 | 18/40(高いほど重い)。 |
| 所見の要約 | 歩行ターンで不安定、立位で閉眼影響大。上肢は右で過大運動、交互反復は持続性低下。 |
| 安全配慮 | 歩行・立位は2名見守り。適宜休憩。 |
| 次回計画 | 2週間後に同条件で再評価。体幹安定化練習と歩行訓練を継続。 |
再評価の目安(フォローアップ)
- 急性期:数日〜1週間単位で変化を確認。
- 回復期・外来:2–4週間に1回を目安に、同条件で再評価。
- レポート:総点の推移と臨床所見を併記(例:18 → 14 へ改善、歩行安定性向上)。
よくある誤差と対策
- 学習効果:練習を短く固定、本番は別カウント。
- 疲労の混入:休憩タイミングを標準化、後半の質低下は所見へ。
- 介助の揺らぎ:触れる/触れないの基準を事前合意。
- 記録の省略:自由記載欄に「左右差」「時間経過」「代償」を最低3点書く。
患者・家族への説明(例文)
「この検査は、運動の協調性やバランスを8つの観点で見て、0〜40点で“今の状態”を数字にします。数字は高いほど症状が強いことを示します。同じ条件で繰り返して、変化の方向を見ていきます。」
参考文献
- Schmitz-Hübsch T, et al. Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA): development and validation. Neurology. 2006.