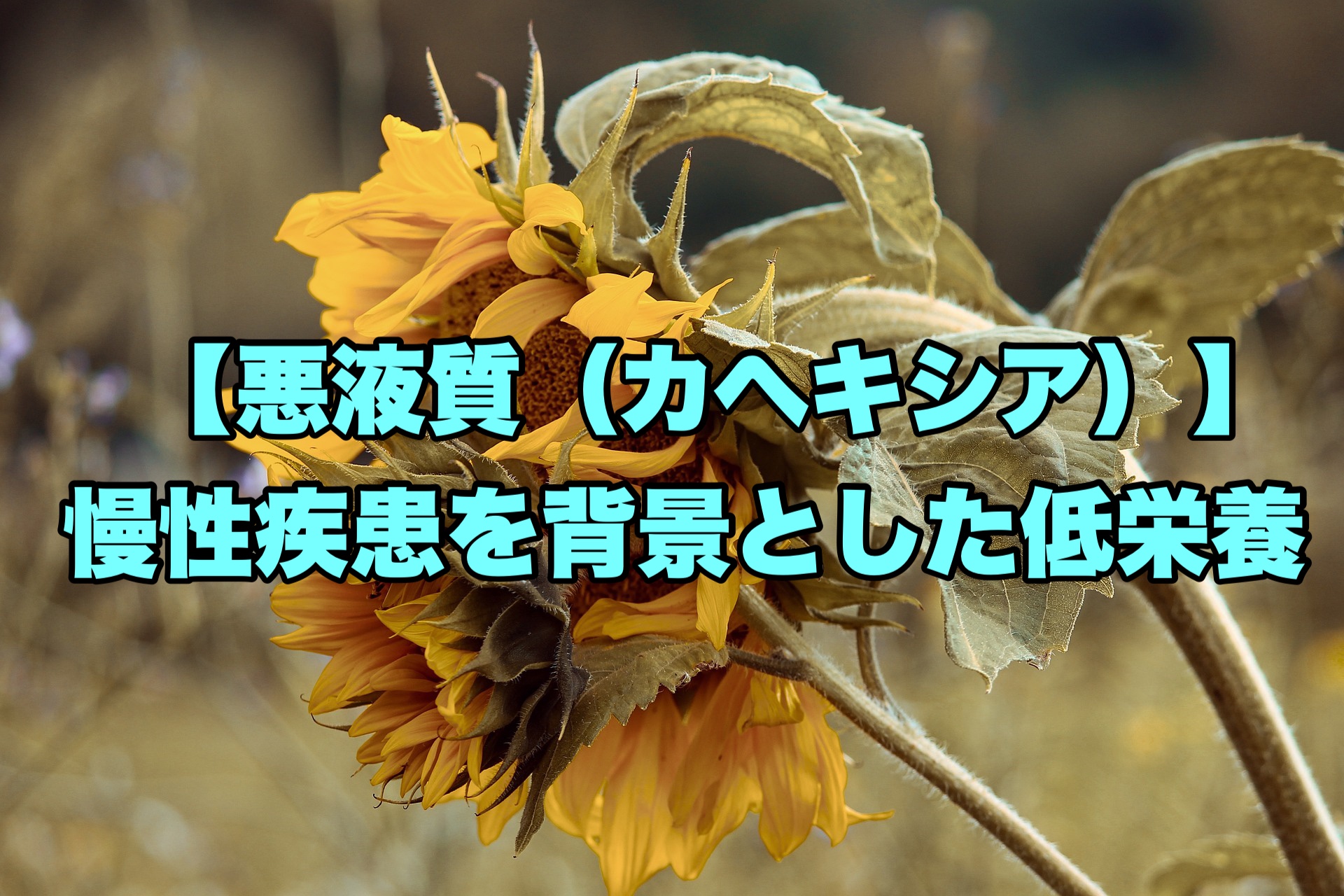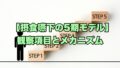がん悪液質(カヘキシア)とは?(要点と臨床での意味)
がん悪液質(カヘキシア)は、炎症に伴う代謝異常により 骨格筋量が進行性に低下し、体重減少・倦怠感・ ADL 低下・治療継続困難をきたす病態です。単なる栄養不足と異なり、栄養介入だけでは筋量や体重が戻りにくい(アナボリックレジスタンス)ことが臨床上のポイントです。
理学療法では、筋力・持久力低下の背景にある炎症・代謝異常を踏まえ、運動 × 栄養 × 原疾患治療をチームで同期させる必要があります。本稿では「とは」「診断・評価」「理学療法介入」を 現場で使える運用フローに落とし込みます。まずは「体重変化・ BMI ・筋量・炎症マーカー」をセットで把握し、関連:栄養スクリーニング運用プロトコル(親記事)の流れに沿って、スクリーニング結果と機能指標(握力、歩行、持久力など)を同じ指標・同じ条件で反復して追跡するイメージです。
病態のキモ(炎症・代謝・アナボリックレジスタンス)
悪液質では IL-6 ・ TNF-α などの炎症性サイトカインにより、ユビキチン–プロテアソーム系が亢進し筋蛋白分解が増大します。さらにインスリン抵抗性やアナボリックレジスタンスが重なることで、エネルギーとたんぱく質を入れても筋量が増えにくい状態になります。このため「食べられないから筋力が落ちている」という単純図式では説明できません。
実務上は、筋力・持久力低下を「廃用」「サルコペニア」とだけ捉えると、運動負荷か栄養どちらか一方に寄った介入になりやすくなります。悪液質が疑われる場合は、主治医・栄養・がん専門薬剤師と共有し、運動(レジスタンス+有酸素)と栄養介入のタイミング・用量をすり合わせることが、 PT の重要な役割です。
| 項目 | 悪液質 | サルコペニア | 飢餓(単純栄養不足) |
|---|---|---|---|
| 主因 | 炎症性代謝異常(腫瘍・慢性疾患) | 加齢・活動低下・疾患 | 摂取不足中心 |
| 筋量 | 進行性低下(可逆性は限定的) | 低下(運動・栄養で改善しやすい) | 相対的に保たれることも |
| 体重 | 短期間での減少が目立つ | 不変〜やや減少 | 減少(栄養介入で回復しやすい) |
| 炎症 | しばしば高値( CRP ↑) | 必須ではない | 基本的にはなし |
| 一次介入 | 運動 × 栄養の同時実施+原因治療 | 運動中心+栄養 | 栄養中心 |
診断:Fearon 2011 の国際コンセンサス
がん悪液質は、以下のいずれかを満たすと診断されます( Fearon 2011 )。
- 6 か月で体重減少 ≥ 5 %
- BMI < 20 かつ 体重減少 > 2 %
- 筋量低下( DXA / BIA / CT など)を伴う体重減少 > 2 %
補助所見として、食欲不振・倦怠感・筋力低下・炎症反応( CRP ↑ など)が挙げられます。すでにやせている人で「最近さらに 3 %程度落ちた」ケースでも、筋量低下を伴えば悪液質の範囲に入る可能性があります。
臨床では「最近の体重変化」と「栄養スクリーニング結果(例: MNA-SF 、 GNRI 、 PG-SGA など)」を必ずセットでカルテに残すと、カンファレンスでの共有が速くなります。診断名の確定が先でも、早期の“疑い”段階から運用を回すことが重要です。
リハでの評価(体組成+機能の統合)
体組成評価: DXA / BIA / CT-L3 筋量、 Alb / PreAlb 、 CRP 、リンパ球数などを参照し、栄養・医師と共通言語を持ちます。ベッドサイドでは「体重推移」「 BMI 」「下肢周囲径」などの連続データも役立ちます。
機能評価:握力、歩行速度、移動(例: TUG )、持久力(例: 6MWT )、主観的疲労( Borg スケールなど)を組み合わせます。
ポイント:「体重・筋量」と「移動能力・持久力」をペアで追跡し、治療サイクルごと(例:化学療法コースごと)に同じ指標で再評価することで、介入の効き方や悪化の早期サインを掴みやすくなります。
理学療法アプローチ(運動 × 栄養を同期)
レジスタンストレーニング:週 2〜3 回、主要筋群 8〜10 種目、 8〜12 回 × 2〜3 セットを目安にしつつ、 RPE 13 前後(ややきつい)から開始します。倦怠感が強い時期は、 1 日複数回の小分け(例: 5 分 × 3 セット)で「頻度を優先」する方が続けやすいです。
有酸素運動:週 3〜5 回、 20〜40 分程度を目標に、会話可能な強度( RPE 11〜13 )で実施します。歩行・エルゴメータ・室内周回など、患者さんの安全性と嗜好に合わせて選択します。
実装のコツ:食事・補食を運動前後 ± 1 時間に合わせることで、少ないたんぱく・エネルギーをできるだけ筋合成に生かします。 EAA /プロテインなどの導入は、主治医・栄養士と相談しながら可否やタイミングを検討します。疼痛・悪心・抑うつ・睡眠といった「運動量のブレーキ要因」は、他職種と連携して整えることで、実際のトレーニング量を引き上げやすくなります。
推奨される全体像は、 ESPEN / ESMO のがん栄養ガイドラインが整理しています(下記参考文献)。 PT はこれらの方針を踏まえて、患者ごとの「今日の現実的な一歩」を具体的な運動処方に落とし込みます。
現場の詰まりどころ・よくある落とし穴
- 栄養だけ・運動だけで完結してしまう
「食べられていないから栄養」「筋力が落ちているから運動」とどちらか一方に寄ると、悪液質特有のアナボリックレジスタンスに対応しきれません。運動と栄養の時間関係まで含めてプランを組むことが重要です。 - 機能指標を追わず、効いているか評価できない
移動・持久力・握力などを定期的に記録しないと、介入効果も悪化サインも見逃しがちです。最低でも「体重+ 1 つの機能指標」をセットで残すようにすると、カンファレンスで議論しやすくなります。 - サルコペニアとの評価枠の混同
サルコペニアのフレームだけで考えると「運動を増やせばよい」となりがちです。炎症や体重減少のスピードが目立つ場合は、表のように悪液質としての視点を持ち直すことで、チーム内の共有がスムーズになります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q. がん悪液質の患者さんに、どこまで運動負荷をかけてよいですか?
A. まずは「翌日以降に持ち越す疲労や痛みが出ていないか」を基準に、 RPE 11〜13 程度から開始し、頻度と継続を優先します。化学療法直後や炎症高値の時期は、 1 回あたり 5〜10 分の低負荷でも構いません。移動・持久力・主観的疲労を同じ条件で追い、「悪化していないか」「頭打ちになっていないか」を多職種と共有しながら少しずつ負荷を上げていきましょう。
Q. “食べられている” のに体重が落ち続けるとき、何を優先して確認しますか?
A. 摂取量だけで判断せず、直近の体重推移( 1〜2 週単位)、炎症( CRP など)、筋力(握力など)、活動量(歩数や病棟内移動の変化)をセットで確認します。疼痛・悪心・下痢・便秘・睡眠不良などの症状があると、摂取が維持されていても活動が落ちて筋蛋白分解が進みやすくなります。必要時は栄養・薬剤・医師へ速やかに共有し、症状緩和 → 栄養 → 運動が同じ方向を向くように調整します。
おわりに
がん悪液質の理学療法では、「早めの気づき → 評価セット化 → 小さくても続く運動 × 栄養 → 再評価」というリズムを作れるかどうかが、患者さんの QOL と治療継続性を左右します。 PT が悪液質のフレームを押さえておくことで、廃用やサルコペニアだけでは説明できない変化にも早く気づけるようになります。
臨床の抜け漏れを減らすには、面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )で「症例経験・教育体制・多職種連携」を一度見える化しておくのも有効です。印刷してそのまま使えます。資料のダウンロードはこちら。
参考文献
- Evans WJ, Morley JE, Argilés J, et al. Cachexia: a new definition. Clin Nutr. 2008;27(6):793-799. PubMed / doi:10.1016/j.clnu.2008.06.013
- Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 2011;12(5):489-495. PubMed / doi:10.1016/S1470-2045(10)70218-7
- Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913. PubMed / doi:10.1016/j.clnu.2021.02.005
- Arends J, Strasser F, Gonella S, et al. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guideline. ESMO Open. 2021;6(3):100092. PMC / doi:10.1016/j.esmoop.2021.100092
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下