筋緊張低下と筋力低下の違い| 5 分で見極める鑑別フローと症例
「力が入らない」は、筋力低下(ウィークネス)だけでなく、筋緊張(トーン)の低下/亢進でも起こります。ここを取り違えると、負荷設定や介入の優先順位がズレやすいのが現場の落とし穴です。本記事は、ベッドサイドで 5 分以内に「まず何を疑うか」を仮決定できるように、受動(張り)→ 反射(ループ)→ 随意(押す力)→ 反復(疲労)の順で見分け方を整理しました。
対象は成人(急性期〜回復期・訪問を含む)の臨床を想定しています。筋緊張低下(低緊張)と筋力低下の違いを、所見の取り方・早見表・ミニ症例でつなげて解説し、最後に「直後に追加すべき評価」まで一本道で示します。チェック用に、鑑別チェックリストと症例記録シート( A4 )も併用できます。
- ✔ レッドフラッグ確認 → 5 分鑑別フローで仮決定
- ✔ 見分け方 早見表(痙縮/固縮/低緊張/筋力低下)
- ✔ A4 配布物:鑑別チェックリスト/症例記録シート
- ✔ 症例ミニケース 3 本(所見 → 解釈 → 次アクション)
- ✔ 直後に行うべき関連評価(追加する順番がわかる)
鑑別チェックリスト( A4 ・印刷) 症例記録シート( A4 )
用語の整理:筋緊張低下と筋力低下の違い(定義)
結論:筋緊張低下は「受動抵抗(張り)と反射ループ」の低下が中心、筋力低下は「随意最大出力(押す力)」そのものの低下が中心です。
見分けの軸:受動(張り)と反射が落ちているか/近位を支えると出力が乗るか/反復で出力が落ちるか(易疲労)を同じ順番で確認します。
- 筋緊張低下:安静時の受動抵抗や張力が低い状態。反射の低下を伴いやすく、速度非依存の弛緩が目立つ。
- 筋力低下:随意収縮の最大発揮力が低い状態。 HHD / MMT などで定量化し、反復で出力低下(易疲労)を伴いやすい。
- 関連:痙縮(スパスティシティ)は速度依存の抵抗増加、固縮(リジディティ)は速度非依存の持続抵抗(粘土様/鉛管様)。
まず安全確認(レッドフラッグ)
- 急性の片麻痺・失語など中枢神経徴候、急速進行、激しい頭痛/頸部痛
- 進行性の筋萎縮や嚥下・呼吸筋症状の急悪化(むせ増加/呼吸苦の増悪)
- 重篤な電解質異常や脱水が疑われる(けいれん、意識変容、強い倦怠感など)
該当時は医師へ即時共有し、評価は安全確保を優先します。該当がなければ以下のフローへ進みます。
現場の詰まりどころ|「低緊張なのに MMT が低い」をどう読む?
- 低緊張は “押す力” を下げて見せる:近位が不安定だと、随意出力が乗らず、結果として MMT が低く出やすい。
- 支えで改善するかが分岐点:近位固定(体幹・骨盤・肩甲帯)を作って再テストし、出力が上がるなら「トーンの影響」が濃い。
- 反復で落ちるかが分岐点: 10 回反復で明確に落ちるなら、筋力低下(易疲労)や神経筋接合部の要素を疑う。
筋緊張低下と筋力低下のメカニズム(新人向けやさしい解説)
筋緊張=「無意識の下地の張り」、筋力=「意思で出す押す力」と捉えると区別しやすいです。緊張は姿勢保持のために常時オンの微小出力、筋力は課題時にぐっと上げる出力です。
つまり、下地(緊張)が崩れると「出力を乗せる土台」が弱くなり、筋力そのものが保たれていても “力が入らない” 形になり得ます。
まず基礎:緊張はどこで決まる?
- 感覚入力(筋紡錘・皮膚・関節):長さや張力の変化を検知
- 脊髄ループ( α ・ γ 連関): γ で「張りの基準」を調整 → α 運動ニューロンの発火へ
- 上位中枢(小脳・網様体・皮質):姿勢制御や予測で「基準つまみ」を微調整
イメージ: γ は “張力のつまみ” 、 α は “実際に出る微小トルク”。つまみを下げると全体の張りがふわっと下がります。
筋緊張低下(低緊張)が起きる仕組み
- γ ドライブ低下:小脳障害や急性期反応などで「張りの基準」が下がる
- 求心性入力の低下:感覚器/末梢神経障害で筋紡錘情報が弱く、反射ループが回りにくい
- 運動ニューロンプールの興奮性低下: LMN 障害、重度脱力の急性期など
臨床像:受動抵抗↓、 DTR ↓、関節のぶらつき、振り子様膝蓋腱反射(小脳性)など。
誤解あるある:「力が入らない=筋力だけの問題」ではなく、下地の張りが弱いと、随意出力も乗りにくい点に注意します。
筋力低下(ウィークネス)が起きる仕組み
- 発火側の問題:皮質〜脊髄〜末梢の伝導低下( UMN / LMN 障害、神経伝導障害)
- 収縮装置の問題:筋線維損傷・萎縮・代謝障害(廃用、サルコペニア、筋疾患)
- エネルギー供給の問題:嫌気代謝への早期移行、神経筋接合部の易疲労など
臨床像:最大随意収縮↓、反復で出力低下(易疲労)、トルク立ち上がり遅延。緊張が正常〜やや低下でも、「押す力」そのものが出ないのが本質です。
新人向けクイックチェック( 60–90 秒)
| 項目 | 低緊張(筋緊張低下) | 筋力低下 | ベッドサイドの一手 |
|---|---|---|---|
| 受動抵抗 | 著明に低い/ぶらつく | 多くは正常 | 近位を支えつつ可動域内で姿勢づくり |
| 腱反射( DTR ) | 低下〜消失(小脳性は振り子様) | 正常〜低下(病態に依存) | DTR +リバウンドで手早く確認 |
| 随意最大出力 | 「乗りにくい」が、支えで改善 | 支えても最大値が上がりにくい | 近位安定 → HHD /握力で定量 |
| 反復での変化 | 姿勢戦略が整うと改善しやすい | 出力が落ちる(易疲労) | 10 回反復でトルク低下を観察 |
メカニズム別:初期介入の考え方
| 原因機序 | ねらい | 具体策(例) | 評価更新 |
|---|---|---|---|
| 低緊張( γ ドライブ低下) | 近位安定・姿勢入力で「張りの基準」を上げる | ポジショニング、近位共同収縮、荷重入力、短距離反復課題 | 姿勢保持時間、 HHD (近位固定あり/なし) |
| 感覚入力低下 | 求心性情報を補い反射ループを回す | 関節圧縮・皮膚入力、タッピング、閉鎖運動連鎖での反復 | DTR ・リバウンド、動作の滑らかさ |
| 筋力低下(廃用・サルコペニア) | 筋量・神経動員の回復と持久性向上 | RPE 目安の反復課題、 STS 、歩行速度練習、栄養連携 | HHD /握力、反復による出力低下率、歩行速度 |
| 末梢神経障害 | 代償戦略の学習と安全な負荷設定 | 装具・支柱、感覚代替入力、低負荷高回数の機能課題 | MMT / HHD 、機能到達度、疼痛・疲労の推移 |
指導のコツ(新人・学生向け)
- 比喩で伝える:「低緊張=布団の中のバネが弱い」「筋力低下=バネはあるが押し込む腕力が弱い」
- 順番を固定:観察 → 受動 → 反射 → 随意 → 反復(この順で毎回)
- “近位を支える” を合言葉に:低緊張では近位安定で随意出力が “乗る” 体験を作る
- 数値で残す: HHD /握力と「支えあり/なし」の差、 10 回反復での低下率を記録
5 分で仮決定:観察 → 受動 → 筋力 → 機能(見分け方)
- 観察・触診( 30–60 秒):抗重力保持、姿勢・アライメント、筋容積(萎縮/左右差/線維束攣縮)、安静時の張力。
- 受動運動・反射( 60–90 秒):速度依存の抵抗、クローヌス、 DTR 、病的反射。必要に応じ MAS を簡易評価。
- 筋力・持久( 60–90 秒): MMT / HHD 、握力、反復での易疲労や速度低下。
- 機能課題( 60–90 秒):立ち上がり( STS )、歩行観察。必要に応じ TUG /歩行速度。
迷ったときは、近位固定あり/なしで筋力テストを 2 回行い、「支えで改善するか」をまず見ます。
違い・見分け方 早見表(鑑別)
| パターン | 典型所見 | よくある背景 | 次の一手(臨床) |
|---|---|---|---|
| 痙縮( UMN ) | 速度依存の抵抗↑、クローヌス、 DTR ↑、折りたたみナイフ現象 | 脳卒中、 SCI 、脳性麻痺など | MAS で重症度把握 → 伸張・ポジショニング・課題特異的練習(必要時は装具や治療連携) |
| 固縮(錐体外路) | 粘土様/鉛管様で速度非依存、歯車様 | パーキンソン病、 PSP など | オン/オフ把握 → リラクセーション+運動課題、姿勢戦略・歩行戦略 |
| 筋緊張低下 | 安静時弛緩、受動抵抗低下、 DTR 低下 | 末梢神経障害、低緊張傾向、急性期反応など | ポジショニング/関節保護 → 近位安定化と反復課題、必要時は装具 |
| 筋力低下(末梢/筋原性/廃用) | 随意出力低下、反復で易疲労、筋萎縮/線維束攣縮、 DTR 低下 | サルコペニア、廃用、末梢神経障害、筋疾患など | HHD ・握力で定量化 → 目標設定、負荷量調整、栄養・活動量の連携 |
症例ミニケース(所見 → 解釈 → 次アクション)
- 脳卒中後(屈筋群の痙縮優位):速度依存抵抗↑、 DTR ↑、クローヌスあり。解釈:痙縮優位。次: MAS で重症度 → 伸張・ポジショニング → 課題特異的練習(必要時は装具や治療連携)。
- パーキンソン関連の固縮:粘土様抵抗、オン/オフで所見が変動。次:服薬タイミング確認 → リラクセーション → 姿勢・歩行戦略のセット化。
- 高齢・廃用の筋力低下: DTR 低下、筋萎縮、反復で出力低下。次: HHD /握力で定量 → 負荷量(頻度・強度)を決め、短期目標を設定。
直後に行う関連評価(要点と導線)
- 「支えあり/なし」での HHD 差(近位安定の影響)
- 10 回反復での出力低下率(易疲労の有無)
- 機能課題の “最小セット”(立ち上がり+歩行観察)を固定して経過を追う
関連する評価指標の全体像は、評価ハブにまとめています。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
MMT と HHD はどちらを優先すべき?
痙縮と固縮の違い・見分け方は?
筋緊張低下と筋力低下の違い(鑑別)は?
次にやるべきこと
鑑別がついたら、短期目標( 2–4 週)と再評価タイミングを症例記録シートに記入し、多職種で共有します。まずは「支えあり/なし」と「反復での低下率」を固定して記録し、介入の効き方(トーン優位か、ウィークネス優位か)を毎週アップデートしてください。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

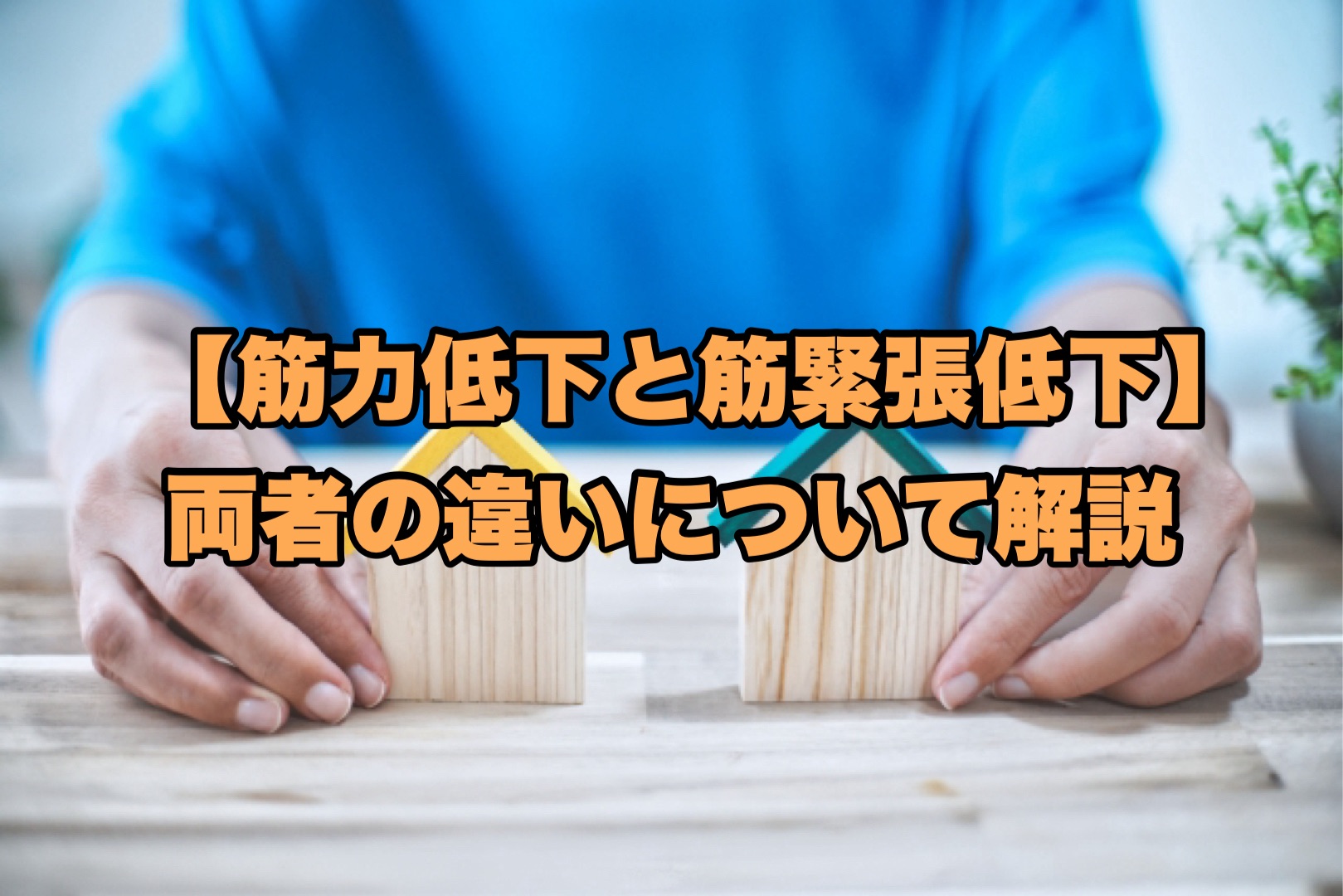
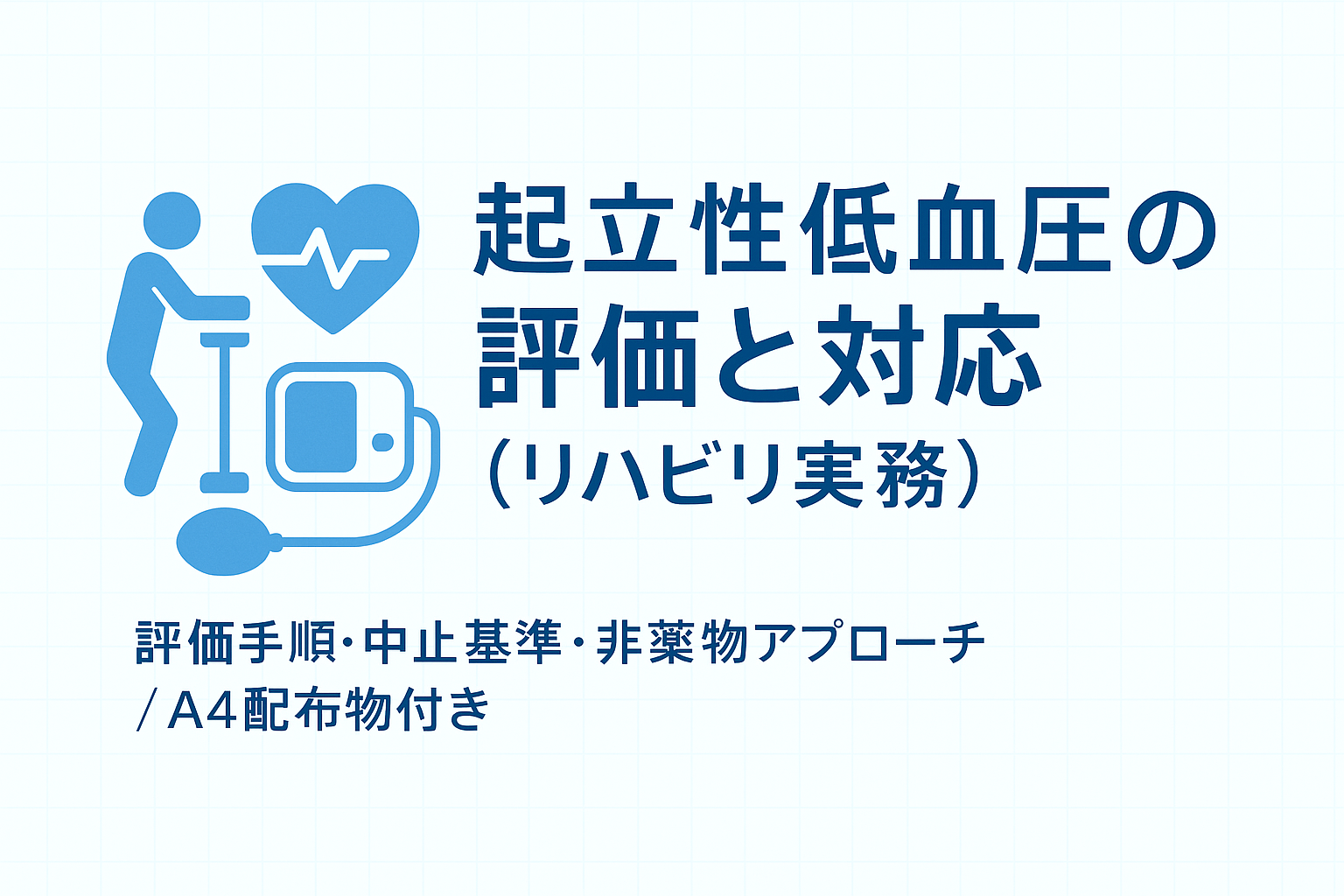
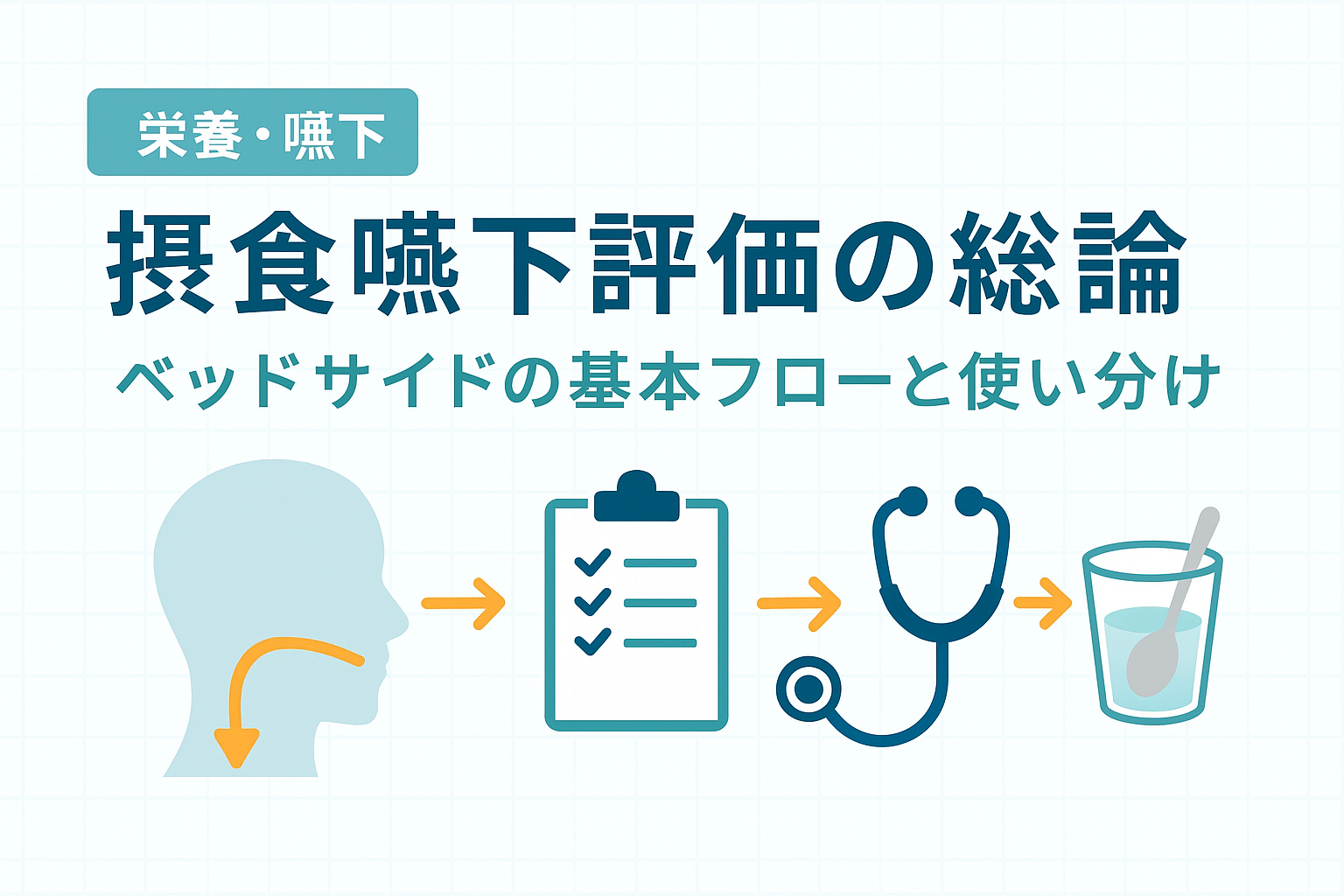
コメント