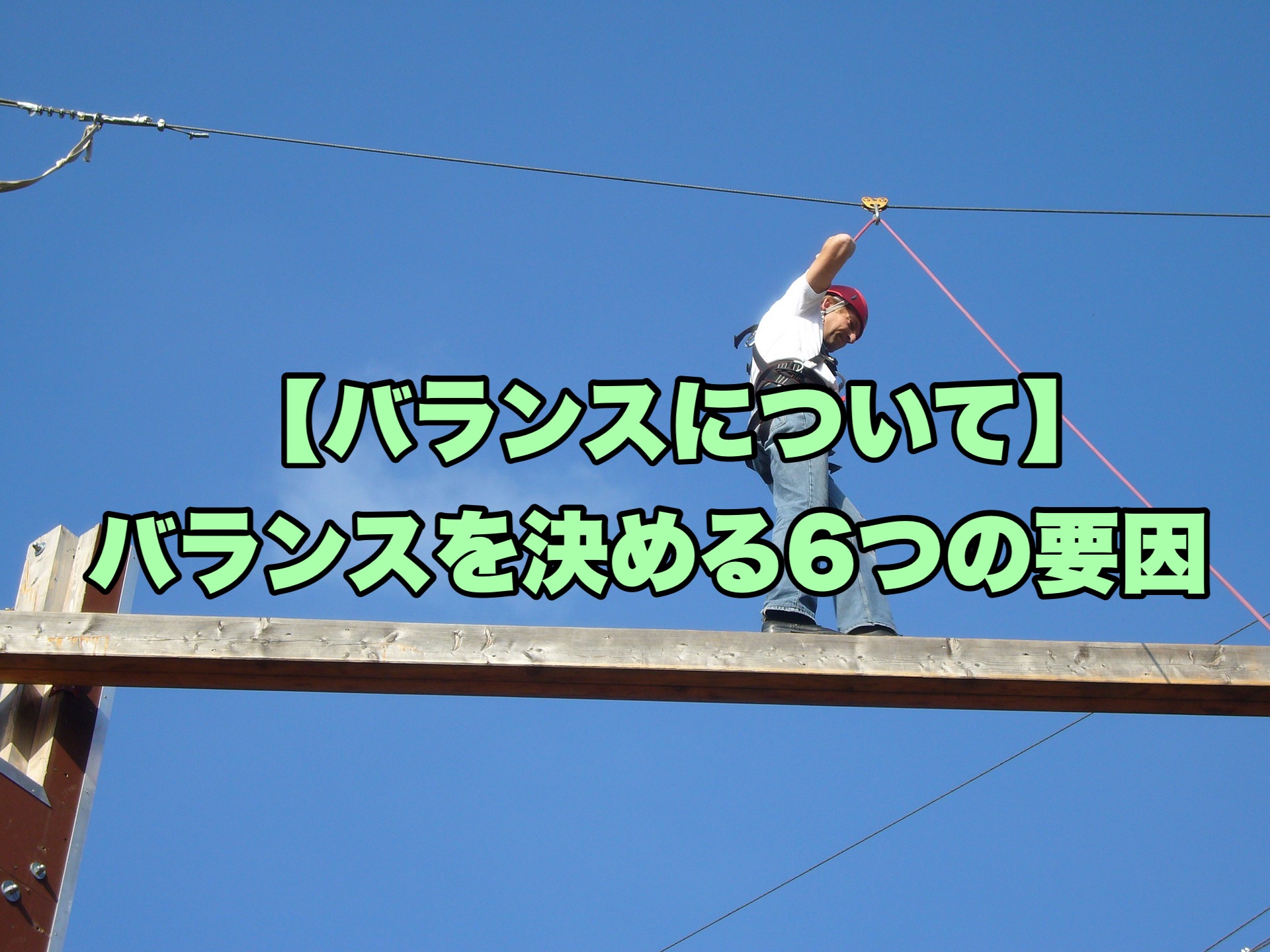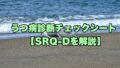バランス能力とは?(結論と臨床での定義)
本記事では、リハ場面で使う「バランス=姿勢制御」を概念ハブとして整理します。ここでの実務的な定義は「課題や外乱に応じて 重心( COM )を支持基底面( BOS )内に保つ能力」です。転倒予防・歩行安全・ ADL 自立の土台であり、評価と訓練の「言語」をそろえることが介入精度の第一歩になります。
まずは BOS ・ COM ・安定限界、感覚統合(視覚 / 体性感覚 / 前庭)、そして静的 / 動的、予測的( APA )/ 反応的という 3 つの軸で整理しておくと迷いにくくなります。評価スケールの全体像を先に押さえたい場合は、関連:評価ハブもあわせて参照してください。
| 目的 | おすすめ(記事名) | 使いどころ |
|---|---|---|
| 感覚統合 | mCTSIB(改変感覚統合検査) | フワつき・閉眼で破綻・床面条件で変わる |
| 包括的評価 | Mini-BESTest(プロトコル) | 予測的 / 反応的 / 感覚 / 歩行の弱点抽出 |
| 慢性期フォロー | BBS ・ TUG(比較・使い分け) | 縦比較で変化を追う(天井 / 床効果に注意) |
| 歩行の難所 | FGA(プロトコル) | 方向転換・速度変化・頭部運動で崩れる |
| 恐怖 / 自己効力 | ABC / FES-I(主観尺度) | 「筋力は戻るが活動が広がらない」を拾う |
姿勢制御のメカニズム( BOS / COM / 安定限界・ 3 システム)
BOS は足部や椅子などの支持基底面、COM は身体の重心投影、安定限界は「転ばずに COM を移動できる範囲」です。バランス不良は大きく、COM の制御がうまくいかないか、疼痛・拘縮・姿勢変化などで安定限界そのものが小さいかのどちらかとして整理できます。運動方略は足関節 → 股関節 → ステッピングの順に動員され、足幅・面の硬さ・頭部位置・外乱の有無など課題設定によって要求が変化します。
情報処理面では視覚・体性感覚・前庭の「重みづけ(リウェイティング)」が重要です。床面を柔らかくする / 閉眼にするなどで体性感覚や視覚の信頼性を下げると、前庭への依存度が高まります。感覚入力の「どれに頼りやすいか」を見える化しておくと、訓練で操作すべき条件(視覚条件 / 支持面 / 頭部運動など)が決めやすくなります。
静的 / 動的・予測的 / 反応的バランスの違い
静的バランスは立位保持や座位保持などの「姿勢を保つ」課題、動的バランスは歩行・方向転換・リーチなど COM を意図的に動かす課題です。静的が安定すれば自動的に動的も改善するとは限らず、目標 ADL に近いタスクで評価・訓練を設計する必要があります。
予測的バランス( APA )は立ち上がりや物を持ち上げる際など、「動作前に身体を用意しておく調整」、反応的バランスは予期しない外乱(押される・つまずく)に対する即時応答です。 APA に弱い症例は「動く前の準備」が遅れ、反応的に弱い症例は外乱時のステップが出にくい / 遅い傾向があります。どの軸が弱いかを先に言語化できると、評価選択と訓練ターゲットがブレにくくなります。
臨床評価の選び方と使い分け
評価は「何が原因で不安定か?」に合わせて目的から逆算して選びます。感覚統合の問題が疑われるとき、予測的・反応的制御や歩行の難所をまとめて把握したいとき、慢性期で縦比較を軸にしたいとき、恐怖や自己効力を確認したいときでは、適した尺度や条件設定が変わります。
カットオフ値は集団レベルのリスク指標であり、臨床では同一患者の縦比較(ベースラインと再評価)を優先します。病期や環境が変われば最適な尺度も変わるため、評価 → 介入 → 再評価を 1 サイクルとしてあらかじめ設計しておくと「測りっぱなし」を防ぎやすくなります。
※この表は横にスクロールできます。
| 評価 | 主目的 | 対象 / 場面 | 所要 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| mCTSIB | 感覚統合(視覚 / 体性感覚 / 前庭)の偏り把握 | 立位保持の不安定・フワつき | 約 5 分 | フォーム / 閉眼など条件操作が簡便 |
| Mini-BESTest | 予測的・反応的・感覚・歩行の総合評価 | 多面的に弱点を特定したいとき | 約 15 分 | 訓練ターゲットの抽出に有用 |
| BBS ・ TUG | 転倒リスクの縦比較・経過観察 | 慢性期・施設 / 在宅のフォロー | 各 5〜10 分 | 天井 / 床効果に注意 |
| FGA | 歩行中の方向転換・速度変化など | 屋内外歩行での不安・つまずき | 約 10 分 | 転倒既往者の「難所抽出」に向く |
| PASS | 寝返り〜座位・立位の姿勢コントロール | 脳卒中 亜急性期 | 約 10 分 | 早期段階の小さな変化検出に向く |
| ABC | 自己効力(バランス自信)の把握 | 活動範囲を広げたいが怖さが強い症例 | 約 5 分 | 恐怖が主因かどうかの見極めに |
| FES-I | 転倒恐怖の主観的評価 | 日常生活場面での不安の強さ | 約 5 分 | 教育・セルフマネジメントと併用で効果的 |
現場の詰まりどころ(よくある見落とし)
バランス訓練でよくあるのは、「不安だからとりあえず立位保持」で終わってしまい、方向転換やデュアルタスクなど実際に転倒しやすい場面まで評価・訓練が届かないケースです。また、体幹や下肢筋力ばかりに注目し、感覚統合や COM 制御、ステップ方略の問題が見逃されることも少なくありません。
もう一つの詰まりどころは、患者の恐怖・自己効力の低下が十分に評価されていない点です。 ABC や FES-I で恐怖の程度を言語化しておくと、「筋力は改善しているが活動が広がらない」パターンを早期に拾いやすくなり、教育・環境調整・段階づけの方向性が立てやすくなります。
訓練戦略(方略 × 課題特異性 × デュアルタスク)
訓練は弱点に合わせて足関節・股関節・ステップ方略を段階づけます。 BOS を広く → 狭く、支持面を硬 → 柔へ、視覚を開眼 → 閉眼へ、外乱を小 → 大へと少しずつ負荷を調整します。動的課題では方向転換・歩行速度・ヘッドターン・障害物などを組み合わせ、目標とする生活場面に近いタスクを設定します。
実生活では認知課題の併存が常態であり、デュアルタスク(計算・言語・ワーキングメモリなど)を安全な範囲で早期から少量導入することが転倒予防に直結します。評価の軸(静的 / 動的、予測的 / 反応的、感覚統合)をそろえたうえで、生活場面に合わせて「難所」を再現するのが改善を早めるコツです。
よくある誤解 Q&A
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップすると閉じます。
体幹が弱い = バランスが悪い?
必ずしも同義ではありません。体幹筋力は一要素であり、感覚統合や COM 制御、ステップ方略の選択が改善すれば、筋力が大きく変わらなくても安定する症例は多いです。逆に筋力は十分でも、恐怖や方略選択の問題でバランス不良が続くこともあります。
静的が安定してから動的へ進めるべき?
安全を確保したうえで、目標 ADL に合わせた動的課題を小さく早期から取り入れた方が、実生活への汎化は得られやすいです。静的のみで長期間過ごすと、実際に転倒しやすい状況(方向転換・デュアルタスクなど)に対する耐性が育ちにくくなります。
mCTSIB と Mini-BESTest の違いは?
mCTSIB は感覚統合の偏りをみるスクリーニング、 Mini-BESTest は APA ・反応的制御・感覚・歩行をまとめてみる包括的評価です。「感覚のクセをざっと把握したい」ときは mCTSIB 、「どこから訓練を始めるかまで決めたい」ときは Mini-BESTest というイメージで使い分けます。
おわりに
バランス評価と訓練は「原因の仮説 → 評価での確認 → タスク特異的訓練 → 再評価」というリズムで回すことで、転倒リスクや恐怖の変化をチームで共有しやすくなります。静的・動的、予測的・反応的、感覚統合の 3 つの軸を意識しておくと、評価選択やゴール設定の迷いも減らせます。
働き方を見直したいときは、見学や情報収集の段階から使える面談準備チェック( A4 )と職場評価シート( A4 )を活用してみてください。面談準備チェック & 職場評価シート(無料ダウンロード)は印刷してそのまま使えるようにしています。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下