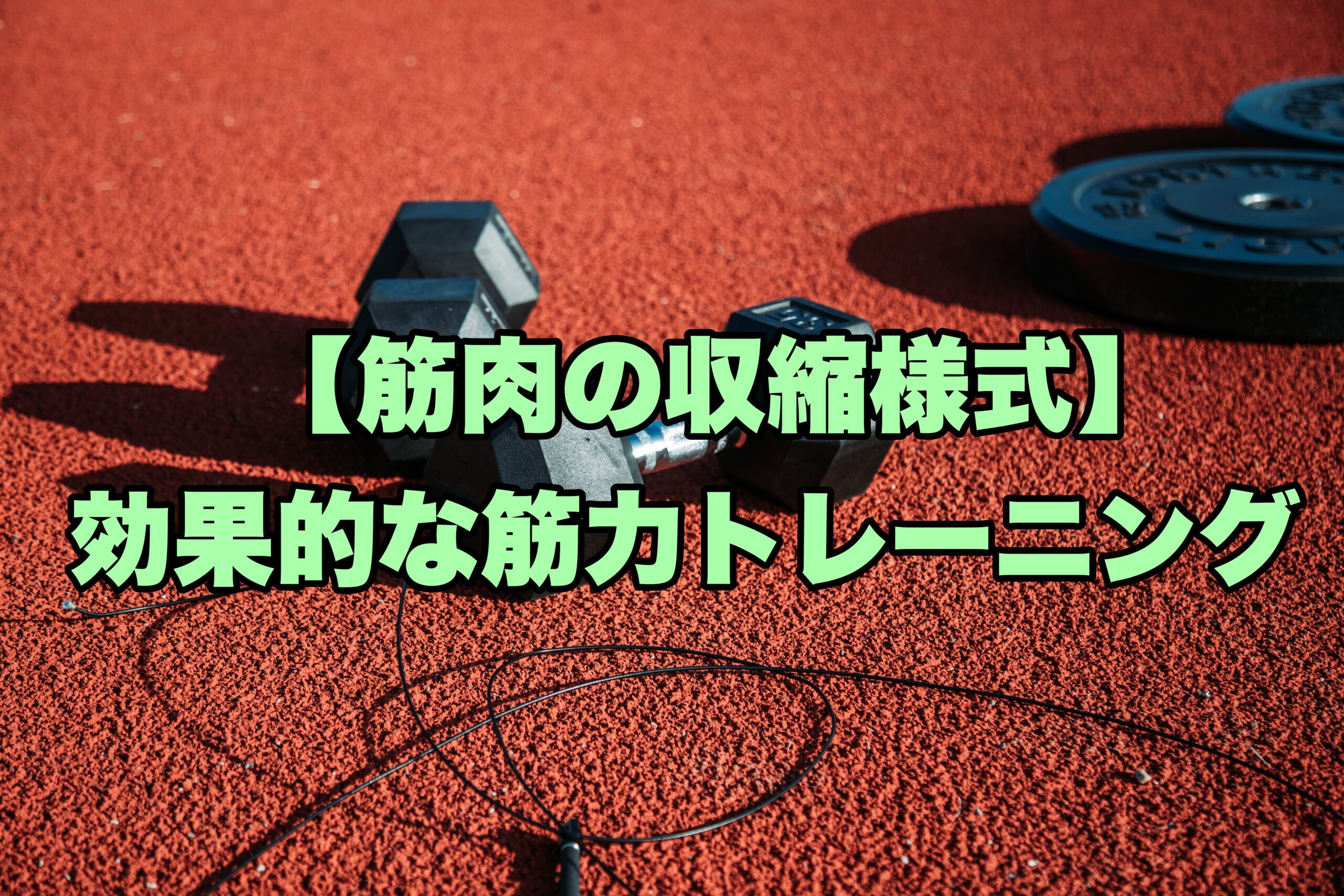筋肉の収縮様式とは?(求心性・遠心性・等尺性・等速性)違いと使い分け
評価 → 介入 → 再評価の「型」をまとめて見る( PT キャリアガイド )
「筋肉 収縮様式」は、筋トレの成果を左右する超基本です。重量や回数が同じでも、求心性(持ち上げる)/遠心性(下ろす・減速する)/等尺性(止める・支える)のどれを狙うかで、負荷の感じ方・関節ストレス・筋痛・運動学習のしやすさが変わります。
本記事では、臨床で迷いがちな「等張性(等速性と混同)」「遠心性の増やし方」「等尺性はいつ使う?」を、手順 → 目安 → 失敗回避の順で整理します。
まず押さえる整理(3 つの軸)
収縮様式は「名前が多くて混乱」しやすいので、最初に3 軸で整理します。
| 軸 | 代表用語 | 結論 | 臨床での言い換え |
|---|---|---|---|
| ① 筋長が変わるか | 等尺性/等張性 | 等尺性=筋長ほぼ一定、等張性=筋長が変わる | 止める/支える(等尺) vs 動かしながら出す(等張) |
| ② 筋長の方向 | 求心性/遠心性 | 短くなる(求心)と伸ばされる(遠心) | 持ち上げる(求心) vs 下ろす・減速(遠心) |
| ③ 速度条件 | 等速性( isokinetic ) | 角速度一定は「機器条件」。徒手・自重では再現しづらい | ダイナモ等で速度を固定して測る/鍛える |
ポイントは、「等張性( isotonic )」は求心性と遠心性を含む“上位概念”ということです。日常の筋トレで扱う収縮は、ほとんどが「等張性(求心+遠心)」と「等尺性」の組み合わせです。
求心性収縮( concentric ):押す・持ち上げる
求心性は、筋が短くなりながら力を発揮します。ベンチプレスでバーを押す、スクワットで立ち上がる、立ち上がり動作の加速などが代表例です。
利点は「運動学習が分かりやすい」「痛みが強いときもフォーム調整で回避しやすい」こと。注意点は「勢いで誤魔化しやすい」ことです(反動や代償で負荷が抜ける)。
| 狙い | コツ | よくある失敗 | 修正 |
|---|---|---|---|
| 対象筋に乗せる | 「止めてから上げる」:切り返しで 0.5–1 秒停止 | 反動で上げる | 反動禁止、停止を入れる |
| 代償を減らす | ROM を先に“安全域”へ(痛みが出ない角度に) | 痛み回避でフォーム崩れ | 可動域を狭め、回数で稼ぐ |
| 記録を安定させる | テンポを固定(例:上げ 1–2 秒) | 日によってテンポがバラバラ | テンポをメニューに明記 |
遠心性収縮( eccentric ):下ろす・減速する(ここが伸びる)
遠心性は、筋が伸ばされながらブレーキをかける収縮です。スクワットでしゃがむ局面、階段の下り、着地・減速などが典型です。
遠心性は高い張力を出しやすい一方で、DOMS(遅発性筋痛)が出やすく、関節痛や炎症がある時期は「増やし方」を間違えると悪化させます。
| ステップ | 具体例 | 目安 | 中止・調整サイン |
|---|---|---|---|
| ① テンポを遅く | 下ろし 3–5 秒/上げ 1–2 秒 | RPE 6–7 程度で開始 | 翌日痛みが強い → 回数を 2–3 割減 |
| ② 可動域を短く | 痛みの出ない範囲だけで“下ろし”を丁寧に | セットは 1–2 から | 関節痛増悪 → ROM をさらに狭める |
| ③ 負荷を少しだけ上げる | 0.25–0.5 kg 単位で小刻み | 2–3 セッションで反応を見る | フォーム崩れ → 負荷よりテンポ優先 |
負荷設定が迷う場合は、基礎の漸増・特異性を先に整理しておくとブレません(関連:筋トレの 3 原理・6 原則)。
等尺性収縮( isometric ):止める・支える(関節を守りやすい)
等尺性は、筋長をほぼ変えずに力を出し続ける収縮です。プランク、壁押し、膝伸展位での保持、痛みの出やすい角度を避けた“保持”などが代表です。
利点は「関節運動を小さくできる」「痛みが強い局面を避けやすい」こと。注意点は「呼吸停止・血圧上昇(いきみ)」と「角度特異性(角度が変わると効果が落ちる)」です。
| 目的 | おすすめ | 目安 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 痛みがある時期の導入 | 痛みの出ない角度で 5–10 秒保持 | 5 回 × 1–3 セット | 息止め防止(声かけ・回数より呼吸) |
| 姿勢保持・安定性 | 体幹・股関節の保持(プランク等) | 10–30 秒 | 代償(腰椎過伸展)を先に修正 |
| 等張性への橋渡し | 保持 → 小さな ROM → 通常 ROM | 段階化 | 角度を変えて複数点で保持 |
等速性( isokinetic ):速度一定(主に測定・機器トレ)
等速性は「角速度を一定に固定する」条件での収縮です。徒手や通常の自重・フリーウェイトでは角速度を一定に保つことが難しく、臨床ではダイナモメーター等の機器を用いる場面が中心になります。
特徴は「速度条件を固定して比較しやすい」「ピークトルクやパワーを定量化しやすい」こと。反対に、機器がない環境では等速性そのものを狙うより、等張性(求心・遠心)と等尺性の設計を丁寧に行う方が再現性が高いです。
目的別:どの収縮様式を優先する?(早見表)
現場では「全部やる」より、目的に合わせて優先順位を決めた方が、記録・再現・説明がラクになります。
| 目的 | 優先 | テンポ例 | 目安(強度・反復) | 詰まりどころ |
|---|---|---|---|---|
| 痛みがある/導入 | 等尺性 → 求心性 | 保持 5–10 秒 | RPE 5–7 | 息止め・いきみ |
| 筋肥大(ボリューム重視) | 等張性(求心+遠心) | 上げ 1–2 秒/下ろし 2–4 秒 | RPE 7–8(6–12 回) | 反動で効かない |
| 筋力(高強度) | 求心性+遠心性 | 上げ 1 秒/下ろし 2–3 秒 | RPE 8–9(3–6 回) | フォーム破綻 |
| 減速・着地・下り動作 | 遠心性 | 下ろし 3–5 秒 | 低〜中強度から段階化 | 筋痛が強すぎる |
| 姿勢・安定性(体幹) | 等尺性 | 10–30 秒保持 | 代償が出ない範囲 | 腰椎過伸展 |
安全管理:中止基準・調整基準(筋トレ全般)
「収縮様式」以前に、中止すべきサインを共通言語にしておくと、現場での事故を減らせます。
| サイン | その場の対応 | 次回の調整 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 胸痛/強い息切れ/冷汗 | 直ちに中止、安静、必要時に医療者へ報告 | 強度を下げる/有酸素を先行 | 発生時刻・動作・バイタル |
| めまい/ふらつき | 座位・臥位で回復確認 | 休息を長く/起立負荷を段階化 | 姿勢変化の直後か |
| 鋭い関節痛(刺す痛み) | ROM を戻す/中止 | 等尺性から再導入 | 痛む角度・動作局面 |
| フォーム崩れが止まらない | 負荷を下げる/セット終了 | 回数よりテンポ固定 | どの代償が出たか |
現場の詰まりどころ(よくある失敗 → 1 手で戻す)
| よくある失敗 | 起きる理由 | 対策( 1 手) | 評価・記録 |
|---|---|---|---|
| 遠心性で筋痛が強すぎる | いきなり負荷を上げた/テンポが速い | まず「下ろし 3–5 秒」だけを増やす | 翌日の痛み( 0–10 )と ADL 影響 |
| 等尺性で息止めが出る | 保持が長い/“いきみ”の癖 | 保持を 5 秒に短縮+声かけで呼吸 | 呼吸の有無、血圧反応 |
| 求心性が反動になる | 切り返しが速い/目標が回数だけ | 「止めてから上げる」を 0.5–1 秒入れる | テンポとフォームの一致 |
| 等速性と等張性が混同 | 言葉が似ている | 「等速は機器条件、等張は日常筋トレ」と固定 | 実施環境(機器の有無) |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
収縮様式は「全部」やった方が良いですか?
基本は「全部」より、目的に合わせて優先順位を決めた方が、再現性と記録が安定します。痛みがある時期は等尺性から、下り動作や減速を鍛えたいなら遠心性を丁寧に、というように“主役”を決めてください。
遠心性は筋肥大に効くと聞きますが、痛みが心配です
遠心性は張力を出しやすい一方、DOMS が出やすいので、まずはテンポを遅くする(下ろし 3–5 秒)→ ROM を安全域にする → 小刻みに負荷を上げる、の順で段階化すると失敗しにくいです。
等尺性は「角度が変わると効きにくい」って本当?
等尺性は角度特異性があるため、1 点の保持だけだと動作全体への汎化が弱くなります。臨床では、痛みの出ない範囲で複数角度(例:膝 3 点)で保持を入れると実用性が上がります。
等速性トレーニングができない環境ではどうしますか?
等速性は機器条件なので、機器がない場合は「等張性(求心・遠心)+等尺性」の設計で十分代替できます。速度を揃えたい時は、メトロノーム等でテンポを固定して記録を揃えるのが現実的です。
まとめ:収縮様式は「狙い」を言語化すると伸びる
収縮様式は、① 安全の確保 → ② 収縮様式の選択 → ③ テンポ/負荷の段階づけ → ④ 記録 → ⑤ 再評価の順に整えると、臨床でも筋トレでも迷いが減ります。
指導や面談の準備では、評価と介入の意図を 1 枚に整理できると強いです。面談準備チェックと職場評価シートは、こちら(ダウンロード)にまとめています。
参考文献
- Lee SEK, de Lira CAB, Nouailhetas VLA, Vancini RL, Andrade MS. Do isometric, isotonic and/or isokinetic strength trainings produce different strength outcomes? J Bodyw Mov Ther. 2018;22(2):430-437. doi: 10.1016/j.jbmt.2017.08.001
- Avin KG, Frey Law LA. Age-related differences in muscle fatigue vary by contraction type: a meta-analysis. Phys Ther. 2011;91(8):1153-1165. doi: 10.2522/ptj.20100333 (PubMed: 21616932)
- Webber SC, Porter MM. Reliability of ankle isometric, isotonic, and isokinetic strength and power testing in older women. Phys Ther. 2010;90(8):1165-1175. doi: 10.2522/ptj.20090394 (PubMed: 20488976)
- Runnels ED, Bemben DA, Anderson MA, Bemben MG. Influence of age on isometric, isotonic, and isokinetic force production characteristics in men. J Geriatr Phys Ther. 2005;28(3):74-84. doi: 10.1519/00139143-200512000-00003 (PubMed: 16386169)
- Kim MK, Choi JH, Gim MA, Kim YH, Yoo KT. Effects of different types of exercise on muscle activity and balance control. J Phys Ther Sci. 2015;27(6):1875-1881. doi: 10.1589/jpts.27.1875 (PubMed: 26180340)
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下