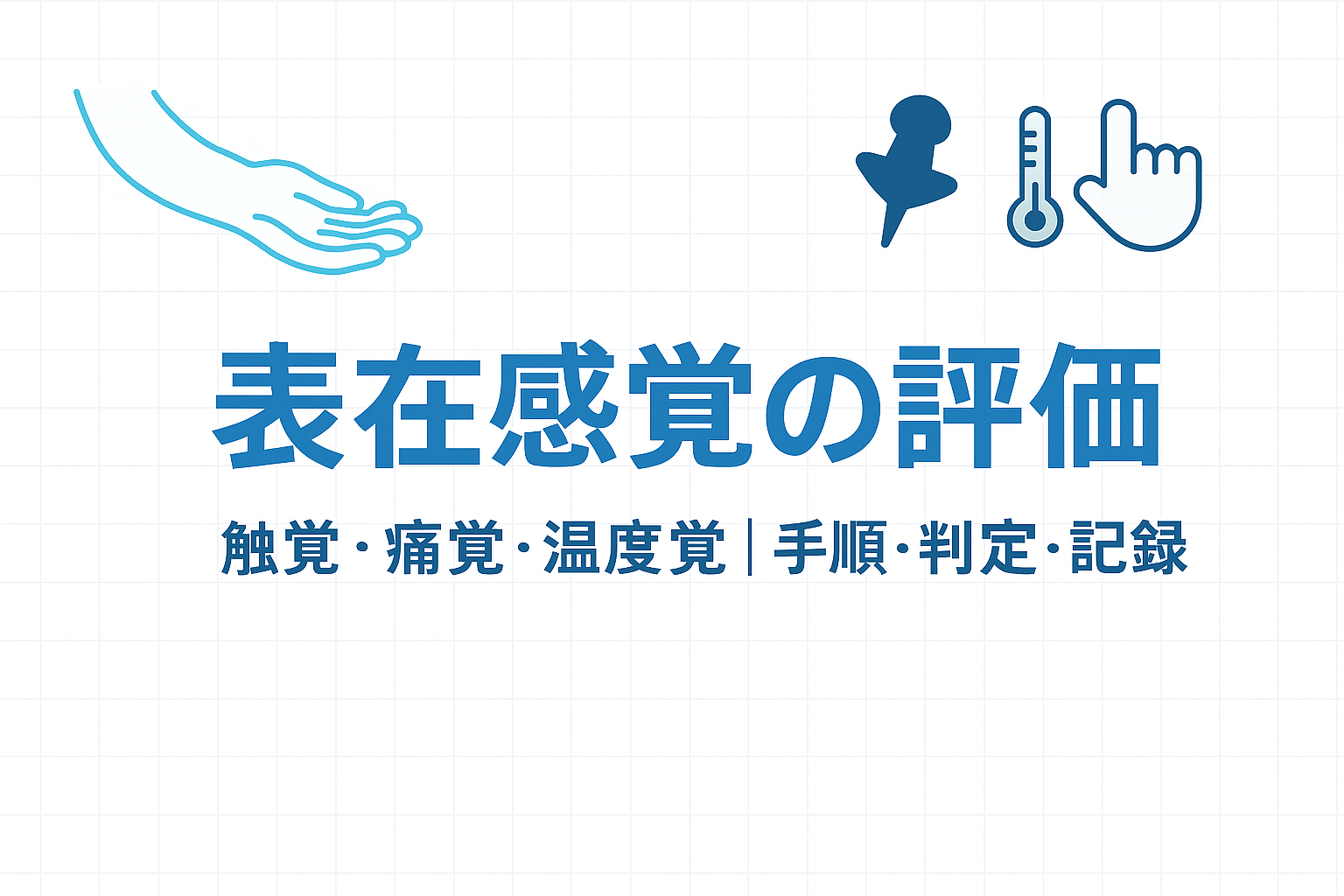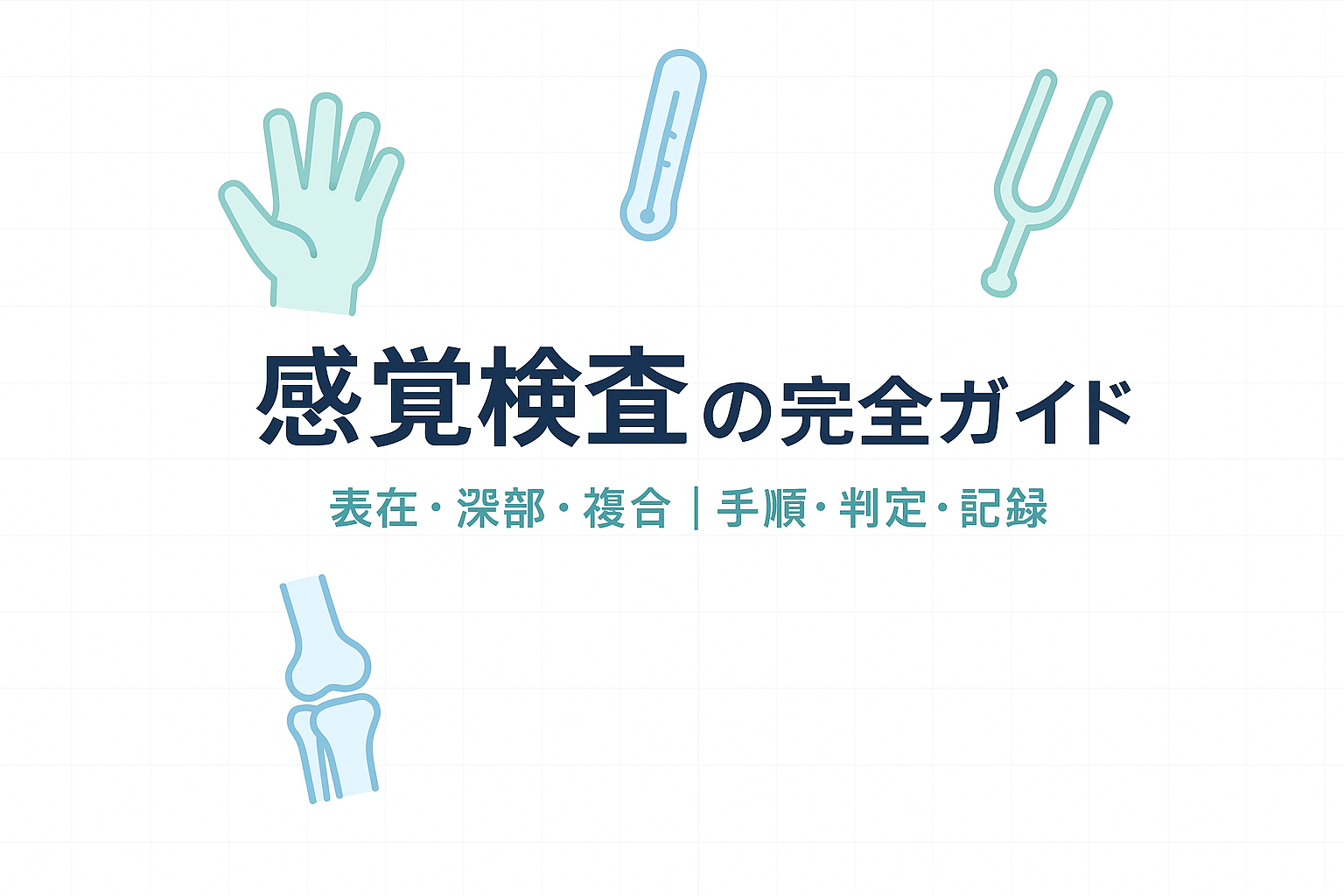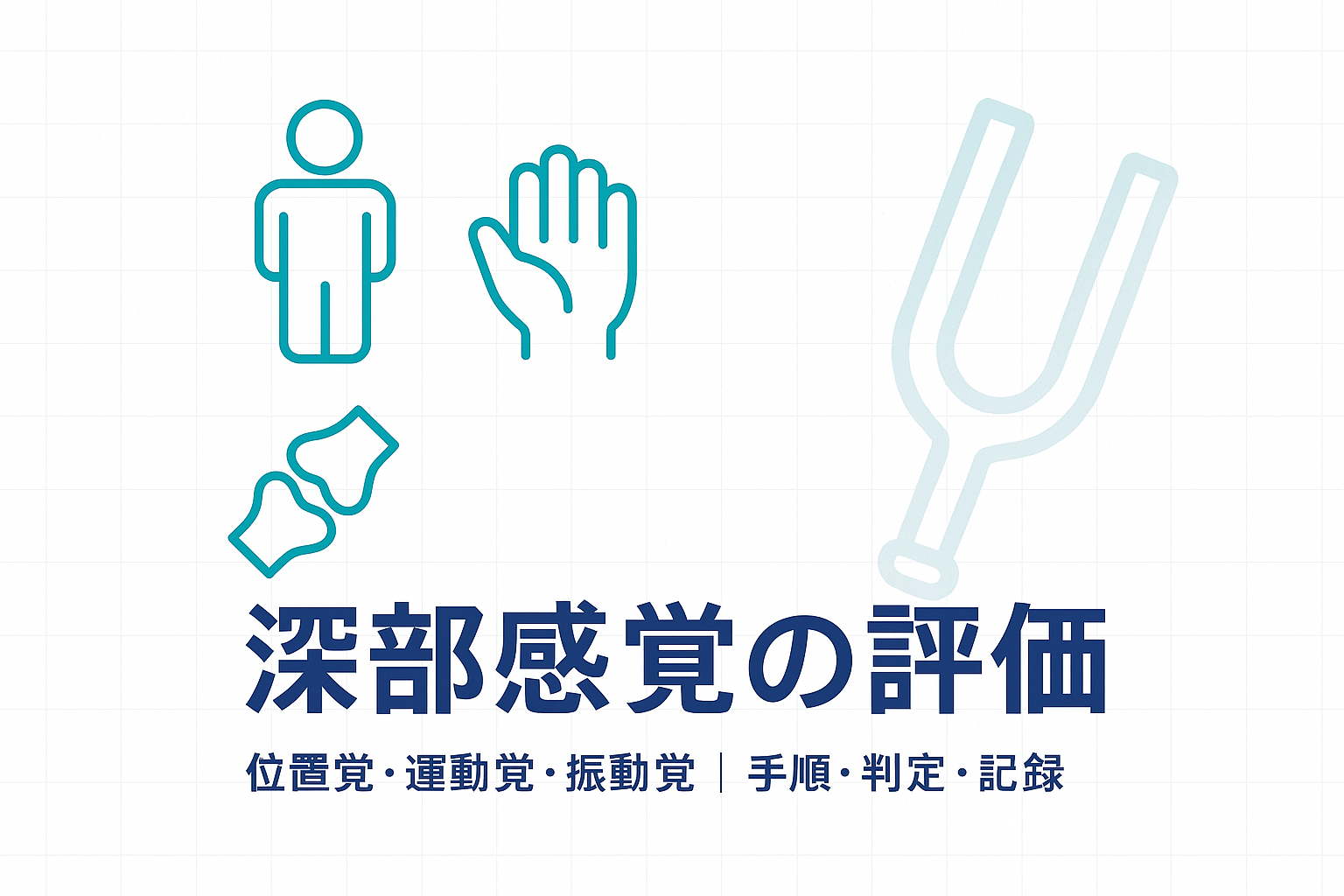表在感覚とは(触覚・痛覚・温度覚)
表在感覚は皮膚由来の情報で、触覚・痛覚・温度覚が中心です。本記事は、理学療法評価としての表在感覚検査のやり方を整理し、短時間で再現性高く行うための順序、患者さんへの説明文、判定語彙、記録テンプレをまとめました。明日からのベッドサイドでそのまま 1 セットとして使える構成をねらいます。
評価の狙いは左右差と一貫性の把握です。まず視覚遮蔽でバイアスを排し、一定強度・一定時間の刺激をランダムに提示します。ダミー刺激を 20–30 % 程度混ぜて反応の信頼性を確認し、部位差と遅延の有無を明確に記録します。本記事は 「感覚検査の完全ガイド」 の子記事として、表在感覚に特化して手順化します。
準備と標準化(視覚遮蔽・刺激・ダミー)
まず静かな環境を整え、体位を安定させます。評価前に目的と流れを短く説明し、健常と思われる部位で練習試行を 1–2 回行います。視覚遮蔽はアイマスクや閉眼で代替し、皮膚に病変や疼痛がある部位は回避します。評価中も「痛みが強いときはすぐ教えてください」など、中止基準をあらかじめ共有しておきます。
標準化の鍵は「刺激の一貫性」です。綿球や筆での軽接触、鈍針の軽いピンプリック、温冷試験片の一定時間接触など、刺激の強さ・時間・間隔をあらかじめ決めておきます。順序は左右を交互に、部位は近位・遠位を織り交ぜ、同じ部位に続けて当てないようランダム化します。ダミー刺激(触れていないのに「今」と尋ねるなど)を 20–30 % 混在させて、反応の信頼性を確認します。
触覚:手順・判定・NG/OK
手順:視覚遮蔽下で綿球や筆を用い、皮膚へ軽く接触します。「今・どこ」を即答してもらい、左右と複数部位にランダム提示します。応答が遅い・不安定な場合は、まず健常部位での練習を追加し、言語理解が難しい場合は「触れたら手を握る」などの合図方式に切り替えます。
判定:左右差、遅延、部位特異の有無を整理して記録します。語彙は「正常/低下/消失」「遅延」「誤認」など、チーム内で統一しておくことが重要です。NG はメトロノームのようなリズミカルな提示や、「今触ったよね?」といった誘導尋問的な声掛けです。半側空間無視が疑われる場合は、健側からの注意喚起や体幹・頭位の工夫で補助します。
痛覚(鋭鈍):安全配慮と弁別の設計
手順:安全な鈍針先や使い捨てピンを用いて、軽い刺刺激を提示し、「鋭い/鈍い」を弁別してもらいます。視覚遮蔽とランダム提示、ダミーを併用し、各部位で 3 回程度を目安にします。疼痛の既往や皮膚損傷がある部位は避け、「痛みが強ければすぐ止めます」とあらかじめ伝えておきます。
判定:鋭鈍弁別の誤認率、遅延、過敏の有無を左右別に記録します。痛覚過敏が強い場合は刺激強度を最小限にし、休憩を挟みながら進めます。「鋭鈍の区別はつくが強く痛い」「触れただけでも痛い」などの所見は、慢性痛や中枢性感作を示唆することがあり、表在感覚検査の情報を疼痛評価と統合して解釈します。
温度覚:提示順序と誤認対策
手順:温冷試験片(例:金属スプーンに温水/冷水をつけたものなど)を用いて、「温かい/冷たい」を弁別してもらいます。提示時間は各 1–2 秒とし、左右・部位をランダムに切り替えます。同じ種類の刺激を連続して当て続けると予測で答えやすくなるため、温・冷・ダミーをバランスよく混ぜます。
判定:誤認の傾向(常に温に寄る、遅れて答える等)を把握し、左右差と遠位優位のパターンを確認します。末梢循環が悪いと閾値が上がるため、手足の冷感や浮腫の有無は備考に明記しておきます。必要に応じて再加温後に再評価し、「環境要因で悪く見えていないか」を確認します。
感覚検査のスコアリング(10 点法・5 回法)
表在感覚検査では、所見をただの文章だけで残すより、「感覚検査 10 点法」「感覚検査 5 回法」のように刺激回数を決めてスコア化すると比較がしやすくなります。10 点法は「 1 部位につき 10 回刺激して正答数を 0〜10 点で記録」、5 回法は「 5 回中の正答数を 0〜5 点で記録」するイメージです。
やり方のポイントは、(1) あらかじめ刺激回数( 10 回/ 5 回)と刺激間隔を決める、(2) 「今」「どこ」「温かい/冷たい」「鋭い/鈍い」など問いかけを一定にする、(3) 正答率だけでなく、誤答のパターン(常に同じ側を答える・遅延が目立つ等)も欄外にメモする、の 3 点です。スコアはカットオフで「正常/疑い」などと分けるより、経時変化や左右差を見る指標として使うと、臨床での解釈がしやすくなります。
記録テンプレ(語彙統一)
記録は「左右・部位・語彙」を統一し、再評価日と検者名を必ず残します。自由記載のみでは共有性が低く、他職種連携で解釈がばらつきます。下の最小フォーマットをコピーして使い、院内様式がある場合は語彙を合わせます。
スクリーニングで異常が出た項目は、同日に再検して一貫性を確認します。ダミーへの反応、遅延、過敏、誤認の有無も「備考」に簡潔に追記します。写真や動画記録は、同意がある場合のみ併用します。
| 項目 | 左 | 右 | 所見/語彙 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 触覚 | 正常/低下/消失 | 正常/低下/消失 | 遅延/誤認 など | 部位・再現性 |
| 痛覚(鋭鈍) | ○/△/× | ○/△/× | 誤認率 xx % | 過敏の有無 |
| 温度覚 | 温/冷 の弁別可否 | 温/冷 の弁別可否 | 遅延/一貫性 | 冷感・浮腫 |
よくあるミスと対策(OK/NG 早見)
表在感覚検査の質は「説明」「刺激」「記録」の 3 点で決まります。説明は短く具体的に、刺激は一定強度・一定時間・ランダム、記録は語彙を統一して左右差と一貫性を明確化します。患者さんの理解度や疲労度に応じて、刺激回数や休憩を柔軟に調整しましょう。
NG はリズミカル提示、誘導質問、「当たり」を教える反応、自由記載のみの記録です。OK は練習試行の導入、ダミーの併用、誤答時の追試、再評価日の明記です。下の OK/NG 表をチームで共有しておくと、「やり方のブレ」が減り、中止基準の共通理解にもつながります。
| 場面 | OK(推奨) | NG(避ける) | 理由/メモ |
|---|---|---|---|
| 説明 | 短く具体的+練習試行 | 冗長・抽象的説明 | 理解不足で偽陽性/偽陰性 |
| 刺激 | 一定強度・時間・ランダム+ダミー | 予測可能なリズム | 期待バイアスを増やす |
| 記録 | 語彙統一・左右/部位・再評価日 | 自由記載のみ | 多職種共有が困難 |
表在感覚と深部感覚の違い・伝導路の整理
表在感覚と深部感覚の違いを押さえておくと、所見から障害部位を推定しやすくなります。表在感覚(触覚・痛覚・温度覚)は主に皮膚からの入力で、温痛覚は脊髄視床路、粗大な触圧覚や一部の表在感覚は脊髄視床路と後索路を通ります。一方、深部感覚(位置覚・運動覚・振動覚)は関節・筋・腱からの入力が中心で、主に後索路を通ります。
臨床では、「表在感覚だけ障害」「深部感覚だけ障害」「両方障害」の 3 パターンを意識すると、表在感覚 伝導路レベルの障害や、小脳・大脳での統合障害をイメージしやすくなります。例えば、温痛覚のみの障害は脊髄視床路主体の障害を、深部感覚の障害は後索障害や大脳の体性感覚野障害をまず疑う、といった考え方です。
評価結果をリハビリにどう活かすか
表在感覚 リハビリのポイントは、「安全確保」と「フィードバック手段の選択」に直結させることです。痛覚・温度覚の低下があれば褥瘡や火傷のリスクが上がるため、ポジショニングや体位変換の頻度、皮膚チェック体制を強化します。触覚の低下や誤認があれば、荷重訓練や歩行練習での荷重フィードバックを視覚・聴覚情報で補う工夫が必要です。
また、「触覚はほぼ正常だが痛覚が過敏」「温度だけ誤認が目立つ」などの所見は、慢性痛や自律神経の関与を示唆する手がかりになります。表在感覚検査の結果を、バランス評価・歩行評価・ ADL 評価と組み合わせて解釈し、「どの場面で危険が出やすいか」「どの感覚チャネルを使えば学習しやすいか」を具体的にリハプログラムへ落とし込むことが重要です。
現場の詰まりどころ
現場でよく詰まりやすいのは、「とりあえず一通りなぞっているが、結果の意味づけがあいまい」というケースです。例えば、痛覚低下を確認したあとに褥瘡リスク評価やポジショニング計画へ反映できていない、触覚低下を確認したあとに立位・歩行時の荷重訓練でどの感覚チャネルを使うかまで検討できていない、などが典型です。検査を「やった」で終わらせず、「どの生活場面で危険になるのか」「どの介入の優先度が上がるのか」までセットで考えるのがポイントです。
もう 1 つの詰まりどころは、認知症・失語・注意障害を合併している人への対応です。うまく答えられない=感覚障害とは限らず、理解・注意・遂行機能の問題が紛れ込みます。こうした場合は、質問文を短く区切る、合図方式に切り替える、健側からのアプローチで注意を引きつけるなど、「検査課題のハードル」を下げる工夫が必要です。それでも判定が難しいときは、「判定不能」や「信頼性低い」と明記しておくことで、無理に正常/異常で切らないことも大切です。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
感覚検査 10 点法と 5 回法は、どちらを使えばよいですか?
目的と現場のリソースで使い分けて構いません。細かく経時変化を追いたい場合や研究データとして扱う場合は 10 点法の方が分解能が高く、回復期リハや外来でのフォローに向きます。一方で、急性期病棟や短時間で全体像を把握したい場面では 5 回法でも十分です。重要なのは「同じ患者さんには毎回同じ方法を使うこと」と「点数だけでなく、誤答パターンや遅延などのメモもセットで残すこと」です。
表在感覚検査は、1 人あたりどれくらい時間を見ておけばよいですか?
フルセットで丁寧に行うと 10〜15 分程度を想定すると現実的です。急性期で全身状態が不安定な場合は、リスクの高い部位(踵・仙骨周囲・荷重部位など)と症状の強い部位を優先し、短時間でスクリーニング的に行います。逆に、回復期で麻痺側の再学習をねらう場合は、時間をかけて反応の一貫性や誤認の傾向まで詳細に確認した方が、その後の練習設計に役立ちます。
認知症や失語がある人には、どのように工夫して実施すればよいですか?
まず、説明文を短くし、 1 つの指示に含める情報を減らします(例:「今から触ります。触れたら手を握ってください」のように、 1 文で完結させる)。口頭回答が難しければ、「触れたら手を握る」「痛いときだけ『はい』と言う」など、反応パターンをシンプルにします。また、注意障害がある場合は、検査前に覚醒度を高める工夫や、検査時間を 2 回に分けるなど、負荷を下げることも有効です。そのうえで、「感覚障害」と「認知・注意の問題」が混在している可能性を常に意識して解釈します。
おわりに
表在感覚検査は、「なんとなく一通りやる」から「結果をリハビリに結びつける」へシフトさせることで、評価の価値が大きく変わります。触覚・痛覚・温度覚のそれぞれで左右差・部位差・一貫性を整理し、褥瘡リスク、荷重コントロール、慢性痛の感作など、具体的なリスクや介入目標に落とし込むことが重要です。
深部感覚や複合感覚の結果、歩行・バランス評価、 ADL 評価と組み合わせて全体像を描くことで、「どの場面で事故が起きやすいか」「どの感覚チャネルをリハで強調すべきか」が見えやすくなります。日々の評価の中で少しずつ手順と記録様式を標準化し、チーム全体で同じ言葉・同じ視点で感覚所見を共有していきましょう。
参考文献
- 神経学的検査の標準テキスト(感覚検査の章)
- 触覚・痛覚・温度覚検査の信頼性・妥当性を検証した臨床研究
- 脊髄視床路・後索路など表在感覚 伝導路に関する神経解剖学の教科書
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下