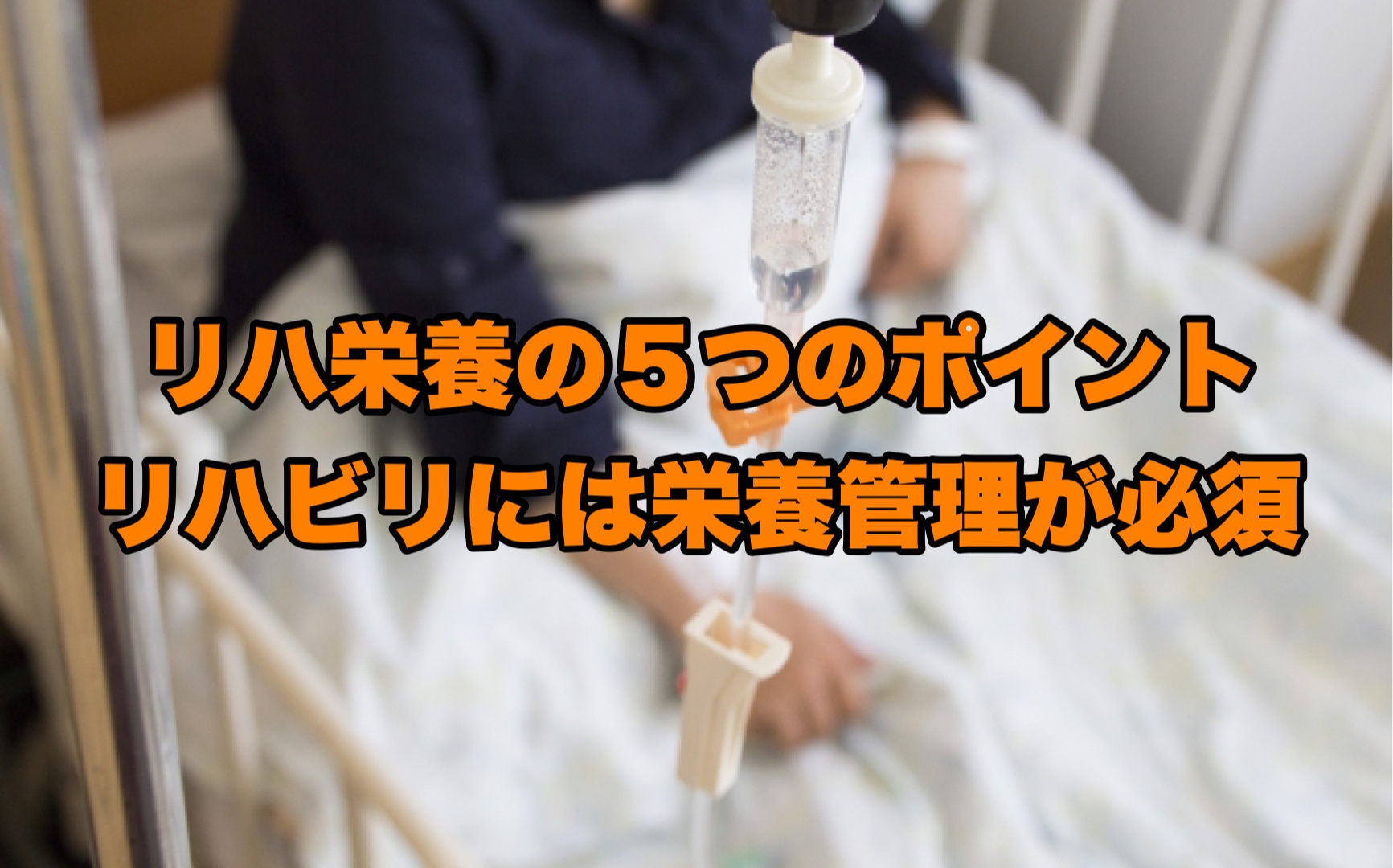- リハ栄養の全体像(「何を・いつ・どう記録するか」まで 5 分で整理)
- リハ栄養とは?(リハの目標を「食べられる/動ける」へ同時に近づける考え方)
- 5 ステップ早見表(チームで共有する “最短ルート” )
- ① スクリーニング(最初の 48 時間で “低栄養リスク” を見逃さない)
- ② 栄養評価( GLIM 的に “原因と重症度” をそろえる)
- ③ 目標設定(「栄養目標」だけを立てない:機能目標とセットで書く)
- ④ 介入(食事・補食・運動を “同じ設計図” に載せる)
- ⑤ モニタリング( “体重だけ” を卒業:反応を 3 点セットで追う)
- 現場の詰まりどころ( OK / NG 早見:ここを直すと回り出す)
- よくある質問(FAQ)
- 参考文献
- 著者情報
- 関連記事
- おわりに
リハ栄養の全体像(「何を・いつ・どう記録するか」まで 5 分で整理)
リハ栄養で詰まりやすいのは、「評価が点在していて方針に結びつかない」「介入しても再評価が曖昧で、効果が説明できない」の 2 点です。本記事は、リハ栄養を ①スクリーニング → ②評価 → ③目標設定 → ④介入 → ⑤モニタリング の流れで整理し、チームで共有できる “記録の型” までまとめます。
ポイントは、栄養そのものを “単独” で追うのではなく、機能( ADL / 歩行 / 持久力 )と同じように「介入→反応→再評価」 で回すことです。体重・摂取量・筋量 “だけ” でも、筋トレ “だけ” でも改善しにくい場面ほど、この流れが効きます。
リハ栄養とは?(リハの目標を「食べられる/動ける」へ同時に近づける考え方)
リハ栄養は、低栄養・サルコペニア・フレイルなどの栄養課題を、運動療法・活動量・食事(補助食品含む)とセットで設計し、生活機能の改善につなげるアプローチです。臨床では「栄養は栄養科、リハはリハ」の分業になりがちですが、実際は “食べられないと動けない/動けないと食べられない” が同時に起こります。
だからこそ、リハ側の役割は「栄養評価の代行」ではなく、機能の見立てに必要な栄養情報を揃え、目標と介入を同じ言葉でつなぐことです(例:歩行練習量が増えた → 摂取不足が顕在化 → 介入を調整、など)。
5 ステップ早見表(チームで共有する “最短ルート” )
まずは 1 枚で全体像を揃えます。会議・カンファ・申し送りでは、「いま何番をやっているか」が一致するだけでスピードが上がります。
※表は横スクロールで見られます。
| ステップ | 目的 | 最低限みる項目 | 記録の型(例) | 次アクション |
|---|---|---|---|---|
| ① スクリーニング | 低栄養 “かも” を早期に拾う | 体重変化、食欲・摂取量、浮腫、炎症の有無 | 「◯日で体重 −◯ kg/摂取 ◯ 割/CRP ◯」 | ② へ(必要なら栄養科へ依頼) |
| ② 栄養評価 | 原因と重症度を整理 | 体重・ BMI、筋量(可能なら)、食事内容、嚥下・口腔、疾患・薬剤 | 「不足:エネルギー/蛋白/水分。原因:…」 | ③(優先度とリスクを合意) |
| ③ 目標設定 | リハ目標と “栄養目標” を同期 | ADL / 歩行 / 耐久性の短期目標、摂取目標、体重・筋量の目標 | 「 2 週で摂取 ◯ kcal → ◯ kcal、歩行量 ◯→◯」 | ④(介入を選ぶ) |
| ④ 介入 | 摂取↑ と活動↑ を同時に | 食形態、補食、タイミング、運動量、休養、疼痛・抑うつ | 「介入:補食◯回+筋トレ◯回、観察:…」 | ⑤(反応を追う) |
| ⑤ モニタリング | 効いているか/副作用はないか | 体重、摂取率、便通、浮腫、尿量、活動量、筋力・歩行 | 「 7 日で体重 +◯ kg、摂取 ◯% 、 TUG ◯→◯」 | 介入を継続・強化・修正 |
① スクリーニング(最初の 48 時間で “低栄養リスク” を見逃さない)
スクリーニングは “診断” ではなく、介入が必要になりそうな人を早く拾うための工程です。重要なのは、採用する尺度よりも 「いつ・誰が・どこに記録するか」を決めることです。回復期・地域包括・外来・訪問でも、体重と摂取状況は共通言語になります。
スクリーニングで迷う場合は、「体重変化」と「摂取量」を最優先に押さえます。ツールの使い分けは別記事で整理しているので、続けて読む場合は 栄養スクリーニング(低栄養リスク)の使い分け を参照してください。
② 栄養評価( GLIM 的に “原因と重症度” をそろえる)
評価の目的は、「なぜ不足しているのか」を分解し、重症度(どれくらい急ぐか)を合意することです。現場では “アルブミンだけ” で判断が固定されることがありますが、炎症や水分で変動するため、単独で結論を出すとズレやすくなります。
実務では、①体重(推移)②摂取量(割合)③炎症・疾患活動性 ④嚥下・口腔 ⑤活動量を最低セットにし、必要に応じて筋量( BIA / CT / 周径 )などを追加します。ここで “原因の仮説” が立つと、次の目標設定が一気に具体化します。
③ 目標設定(「栄養目標」だけを立てない:機能目標とセットで書く)
目標設定は、体重・摂取量の数値目標と、機能の短期目標を同じ期間で結ぶのがコツです。例えば「 2 週間で歩行練習量を増やす」なら、「その増量に見合う摂取(特に蛋白)を確保する」まで 1 セットで合意します。
書き方の型は、期限→栄養→機能→観察指標の順がおすすめです。例:「 14 日で摂取率を ◯% → ◯% 、起立練習を 1 日 ◯ 回へ。体重・浮腫・便通・疲労度を毎日確認。」のように、誰が見ても “次にやること” が分かる形にします。
④ 介入(食事・補食・運動を “同じ設計図” に載せる)
介入でよくある失敗は、運動量だけ上げて摂取が追いつかない、または 補食だけ増やして活動が上がらないことです。リハ場面では、運動前後の疲労・食欲・嚥下状況を観察できる強みがあるので、タイミング調整(例:運動後に摂りやすい形へ)を提案しやすくなります。
高齢者では、減量が必要な肥満でも “食事制限を強めすぎない” バランスが課題になります。体重だけに引っ張られず、筋量維持(蛋白)+安全な活動量を優先し、必要時は多職種で “制限の度合い” を調整します。
⑤ モニタリング( “体重だけ” を卒業:反応を 3 点セットで追う)
モニタリングは、リハの再評価と同じで 「介入の反応を見る」工程です。体重は重要ですが、浮腫や水分でブレます。そこで、①摂取率 ②体重(推移)③機能(筋力・歩行・持久力)の 3 点セットで追うと、解釈が安定します。
週単位のレビューでは、「摂取は上がったか」「活動は上がったか」「副作用(便秘・下痢・浮腫・倦怠感)はないか」を確認し、継続/強化/修正を決めます。数字が動かないときは、評価に戻って “原因の仮説” を更新するのが近道です。
現場の詰まりどころ( OK / NG 早見:ここを直すと回り出す)
「できているつもり」でも、運用で止まりやすいポイントをまとめます。詰まったら、この表の “ NG 側” に寄っていないかを確認してください。
| 場面 | NG(起こりがち) | OK(こう直す) | 記録に残す一言 |
|---|---|---|---|
| 情報収集 | 体重・ Alb のみで判断 | 体重推移+摂取率+炎症(疾患活動)をセット | 「体重推移/摂取 ◯%/炎症 ◯」 |
| 目標 | 栄養目標と機能目標が別々 | 期限をそろえて同期(例: 2 週で摂取↑+歩行量↑) | 「 14 日で摂取 ◯%→◯% 、歩行 ◯→◯」 |
| 介入 | 運動↑ で食事が追いつかない | 運動量と “摂れる形・タイミング” を同時調整 | 「運動後の摂取形態を調整」 |
| 再評価 | 体重だけ見て一喜一憂 | 摂取率+体重推移+機能の 3 点で解釈 | 「摂取 ◯%/体重 ◯/ TUG ◯」 |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 栄養科がない職場でも、リハ側が最初にやるべきことは?
A. まずは “拾い上げ” の運用を作ります。体重推移と摂取率(主観でよいので何割食べたか)を決めた頻度で記録し、低下があれば ②評価へ進める流れにします。最初から完璧な評価項目を揃えるより、「見逃さない仕組み」を優先すると回り出します。
Q2. エネルギーや蛋白の目標量は、どのタイミングで決めますか?
A. 目標設定(③)で “機能目標と同期” させて決めます。数式での推定は目安にして、摂取率・疲労・便通・浮腫などの反応を ⑤モニタリングで見ながら調整するのが現実的です。
Q3. 肥満の高齢者は、減量を優先してよいですか?
A. 体重だけで強い制限をかけると、筋量低下や活動性低下につながりやすいので注意が必要です。合併症や膝・腰の負担など “減量の目的” を明確にしたうえで、筋量維持(蛋白)と運動をセットにして進めます。
Q4. どれくらいの頻度で再評価すればいいですか?
A. まずは 1 週単位のミニレビュー(摂取率・体重推移・機能)がおすすめです。急性期や状態変動が大きい場合は短い周期で、安定期は週 1 回でも回ります。重要なのは “再評価のたびに介入を修正する” ことです。
参考文献
- Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.08.002 / PubMed: 30181091
- Volkert D, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019;38(1):10-47. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.05.024 / PubMed: 30005900
- Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51(2):241-247. DOI: 10.1093/ajcn/51.2.241 / PubMed: 2305711
- Finger D, Goltz FR, Umpierre D, et al. Effects of protein supplementation in older adults undergoing resistance training: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2015;45(2):245-255. DOI: 10.1007/s40279-014-0269-4 / PubMed: 25315533
- Chen LK, Woo J, Assantachai P, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(3):300-307.e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.12.012 / PubMed: 32033882
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
関連記事
| 記事 | おすすめの読みどころ |
|---|---|
| 栄養スクリーニング(低栄養リスク)の使い分け | 現場で迷いやすい尺度選びと、最短で運用に乗せる考え方 |
| MST( Malnutrition Screening Tool )の使い方 | 短時間で拾う運用設計(誰が/いつ/どこに記録するか) |
おわりに
リハ栄養は、「拾い上げ→原因の仮説→目標同期→段階介入→反応の再評価」という “リズム” で回すほど、チームの迷いが減り、成果の説明もしやすくなります。面談準備チェックと職場評価シートを使って次の一手を整えたい場合は、/mynavi-medical/#download もあわせて活用してください。