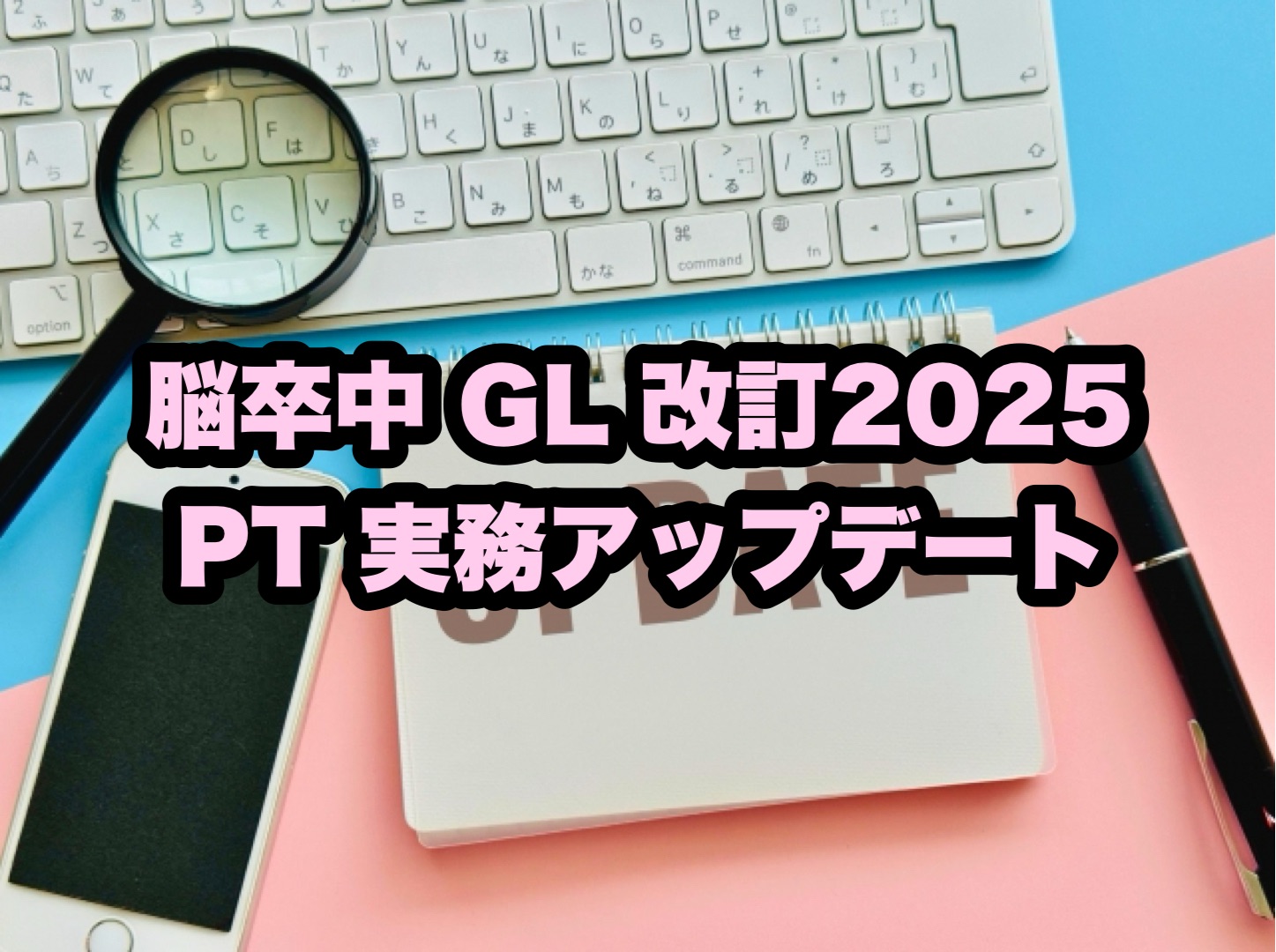脳卒中ガイドライン 2025 の要点( PT 実務に直結 )
日本脳卒中学会『脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂 2025〕』では、回復期以後のリハ診療( VII 章 )を含む要所が整理・更新されています。本稿は 「変更点」→「明日から何を変えるか」の順で、評価束・介入・記録・再評価までを PT の実務に落とし込む設計でまとめました。
読む順番は ①章別の早見表 → ② VII 章のテンプレ → ③現場の詰まりどころ(失敗回避)が最短です。一次情報(学会など)へのリンクは末尾に集約しています。
ガイドラインを読むだけで終わらせず、「評価→介入→再評価」の型で現場に落とし込みたい方へ。 臨床に活きる PT キャリアガイド(準備〜流れ)を確認する ※同一タブで開きます(チェックリスト形式で抜け漏れ防止)。
章別:改訂のポイント早見表
横スクロールできます(スマホ向け)。臨床インパクトの大きい VII 章(回復期以後のリハ診療)は行を厚めにしています。
| 章・領域 | 改訂の要点(要約) | PT 実務インパクト |
|---|---|---|
| 総論・評価 | 推奨の表現整理、測定の標準化・再評価の重要性が強調。 | 施設基準で 評価束を固定( 10 m 速度/ TUG / 5STS / SPPB / BBS など)。週 1 回以上の同条件・同時刻で再評価をルーチン化。 |
| 急性期〜亜急性期 | 早期離床・合併症予防と安全管理の具体化。 | 離床プロトコルの段階刺激と red flags の明文化(起立性低血圧・心肺イベント・嚥下リスクの同時管理)。 |
| VII 章:回復期以後のリハ診療 | 歩行ロボット/ BWSTT / FES / NMES / rTMS / tDCS / BCI などの位置づけが整理。上肢機能は反復課題練習を軸にニューロモデュレーション併用が示唆。嚥下は段階的アプローチを推奨。 | 評価 → 介入 → 記録 → 再評価をテンプレ化。 ・歩行:ロボット/免荷トレッドミル+地上課題(デュアルタスク・障害物・方向転換)。 ・上肢:FMA-UE / ARAT をアウトカムに NIBS・BCI 併用を検討。 ・嚥下:体位・代償 → CTAR/シェイカー → 呼吸筋訓練 → 適応あれば NMES/ rPMS / rTMS 。 |
| 痙縮・二次的問題 | ボツリヌス療法や装具療法の協働を明確化、目標設定と機能転移を重視。 | 痙縮目標を ADL ・移動・疼痛で統合。ボツリヌス注射後の「タイムウィンドウ」に合わせて反復課題を増量。 |
| 退院支援・社会参加 | セルフマネジメント、生活環境下での転倒予防・活動量確保を強調。 | 屋外移動課題・目標歩数・自己記録(歩行日誌)を導入。家屋調整と IADL 支援を多職種で。 |
脳卒中 ガイドライン 2025 リハビリ( VII 章の実務対応テンプレ )
VII 章は「何をやるか」よりも、誰に・どの順番で・どれだけ(用量)・どう記録して再評価するかが勝負です。院内で迷いにくいよう、最小セットで型にしました。
1)評価束(最小セット)
- 10 m 歩行速度(通常/最良)、TUG、5 回立ち上がり( 5STS )、SPPB、BBS。
- 条件固定:靴/補装具、助走・測定区間、イス高、デバイス(同機種)を施設基準で文書化。再評価は週 1 回以上、同条件・同時刻で。
2)歩行:12 週プロトコル例
- 1–2 週:基準化( 10 m / TUG / 5STS / SPPB )→ 体重免荷/ロボット適応判定。
- 3–8 週:ロボット or BWSTT 20–30 分+地上でデュアルタスク・障害物・方向転換を組合せ。
- 9–12 週:屋外移動(負荷漸増)+セルフトレ(目標歩数・目標速度)。
記録:介入(種類・分数・反復 )/ 10 m 速度/ TUG / 5STS / SPPB / 患者報告(疲労・恐怖感)。
用量( dose )の決め方(歩数・分数・頻度の固定)と、「増やせない時の代替策」は別記事で整理しています。脳卒中 歩行リハの用量設計( dose )
3)上肢:反復課題 × ニューロモデュレーション
- 対象:慢性期で随意回復が頭打ち、集中訓練が可能、禁忌を満たさない例。
- 介入:反復課題練習を軸に、適応があれば tDCS / rTMS / BCI / NMES を段階併用。
- アウトカム:FMA-UE / ARAT / 作業課題の順守率・実使用時間。
導入時に迷いやすい 「何を選ぶか/どのタイミングで併用するか/安全の確認」は、別記事で実務用にまとめています。脳卒中 上肢リハ×ニューロモデュレーション(使い分け)
4)嚥下:段階的アプローチ
- 体位・代償(姿勢・食形態・ペーシング)から開始。
- CTAR / シェイカー、呼吸筋訓練を導入。
- 適応があれば NMES / rPMS / rTMS を多職種で設計(安全管理・説明同意を徹底)。
記録:EAT-10 の手順と解釈、水飲み/ゼリー試験、必要に応じ VF / VE 所見。
5)安全管理と説明同意
- 禁忌・注意:金属・てんかん・皮膚病変・刺激閾値・服薬状況などを事前チェック。
- 用量管理:週あたりのアクティブ練習時間・歩数/反復をダッシュボード化し到達度を見える化。
- 説明同意:目的・期待効果・不確実性、適用(保険/自費/研究)を明記。
現場の詰まりどころ(よくある失敗)
ガイドラインの内容が合っていても、運用(条件固定・用量・記録)が曖昧だと効果が伸びません。失敗しやすいポイントを「立て直し手順」つきで整理します。
| 詰まりどころ | ありがちなパターン | 立て直し(最小手順) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 評価束が揃わない | 測定条件が人によって違う/再評価の曜日が固定されない。 | まず 靴・補装具・助走・イス高を紙 1 枚に固定。週 1 回の「再評価枠」をカレンダーで確保。 | 条件(補装具・歩行補助具・測定区間)を毎回同じ欄に記載。 |
| 歩行の用量が積めない | ロボットや免荷で「やった感」はあるが、歩数・時間が増えない。 | 分数 → 歩数 → 難易度の順に 1 つだけ増やす。増やせない日は「地上課題の短時間反復」に置き換える。 | 分数/歩数/ RPE / 10 m 速度をセットで残す。 |
| 上肢の追加手段で迷う | 機器( tDCS / rTMS / NMES / BCI )の導入が目的化する。 | 先に 反復課題(目標課題)を決め、併用は「前処置/同時/後追い」のどれか 1 つに固定して検証。 | 課題の反復回数・達成率・ FMA-UE / ARAT の変化。 |
| 振り返りが続かない | 記録が増えすぎて運用が崩れる/教育が属人化する。 | まずは 最小テンプレ( 5 項目 )で回す。見学・配属直後は「抜け漏れ防止のチェック」を先に整える。 | 記録テンプレの入力率(欠損の有無)を追う。 |
院内の標準手順づくりや、見学時の確認ポイントの抜け漏れ防止に。面談準備チェック( A4 ・ 5 分 )と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。ダウンロードはこちら
明日から変える 3 点
- 介入前に 評価束を固定( 10 m / TUG / 5STS / SPPB / BBS )。
- 歩行は ロボット/免荷+地上の実環境課題でアウトカム直結にする。
- 上肢・嚥下・痙縮は 対象選択 × 用量 × 安全をテンプレ化し、週 1 回以上の再評価を定例化する。
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 改訂項目の全体像はどこで確認できますか?
A. 日本脳卒中学会の公式サイト、および改訂ポイントの資料( PDF )が公開されています。まずは一次情報を起点に確認し、院内プロトコルへ落とし込みましょう。
Q2. 院内での運用に向けて、まず何を整備すべき?
A. 評価束( 10 m / TUG / 5STS / SPPB / BBS )の測定条件を文書化し、週 1 回以上の再評価枠を固定します。次に「介入(種類・分数・反復)」「患者報告」「アウトカム」を最小テンプレで 1 枚にまとめると運用が崩れません。
Q3. VII 章で注目される治療は?導入時の注意点は?
A. tDCS / rTMS / BCI / NMES / FES / ロボット( BWSTT 含む )などです。導入は 目的・用量・安全・再評価を 1 セットで設計し、禁忌や説明同意、院内の実施条件(保険/自費/研究)を明確にしてから運用してください。
次の一手
- 脳卒中の記事をまとめて辿る:脳卒中ハブ
- 歩行の運用を詰める:脳卒中 歩行リハの用量設計( dose )
- 上肢の伸びしろを作る:脳卒中 上肢×ニューロモデュレーション実務
参考文献・一次情報( Vancouver 風 )
- 一般社団法人日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂 2025〕改訂項目( PDF ). https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
- Podsiadlo D, Richardson S. The Timed “Up & Go”: A test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142–148. doi:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x. PMID:1991946
- Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000;80(9):896–903. PMID:10960937
- Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function. J Gerontol. 1994;49(2):M85–M94. doi:10.1093/geronj/49.2.M85. PMID:8126356
- Buatois S, Miljkovic D, Manckoundia P, et al. Five times sit to stand test is a predictor of recurrent falls in healthy community-living subjects aged 65 and older. J Am Geriatr Soc. 2008;56(8):1575–1577. doi:10.1111/j.1532-5415.2008.01777.x. PMID:18808608
- Perry J, Garrett M, Gronley JK, Mulroy SJ. Classification of walking handicap in the stroke population. Stroke. 1995;26(6):982–989. doi:10.1161/01.STR.26.6.982. PMID:7762050
- Yardley L, Beyer N, Hauer K, et al. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International ( FES-I ). Age Ageing. 2005;34(6):614–619. doi:10.1093/ageing/afi196. PMID:16267188
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下