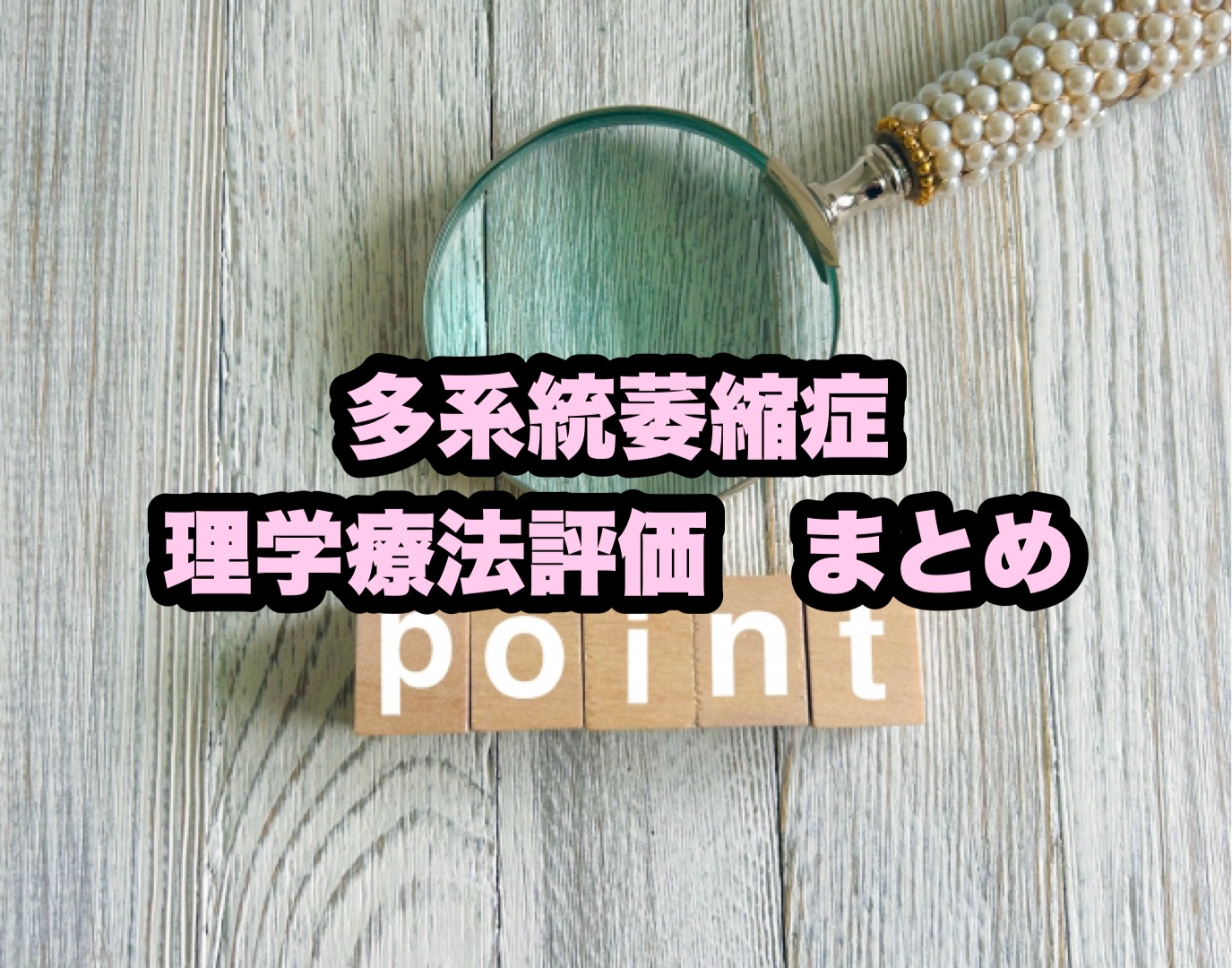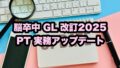多系統萎縮症( MSA )の理学療法評価: UMSARS と SARA を軸に、転倒・嚥下・起立性低血圧( OH )まで同日で“バンドル”する
評価の迷いを減らすには「リスク確認 → 機能 → 病勢」の順番を固定するのが最短です。 理学療法士の転職ガイド(準備〜流れ)を見る
多系統萎縮症( MSA )は、小脳失調・パーキンソニズム・自律神経障害が混在し、同じ患者さんでも日によって「前に出る症状」が変わります。だからこそ評価は、①転倒/誤嚥/ OH などのリスク確認 → ②機能(歩行・バランス) → ③病勢(疾患特異尺度)の順で束ね、同日・同条件で縦断取得できる形に整えるのがコツです。
本ページは、病勢は UMSARS 、失調重症度は SARA を核に置きつつ、転倒・誤嚥・起立性低血圧( OH )などの臨床リスクまで一気通貫で整理します。まずは「同日バンドルの最小セット」を固定し、余力が出たら追加評価(詳細な歩行解析、より網羅的な失調尺度など)を積み上げてください。
クイックリンク(このページ内)
- MSA の病態と評価の意義
- 初回 10 分フロー(リスク確認 → 機能 → 病勢)
- 同日バンドルの最小セット(早見表)
- 現場の詰まりどころ/よくある失敗
- 疾患特異的評価: UMSARS
- 失調重症度: SARA / ICARS
- パーキンソニズム合併の見立て
- 自律神経:起立性低血圧( OH )
- 歩行・バランス・転倒リスク
- 嚥下・構音・呼吸(赤旗つき)
- 再評価間隔と指標の束ね方
- よくある質問
- 次の一手
MSA の病態と評価の意義
MSA は、小脳失調・パーキンソニズム・自律神経障害が混在する進行性疾患です。臨床では疾患特異的尺度・機能評価・合併症リスク評価を同日に束ねて縦断取得すると、転倒・誤嚥・ OH などの二次予防に直結します。
運用を安定させる要点は 2 つです。①病勢は UMSARS 、失調は SARA を核にして「縦の軸」を作る。②転倒/誤嚥/ OH を先に拾ってから歩行・バランスへ進み、「中止基準とリスク管理の線引き」を明確にする。これだけで、評価の迷いと手戻りが一気に減ります。
初回 10 分フロー(リスク確認 → 機能 → 病勢)
初回は「精密さ」より「方向づけ」が優先です。転倒/誤嚥/ OH のサインが強いと、歩行練習そのものが破綻しやすくなります。まず“止める基準”を固め、次に機能(歩行・バランス)、最後に病勢( UMSARS / SARA )へつなげます。
| 順番 | 目的 | 最低限みること | 記録の要点 |
|---|---|---|---|
| ① リスク確認 | 中止基準と実施条件を決める | 起立時の前失神/ふらつき、むせ・湿性嗄声、呼吸の違和感 | 症状の有無と出現タイミング(起立後 1–3 分、食後など) |
| ② 機能 | 転倒の起点を同定 | 起立・方向転換・停止・狭所での破綻 | 補助具・靴・装具・介助量を固定 |
| ③ 病勢 | 縦断の軸を作る | UMSARS( I・II・IV )+ SARA | 同日取得、前回比(%)と条件(内服・疲労)を併記 |
同日バンドルの最小セット(早見)
臨床で回しやすい「最小セット」は次の構成です。まずはこのセットを同日取得できる形に整え、余力が出てから追加項目(詳細な歩行解析、より網羅的な失調尺度など)を積みます。
- 病勢: UMSARS( I・II・IV )
- 失調: SARA(必要時のみ ICARS )
- 転倒:バランス指標(例: BBS )+機能的移動(例: TUG )+歩行速度(例: 10 m )
- OH :臥位 → 立位の血圧・心拍( 1 分・ 3 分 )
- 嚥下:ベッドサイドスクリーニング( RSST → 必要時 MWST )
現場の詰まりどころ/よくある失敗
MSA の評価は「項目の多さ」よりも、同じ条件で縦断比較できないことが詰まりやすいポイントです。まずは条件固定(内服・時間帯・補助具・介助量)を型にしてから、スケールの精度を上げていくほうが、結果的に早く安定します。
振り返りや申し送りが散らばる場合は、面談準備チェック(抜け漏れ防止)と職場評価シート(観点の統一)をテンプレ化しておくと、チームの記録が揃いやすくなります。配布物のダウンロードはこちら
| よくある失敗 | 起きやすい理由 | 整え方(最小手順) | 記録テンプレの一言 |
|---|---|---|---|
| 毎回、実施順がバラバラ | 症状の揺らぎで“その日できること”に流される | 順番を固定( OH/嚥下 → 機能 → UMSARS/SARA )し、できない項目は「欠測理由」を残す | 「本日は OH 症状ありのため歩行は中止、病勢のみ実施」 |
| 点数は取れるが、介入に繋がらない | 転倒の起点(開始/ターン/停止)が言語化されない | 点数に 1 行コメント(どこで崩れたか)を必ず併記する | 「ターンで外側へ流れる/停止で前方へ突っ込む」 |
| 前回比が解釈できない | 内服・時間帯・補助具が揃っていない | 条件を固定し、変えた場合は“変更点だけ”を書き足す | 「内服後 60 分、四点杖、介助量 1 名見守り」 |
| OH の数値だけで判断してしまう | 症状(前失神)が拾えていない | 数値 + 症状 + 出現タイミングをセットで残す | 「起立後 2 分で眼前暗黒、着座で改善」 |
疾患特異的評価: UMSARS
UMSARS は Part I(症状・ ADL )、Part II(運動)、Part IV(全体障害度)で病勢を縦断把握する標準尺度です。運用のコツは、 I・II・IV を同日に取得し、取得条件(内服、装具、補助具、時間帯、疲労)を短文で併記することです。これだけで、小さな変化の解釈が安定します。
Part II の「姿勢・歩行」は、移動課題(起立・方向転換・停止)で破綻点を観察し、バランス指標と歩行速度を並記して立体的に捉えます。点数そのものより、転倒の起点(どの場面で崩れるか)とセットで残すと、介入の方向づけがブレません。
失調重症度: SARA / ICARS
SARA( 0–40 点、 8 項目)は簡便で頻回再評価に適し、 ICARS( 0–100 点、 19 項目)は網羅性が高く研究・精査向けです。実務では外来= SARA 中心、詳細が必要な局面でのみ ICARS 併用が現実的です。
協調障害のばらつきは、失調尺度だけで完結させず、歩行(通常・最大)や移動課題で「破綻の質」を併記すると解釈が安定します。採点は「できた/できない」ではなく、崩れる理由(速度、視線、二重課題、疲労)を短文で残すと再現性が上がります。
パーキンソニズム合併の見立て
MSA では固縮、寡動、姿勢反射障害、すくみ足が共存し、動作が「詰まる」場面が転倒の起点になります。評価では、起立・方向転換・狭所・停止での破綻を観察に組み込み、症状の揺らぎ(時間帯・疲労)も合わせて記録します。
薬剤反応性が乏しい例では、訓練の順序と休息設計が転倒リスク低減に直結します。つまり「評価で拾った破綻点」を、介入の優先順位(転倒の起点から潰す)にそのまま接続する設計が重要です。
自律神経:起立性低血圧( OH )の評価
臥位 5 分・立位 1 分・立位 3 分で血圧/心拍数を測定し、起立後 3 分以内の収縮期 20 mmHg 以上または拡張期 10 mmHg 以上の低下を OH とします。食後・脱水・降圧薬などの影響は必ず併記し、神経原性が疑われる場合は立位時の心拍上昇が乏しい所見にも注意します。
評価は「数値」だけでは不十分です。症状(前失神、気分不良、眼前暗黒)の有無と出現タイミングをセットで記録し、症状が強い日は歩行系を後回しにして、まず条件(休息・水分・タイミング)を整えます。
歩行・バランス・転倒リスク
バランス指標・移動課題・歩行速度を中核に、座位 → 立位 → 歩行の順で実施します。 MSA では方向転換の不安定が目立ちやすいため、ターンや停止の場面で「破綻点」を明確にし、同じ条件(補助具・靴・装具・介助量)で再評価します。
天井/床効果が疑われる場合は、点数に加えて「どこで崩れるか」を短文で残し、次回の比較(同条件)で解釈がブレないようにします。
嚥下・構音・呼吸
嚥下はベッドサイドでスクリーニングし、異常時は精査へ連携します。 MSA では吸気性喘鳴や声帯運動異常が臨床上のリスクになり得るため、会話後・食後・夜間など「いつ悪化するか」をチームで共有できる形に整えます。
| 赤旗 | その場でやること | 記録の要点 |
|---|---|---|
| 吸気性喘鳴/夜間喘鳴 | 負荷を上げない。耳鼻科/呼吸器の連携を検討 | 時間帯(夜間/運動後)と増悪条件 |
| 湿性嗄声/むせ増悪 | 食形態・水分戦略を再評価。精査へ連携 | 食後/会話後などのタイミング |
| 微熱・痰増加・呼吸苦 | 離床・運動負荷を下げる。医師へ報告 | SpO₂ 、咳嗽、痰の性状 |
| 体重減少・脱水徴候 | 栄養・水分の評価と連携を優先 | 摂取量、食事時間、疲労 |
再評価間隔と指標の束ね方
外来・病棟とも 4–8 週を目安に、 UMSARS( I・II・IV )、 SARA 、バランス指標、移動課題、歩行、起立試験、嚥下スクリーニングを同日に取得します。短期 KPI は転倒・誤嚥・ OH などのリスク、長期 KPI は QOL と介護負担に設定し、同一様式で連続可視化すると意思決定が安定します。
欠測が出る場合は、歩行距離・食事時間・介助量など代替アウトカムを並走し、「前回より悪いのか、測れなかったのか」を分けて残すのがポイントです。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
UMSARS と SARA / ICARS の使い分けは?
実務は UMSARS + SARA を同日に取得して「病勢 × 失調」の二軸で追います。 SARA は頻回再評価に向き、 ICARS は網羅性が高い一方で運用負荷が上がるため、詳細が必要な局面でのみ併用するのが現実的です。
MSA-P と MSA-C で評価は変えますか?
基本セットは同じですが、初回の優先順位が変わります。 MSA-P は動作破綻(開始・ターン)を先に、 MSA-C は OH ・嚥下を先に拾ってから機能へ進めると迷いが減ります。
起立性低血圧( OH )を“中止基準つき”で回すコツは?
臥位 5 分 → 立位 1 分・ 3 分で測定し、椅子と介助者を近傍に配置します。症状(前失神、気分不良)が強い日は、歩行系を後回しにして OH の観察と条件調整を優先します。
再評価間隔はどれくらいが良いですか?
外来・病棟とも、まずは 4–8 週で「同日バンドル」を回し、条件固定(内服、時間帯、補助具)を徹底します。変化が大きい局面では、より短い間隔で転倒/誤嚥/ OH に寄せたチェックを挟みます。
次の一手
- タイプ別の優先順位を整理する: MSA-P と MSA-C の違い【比較】評価の優先順位
- 失調領域をまとめて辿る: 運動失調ハブ
- 関連:鑑別の整理に使う: 脊髄小脳変性症( SCD )の評価まとめ
参考文献
- Wenning GK, et al. The Movement Disorder Society criteria for the diagnosis of multiple system atrophy. Mov Disord. 2022. doi: 10.1002/mds.29005(PubMed)
- Wenning GK, et al. Development and validation of the Unified Multiple System Atrophy Rating Scale ( UMSARS ). Mov Disord. 2004;19(12):1391-1402. doi: 10.1002/mds.20255(PubMed)
- Schmitz-Hübsch T, Tezenas du Montcel S, Baliko L, et al. Scale for the assessment and rating of ataxia: development of a new clinical scale. Neurology. 2006;66(11):1717-1720. doi: 10.1212/01.WNL.0000219042.60538.92(PubMed)
- Trouillas P, Takayanagi T, Hallett M, et al. International Cooperative Ataxia Rating Scale. J Neurol Sci. 1997;145(2):205-211. doi: 10.1016/S0022-510X(96)00231-6(PubMed)
- Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR, et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale ( MDS-UPDRS ): scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord. 2008;23(15):2129-2170. doi: 10.1002/mds.22340(PubMed)
- Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. Auton Neurosci. 2011;161(1-2):46-48. doi: 10.1016/j.autneu.2011.02.004(PubMed)
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下