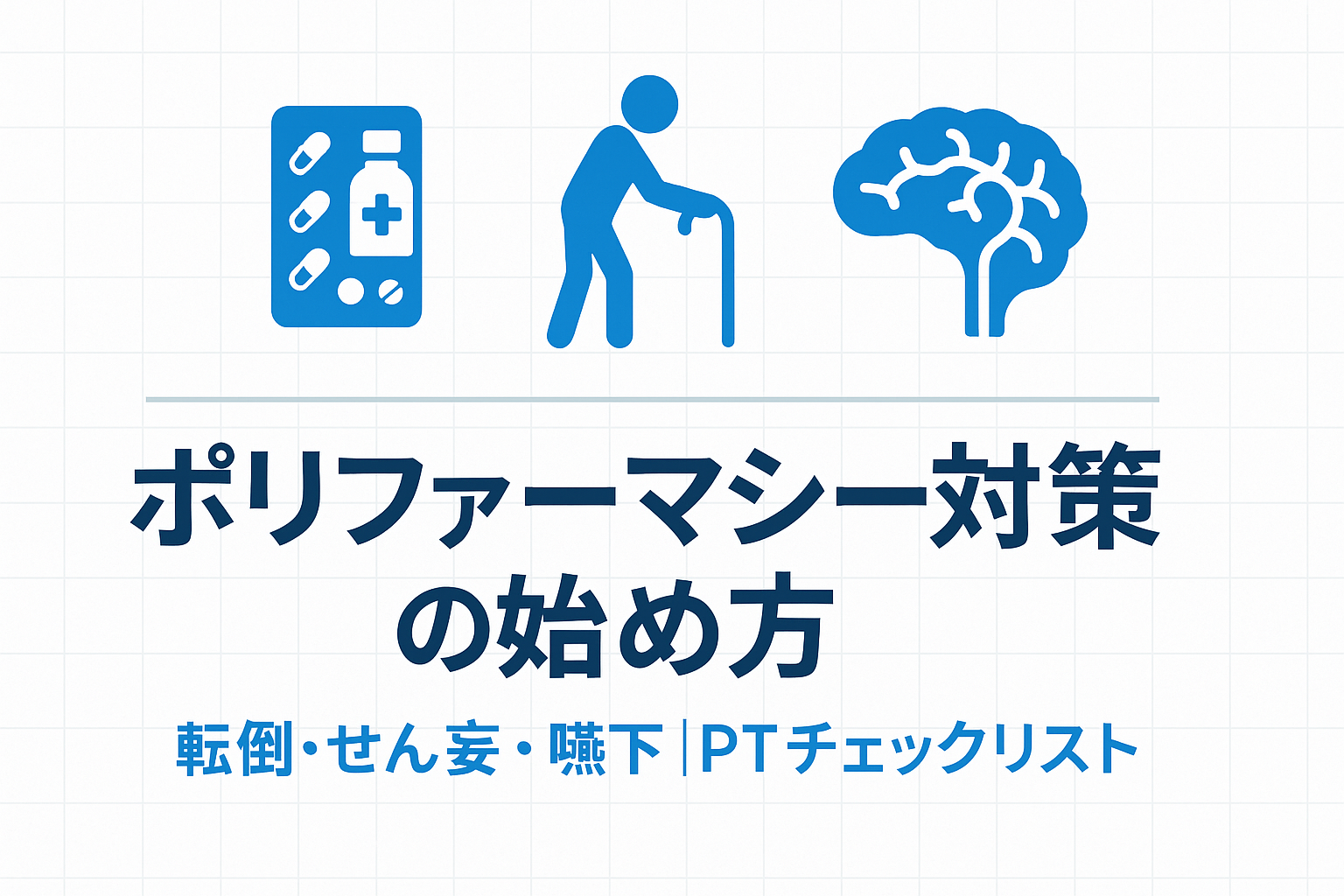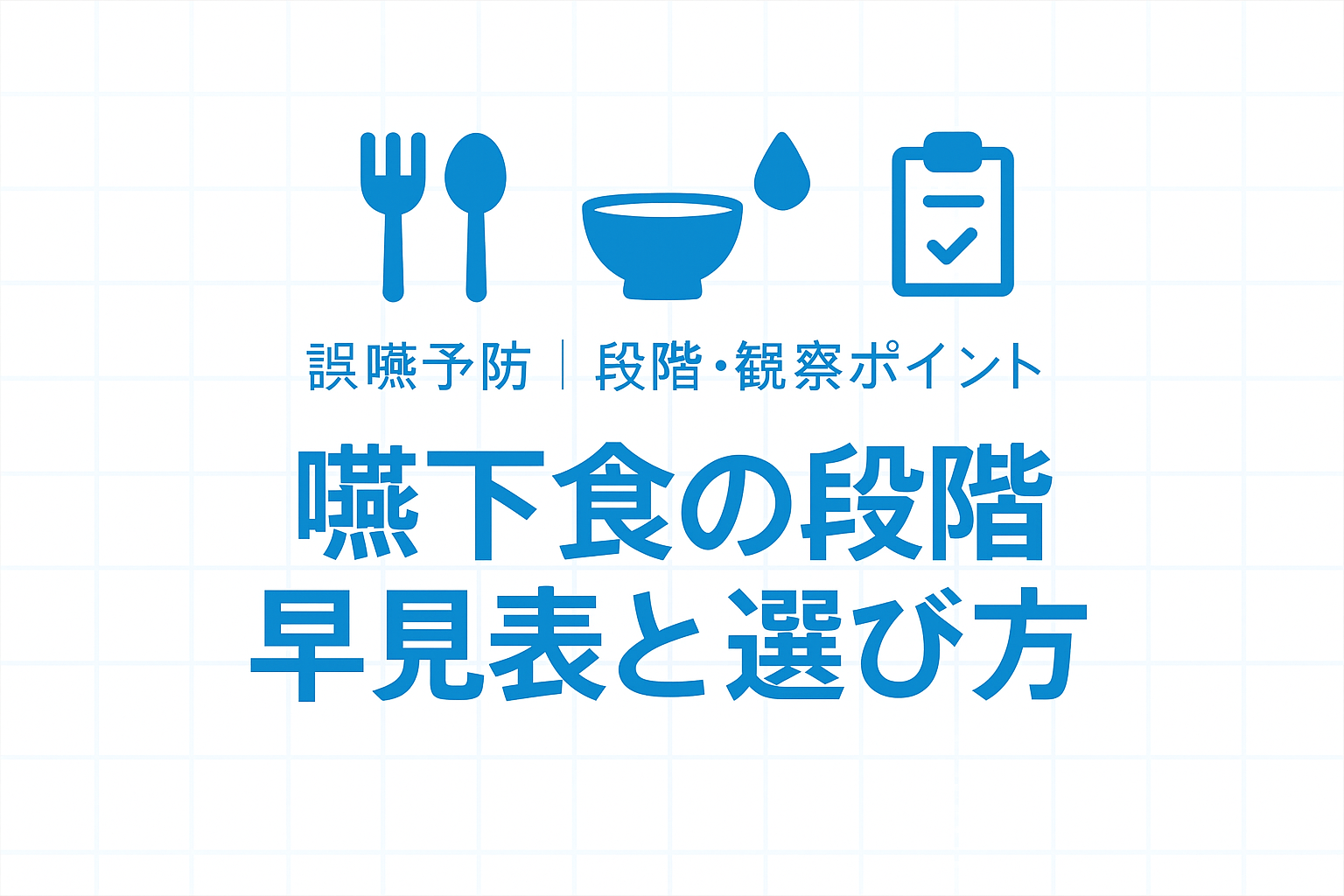ポリファーマシー対策チェックリスト( PT の実務版 )
ポリファーマシーは「薬が多いこと」そのものではなく、害(副作用・相互作用・アドヒアランス低下など)の可能性を含む状態を指します。厚生労働省の手引きでも、単なる薬剤数ではなく「有害事象の発生や服薬過誤につながる状況」を含めて捉える考え方が示されています。臨床の PT は、処方変更を直接行わなくても、薬剤起因性イベントを“早く拾って連携につなぐ”ことでアウトカムに貢献できます。
| 確認 | 見るポイント | 当てはまるときの次アクション |
|---|---|---|
| 薬剤数 | 目安として 5 剤以上/頓用・ OTC・サプリも含めて把握 | 「いつから増えたか」「増えた後に症状が出ていないか」を聴取し、記録へ |
| 転倒・ふらつき | 最近の転倒、立ちくらみ、歩行の不安定化、反応低下 | 起立性低血圧・鎮静の可能性を疑い、バイタルと経過をセットで共有 |
| せん妄・眠気 | 日内変動、注意散漫、夜間不穏、過鎮静、昼夜逆転 | 睡眠薬・抗不安薬・抗精神病薬などを念頭に、チームへ早期共有 |
| 排泄・嚥下 | 尿閉、便秘、口渇、嚥下低下、痰の増加 | 抗コリン作用や鎮静の影響を疑い、症状の時系列を整理 |
| 低血糖・脱水 | 冷汗、ふるえ、ぼーっとする/食事量低下・下痢・発熱 | 糖尿病薬・利尿薬などの影響を想定し、食事・水分とセットで共有 |
今日すぐ止めるべき「赤旗」(中止基準の目安)
医学的な中止判断は医師が行いますが、PT は「中止判断に必要な情報」を揃えられます。以下はその場で介入を一旦止めて共有すべきサインです。
- 明らかな過鎮静(呼名反応低下、意識レベル低下、呼吸抑制が疑われる)
- 新規のせん妄(急性発症・日内変動・注意障害)
- 症候性の起立性低血圧(立位でふらつき・眼前暗黒感・失神既往)
- 転倒後の状態変化(歩容の急変、認知の悪化、疼痛の急増)
- 低血糖が疑われる症状(冷汗、ふるえ、強い眠気、見当識低下)
薬剤クラス別:PT が拾いやすい「薬剤起因性イベント」
「薬名を暗記」より、症状 → 疑うクラス → SBAR で共有の順が実務的です。ここでは“よく当たる”パターンだけに絞ります。
| 臨床で見える変化 | 疑う薬剤クラス(例) | PT の観察・確認ポイント | 共有の要点 |
|---|---|---|---|
| ふらつき/転倒が増えた | 睡眠薬・抗不安薬( BZRA )、抗精神病薬、抗うつ薬、抗てんかん薬、オピオイド、降圧薬、利尿薬 | 転倒の時刻・状況、起立時症状、歩行時の注意低下、服薬タイミング | 「いつから」「何が増えた後に」起きたかを時系列で |
| せん妄/日内変動/不穏 | 抗コリン作用のある薬、 BZRA 、抗精神病薬、オピオイド など | 新規か、夜間優位か、便秘・尿閉・感染・脱水の併存 | 非薬物因子(便秘・尿閉・脱水)も一緒に |
| 立ちくらみ/失神 | 降圧薬(特に追加直後)、利尿薬、 α 遮断薬、硝酸薬 など | 臥位→座位→立位の血圧変化、症状の再現性、水分摂取 | 起立性低血圧の所見と、服薬変更の有無 |
| 尿閉/便秘/口渇 | 抗コリン作用のある薬、抗ヒスタミン薬、三環系抗うつ薬 など | 排尿・排便の頻度、腹部膨満、口渇、嚥下の変化 | 「排泄の変化 → 活動量低下」の連鎖で |
| 強い眠気/反応低下 | BZRA、鎮痛薬(オピオイド)、抗精神病薬、抗てんかん薬 など | 訓練中の覚醒レベル、注意の維持、呼吸状態 | 安全面(転倒・誤嚥・呼吸)を最優先に共有 |
持参薬確認 → 共有 → 介入 → 再評価:回るワークフロー
厚生労働省の「始め方と進め方」でも、持参薬の把握と情報共有、介入後の評価が一連の流れとして整理されています。PT は、症状の時系列と機能変化(歩行・注意・バイタル)を“同じシート”で残すと連携が通ります。
- 把握:処方薬+頓用+ OTC+サプリ(可能なら「いつ飲んだか」も)
- 拾い上げ:転倒・せん妄・低血圧・過鎮静・排泄・低血糖をスクリーニング
- 共有:SBAR で「変更後に起きたこと」を短く伝える
- 再評価:介入後 24〜72 時間で、同じ指標(例:起立時症状、ふらつき、眠気)を再チェック
SBAR:そのまま使える連携テンプレ(例文)
口頭でも記録でも、短く整えると通ります。
| 項目 | 書く内容(例) |
|---|---|
| S(状況) | 「昨日からふらつきが増え、立位で眼前暗黒感があります。転倒リスクが上がっています。」 |
| B(背景) | 「 3 日前に降圧薬が追加。服薬後の夕方に症状が出やすいです。水分摂取は少なめ。」 |
| A(評価) | 「臥位 → 立位で血圧低下と症状を再現。歩行中の注意低下もあります。」 |
| R(提案) | 「薬剤性の起立性低血圧の可能性があり、処方の確認と調整可否をご相談したいです。訓練は一旦負荷を下げます。」 |
現場の詰まりどころ/よくある失敗(ここで事故る)
- 薬剤数だけで判断する:数は“きっかけ”。害(転倒・せん妄・低血圧)をセットで拾う
- 症状の時系列が抜ける:「いつから」「何が変わった後に」を書かないと介入が進まない
- 頓用・ OTC・サプリが抜ける:睡眠薬の頓用、感冒薬、抗ヒスタミンなどが盲点
- 共有が長い:SBAR で 30 秒に圧縮すると通る
- 再評価がない:調整後に同じ観察項目で“戻ったか”を確認する
連携が詰まるときは、面談や情報整理の準備があるだけで進みます。必要なら 面談準備のチェックリスト(ダウンロード)で、状況整理の型を先に作っておくのも手です。
記録テンプレ(コピペで使える最小セット)
「持参薬の把握 → 症状 → 機能変化 → 共有内容」を 1 枚に収めます。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 薬剤(頓用・ OTC 含む) | 薬剤名/用量/回数/服薬タイミング(分かる範囲で) |
| 変化(いつから) | 〇月〇日から ふらつき増/昼間の眠気/夜間不穏 など |
| PT 所見 | 起立時症状、歩行中の注意、バイタル推移、転倒状況 |
| 共有( SBAR ) | S:…/B:…/A:…/R:… |
| 対応・再評価 | 負荷調整、見守り強化/ 24〜72 時間で同一項目を再チェック |
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1.何剤から「ポリファーマシー」と考えますか?
「 5 剤以上」を目安にすることは多いですが、重要なのは害が起きうる状態かどうかです。薬剤数だけで決めず、転倒・せん妄・低血圧・過鎮静・排泄トラブルなどの“イベント”とセットで判断し、時系列で共有すると介入が進みます。
Q2. PT が薬の話をしてもいいですか?
診断や処方変更を行うのではなく、訓練中に観察した変化(転倒、眠気、起立時症状など)を「いつから」「どの場面で」を整理して共有するのが役割です。SBAR で短く伝えるとチームで扱いやすくなります。
Q3.「薬剤性」をどう見分けますか?
鍵は時系列です。「薬が増えた/減った/用法が変わった」後に症状が出たか、頓用や OTC を使った日と一致するかを確認します。非薬物因子(脱水・便秘・感染・睡眠不足)も併存しやすいので、まとめて共有します。
Q4.睡眠薬( BZRA )はなぜ要注意ですか?
高齢者では転倒などの害と関連しやすく、減薬( taper )を支援するガイドラインも整備されています。眠気・注意低下・反応遅延がある場合は、服薬タイミングと症状をセットで共有してください。
次の一手(迷ったらここから)
- まずは「表 1」の 60 秒チェックを回し、時系列とSBARで共有する
- 転倒が絡む症例は、施設の転倒プロトコル(標準手順)と合わせて運用する
- 薬剤リスク全体を束ねるページ(ハブ)を作り、関連テーマを 1 カ所に集約する
参考文献
- 厚生労働省.病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(令和 6 年 7 月 22 日).https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41542.html
- American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023. doi: 10.1111/jgs.18372
- O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing. 2015;44(2):213-218. doi: 10.1093/ageing/afu145(PubMed: 25324330)
- Pottie K, et al. Deprescribing benzodiazepine receptor agonists: Evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician. 2018.(PMC: PMC5951648)
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下