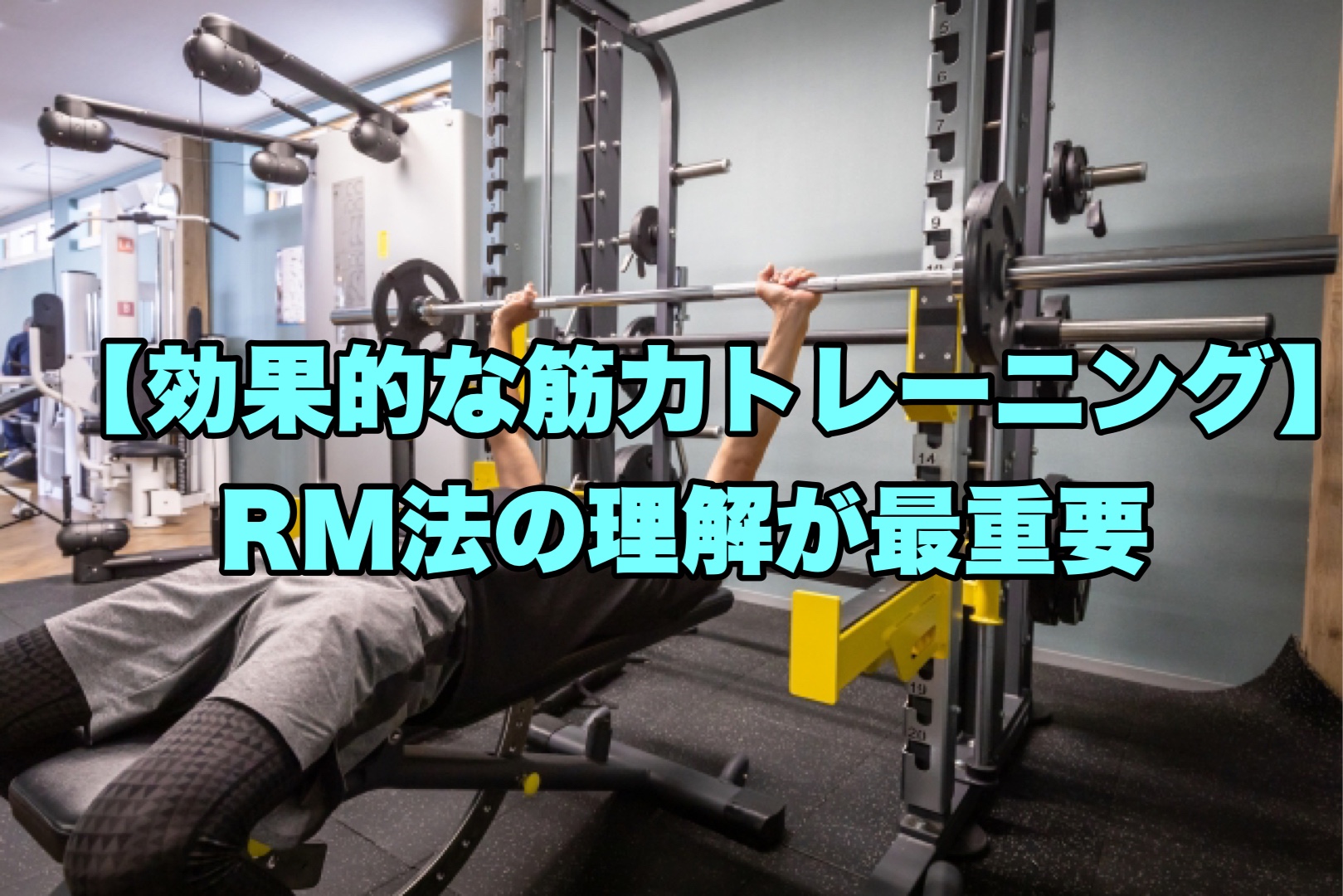理学療法士が解説する筋力トレーニングの方法(まず結論)
臨床で迷わない「評価 → 介入 → 再評価」の型を見る( PT キャリアガイド )
筋力トレーニングは「目的(筋力/筋肥大/筋持久力)に合わせて、強度・回数・セット・休息・頻度をそろえる」だけで、成果と安全性が一気に上がります。やり方を曖昧なまま回数だけ増やすより、まずは 負荷設定のルール と フォームの共通原則 を決めて、記録しながら微調整するのが近道です。
本記事では、臨床で再現しやすい形に落とし込み、① 5 分で組む流れ → ② 負荷設定( RPE/ RM )→ ③ 例メニュー → ④ よくある失敗と修正の順で整理します。原理・原則を深掘りしたい場合は、筋力トレーニングの 3 原理・ 6 原則も合わせて読むと、説明と指導がブレにくくなります。
まずは 5 分フロー(負荷設定 → 実施 → 記録 → 再調整)
現場で迷いが減る最短手順は、目的の決定 → 目標回数帯の設定 → RPE(または RM )で重さ調整 → 実施 → 記録 → 次回の微調整です。とくに「どれくらい頑張ったか」を共通言語にできる RPE は、外来・病棟・在宅のどこでも運用しやすい指標です。
流れを固定すると、患者さん側も「今日はここまで」「次はこれを伸ばす」が理解でき、継続率が上がります。逆に、強度や回数が毎回バラつくと、疲労だけが溜まりやすく、痛みや中断につながりがちです。
目的別に「回数帯」と「休息」を先に決める
筋トレの設計は、最初に 回数帯( rep range ) を決めると簡単になります。筋力なら「低回数・高強度」、筋肥大なら「中回数・中〜高強度」、筋持久力なら「高回数・低〜中強度」が基本です。休息は、筋力ほど長め、持久力ほど短めが目安になります。
ただし臨床では「疼痛」「循環器リスク」「筋痙縮」「易疲労」などの制約が入るため、理論どおりにいかない場面もあります。その場合は、回数帯を無理に守るより RPE とフォームの質 を優先し、安全に続けられる設定へ寄せます。
| 目的 | 目標回数 | 強度の目安 | 休息 | 主観強度 |
|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 1〜 6 回 | 高強度(高負荷) | 2〜 5 分 | RPE 8〜 10 |
| 筋肥大 | 6〜 12 回 | 中〜高強度 | 1〜 3 分 | RPE 7〜 9 |
| 筋持久力 | 12〜 20 回 | 低〜中強度 | 30〜 90 秒 | RPE 6〜 8 |
強度設定は RPE が最も実用的( 1 RM が測れない場面でも OK )
臨床では 1 RM( 1 回だけ挙がる最大重量) を正確に測れない場面が多いため、実務では RPE(主観的運動強度) が扱いやすいです。目標回数帯で実施し、最後の 1〜 3 回が「かなりきつい」程度( RPE 7〜 9 )になる重さに調整すると、負荷が安定します。
「軽すぎる」「重すぎる」を避けるコツは、同じ種目・同じフォーム で記録を残すことです。重量(またはバンド強度)・回数・セット数・RPE を 1 行で書くだけでも、翌週に「重量を少し増やす/回数を 1〜 2 回増やす/休息を調整する」の判断がしやすくなります。
頻度とボリュームの基本(週 2〜 3 回から始める)
初心者や低体力の方は、まず 週 2 回 からで十分です。全身をまんべんなく刺激し、フォームが安定してきたら週 3 回へ増やすと、疲労のコントロールがしやすいです。忙しい外来や訪問でも、週 2 回を固定できると継続率が上がります。
ボリューム(総負荷量)は「セット数」で管理すると簡単です。大筋群(下肢・体幹・押す/引く)を 1 種目 2〜 3 セットから開始し、痛みや疲労が少なければ 1 セットずつ増やします。増やす順番は、重量より先に フォームの質 → セット数 → 重量が安全です。
初心者向け:全身メニュー例(器具が少ない環境でも)
まずは「しゃがむ」「立つ」「押す」「引く」「体幹を固める」をそろえると、生活動作につながりやすいです。特定の筋だけを狙うより、複合動作を中心にすると効率が良く、指導も簡単になります。
下のメニューは、痛みやリスクがある場合に調整しやすいよう、負荷を段階化できる種目を選んでいます。最初の 2 週間は「できた体験」を優先し、 RPE 6〜 7(余力あり)でフォームを固めるのがおすすめです。
| 分類 | 種目例 | 回数 × セット | RPE | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 下肢(しゃがむ) | 椅子立ち上がり/スクワット(浅め) | 8〜 12 回 × 2 セット | 6〜 8 | 膝が内側に入らない/体幹を保つ |
| 股関節(ヒンジ) | ヒップヒンジ/軽いデッドリフト動作 | 6〜 10 回 × 2 セット | 6〜 8 | 背中を丸めない/股関節主導 |
| 押す | 壁腕立て/ダンベルプレス/チューブプレス | 8〜 12 回 × 2 セット | 6〜 8 | 肩をすくめない/可動域は痛みのない範囲 |
| 引く | チューブロー/シーテッドロー | 8〜 12 回 × 2 セット | 6〜 8 | 肩甲骨を寄せる意識/首を詰めない |
| 体幹(固める) | ブレーシング/プランク(短時間) | 10〜 20 秒 × 2〜 3 回 | 5〜 7 | 呼吸を止めない/腰を反らしすぎない |
フォームと安全管理(痛み・息切れ・血圧変動のサインを見る)
筋トレで最も多い失敗は「重さを上げることが目的化してフォームが崩れる」ことです。フォームが崩れたまま続けると、狙った筋に刺激が入らず、関節痛や代償が増えます。まずは 可動域を小さくしても良いので、軸(体幹)と関節アライメントを守ることが大切です。
安全管理では、循環器症状や疼痛増悪の見逃しを避けます。特に息こらえ(過度なバルサルバ)で血圧が上がりやすいため、「吐きながら力を出す」を合言葉にし、症状が出る場合は負荷・回数・休息を調整します。
| 状況 | OK の目安 | いったん中止・調整 | 受診・医療相談を検討 |
|---|---|---|---|
| 痛み | 違和感〜軽い痛みで、翌日に悪化しない | 鋭い痛み/フォームが保てない痛み | 安静時痛/夜間痛/しびれ増悪 |
| 呼吸・循環 | 会話ができる範囲の息切れ | めまい/冷汗/強い息苦しさ | 胸痛/失神/動悸の強い増悪 |
| 疲労 | 翌日に回復し、次回も実施できる | 倦怠感が 48 時間以上続く | 日常生活が保てないレベルの疲労 |
負荷の上げ方(停滞を作らない「小さな進歩」)
負荷の進め方は「毎回増やす」より、 2〜 4 週単位で小さく上げるほうが安全です。方法は 3 つで、① 回数を 1〜 2 回増やす、② セットを 1 セット増やす、③ 重量を少し増やす、の順に優先します。痛みや疲労が出やすい場合は、重量を上げる前に回数やセットで調整します。
停滞したときは「頑張りが足りない」ではなく、睡眠・栄養・回復の影響を疑います。週 1 回だけでも、前回より 1 回多くできた/フォームが良くなった、という“質の進歩”を記録すると、継続が途切れにくくなります。
現場の詰まりどころ:よくある失敗と対策
筋トレが続かない主因は「きつすぎる」「痛くなる」「成果が見えない」の 3 つです。ここを先回りして潰すには、① 最初は余力を残す( RPE 6〜 7 から)、② 痛みが出たら可動域と種目を変える、③ 記録で成果を見える化する、の 3 点が効きます。
特に「フォームを意識しすぎて動けない」方もいます。その場合は、まずは 安全な範囲で回数をこなすことを優先し、後からポイントを 1 つずつ足すと学習が進みます。
| 失敗 | 起こりやすい原因 | 修正のコツ | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 軽すぎて効かない | 「安全」を優先しすぎる/回数だけ増やす | 目標回数帯で RPE 7〜 9 を狙う | 重量・回数・ RPE を 1 行で残す |
| 重すぎて痛くなる | フォームより重量を優先 | 可動域を小さくする/種目変更(分解) | 痛みの部位・タイミング(当日/翌日) |
| 疲労が抜けない | 頻度・セットが多い/休息が短い | 週 2 回へ戻す/セットを 1 減らす | 翌日の倦怠感・睡眠・歩数 |
| 継続できない | メニューが複雑/時間が長い | 種目を 4〜 5 つに絞る/ 20 分で終える | 実施日だけ丸をつける(達成ログ) |
リハでの記録のコツ(短く、比較できる形にする)
記録は長文よりも、後から比較できる形式が有効です。おすすめは「種目/重量(またはチューブ)/回数×セット/ RPE /痛み」の 5 つだけです。これだけで「次回は回数を 1 回増やす」「休息を 30 秒伸ばす」などの判断ができます。
また、患者さんの自己管理には「自宅実施のチェック欄」を付けると継続しやすいです。紙でもスマホでも良いので、実施できた日を見える化し、成功体験を積み上げる設計にします。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
筋トレは週何回が一番いいですか?
多くの方は、まず 週 2 回からで十分です。週 2 回を安定して回せるようになり、疲労や痛みの問題がなければ週 3 回へ増やします。大切なのは「毎週続く頻度」に合わせて、負荷と量を調整することです。
毎回「限界まで( failure )」やった方が早く伸びますか?
初心者や痛みが出やすい方は、毎回の failure は疲労が強く出やすく、継続を阻害することがあります。まずは RPE 7〜 9(限界の少し手前)を目安にし、フォームが安定してから、必要に応じて一部のセットで追い込むのが無難です。
筋肉痛が強い日は休んだ方がいいですか?
強い筋肉痛( DOMS )がある日は、無理に同じ部位を高負荷で行わず、可動域を小さくした軽い運動や、別部位のトレーニングに切り替えるのがおすすめです。痛みが関節由来に変わっている場合は、種目・フォームの見直しを優先します。
高齢者でも筋肥大や筋力向上は狙えますか?
高齢者でも、適切な負荷設定と継続ができれば、筋力や筋量の改善は十分に狙えます。最初は安全第一で RPE 6〜 7から始め、フォームが安定したら少しずつ負荷を上げる設計が現実的です。
おわりに
筋トレは「安全の確保 → 目的の回数帯を決める → RPE で負荷をそろえる → 記録して微調整 → 再評価」というリズムを作ると、成果が再現しやすくなります。面談準備チェックと職場評価シートで学びの環境も整えたい方は、こちらからまとめて確認できます。
参考文献
- American College of Sports Medicine. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687-708. doi:10.1249/MSS.0b013e3181915670
- Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. J Strength Cond Res. 2010;24(10):2857-2872. doi:10.1519/JSC.0b013e3181e840f3
- Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2016;46(11):1689-1697. doi:10.1007/s40279-016-0543-8
- Grgic J, Schoenfeld BJ. Are the Hypertrophic and Strength Benefits of Resistance Training to Failure Supported by Evidence? J Sport Health Sci. 2022;11(1):30-34. doi:10.1016/j.jshs.2021.01.007
- Rhea MR, Alvar BA, Burkett LN, Ball SD. A meta-analysis to determine the dose response for strength development. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(3):456-464. doi:10.1249/01.MSS.0000053727.63505.D4
- Peterson MD, Rhea MR, Sen A, Gordon PM. Resistance exercise for muscular strength in older adults: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2010;9(3):226-237. doi:10.1016/j.arr.2010.03.004
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下