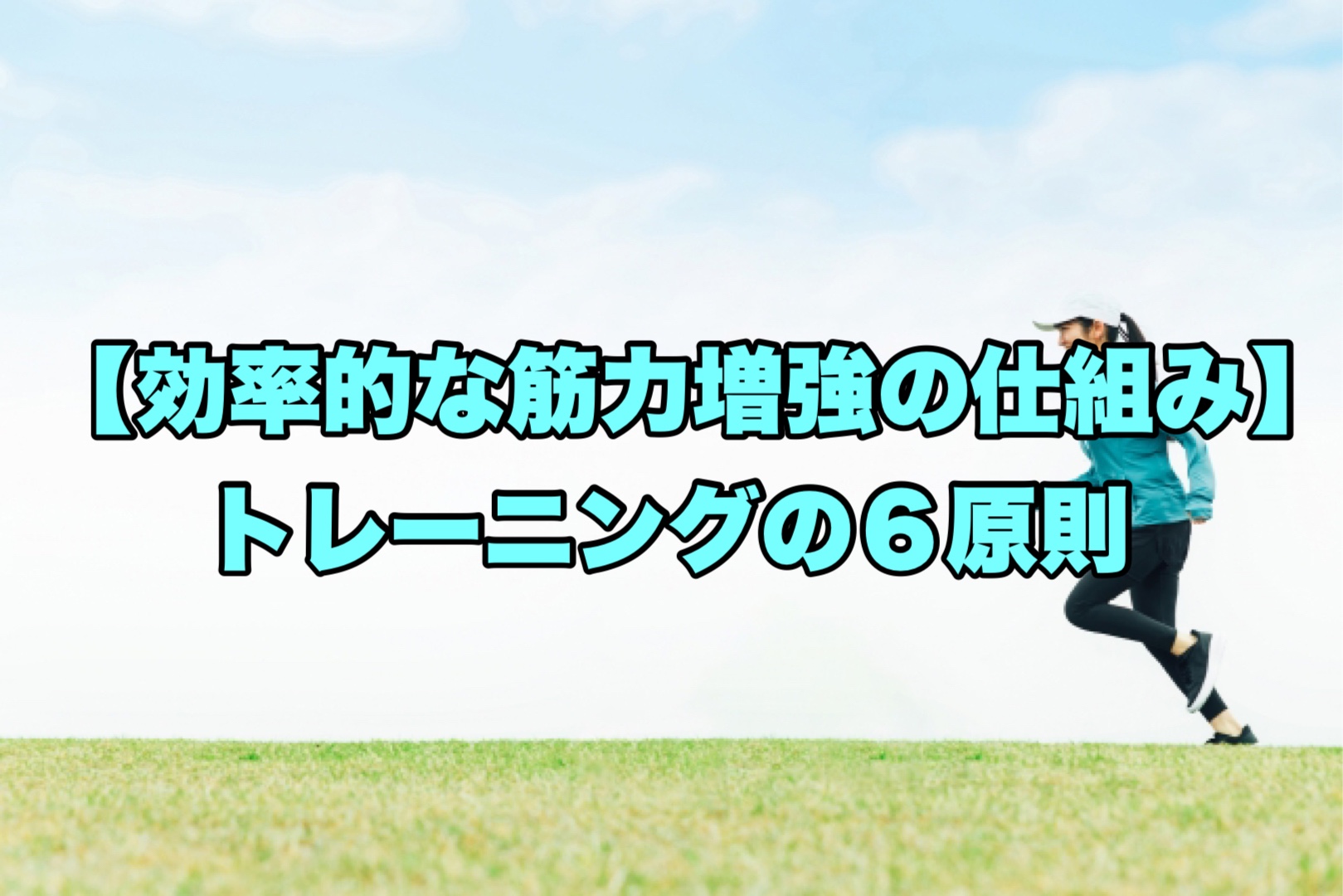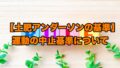筋トレの 3 原理・ 6 原則(過負荷/特異性/可逆性)|臨床で “迷わず回す” ための実践ガイド
筋トレの効果は「頑張ったかどうか」ではなく、狙い(目的)に合った刺激を、無理なく継続できる形で積み上げられたかで決まります。本記事では、トレーニングの基本である 3 原理(過負荷・特異性・可逆性)と 6 原則(漸進性/反復・周期性/個別性/意識性/全面性/継続性)を、臨床で説明・設計・修正できる形に落とし込みます。
読後は、患者さん(利用者さん)に「なぜこの強度・回数なのか」を言語化でき、記録から次回の調整(漸進)まで一貫して回せるようになります。まずは 1 種目・週 2 回・ 4 週間の小さな設計から始めましょう。
結論: 3 原理は “方向” 、 6 原則は “運用” を決める
3 原理は「何を守れば効果が出るか」という方向性、 6 原則は「現場でどう回して継続させるか」という運用ルールです。臨床では、まず 安全の確保 → 目的を 1 つに絞る → 変える変数を 1 つに絞るの順に整えると、迷いが減ります。
とくに “漸進性” は「重くする」だけではありません。痛み・恐怖感・疲労が課題なら、重量よりも 反復・セット・レスト・頻度を先に調整して、続けられる形で過負荷を作るのがコツです。
トレーニングの 3 原理(過負荷・特異性・可逆性)
成果の土台はこの 3 つです。過負荷 は「現状より少しだけ高い刺激」で適応を引き出す原理、特異性 は「鍛えた能力が伸びる」ため目的動作・筋群・エネルギー系に似せる発想、可逆性 は「やめれば戻る」ため “細く長く続く仕組み” が最重要という考え方です。
| 原理 | 定義 | 臨床メモ(説明のコツ) |
|---|---|---|
| 過負荷 | 現状能力を “わずかに” 超える刺激で適応を促す | 「昨日より少しだけ」/やり過ぎは逆効果。痛みやフォーム破綻が出たら調整 |
| 特異性 | 刺激した能力が向上する(動作・筋群・エネルギー系の一致) | 目的動作に “似せる” ほど効果が出やすい(立ち上がりなら股関節・膝伸展を狙う) |
| 可逆性 | 刺激を中断すると効果は減弱・消失する | 「続ける仕組み(予定・記録・同伴者)」が成果の差を作る |
トレーニングの 6 原則(実装のコツ)
6 原則は、現場で “続く形” に落とすための運用ルールです。ポイントは 増やす変数は 1 回に 1 つだけ。重量・反復・セット・レスト・頻度のどれを動かすかを決め、効果(できるようになったこと)と疲労(翌日以降の反応)を観察します。
| 原則 | 要点 | 実装ヒント |
|---|---|---|
| 漸進性 | 負荷を少しずつ上げる | 2–5 % の小刻み増量、または +1 セット/反復 +1 など “小さく” 進める |
| 反復・周期性 | 刺激と回復の設計 | 部位あたり 週 2–3 回 を目安。疲労が強い週はボリュームを下げる |
| 個別性 | 年齢・既往・体力に合わせる | 同じ重量でも感じ方は違う → RPE を共通言語にする |
| 意識性 | 狙いを明確にする | 毎セット「どこに効かせたいか」を 1 言で言語化 |
| 全面性 | 全身バランスを整える | 押す・引く・股関節・膝関節・体幹を網羅(偏りを作らない) |
| 継続性 | 続ける仕組み | 短時間ルーティン/記録/リマインド/家族の巻き込みで中断を防ぐ |
強度 × 回数 × セット × 頻度の設計( RPE ・ % 1RM の考え方)
臨床では、 % 1RM を正確に測れない場面が多いため、まずは RPE(自覚的運動強度)で “きつさ” を揃えるのが現実的です。フォームが安定してきたら、RPE を 6 → 7 → 8 と段階的に上げることで、過負荷と漸進性を同時に満たせます。
迷ったら 2-for-2 ルール(目標回数を 2 回以上上回る状態が 2 セッション続いたら、次回は 2–5 % 増量 or +1 セット)をチームの共通ルールにすると、調整が標準化しやすくなります。具体的な負荷設定( RPE )の型は、下の記事にまとめています。
高齢者・内科合併での安全運用( “強度より先に” 揃えるもの)
高齢者や循環器・呼吸器の合併がある場合は、強度を急がず フォーム優先 → 反応観察 → 微調整が基本です。開始は RPE 5–7 を目安に、週 2 回から。めまい・胸痛・会話困難・動悸・不整脈感・鋭い痛みが出たら中止し、症状と条件(体位・時間帯・補装具・介助量)をセットで記録します。
“負荷を上げる” よりも、まずは ボリューム(セット数)・休息・頻度の微調整で過負荷を作ると、安全に継続しやすくなります。
現場の詰まりどころ(よくある失敗 → 直し方)
| よくある失敗 | 起こりやすい背景 | 直し方(次回の一手) |
|---|---|---|
| 軽すぎる負荷のまま数か月続く | フォーム不安/痛みが怖い/ “安全側” に寄りすぎる | フォームが安定したら “卒業ライン” を決め、RPE を 1 段階だけ上げる |
| 漸進性が感覚任せ | 増量のルールがない/記録が残らない | 2-for-2 ルールなど “トリガー” を決め、変える変数は 1 つに固定 |
| 強度だけを急に上げて中断 | 短期で結果を求める/疲労・痛みの見立て不足 | 強度より先に、セット・レスト・頻度で微調整して “続く形” を作る |
| 特異性がずれて効果が出ない | 目的動作と種目が一致していない | 目的(例:立ち上がり)→必要要素(股関節伸展・膝伸展)→種目の順に組み直す |
今日から使えるチェックリスト( 5 分で自己点検)
| チェック項目 | OK の目安 | NG のサイン |
|---|---|---|
| 目的は 1 つに絞れている | 筋力/筋肥大/筋持久のいずれかが明確 | “全部やる” になって設計がブレる |
| 増やす変数は 1 つだけ | 重量 or 反復 or セット or レストのどれか 1 つ | 同時にいじって原因が分からない |
| RPE とフォームを言語化 | 毎セット「きつさ」と「効かせたい場所」を共有 | “なんとなく” 実施で再現性が落ちる |
| 反応をセットで記録 | 症状・疲労・条件(体位など)を一緒に残す | 次回の調整材料がない |
| 再評価のタイミングが決まっている | 2〜 4 週間で見直す(小さく回す) | やりっぱなしになりやすい |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
週何回が効率的?セット数はどれくらい?
扱いやすい目安は、部位あたり 週 2–3 回です。ボリュームは “部位あたり 週 10–20 セット” を起点に、疲労や疼痛反応を見ながら個別に調整します。疲労が強い週はボリュームを 20–40 % 下げる “デロード” も有効です。
重量が伸びない時は何を変える?
いきなり重量を上げず、(1)総セット数(+ 1 セット)→(2)レスト延長→(3)種目の入替(同パターンで負荷が乗る種目へ)→(4)頻度の見直しの順に検討すると、安全に漸進しやすくなります。
高血圧や循環器の既往がある場合の注意点は?
RPE 5–7 から開始し、息こらえ(バルサルバ)を避けて呼吸を統制します。胸痛・息切れ・めまい・動悸などが出たら中止し、症状と条件を記録して主治医と共有してください。
おわりに
筋トレの原理原則をおさえると、「安全の確保 → 適切な刺激設定 → 記録とフィードバック → 再評価」という臨床のリズムが整い、患者さんにとっても “狙いが分かる筋トレ” に変えていけます。まずは 1 種目・週 2 回・ 4 週間の小さな設計から始め、再評価で次の 1 手(変数 1 つ)を決めていきましょう。
面談準備チェックと職場評価シートも使えるようにしておくと、学び直しの計画が立てやすくなります:/mynavi-medical/#download
参考文献
- Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. J Strength Cond Res. 2010;24(10):2857–2872. doi:10.1519/JSC.0b013e3181e840f3
- American College of Sports Medicine. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687–708. doi:10.1249/MSS.0b013e3181915670
- Garber CE, et al. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining fitness. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334–1359. doi:10.1249/MSS.0b013e318213fefb
- Fragala MS, et al. Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. J Strength Cond Res. 2019;33(8):2019–2052. doi:10.1519/JSC.0000000000003230
- Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. PubMed
- Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451–1462. PubMed
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下