 神経筋疾患
神経筋疾患 【ALSの重症度分類】障害度を5段階で評価【ALS評価スケール】
ALS の重症度を評価する方法はいくつかありますが、本邦においては神経変性疾患領域における基盤的調査研究班(厚生労働省)による「ALS 重症度分類」が主に使用されています。「ALS 重症度分類」について解説します。
 神経筋疾患
神経筋疾患 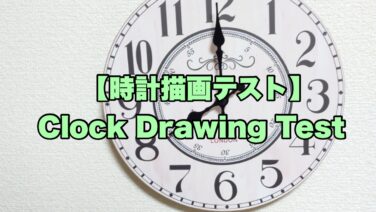 認知・精神機能
認知・精神機能 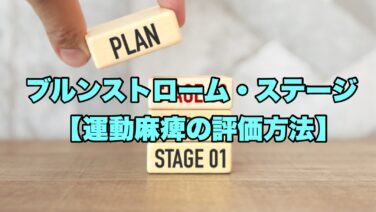 脳卒中
脳卒中 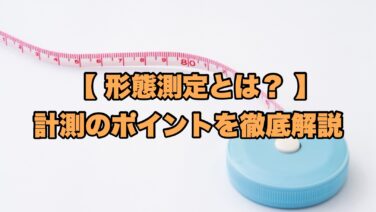 基礎的評価
基礎的評価 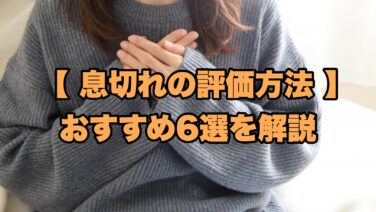 呼吸器系
呼吸器系 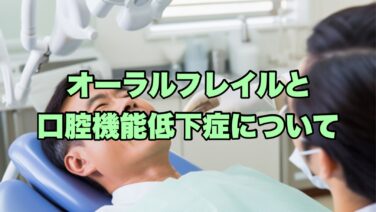 摂食・嚥下
摂食・嚥下  認知・精神機能
認知・精神機能 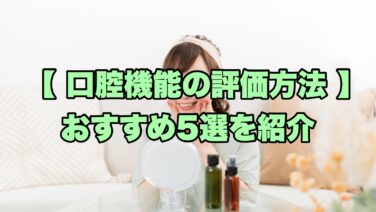 摂食・嚥下
摂食・嚥下 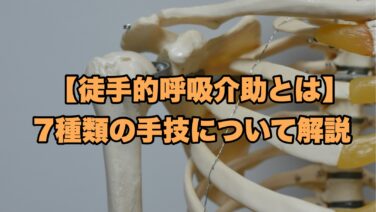 呼吸器系
呼吸器系  基礎的評価
基礎的評価