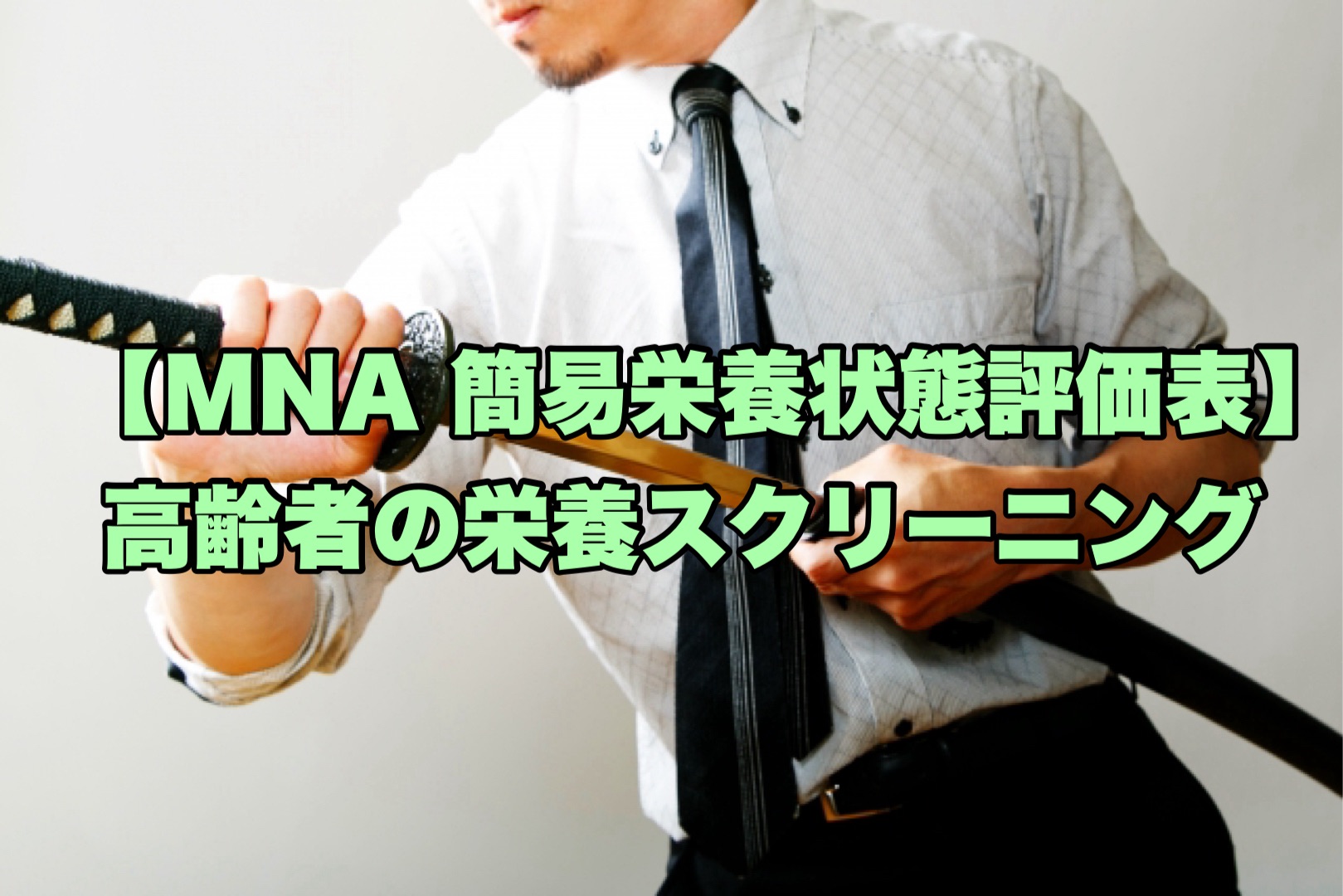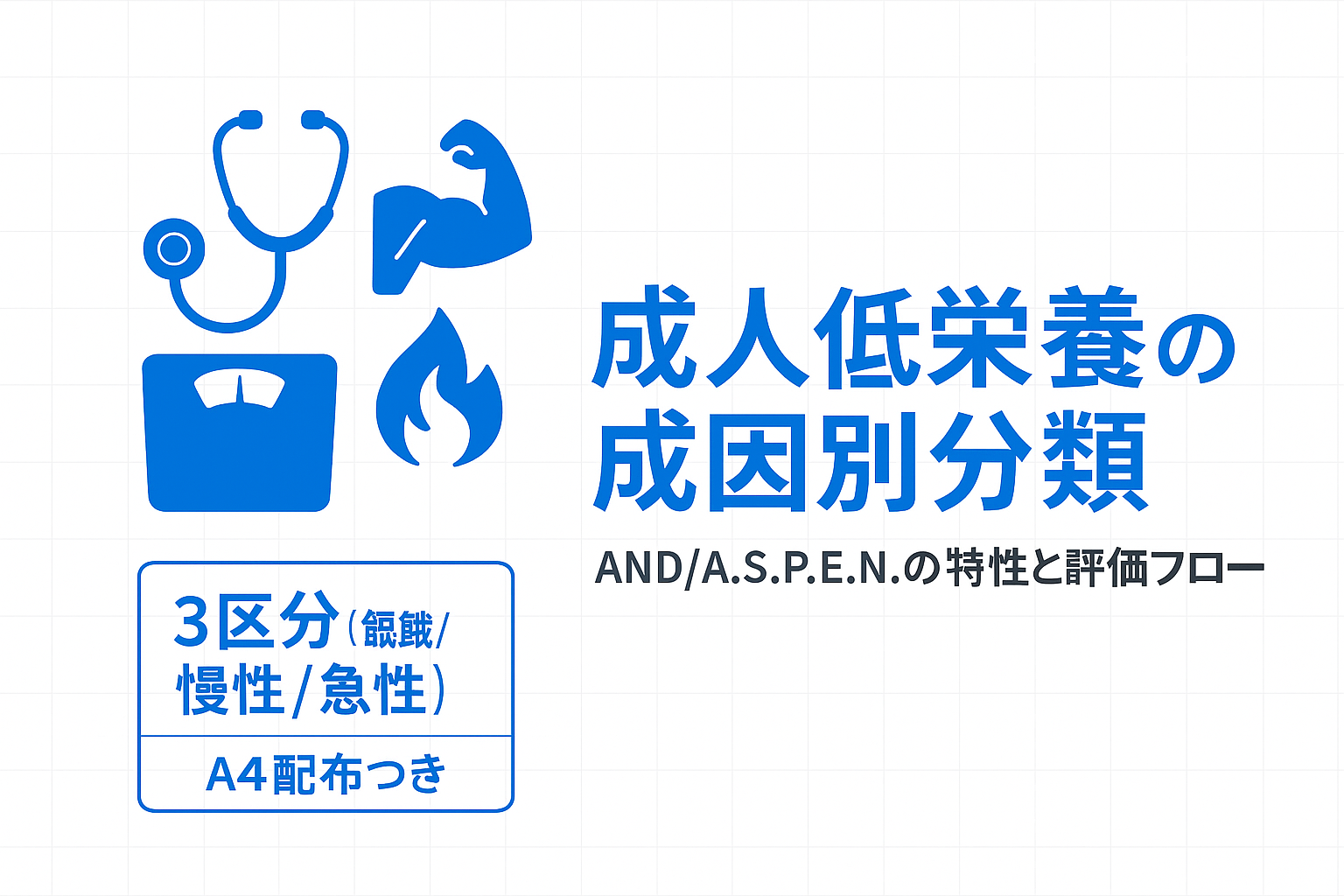MNA(本式)とは?(この記事でわかること)
栄養評価を「点数で終わらせず」、介入まで一直線につなげる。 臨床で役立つ評価と介入の流れを復習する
本記事は MNA(本式) 0–30 点の使い方に特化します。実務は「① MNA-SF で一次判定 → ② 8–11 点は本式 MNA で精査 → ③ 本式のカットオフ( ≥ 24 / 17–23.5 / < 17 )で対応決定」の流れが最短です。
以降では、 18 項目それぞれの趣旨/判定の考え方/観察ポイント/臨床目安を “原文を引用せず” に整理しました。スコアリングの細目は公式表に従い、本文では解釈と運用のコツに絞ります。関連:MNA-SF(短縮版)の使い方
MNA(本式)の使い方| 6 ステップ
- 対象と準備:主に 65 歳以上。直近体重・身長(または推定)・既往・服薬・嚥下状況・食事形態を確認します。
- 一次判定:一次は短縮版で判定します。8–11 点なら本式を実施( 12–14 点は概ね経過観察/ 0–7 点は速やかに対処)。
- 本式の実施:設問順に採点(合計 0–30 点)。問診が難しい場合は家族/介護者情報を補助にします。
- 合計と分類:≥ 24 正常/ 17–23.5 低栄養リスク/ < 17 低栄養。
- 対応決定:食事量・間食・補助食品・口腔/嚥下・活動量・疾患管理・多職種連携へ展開します。
- 再評価:入院 1–2 週、在宅/外来 2–4 週を目安に、同一条件で追跡します。
判定・対応の早見(本式 MNA)
(スマホは横スクロール可)
| 合計点( 0–30 ) | 分類 | 初期対応の例 |
|---|---|---|
| ≥ 24 | 正常 | 経過観察、食事の質・多様性の確保、活動量維持、再評価時期設定 |
| 17–23.5 | 低栄養リスク | 摂取量の把握(主食/主菜/副菜/間食)、栄養補助食品、嚥下・口腔ケア、 2–4 週で再評価 |
| < 17 | 低栄養 | 原因評価(炎症/嚥下/抑うつ/社会要因)、多職種連携、補助栄養の積極導入、短期で再評価 |
現場の詰まりどころ|よくある失敗と対策
MNA(本式)は “点数を付けること” 自体より、測定条件・聞き取り条件のズレで結果がブレやすいのが落とし穴です。再評価で差が出るほど、介入の効果判定が難しくなるため、最初に “条件の固定” をしておくと運用が安定します。
| よくある失敗 | 起きる理由 | 対策(記録ポイント) |
|---|---|---|
| 体重変化の “期間” が混ざる | 入院前後で測定条件や参照期間が変わる | 「いつからいつまで」を固定して明記。測定条件(衣類/時間帯/車椅子)もセットで記録。 |
| 身長が推定でバラつき BMI が動く | 高齢者は身長測定が困難 | 推定法(過去身長/膝高など)を統一し、 “推定” と明記。次回も同法で追跡。 |
| 周囲径が浮腫で過大評価される | 下腿浮腫や左右差の影響 | 左右・浮腫の有無・測定肢位を併記。メジャー位置(最大周径部など)も固定する。 |
| 問診が本人の主観だけで偏る | 認知・抑うつ・失語などで情報が不十分 | 家族/介護者情報で補完。客観情報(摂取割合、配食、買い物頻度)も併記する。 |
18 項目の “趣旨・判定の考え方・観察ポイント・臨床目安”
原文の設問文は掲載しません。以下は解釈と運用のガイドです(★は短縮版と重複しやすい観点)。
| 区分 | 項目(略称) | 趣旨 | 判定の考え方(要約) | 観察ポイント/臨床目安 |
|---|---|---|---|---|
| A 人体計測 | 過去 3 か月の食事量変化 ★ | 摂取低下の有無・程度を把握 | 持続的な摂取低下は栄養リスク増大 | 原因(嚥下・疼痛・消化器症状)を併記。 “いつから” を記録し、再評価で比較可能に。 |
| A | 体重変化 ★ | 非意図的体重減少の把握 | 短期間の有意な減少は栄養障害の指標 | 3 か月で約 3 kg 以上の減少は要注意。体重の測定条件(時間帯・衣類)を統一。 |
| A | BMI ★ | 低体重/やせの把握 | BMI 低下は合併症・予後と関連 | 高齢では BMI < 20 前後は注意、< 18.5 はリスク高(施設基準に準拠)。 |
| A | 上腕周囲径(MAC) | 筋量の簡便指標 | 低いほど筋量不足の疑い | MAC < 約 21 cm はやせ傾向の目安。利き腕/浮腫の有無を記載。 |
| A | ふくらはぎ周囲径(CC) ★ | 下肢筋量・サルコペニアの示唆 | 一定未満で筋量不足疑い | CC < 31 cm は低値の目安。左右差・浮腫の影響に注意。 |
| B 全身状況 | 移動能力 ★ | 活動量・自立度の推定 | 外出可 > 屋内のみ > ベッド/椅子の順にリスク上昇 | 歩行補助具、転倒歴、離床時間を併記。 |
| B | 心理的ストレス/急性疾患( 3 か月) ★ | 代謝亢進・摂食不良の誘因 | 最近の発熱/感染/入院/喪失体験はリスク | 発症日・治療内容・発熱期間を記録し、摂取低下の時系列とセットで残す。 |
| B | 認知・抑うつ ★ | 摂食・自己管理への影響 | 軽度~重度でリスク増 | 既存評価(HDS-R、GDS 等)の結果を参照し、見当識/興味低下を観察。 |
| B | 生活の自立度 | 生活環境による摂食機会の変動 | 完全自立 > 一部介助 > 施設依存でリスク増 | 買い物/調理/配食の有無、食事の同席者数、欠食の頻度を記録。 |
| B | 常用薬の数 | 多剤併用による副作用・食欲低下 | 薬剤数増で相互作用・副作用リスク増 | 3 剤以上は要注意。眠気・口渇・便秘・悪心などの症状も併記。 |
| B | 褥瘡/皮膚潰瘍 | 炎症・蛋白消費の増大 | 創の存在・重症度でリスク増 | 部位/ステージ/滲出量/感染徴候を記録。タンパク需要増を想定。 |
| C 食事 | 1 日の食事回数 | 食事パターンの安定性 | 3 食確保が望ましいが、少量高頻度も選択肢 | 2 食以下なら間食導入を検討。時間帯の偏り(朝欠食など)も確認。 |
| C | たんぱく質摂取 | 筋量維持に必須 | 乳製品・卵/豆・肉魚の摂取頻度で評価 | 主菜量・咀嚼/嚥下の制限を確認。補助食品の適応も検討。 |
| C | 果物・野菜の摂取 | 微量栄養素と食物繊維の確保 | 毎日の摂取が望ましい | 咀嚼困難なら調理形態(刻み/軟菜/ピュレ)で代替。便秘も併せて確認。 |
| C | 水分摂取量 | 脱水・便秘・食欲低下の予防 | 低摂取はリスク増 | おおむね “ 3 杯未満/日” は要注意。嚥下・利尿薬・心不全の制限に留意。 |
| C | 食事の自立度 | 摂食動作の実行可能性 | 自立 > 部分介助 > 全介助の順にリスク増 | ポジショニング、食具、トレイ配置の工夫を記録。 |
| D 主観 | 自己評価:栄養状態 | 本人の気づき・受療行動の指標 | 「良好」から「不良」へ下がるほどリスク増 | 体重変化の自覚、食欲、疲労感の表現を短く引用して残す。 |
| D | 自己評価:健康(同年代比) | 全体的健康観の把握 | 同年代より「悪い」自覚は栄養問題と相関 | 最近の受診・入院歴、ADL/IADL の困難、閉じこもり傾向を添記。 |
点数 → アクション対応表
| 点数帯 | 栄養介入 | 連携 | 再評価 |
|---|---|---|---|
| ≥ 24 | 食事の質・たんぱく質確保、食環境調整 | 必要時のみ情報共有 | 4–8 週 |
| 17–23.5 | 摂取量増(間食/補助食品)、食事形態最適化 | 栄養/口腔・嚥下/薬剤と連携 | 2–4 週 |
| < 17 | 原因評価+集中的介入、経腸/静脈の適応検討 | 多職種カンファレンス | 1–2 週 |
ケースで理解する( 80–120 字 × 2 )
入院回復期:食事 6 割・体重減少あり。MNA 本式 21 点(リスク)。間食と高エネルギー主菜に変更、口腔ケア強化。 2 週後 23.5 点、摂取 8 割へ改善。
在宅独居:主食偏重で調理負担大。MNA 本式 16.5 点(低栄養)。宅配弁当+間食、栄養補助食品導入。訪問看護と連携し 2 週で 18 点、体重減少が停止。
ダウンロード(印刷/運用に)
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
本式の所要時間は?
初回 10–15 分、再評価 5–10 分が目安です。問診が難しい場合は家族/介護者の情報を補助に用います。
欠測が出たときの扱いは?
欠測理由と状況をメモし、可能な範囲で評価します。次回は同一条件で再評価します。
短縮版との使い分けは?
一次は短縮版、8–11 点のときに本式で精査します。 12–14 点は経過観察、 0–7 点は速やかに対処します。
おわりに
MNA(本式)は「条件をそろえる → 情報を補完する(本人+家族) → 点数化 → 原因の見立て → 介入の優先順位 → 再評価」というリズムで回すと、結果が “次の一手” に直結します。まずは体重・周囲径・摂取量の取り方を固定し、再評価で “同じ土俵” で比較できる状態を作ってください。
面談準備チェックと “職場の評価シート” も、連携と介入整理に役立ちます。マイナビコメディカル面談準備チェック(DL)
参考文献
- Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, et al. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition. 1999;15(2):116–122. doi:10.1016/S0899-9007(98)00171-3
- Rubenstein LZ, Harker JO, Salvà A, et al. Screening for undernutrition in geriatric practice: MNA and MNA-SF. J Nutr Health Aging. 2001;5(2):85–93. PubMed
- Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA-SF). J Nutr Health Aging. 2009;13(9):782–788. PubMed
- Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clin Nutr. 2019;38(1):1–9. doi:10.1016/j.clnu.2018.08.002
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下