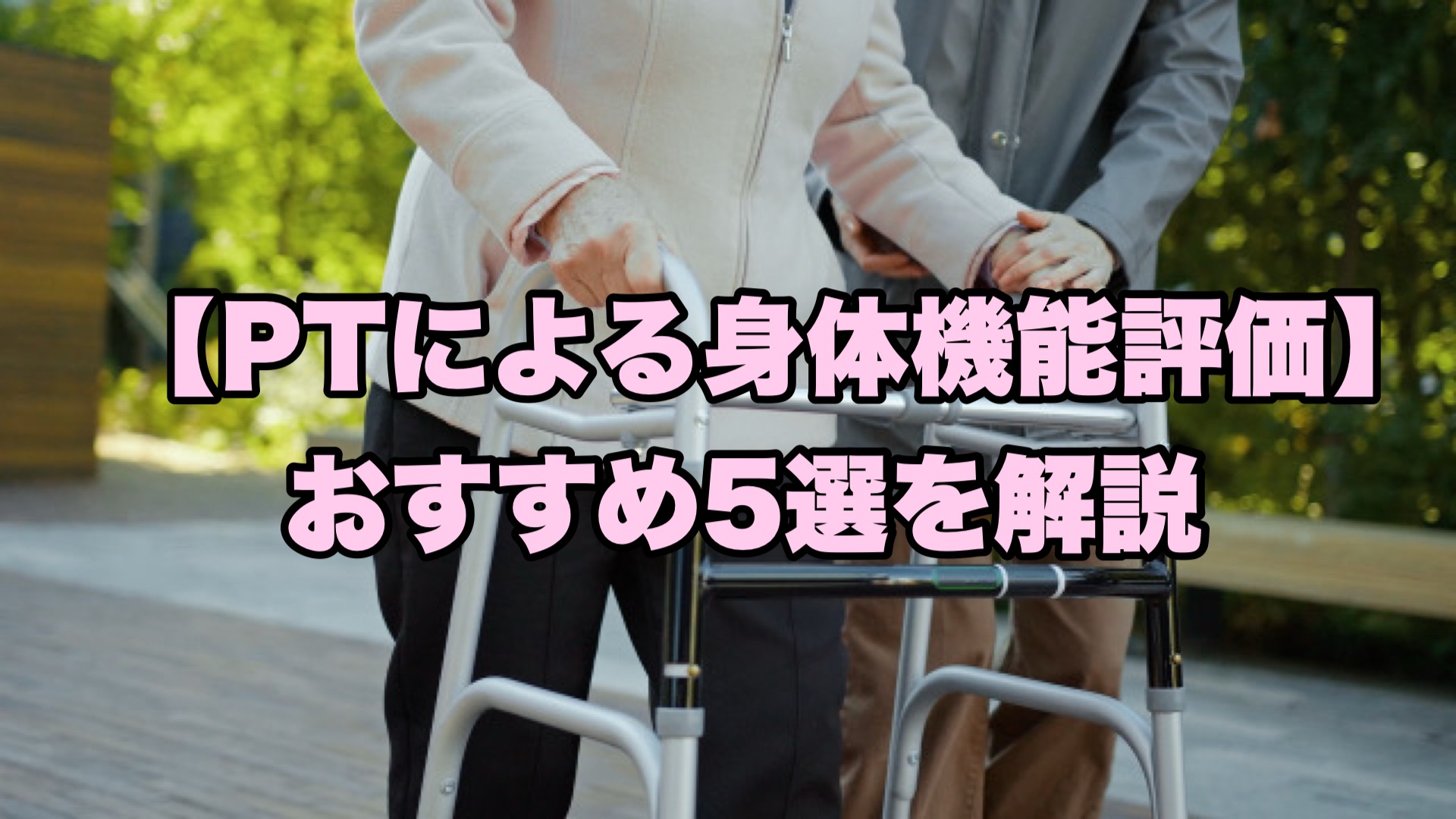身体機能評価の種類(結論)
評価の「選び方」が決まると、記録と再評価が一気にラクになります。 理学療法士のキャリアガイドを見る(全体の流れ)
本ページは「身体機能評価の種類」を、目的 → 代表テスト → 使いどころ → 所要時間 → 機材の順で俯瞰できるように整理した“早見”です。包括スコアの深掘りは個別記事に任せ、ここでは領域別の入り口をそろえて、症例・場面に応じた第一選択を素早く決められる設計にしています。
身体機能評価の全体像(早見)
※表は横にスクロールできます(スマホ)。
| 領域 | 目的 | 代表テスト | 所要 | 機材 | 主な使いどころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 各部位の最大筋力 / 実用筋力 | MMT、握力、CS-30 | 3–10 分 | 徒手、握力計、椅子 | 初期評価、経過観察、退院基準の検討 |
| バランス(静的 / 反応) | 立位・姿勢制御と外乱対応 | Berg Balance Scale、FRT、Romberg | 5–20 分 | 台、メジャー等 | 転倒リスク層別化、在宅移行判断 |
| 動的バランス / 移動 | 移動時の姿勢制御・課題複合 | TUG、DGI、Mini-BESTest | 5–20 分 | 椅子、通路、コーン等 | 屋内外移動の安全性、介助量見積もり |
| 歩行能力 | 歩行速度・耐久・効率 | 10 m 歩行(快適 / 最大)、6MWT | 5–10 分 | 距離表示、ストップウォッチ | 移動自立度、補助具 / 酸素の要否 |
| 持久力 / 運動耐容能 | 反復負荷への耐性 | 6MWT、2MWT、階段昇段テスト | 6–10 分 | 通路、SpO2(任意) | 在宅復帰、外来リハの目標設定 |
| 柔軟性 / 関節可動域 | 関節機能の制限確認 | ROM(ゴニオ計測)、SLR、Thomas など | 3–10 分 | ゴニオメーター | 疼痛 / 機能制限の鑑別、介入方針の選定 |
| 起居・移乗・階段 | 基本動作の自立度 | 5 回椅子立ち上がり、床起立、階段昇降テスト | 5–10 分 | 椅子、階段 | 介護量 / 住宅改修 / 福祉用具選定 |
代表 5 テスト(小記事)への最短導線
このページは“全体像”が役割です。手順・記録・解釈をすぐ確認したいときは、下の個別記事に直行してください。
| テスト | 主に見たいこと | 所要 | 個別記事 |
|---|---|---|---|
| 10 m 歩行(10MWT) | 歩行速度(快適 / 最大) | 3–5 分 | 10 m 歩行の手順・記録・解釈 |
| 5 回椅子立ち上がり(5xSTS) | 下肢筋力 / 立ち上がり能力 | 3–5 分 | 5 回椅子立ち上がりの手順・注意点 |
| SPPB | 下肢機能の包括評価( 0–12 点) | 7–10 分 | SPPB の構成・採点・活用 |
| 6 分間歩行(6MWT) | 運動耐容能 / 歩行耐久 | 6–10 分 | 6MWT の手順・声かけ・中止基準 |
| TUG | 動的バランス / 方向転換を含む移動 | 3–5 分 | TUG の手順・解釈・カットオフ |
| 評価の全体像(ハブ) | 評価を体系で整理して、選び方を迷わない | — | 評価ハブ(全体像) |
理学療法士(PT)が押さえる 5 つの身体機能評価(要点)
ここでは「このテストは何を拾いやすいか」を短くまとめます。細かな手順や記録様式は、上の個別記事で確認してください。
歩行テスト(歩行速度)
歩行速度は、転倒、ADL 低下、活動量低下などと関連しやすく、身体機能評価の代表的な指標になります。フレイルやサルコペニア関連の枠組みでも参照されやすいため、まず「快適速度」と「最大速度」のどちらを使うかを目的で決めると迷いが減ります。
距離は施設の環境に合わせて設定し、距離( m )÷ 時間(秒)で歩行速度( m/s )として解釈するのが基本です。
5 回椅子立ち上がりテスト(5xSTS)
5 回椅子立ち上がりは、居室内や在宅でも実施しやすく、下肢筋力・立ち上がり能力・転倒リスクの目安を短時間で得られます。座面高で難易度が変わるため、可能なら座面高を揃え、記録時に条件を残すと再評価が安定します。
「速く」だけでなく「膝伸展の不十分」「反動」「手の使用」など、代償を合わせて観察すると介入の当たりが付けやすくなります。
Short Physical Performance Battery( SPPB )
SPPB は、立位バランス、歩行、立ち上がりの 3 課題から成る下肢機能の包括評価です。点数化( 0–12 点)できるため、初期評価だけでなく、経過の変化を“ひと目で共有”したい場面で強みがあります。
一方で、採点や条件設定の細部が結果に影響するため、運用は「誰が測っても同じ条件」に寄せるのがコツです。
6 分間歩行テスト( 6MWT )
6MWT は、運動耐容能や歩行耐久をフィールドで評価でき、呼吸・循環領域を含めて幅広く使われます。距離そのものより、同一対象者の経時変化(改善 / 悪化)を丁寧に追うと臨床判断に直結します。
SpO2、息切れ、脈拍、休憩の有無なども合わせて記録しておくと、目標設定と安全管理が一気にやりやすくなります。
Timed Up and Go( TUG )
TUG は、起立・直線歩行・方向転換・着座を 1 セットで評価でき、動的バランスや敏捷性の目安になります。タイムだけでなく、方向転換時のふらつき、歩幅低下、二重課題での破綻など、質的所見を一緒に残すと転倒リスク評価の精度が上がります。
どれを選ぶ?(最短ルート)
| 症例像 / 目的 | まず取るテスト | 補助 / 代替 |
|---|---|---|
| 回復期・転倒リスク推定 | TUG、Berg | FRT、5 回椅子立ち上がり |
| 在宅復帰の移動自立 | 10 m 歩行(快適 / 最大) | 6MWT、DGI |
| フレイル疑い・筋力把握 | 握力、CS-30 | MMT(部位別) |
| 疼痛 / 拘縮の関与評価 | ROM(該当関節) | 徒手検査( SLR / Thomas 等) |
FAQ
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
このページは何のためのページ?(個別ページとどう違う?)
本ページは「身体機能評価の種類」を俯瞰して、目的に合う第一選択を素早く決めるための“総論(親記事)”です。測定手順・記録テンプレ・細かな解釈は、代表 5 テストの個別ページにまとめています。
時間がないときの最小セットは?
転倒リスク中心なら TUG +(可能なら)バランス評価、移動自立なら 10 m 歩行 + 6MWT、筋力なら 握力 + 5 回椅子立ち上がりを起点にします。目的(転倒 / 自立 / 耐久)を先に決めると選びやすいです。
測定の順序はどう決める?
バイタル・疼痛を確認し、安全性の高い項目 → 疲労影響の少ない項目 → 高負荷項目の順で実施します。歩行耐久( 6MWT )は疲労が出やすいので、最後に回す運用が無難です。
参考文献
- Guralnik JM, et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994;49(2):M85–M94. PubMed
- Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142–148. PubMed
- ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111–117. PubMed
- Berg KO, et al. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Can J Public Health. 1992;83 Suppl 2:S7–S11. PubMed
- Shumway-Cook A, et al. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000;80(9):896–903. PubMed
おわりに
身体機能評価は「安全の確保 → 条件統一 → 段階的に負荷を上げる → 数値と質的所見をセットで記録 → 再評価」で回すほど、介入の精度が上がります。面談準備チェックと職場評価シートをまとめて使いたい場合は、こちら(ダウンロード)もあわせて活用してください。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下