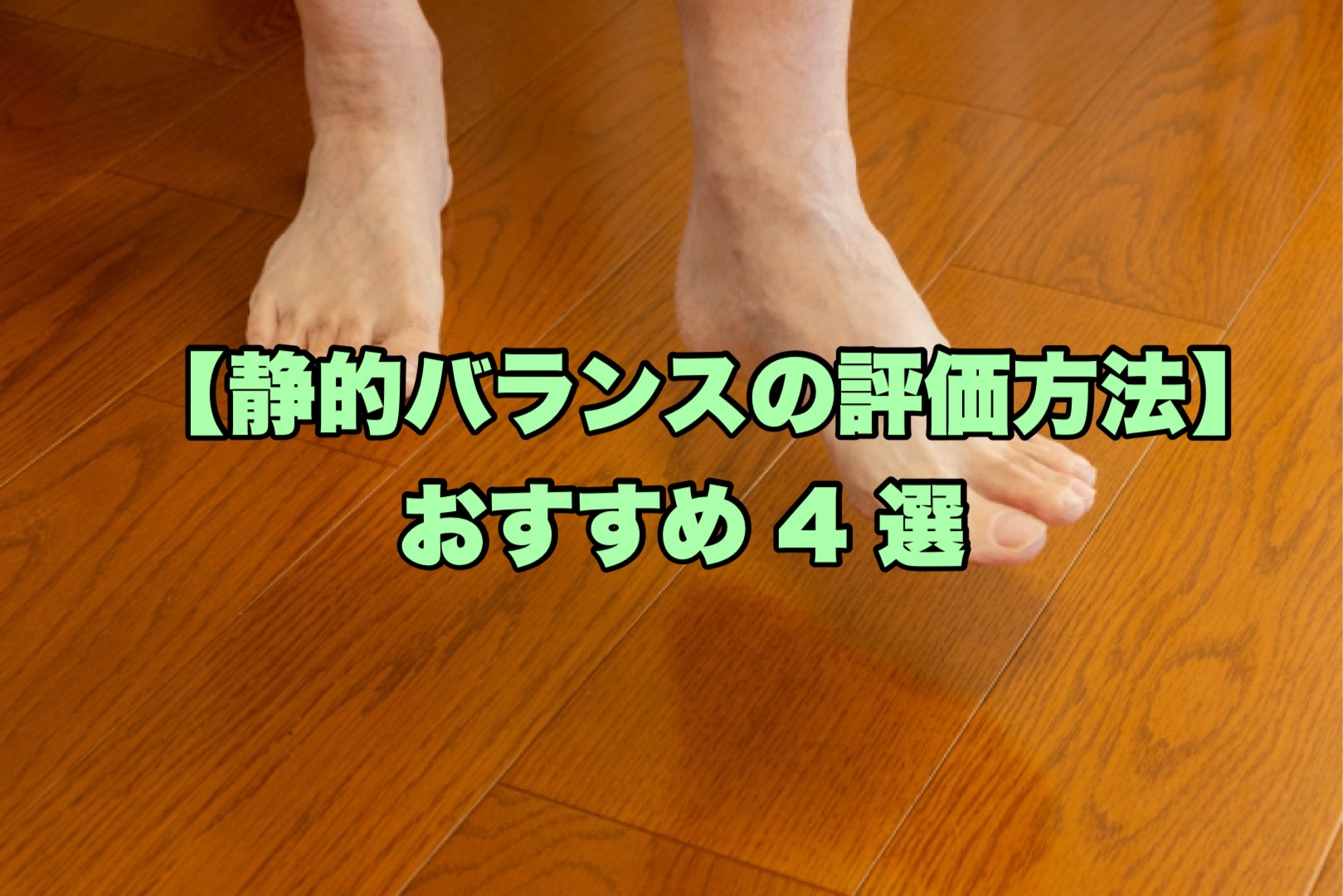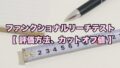静的バランスの評価:目的別の使い分けと臨床運用(直立検査/片脚立位/マン試験/ロンベルグ試験)
静的バランスは「立位姿勢を崩さず保つ力」です。臨床では転倒リスクの抽出と、視覚・前庭・固有感覚(深部覚)の寄与を大まかに見分けるために使います。本記事では 直立検査・片脚立位・マン試験(タンデム)・ロンベルグ試験の 4 法を、安全準備 → 実施 → 判定 → 次アクションまで 1 ページで整理します。
静的バランスは「条件固定」ができると、再評価と申し送りが一気に安定します。 評価 → 介入 → 再評価の型を確認する(PT キャリアガイド)
関連:全体の選び方(静的・動的・尺度の導線)は バランス評価のやり方まとめ に整理しています。
目的別ショートカット(最短で迷わない導線)
- 立位保持の安全確認から:直立検査(足幅を段階的に)
- 転倒リスクを“秒”で追う:片脚立位テスト
- 継ぎ足(タンデム)で限界を引き出す:マン試験(タンデム)
- 開閉眼差で感覚寄与を読む:ロンベルグ試験
使い分けは 3 ステップ(選び方 → 実施 → 記録固定)
静的バランスは、検査そのものよりも「条件を固定して比較できる形にする」ほうが成果が出ます。最短は次の 3 ステップです。
- 目的を 1 つに絞る:「安全確認」「転倒リスク」「感覚寄与(開閉眼差)」のどれを見たいか決める
- 条件を固定する:足幅・足先角度・上肢位置・視線・靴/装具・見守り位置
- “破綻の瞬間”を記録する:いつ・どこで・何が起きたか(足が出る/体幹が崩れる/恐怖で固まる など)
| 目的 | まず選ぶ | 次に足す | 読むポイント |
|---|---|---|---|
| 立位保持の安全確認 | 直立検査(足幅を段階化) | 必要時に片脚/タンデム | 足幅を狭めた時に破綻する段階 |
| 転倒リスク(経時比較) | 片脚立位(開眼) | タンデム(マン) | 保持時間+フォーム逸脱(足接触・位置移動・手離し) |
| 感覚寄与(鑑別の手がかり) | ロンベルグ(開眼→閉眼) | タンデム閉眼(可能なら) | 閉眼で増悪=固有感覚/前庭の示唆、小脳性は開閉眼とも不安定 |
静的バランスの評価方法(早見表+個別手順)
表はスマホで横にスクロールできます。
| 検査 | 姿勢・眼条件 | 保持時間・回数 | 終了条件 | 判定の観点 | 示唆(読み) |
|---|---|---|---|---|---|
| 直立検査 | 両脚立位(足幅を段階的に狭小化)/開眼(必要時に閉眼比較) | 各足位で 20–40 秒(施設 SOP に合わせる) | 転倒危険・著明な動揺・手支持 | 足位ごとの保持可否/保持時間/動揺 | 「どの段階で破綻するか」を安全計画に直結 |
| 片脚立位 | 支持脚膝伸展・両手は腰/開眼(必要時に閉眼) | 最大 120 秒で打切り/ 2 回まで実施し良い方 | 足接触・足位置移動・手離し | 保持時間+フォーム逸脱 | 転倒リスク抽出と経時比較(秒数で追跡) |
| マン試験 | タンデム位(足尖と踵を接する)/開眼→閉眼 | 各 30 秒/左右を入れ替えて評価 | 足の位置ずれ・手支持・明らかな動揺 | 開閉眼差・左右差・動揺方向 | 継ぎ足耐性(狭い BOS )と破綻様式の把握 |
| ロンベルグ | 閉脚立位/開眼→閉眼 | 各 30 秒(必要時に短縮) | 転倒リスク・著明動揺 | 閉眼で動揺増大=ロンベルグ徴候 | 固有感覚/前庭の示唆、小脳性は開閉眼とも不安定 |
直立検査(静的バランス|足幅を段階化して安全域を読む)
準備:壁際/見守り者、滑りにくい床、靴・装具条件を固定します。
実施:足幅を 開脚 → 閉脚 → 継足(タンデム) の順に段階的に狭め、各足位で20–40 秒の保持を観察します(まずは開眼。必要時に閉眼比較)。
判定:「どの足位で破綻するか」「破綻の瞬間(足が出る/体幹が崩れる/上肢で代償する)」を記録します。
片脚立位(静的バランス|開眼基準・打切り・判定)
準備:壁際/見守り者、床の滑り、体調(めまい・疼痛・血圧)を確認します。
実施:両手は腰、支持脚は膝伸展、挙上脚は非接触。開眼で 2 回まで実施し良い方を採用します。長くできる場合は最長 120 秒で打切りにすると運用が揃います。
判定:保持時間に加えて、フォーム逸脱(足接触・位置移動・手離し)を必ず残します。
マン試験(静的バランス|タンデム位・開閉眼・左右入替)
準備:床の一直線目印、壁際、見守り位置を固定します。
実施:タンデム位で開眼 30 秒 → 閉眼 30 秒(可能な範囲で)。左右を入れ替えて同様に行います。
判定:初期支持の必要性(姿勢を作る段階で支えが必要か)と、保持中の動揺方向(前後/左右)を記録すると、次の介入に繋がります。
ロンベルグ試験(静的バランス|陽性の意味と読み分け)
準備:閉脚立位が安全に取れるスペース、壁際、見守り者を配置します。
実施:閉脚立位で開眼 30 秒 → 閉眼 30 秒。
判定:閉眼で動揺が明確に増大(または転倒)する場合をロンベルグ徴候として扱い、固有感覚/前庭の寄与低下を疑う手がかりにします。小脳性は開閉眼とも大きく不安定になりやすい点がポイントです。
現場の詰まりどころ(測定がブレる原因を先に潰す)
静的バランスは、ちょっとした条件差で結果が変わります。再評価で比較できるように、固定すべき項目を最初から決めます。
| よくある失敗(ブレ) | 起きること | 対策(固定ポイント) | 記録に残す |
|---|---|---|---|
| 足幅・足先角度が毎回違う | 保持時間と動揺が変わる | 足幅(例:骨盤幅)と足先角度をルール化 | 足幅/足先角度 |
| 上肢位置(腰/体側)と視線が曖昧 | 代償で安定して見える | 上肢位置と視線(正面固定)を統一 | 上肢位置/視線 |
| タイミング開始がバラバラ | “姿勢を作る時間”が混入 | 「姿勢が安定してから開始」を統一 | 開始基準(安定後) |
| 初期支持の扱いが不統一(タンデムなど) | 数値が過大評価される | 「初期支持あり/なし」を区別して記録 | 初期支持の有無 |
| 靴・装具・杖の条件が混ざる | 結果の比較ができない | 条件を固定し、変更したら別条件として扱う | 靴/装具/杖 |
記録テンプレ(最低限そろえる 6 項目)
「秒数」だけだと再現できません。最低限の固定項目をセットで残すと、経時比較が一気に安定します。
| 項目 | 書き方の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 実施日・評価者 | 2026/01/10、PT A | 比較の前提 |
| 検査名 | 片脚立位(開眼) | 同一プロトコルに揃える |
| 条件 | 上肢:腰、足幅:閉脚、靴:あり | “固定項目”を並べる |
| 環境 | 床:リノリウム、手すり:なし | 床と支持物は影響大 |
| 結果 | 右 8 秒、左 5 秒(良い方) | 回数・採用ルールも書く |
| 所見(破綻の瞬間) | 左で 4 秒以降に体幹側屈、足位置修正で終了 | 次の介入が決まる情報 |
安全管理と中止基準
静的バランスは「転倒を起こさない設計」が最優先です。中止基準を先に共有し、運用を揃えます。
| チェック項目 | OK(実施) | NG(中止・延期) | 記録 |
|---|---|---|---|
| 環境 | 壁際/見守り者配置、滑りにくい床 | 床が滑る、スペース不足、単独実施 | 場所/見守り位置 |
| 体調 | 安静時にめまい・悪心がない | めまい・悪心、疼痛増悪、低血糖疑い | 症状の有無 |
| 循環・呼吸 | バイタル安定 | 顔面蒼白・冷汗、胸部症状、急激な血圧変動 | BP/SpO2 等 |
| 中止基準 | 軽度の動揺(見守りで安全) | 転倒リスクを伴う動揺、手支持が必要 | 中止理由 |
| 再評価 | 同一条件・同一ルールで実施 | 条件が毎回変わる | 条件固定の項目 |
判定から次アクションへ(“静止”を“動作”へつなぐ)
静的バランスで見えた弱点は、そのまま動作課題(立ち上がり・方向転換・歩行)に直結します。ポイントは、結果を「良い/悪い」で終わらせず、破綻の瞬間を言語化して次の練習条件に落とすことです。
- 足幅を狭めた段階で破綻:支持基底面内での制御が課題 → 立位課題の段階設定(足幅・支持物・注意配分)
- 閉眼で急に悪化:視覚依存が強い → 固有感覚入力(足部・足関節)や環境手がかりの調整
- タンデムで姿勢を作れない/初期支持が必要:安全域が狭い → 姿勢獲得(セット)自体を練習対象にする
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
片脚立位は何秒で「異常」と考えますか?
閾値は対象・条件で変わります。実務では「施設ルール(例:打切り 120 秒、 2 回の良い方)」を固定し、秒数+フォーム逸脱+推移で判断するとブレません。転倒リスク抽出の目安として短い秒数(例:数秒台)を用いる報告もありますが、まずは条件固定と経時比較を優先してください。
マン試験とロンベルグ試験の使い分けは?
マン試験は姿勢難度(タンデム)で限界を引き出す目的、ロンベルグは開閉眼差で感覚寄与(固有感覚/前庭/小脳の手がかり)を読む目的が中心です。併用すると「狭い BOS に弱いのか」「閉眼で崩れるのか」が整理しやすくなります。
靴と裸足、どちらで測るべき?
まずは転倒リスクが低い条件を優先し、施設 SOP に合わせてください。靴底の滑りやすさや装具の有無は結果に影響するため、再評価は同条件で行うのが原則です。
参考文献
- Bohannon RW. Single limb stance times: a descriptive meta-analysis of data from individuals at least 60 years of age. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2006;22(1):70–77. doi: 10.1097/00013614-200601000-00010
- Hile ES, Brach JS, Perera S. Interpreting the need for initial support to perform tandem stance tests of balance. Physical Therapy. 2012;92(10):1316–1328. doi: 10.2522/ptj.20110283
- Halmágyi GM, Curthoys IS. Vestibular contributions to the Romberg test: testing semicircular canal and otolith function. European Journal of Neurology. 2021. doi: 10.1111/ene.14942
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The 4-Stage Balance Test (STEADI). 公式 PDF
- 望月 久. バランス能力測定法としての直立検査. 理学療法—臨床・研究・教育. 2008;15:2–8. J-STAGE
- 日本理学療法士協会. 理学療法ガイドライン(身体的虚弱). 公式 PDF
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
おわりに
静的バランスは、安全の確保 → 条件固定 → 段階的に難度を上げる → 破綻の瞬間を記録 → 再評価の順に回すほど、臨床の“リズム”が整います。面談準備チェックと職場評価シートを使って、働き方も含めた次の一手を整理したい方は こちらも参考にしてください。