
いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!
この記事は「筋緊張低下|筋力低下|支持性低下」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。
患者様の心身機能や身体構造を説明するときに筋緊張や筋力、支持性の話になった経験がある方いらっしゃると思います。これらの言葉ってどれもよく使ったり聞いたりはしますが、正しく使おうとすると、意外と複雑で難しいですようね!
例えば、脳卒中片麻痺者の立位姿勢や歩行動作の問題点について説明するときに、どの用語をつかってどのように説明すれば正解であるのかって、私は若手の頃自信がありませんでした。そもそも「支持性」については実習生の頃レポートやレジュメでよく使用した記憶がありますが、よく分かっていませんでした。
しかし、今はこれらの用語の理解は重要だと考えております。患者様に対しては当然ですが、看護士等の他職種に説明をするときに正しい知識が必要になるためです。医療機関で働く理学療法士が円滑に働くための条件として、他職種からの信頼を高めるということが1つにあると思いますが、こういった身体機能に関する専門知識はリハ職から発信することになることが多いと思いますので押さえておきましょう!
そこで今回こちらの記事で、筋緊張低下・筋力低下・支持性低下について正しく理解できるように解説していきたいと思います。

【簡単に自己紹介】
30代の現役理学療法士になります。
理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。
現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。
臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。
そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。
現在、理学療法士として得意としている分野は「脳卒中」「褥瘡」「栄養」「呼吸」「摂食・嚥下」「フレイル・サルコペニア」についてです。そのため、これらのジャンルの記事が中心となっております。
主な取得資格は以下の通りです
脳卒中認定理学療法士
褥瘡 創傷ケア認定理学療法士
3学会合同呼吸療法認定士
福祉住環境コーディネーター2級
筋緊張低下とは
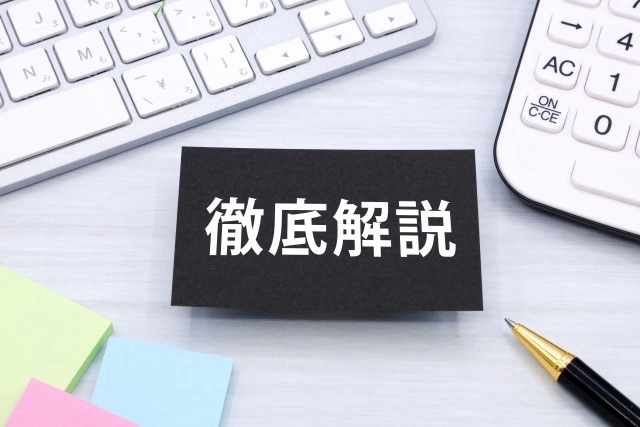
筋緊張とは、神経生理学的に神経支配されている筋に、持続的に生じている筋の一定の緊張状態のことを意味します。
筋緊張は、生体の姿勢保持機構・体温調節機構に関与し、特に姿勢保持機構に関しては、運動あるいは姿勢保持の際に活動する骨格筋の準備状態に重要な意味を持ちます。
筋緊張は疾病などの影響により正常の状態から逸脱して異常を来たす可能性がありますが、筋緊張を表現するのであれば以下の 3 種類に分類することができます。
- 筋緊張低下
- 正常
- 筋緊張亢進
通常、筋肉には適度な緊張(張り)があります。これは身体のどの部位にも共通していえることであり、緊張(張り)をコントロールして私たちは身体を動かしています。
筋緊張低下とは、この緊張(張り)が失われた状態になります。緊張(張り)がなくなると筋肉はだらっと垂れ下がってしまい、力が入らなくなったり、姿勢を保てなくなります。
筋緊張が低下している場合、視診では筋肉が重力に負けて垂れていて容量(ボリューム)が少なくだらっとした感じをうけます。
触診では、検者の圧迫に対する筋肉の跳ね返りが少なく、筋肉が沈み込むような反応を認めます。
他動運動時(被動性検査)では、筋肉に抵抗感を認めず、むしろ筋肉の重さを感じとることができます。
筋緊張の「低下」を評価する方法としては、上述したように視診・触診、被動性検査、懸振性検査などがあげられます。
筋緊張亢進(痙縮)の評価尺度としては modified Ashworth scale が有名ですが、筋緊張低下を段階分けするような国際的な指標は開発されていないというのが現状になります。
筋緊張低下の原因
筋緊張低下の原因としては以下のような疾患、病態があげられます。
- 脳血管障害
- 脊髄損傷
- 小脳疾患などによる中枢神経障害
- ギラン・バレー症候群や末梢神経障害による筋力の低下
- 筋炎による筋組織の破壊
- 廃用による筋萎縮や筋節数の変化
- 神経筋接合部の障害
- 電解質異常
- 筋周囲の軟部組織の緩さ
- 梃子の腕としての骨格の構造、支点の緩み
- がんの骨転移における筋力低下
予防と改善方法
筋緊張低下の診断は、医師や理学療法士などの専門家による問診や視診、触診、筋力や筋反射の検査などで行われます。
筋緊張低下の治療は、原因に応じて薬物療法や手術などが行われますが、一般的には理学療法や運動療法が重要な役割を果たします 。筋緊張低下の予防や改善のためには、以下のような対応が有効となります。
- 適度な運動やストレッチを行う
- 姿勢や動作の改善や指導を受ける
- 筋肉の温めやマッサージを行う
- 筋肉に負担をかけないようにする
- 栄養や水分の摂取を適切にする
- 睡眠や休息を十分にとる
筋力低下とは
骨格筋における随意的な最大筋力は、「絶対筋力」と「筋断面積」の積で表されます。絶対筋力は単位面積あたりに発生する筋出力で 4 ~ 6 kg/cm2 で考えることができます。
筋に発生する張力は筋断面積と相関し、筋収縮速度は筋長と相関します。骨格筋の基本的特性を構成している筋力低下は、これら構成要素の変性や機能不全による出力の低下を意味します。また、筋肉の変性や萎縮のほかに神経筋接合部の障害、神経系障害でも筋力低下は生じます。
臨床的に測定されるのは、関節運動により発生するモーメントであり、いわば関節トルクを筋力として捉えています。臨床では、例えば不動のため筋萎縮が起こり、関節トルク発揮不足があった場合に「筋力低下」と表現します。
筋力低下の責任病巣
筋力低下を呈する疾患の鑑別には筋力低下の分布や程度を正しく把握することが重要になります。
また、筋力低下の発症様式や病歴などの臨床情報、神経学的所見、臨床検査所見などから責任病巣を推定することができます。
- 骨格筋
- 神経筋接合部
- 末梢神経
- 神経叢
- 脊髄神経根
- 脊髄
- 脳幹
- 内包後脚
- 運動野
筋力低下の原因
筋力低下の原因は多岐に渡りますが、一般的には以下の要因があげられます。
- 筋肉の損傷や炎症(筋肉痛、筋断裂、筋炎)
- 筋肉の萎縮や変性(加齢、運動不足、栄養不良、アルコール依存症)
- 筋肉の遺伝性や免疫性の疾患(筋ジストロフィー、多発性筋炎)
- 神経系の障害(脊髄損傷、筋萎縮性側索硬化症、ギラン・バレー症候群)
- 内分泌系の障害(甲状腺機能亢進症、クッシング症候群)
- 薬物の影響(ステロイド、スタチン、抗がん剤)
筋緊張低下と筋力低下の違い

筋緊張低下と筋力低下を混在させてしまうことは良くあることですが、筋緊張低下と筋力低下は全くの別物になります。
両者の鑑別方法として、筋緊張低下や筋力低下を疑ったときに臨床で優先して行うべきことは、筋緊張の評価になります。
具体的には、視診・触診、被動性検査、動作時の筋緊張を観察し、筋緊張を評価します。筋緊張が低下しているのであれば、その部位や程度を確認します。筋緊張を評価してから、必要に応じて筋力の評価を進むことがポイントになります。
筋緊張低下と筋力低下の違いを複雑にしている要因として運動麻痺があります。運動麻痺とは、脳や脊髄、末梢神経が障害されることで、随意運動に支障が出る状態になります。
運動麻痺では、筋力低下と筋緊張の異常(低下、亢進)の両者が併せて生じる可能性があります。そのことで筋力低下であるのか、筋緊張低下であるのかの判断を複雑にしています。
筋力低下と筋緊張低下については以下の 3 つのパターンのいずれかに当てはめることができます。
- 運動麻痺を代表とした神経系障害により筋緊張が低下している
- 神経系障害により筋緊張低下を認め、更に筋力低下も付随している
- 神経系の障害は認めないが、筋力が低下している
筋緊張低下、筋力低下を正確に見極めることで、適切な治療プログラムの立案や効果判定に繋げることができると考えられます。
筋緊張の評価方法については、他の記事で詳しくまとめています!《【被動性検査による筋緊張の評価方法】筋肉の伸張運動による反応が鍵》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
支持性の低下とは
支持性低下は臨床で良く聞く言葉になりますが、誤った使い方をすることも多く、曖昧な表現ともいえます。困った時の「支持性の低下」になってはないでしょうか?
平行棒の中で起立練習、立位保持練習を実施する場合に、膝関節が十分に伸展できず介助量が増大、この要因を「支持性の低下」と表現する人は少なからずいると思います。
実際には可動域制限、筋力低下、バランス能力の低下、運動麻痺、高次脳機能障害など様々な要因が複合されている可能性がありますが、それらを総括して「支持性の低下」と表現するのは適切ではないと考えられます。
「支持性の低下」の適切な使い方としては、単独で使用するのではなく、姿勢制御の説明に絡めて使用するのが良いと思います。
姿勢制御は環境因子や課題内容にも左右されますが、患者個体を考えた場合には、「認知機能」「感覚機能」「骨関節要素」「予測・反応的姿勢調節」「筋協調性要素」「筋力」等の構成要素があげられます。
支持性低下はこのように、複数にわたる患者個体の要素、環境要素が組み合わさり説明できるものになります。姿勢制御やバランス調節が不良であり、その要因が複数ある場合に支持性低下という表現を使うと良いのではないでしょうか。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます!
この記事では「筋緊張低下、筋力低下」をキーワードに解説させて頂きました。
こちらの記事が、筋緊張低下と筋力低下の違いを理解することに繋がり、日々のリハビリテーション診療の一助となれば幸いです。
参考文献
- 根本明宜.筋緊張異常とリハビリテーション.Jpn J Rehabil Med.2020,57,p1069-1076.
- 杉江和馬.歩行障害, 筋力低下, 不随意運動.
月刊薬事.66(4),p705-710,2024.

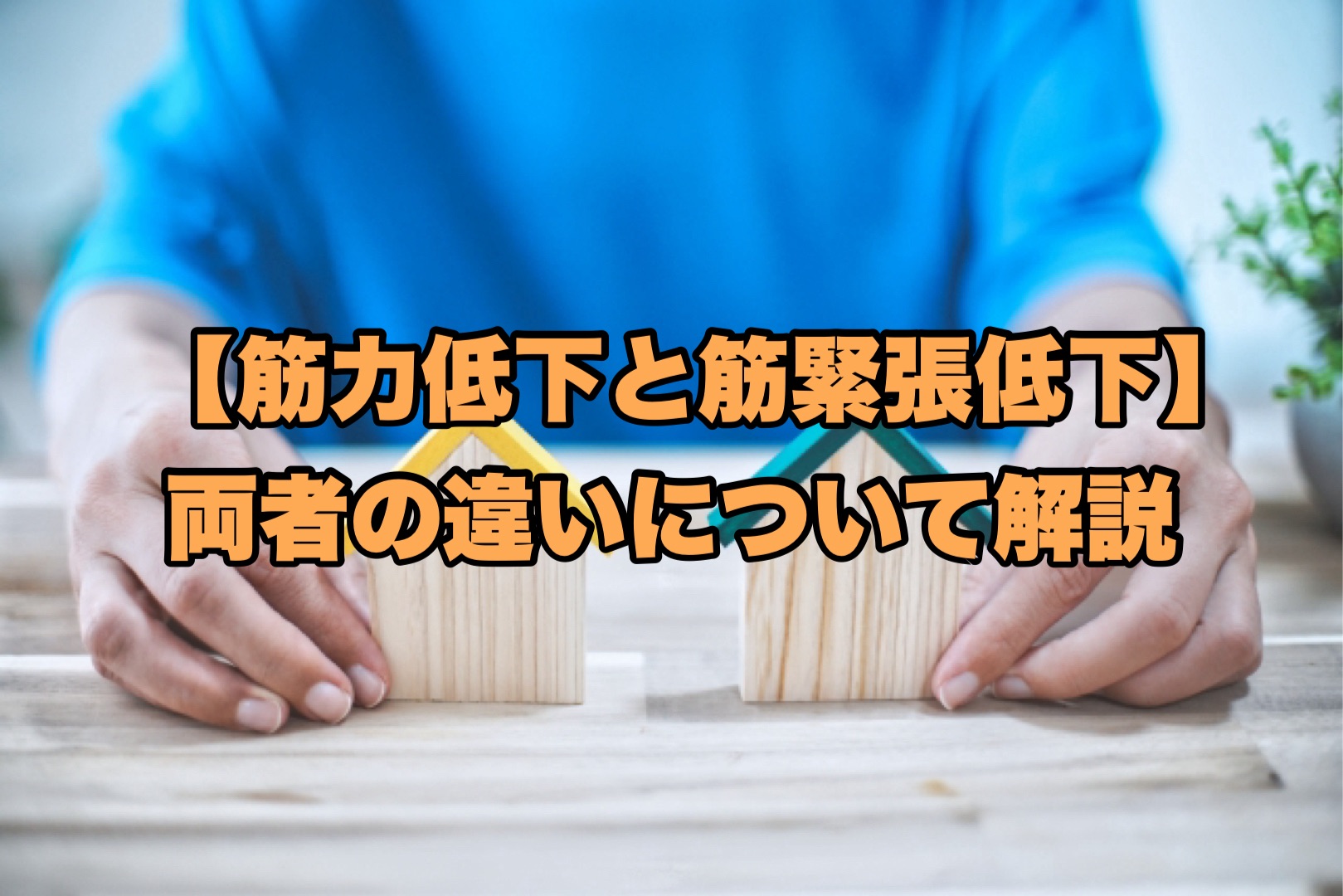


コメント