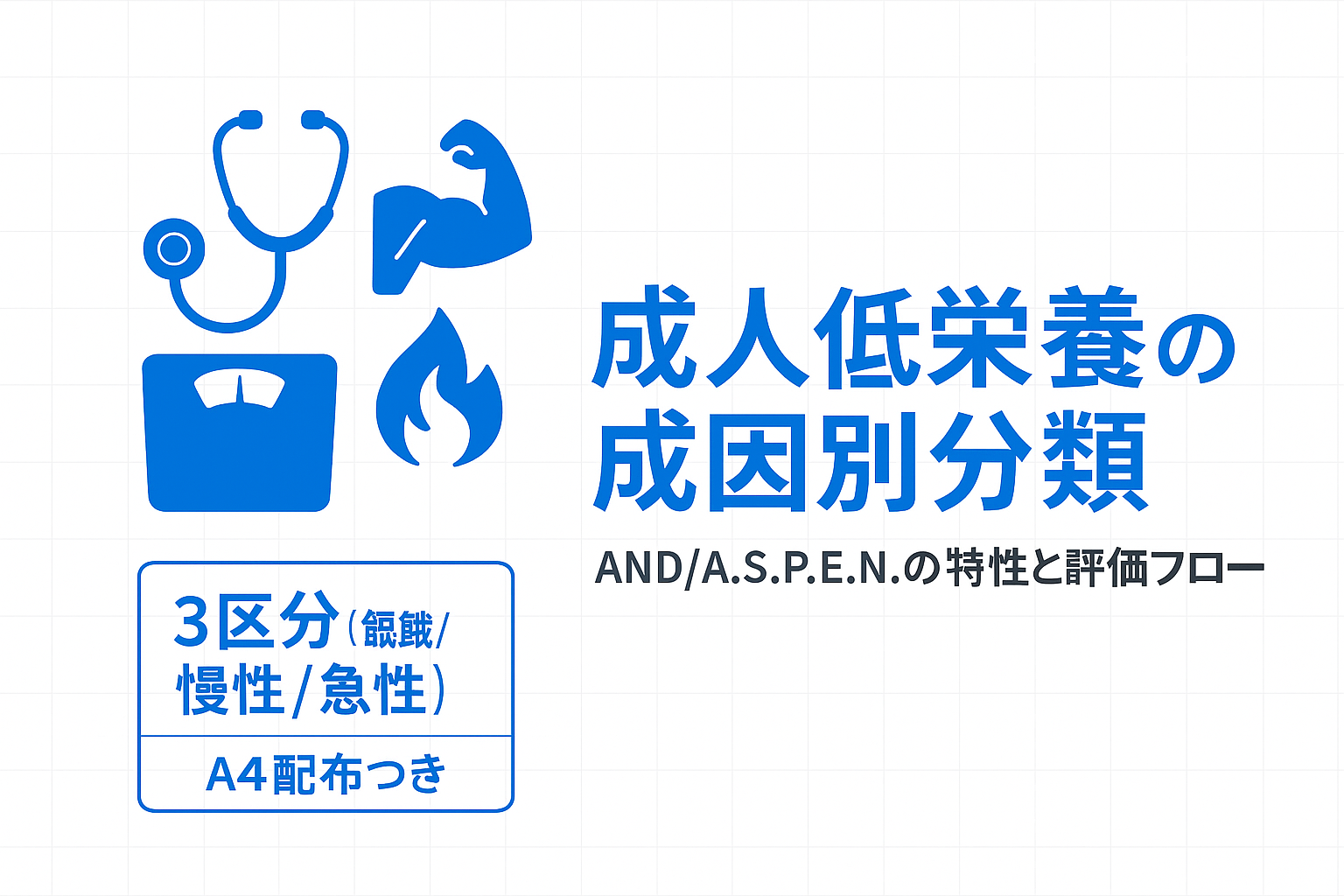この記事でわかること(結論)
本記事は、成人低栄養を 成因別(病因別)に整理する AND / A.S.P.E.N. の枠組みを、臨床で迷わない形に要点化したものです。分類は ① 飢餓関連(炎症なし)、② 慢性疾患関連(軽〜中等度炎症)、③ 急性疾患・外傷関連(著明な炎症)の 3 区分。さらに 6 特性(エネルギー摂取不足・体重減少・筋肉量減少・皮下脂肪減少・浮腫・握力低下)を使って「低栄養らしさ」を裏づけします。
栄養評価・記録・運用まで「迷わない型」を作りたい方へ。 臨床に役立つ評価と仕事術をまとめて見る
なお、診断基準(例:GLIM)での確定・重症度化は別枠の考え方です。スクリーニング〜確定の流れを一続きで整理したい場合は、続けて読む:GLIM 基準の使い方(診断フロー) が近道です。
AND / A.S.P.E.N. の成因別分類とは?
炎症の有無・強さと疾患背景で病態を見立てる枠組みです。炎症が強いほど代謝亢進・蛋白分解が進み、体重・筋量の回復に時間を要します。現場では「体重が減っているか」だけでなく、炎症(急性か慢性か)と摂取不足がどれだけ続いているかをセットで捉えると、介入の優先順位を付けやすくなります。
低栄養の特定(同定)は、以下の 6 特性のうち複数(一般に 2 つ以上)を満たすことが目安です。カットオフは施設方針やガイドラインで扱いが異なるため、本記事は「観察ポイント」と「記録の型」に絞ります。
6 特性の見方(観察ポイントと記録の型)
| 特性 | 何をみる? | 実務での例 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|---|
| エネルギー摂取不足 | 必要量に対する摂取量(期間) | 食事摂取量、経腸・静脈栄養、禁食期間、嘔気・嚥下困難 | 「食べている」でも必要量未満が続く/病棟記録に摂取率が残っていない |
| 体重減少 | 経時変化(どれだけ・どの速度で) | 入院前〜入院後の体重推移、BMI、直近 1 〜 6 か月の変化 | 浮腫・輸液で体重が保たれて見える/ベース体重が不明 |
| 筋肉量減少 | 筋量の低下(定量/半定量) | BIA、CT(SMI)、周径、視診・触診 | ベッド上安静で急速に低下/測定機器がないと「所見なし」扱いになりがち |
| 皮下脂肪減少 | 脂肪の減少(視診・触診) | 上腕三頭筋部、肋骨周囲、眼窩周囲の凹み | 衣服で見えない/元の体型が分からないと判断がぶれる |
| 浮腫(液体貯留) | 体液過剰の有無・部位 | 下腿浮腫、腹水、体重の急増、心不全・腎機能 | 体重減少が隠れる(むしろ増える)/蛋白低下だけで判断しない |
| 握力低下(機能低下) | 筋力・機能の低下 | 握力、立ち上がり、歩行速度、易疲労感 | 疼痛・麻痺・意識レベルの影響で「栄養の影響」と切り分けにくい |
成因別分類の早見表
| 区分 | 炎症 | 代表的な背景 | よくみる所見 | 介入の要点 |
|---|---|---|---|---|
| 飢餓関連(Starvation-related) | なし | 社会的要因・摂食障害・長期の摂取不足 など | 体重減少・皮下脂肪減少・倦怠(炎症所見は乏しい) | 十分なエネルギー / 蛋白質の段階的導入、電解質補正、再栄養症候群に注意 |
| 慢性疾患関連(Chronic disease-related) | 軽〜中等度 | がん慢性期、COPD、心不全、CKD、慢性炎症性疾患 など | 緩徐な体重・筋量低下、食欲低下、CRP 軽度高値 など | 基礎疾患治療+栄養介入、蛋白質重点、むくみ / 電解質管理、運動療法併用 |
| 急性疾患・外傷関連(Acute disease / injury-related) | 著明 | 敗血症・重症外傷・大手術・熱傷・急性増悪期 など | 高度炎症、急速な筋量低下、浮腫、摂取困難 | 早期からの栄養投与(多職種)、蛋白質重点、血糖 / 電解質管理、可及的早期離床 |
迷わない評価フロー(5 分で回す)
- スクリーニング(例:MNA – SF、MUST など)で「栄養リスク」を拾う
- 成因別分類(炎症の強さ+疾患背景)で 3 区分に当てはめる
- 6 特性で裏づけ(複数該当で「低栄養らしさ」を固める)
- 確定・重症度化(施設方針:GLIM、ESPEN、SGA など)に沿って整理する
- 介入 → 記録 → 再評価(体重・摂取量・筋力 / ADL 指標で追う)
現場の詰まりどころ(よくある失敗と回避策)
| つまずき | なぜ起きる? | 回避策(今日から) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 体重が減っていない=低栄養ではない | 浮腫・輸液・腹水で「減少が隠れる」 | 体重だけで判断せず、摂取量・周径・視診触診・機能(握力)をセットで確認 | 浮腫の部位 / 程度、尿量、体重推移の解釈(増減の理由) |
| 炎症評価を CRP だけで決める | 慢性炎症では CRP が軽度〜陰性でも病態が続く | 臨床像(感染徴候、術後 / 外傷直後、急性増悪)を併記して総合判断 | 「急性 / 慢性」「増悪期 / 安定期」を言語化して残す |
| 6 特性が「所見なし」になりがち | 観察・測定の型がなく、記録欄もない | 最低限「摂取量」「体重推移」「筋量(代替指標)」「浮腫」「握力 / 機能」をテンプレ化 | データが取れない項目は「未評価」と明記(ゼロ扱いにしない) |
| 飢餓関連で早期に一気に増量する | 再栄養症候群のリスクを見落とす | 段階的導入、電解質・バイタル・浮腫を短い間隔でモニタリング | 導入量の段階、電解質の推移、むくみ・呼吸苦の有無 |
配布物(A4 ダウンロード)
現場でそのまま使える「早見」と「記録」を A4 で用意しています(院内の運用ルールに合わせて調整してください)。
症例ミニケース(短時間でイメージ)
| 場面 | 区分 | 評価の要点 | 介入の要点 |
|---|---|---|---|
| 在宅・独居(摂取不足が続く) | 飢餓関連 | 摂取量の「継続期間」と体重 / 脂肪減少、見守り体制 | 段階的エネルギー導入+電解質、再栄養症候群に注意、支援体制を整備 |
| 回復期・心不全(慢性の食欲低下) | 慢性疾患関連 | 軽度炎症・むくみで体重評価がぶれる点、筋量 / 機能低下 | 蛋白質重点+むくみ是正、運動療法を安全域で併用、記録テンプレ化 |
| ICU・敗血症(高炎症+筋量低下) | 急性疾患・外傷関連 | 急速な筋量低下、浮腫、摂取困難、血糖 / 電解質 | 早期経腸栄養+蛋白質強化、多職種連携、可及的早期離床 |
FAQ
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
「成因別分類」と「診断基準(例:GLIM)」はどちらを先に使う?
迷わない順番は、① スクリーニングで拾う → ② 成因別分類で病態像(炎症と背景)を押さえる → ③ 施設方針に沿って 診断・重症度化(GLIM など)です。成因別分類は「介入の優先順位」を付けやすくし、診断基準は「確定と記録の統一」に強みがあります。
炎症の把握は CRP だけで良い?
CRP は有用ですが、臨床像(感染徴候、術後 / 外傷直後、急性増悪)と併せて総合判断します。慢性炎症では CRP 上昇が軽度〜陰性でも炎症が持続していることがあります。
筋肉量はどう測る? BIA が無い場合
ふくらはぎ周径・上腕周囲・視診触診・画像診断(CT の SMI など)を組み合わせます。施設方針に準拠し、難しい場合は「未評価」と明記して、代替指標(周径や機能)を残します。
低栄養とサルコペニアの違いは?
低栄養はエネルギー / 栄養摂取不足や炎症に伴う栄養障害の概念、サルコペニアは主に筋力・筋量低下(機能低下)を中核とする概念です。併存は一般的で、評価・介入は相補的に設計します。
参考文献
- Jensen GL, et al. Adult starvation and disease-related malnutrition: a proposal for etiology-based diagnosis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010;34(2):156–159. DOI:10.1177/0148607110361910
- White JV, et al. Consensus statement: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012;36(3):275–283. DOI:10.1177/0148607112440285
- Cederholm T, et al. Diagnostic criteria for malnutrition – An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015;34(3):335–340. DOI:10.1016/j.clnu.2015.03.001
- Jensen GL, et al. GLIM Criteria for the Diagnosis of Malnutrition: A Consensus Report From the Global Clinical Nutrition Community. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019;43(1):32–40. DOI:10.1002/jpen.1440
おわりに
低栄養の整理は、スクリーニング → 炎症と背景の見立て → 6 特性の裏づけ → 記録 → 介入 → 再評価の順に回すと、判断がブレにくくなります。転職や職場選びでも「栄養を回せる体制(多職種連携・評価の型・記録の統一)」は伸びしろになりますので、面談準備チェックと職場評価シートは /mynavi-medical/#download からまとめて使えます。
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下