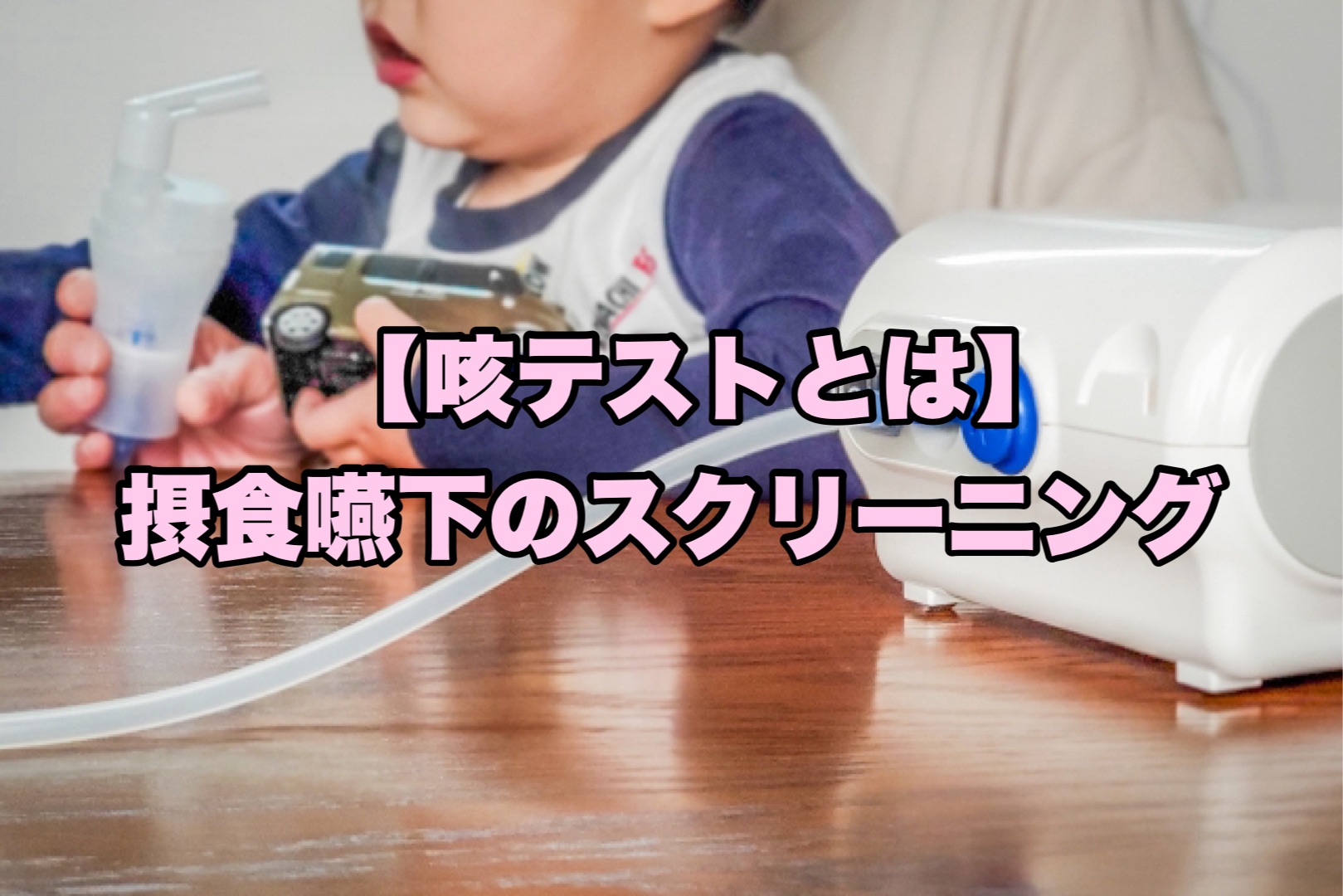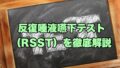咳テスト(不顕性誤嚥スクリーニング)【手順・中止基準・配布物】
咳テスト(咳反射テスト)は、外からの刺激で咳反射が惹起されるか、その強さや質をみることで 不顕性誤嚥リスク を早期に拾い上げるベッドサイドスクリーニングです。水や食物を用いず短時間で行えるため、 ST に限らず PT・OT・看護職も多職種で共有しやすい評価手段です。
本ページでは「咳テストとは?」という基本から、目的、やり方(準備・手順・観察ポイント)、禁忌と中止基準、結果から VE/VFSS など精査・介入につなぐ考え方までを、院内で使える配布物とともに 1 ページに整理します。
関連:ベッドサイドで迷わない全体像は 摂食嚥下評価(総論)の 5 分フロー にまとめています。
実施手順&中止基準( A4 ) 記録シート( A4 ) 患者さま案内( A4 )
咳テストとは?目的と臨床での位置づけ
咳テストとは、咽頭や気道への刺激に対して咳反射が惹起されるか、その 有無・タイミング(即時/遅延)・強さ・連発性・声質の変化 などを観察する検査です。自覚的な「むせ」が少ないのに肺炎を繰り返すケースなどで、気道防御能の低下=不顕性誤嚥を疑う入口として用いられます。
VE/VFSS や RSST・改訂水飲みテストなど「嚥下動作そのもの」をみる検査と組み合わせると、「どこで」「どの程度」誤嚥リスクが高いのかを多面的に把握できます。ベッドサイドで簡便に実施できるため、急性期〜維持期の病棟・施設で ST/PT/OT/看護職が共通言語として活用しやすいスクリーニングです。
咳テストのやり方(準備・手順・観察ポイント)
ここでは「やり方」の全体像を、準備 → 刺激 → 観察 → 判定・申し送り の流れで整理します。刺激方法・濃度・回数は、主治医の指示と各施設のプロトコル を最優先してください(以下は代表例の「型」です)。
代表的な手順( 30 秒法/ 1 分法 )早見
※表は横スクロールで確認できます(スマートフォンなどの狭い画面では左右にスワイプしてください)。
| 区分 | 刺激(例) | 観察のしかた | 判定の目安(例) |
|---|---|---|---|
| 咳テスト( 1 分法 ) | 1% クエン酸生理食塩水をネブライザで 1 分 噴霧し、口から吸入(鼻閉を併用する運用が多い) | 1 分間の咳回数 と、咳の強さ・連発性・遅延、声質、 SpO₂ 変化を記録 | 5 回以上/分 なら陰性(正常)扱い、4 回以下/分 は陽性(不顕性誤嚥リスク)扱い |
| 簡易咳テスト( 30 秒法 ) | 同様の刺激で、30 秒以内 に咳が出るかをみる(メッシュ式ネブライザ運用が多い) | 咳が出るまでの秒数(潜時)を測り、出た時点で観察をまとめる | 30 秒以内に 1 回でも咳 が出れば陰性(正常)扱い、30 秒で咳なし は陽性(リスク)扱い |
※「代表例」をそのまま採用するのではなく、院内マニュアル(薬剤調製・機器・鼻閉の方法・観察時間)に合わせて文言を統一してください。
準備:必要物品・姿勢・モニタリング・ PPE
- 必要物品:施設指定のネブライザ(超音波/メッシュ式など)、マウスピースまたはマスク、ストップウォッチ、ティッシュ・廃棄容器、記録用紙(配布物)など。
- 薬液:濃度や調製手順は施設運用に従う(薬剤部・感染対策・医師指示を優先)。
- 姿勢:座位または半座位で、頭頚部を中間位に保てる姿勢(必要に応じてポジショニング)。
- モニタ:必要に応じて SpO₂/呼吸数/脈拍/血圧を確認し、安静時の値を記録(ベースライン)。
- PPE:飛沫リスクを想定し、手袋・マスク・フェイスシールド等を準備。手指衛生と廃棄手順を徹底。
- 事前観察:安静呼吸を 30 秒ほど観察し、咳・呼吸困難・喘鳴、声質(湿性嗄声の有無)を把握。
手順:刺激と咳反応の観察( 4 ステップ )
- 説明と同意:目的・方法・想定される咳反応・中止基準を簡潔に説明し、同意を得る。
- 刺激の実施:施設標準の方法で、決められた濃度・時間・回数で刺激する(鼻閉の有無も運用に合わせる)。
- 観察・計測:30 秒法なら「咳が出るまでの秒数」、 1 分法なら「 1 分間の咳回数」を軸に、咳の強さ・連発性・遅延、声質、 SpO₂ 変化を同時に記録する。
- 回復確認:咳が落ち着いた後、呼吸状態・ SpO₂ ・自覚症状(息苦しさ・めまい等)がベースラインに戻るか確認する。
チーム内では「何を数えるか(秒数/回数)」と「中止基準」だけでも先に統一しておくと、評価と申し送りが揃いやすくなります。
観察ポイント:不顕性誤嚥を疑うサイン
- 遅延咳/弱い咳:刺激後に時間がたってからの咳、単発で弱い咳のみ、咳が出ない。
- 咳の質:連発が続かない、喀出力が乏しい、呼吸苦が強く「咳で疲れる」。
- 咳後の声質:湿性嗄声(ゴロゴロした声)、話しにくさの訴え。
- バイタル変化:SpO₂ の低下が持続、呼吸数増加、顕著な呼吸苦・胸痛、顔面蒼白・発汗。
- 全身状態:強い倦怠感・めまい・嘔気、意識状態の変化、本人の中止希望。
よくある失敗(詰まりどころ)と対策
※表は横スクロールで確認できます(スマートフォンなどの狭い画面では左右にスワイプしてください)。
| よくある失敗 | 起きること | 対策(チームで統一) |
|---|---|---|
| ベースラインを取らず開始 | もともとの湿性嗄声や咳が評価に混ざり、解釈がブレる | 開始前に「声質・咳・呼吸」を 30 秒観察し、ベースライン欄に必ず記録 |
| 何を判定指標にするか曖昧 | 秒数で書く人/回数で書く人が混在し、申し送りが噛み合わない | 院内で「 30 秒法=潜時」「 1 分法=回数」を固定し、記録シートも統一 |
| 観察が「咳の有無」だけ | 遅延・弱い咳、咳後の湿性嗄声を取りこぼす | 咳の タイミング/強さ/連発性/声質/ SpO₂ の 5 点を必須項目にする |
| 中止基準が共有されていない | SpO₂ 低下や呼吸苦が出ても続行してしまう | 配布物の「中止基準」をカンファで先に共有し、実施者が迷わない運用にする |
| 結果だけで介入が決まらない | 「陽性っぽい」で止まり、次アクションが曖昧 | 陽性/境界は「主治医報告→精査( VE/VFSS )検討→暫定対応(姿勢・食形態・口腔ケア)」までセットで申し送る |
中止基準と禁忌
咳テストは比較的簡便な検査ですが、呼吸・循環への負荷が増すため 禁忌や慎重適応 を明確にし、観察中に中止基準を超えた場合は速やかに終了する必要があります。以下はあくまで一例であり、最終判断は主治医と施設プロトコルに従ってください。
※表は横スクロールで確認できます(スマートフォンなどの狭い画面では左右にスワイプしてください)。
| 区分 | 具体例 | 対応 |
|---|---|---|
| 禁忌 | 重度の低酸素血症(例:安静時 SpO₂ ≦ 90%)、コントロール不良の不整脈、急性冠症候群直後、意識障害や協力不能で指示理解が困難な状態 など | 咳テストは実施せず、主治医と相談し、画像検査・血液ガスなど他の評価方法を優先する。 |
| 慎重適応 | 重度 COPD・高度肺高血圧・重症心不全、安静臥床が必要な急性期、強い不安や拒否がある場合 など | 主治医と事前に適応を検討し、必要最小限の刺激・十分なモニタリング・中止基準の事前共有のもとで慎重に実施する。 |
| 実施中止基準 | SpO₂ が 3–4%以上低下し回復しない、強い呼吸苦・胸痛、顕著なめまい・嘔気・顔面蒼白、意識状態の変化、患者本人からの中止希望 など | 直ちに検査を中止し、安静確保・姿勢調整・酸素投与などを検討。必要に応じて主治医に報告し、以後の評価・治療方針を再検討する。 |
※具体的な数値基準や適応可否は、医師の指示および施設内マニュアルに従ってください。
結果の見方と次アクション
- 陽性/境界:明らかな咳反射低下(咳が出ない/遅延・弱い咳のみ/回数が少ない)があれば、不顕性誤嚥リスクが高いと判断し、主治医へ情報共有のうえ VE/VFSS など精査を検討します。同時に、姿勢(頚部前屈・側臥位など)や食形態の暫定調整、口腔ケア強化、必要に応じて嚥下訓練の優先度を上げます。
- 陰性でも臨床的に疑わしい場合:陰性でも、湿性嗄声・反復肺炎・サチュレーション低下・食後の湿性痰などがあれば、 RSST・改訂水飲みテスト・フードテスト等を併用し、総合的に評価します(「陰性=安全」ではなく、所見とセットで判断)。
- 再評価のタイミング:急性期や介入開始直後は 1–2 週間を目安に再評価し、状態が安定している場合でも、食形態変更や全身状態の変化に応じてフォローします。
不顕性誤嚥リスクは、咳テスト単独ではなく「観察所見+他のスクリーニング+必要時の精査」で確度を上げる運用が安全です。チーム内では「結果(秒数/回数)」「咳の質」「声質」「 SpO₂ 」「次アクション」を 1 枚(記録シート)で揃えると、申し送りが崩れにくくなります。
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
刺激濃度・回数はどう決めればよいですか?
基本は 施設の標準手順+主治医の指示 に従います。代表例として、 1% クエン酸生理食塩水を用いた「 1 分法(回数で判定)」や「 30 秒法(潜時で判定)」が報告されていますが、薬液調製・機器・鼻閉の方法・観察時間は施設差が出ます。本記事では「観察ポイント」と「記録の型」を揃え、院内で運用しやすくすることを目的に整理しています。
咳テストが陰性なら、不顕性誤嚥の心配はありませんか?
いいえ、陰性でも不顕性誤嚥を完全に否定できるわけではありません。湿性嗄声や微熱、反復する肺炎歴、食後の湿性痰、サチュレーション低下など臨床所見で疑いが残る場合は、 VE/VFSS や他のスクリーニング( RSST・改訂水飲みテスト など)を組み合わせて評価します。
高齢で咳が弱い患者さんは、どのように評価すればよいですか?
高齢者では筋力低下や呼吸機能低下により、そもそも強い咳が難しいことがあります。「咳が出た/出ない」だけでなく、咳の立ち上がり(遅延)、連発の有無、咳後の声質や SpO₂ の変化、日常生活でのむせ・肺炎歴なども含めて総合的に判断することが重要です。必要に応じて主治医・ ST と相談し、精査( VE/VFSS )や介入方針まで含めて組み立てます。
おわりに
実地では「安全確認 → 咳テストなどのベッドサイドスクリーニング → VE/VFSS 等の精査 → 姿勢・食形態・口腔ケアの調整 → 再評価」というリズムをチームで共有しておくことが、不顕性誤嚥による肺炎を減らすうえで重要です。咳テストの限界と強みを理解し、多職種で同じ観察ポイント・中止基準・記録の型を使うことで、情報伝達の精度も高まります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集中の段階でも使える 面談準備チェック( A4・5分)と 職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えるので、教育体制や嚥下チームの有無などを整理したいときに活用してみてください。ダウンロードはこちら。
参考文献
- Wakasugi Y, Tohara H, Nakane A, et al. Usefulness of a handheld nebulizer in cough test to screen for silent aspiration. Odontology. 2014;102(1):76–80. doi:10.1007/s10266-012-0085-y. PubMed
- Sato M, Tohara H, Iida T, Wada S, Inoue M, Ueda K. Simplified cough test for screening silent aspiration. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(11):1982–1986. PubMed
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会. 摂食嚥下障害の評価 2019(資料). 日本摂食嚥下リハビリテーション学会; 2019. PDF
- Guillén-Solà A, Messagi Sartor M, Bofill Soler N, et al. Usefulness of citric cough test for screening of silent aspiration in subacute stroke patients. Arch Phys Med Rehabil. 2015. PubMed
- Sun WJ, et al. Diagnostic accuracy of screening tools for silent aspiration in dysphagia: a systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 2025. doi:10.3389/fneur.2025.1576869. PubMed
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下