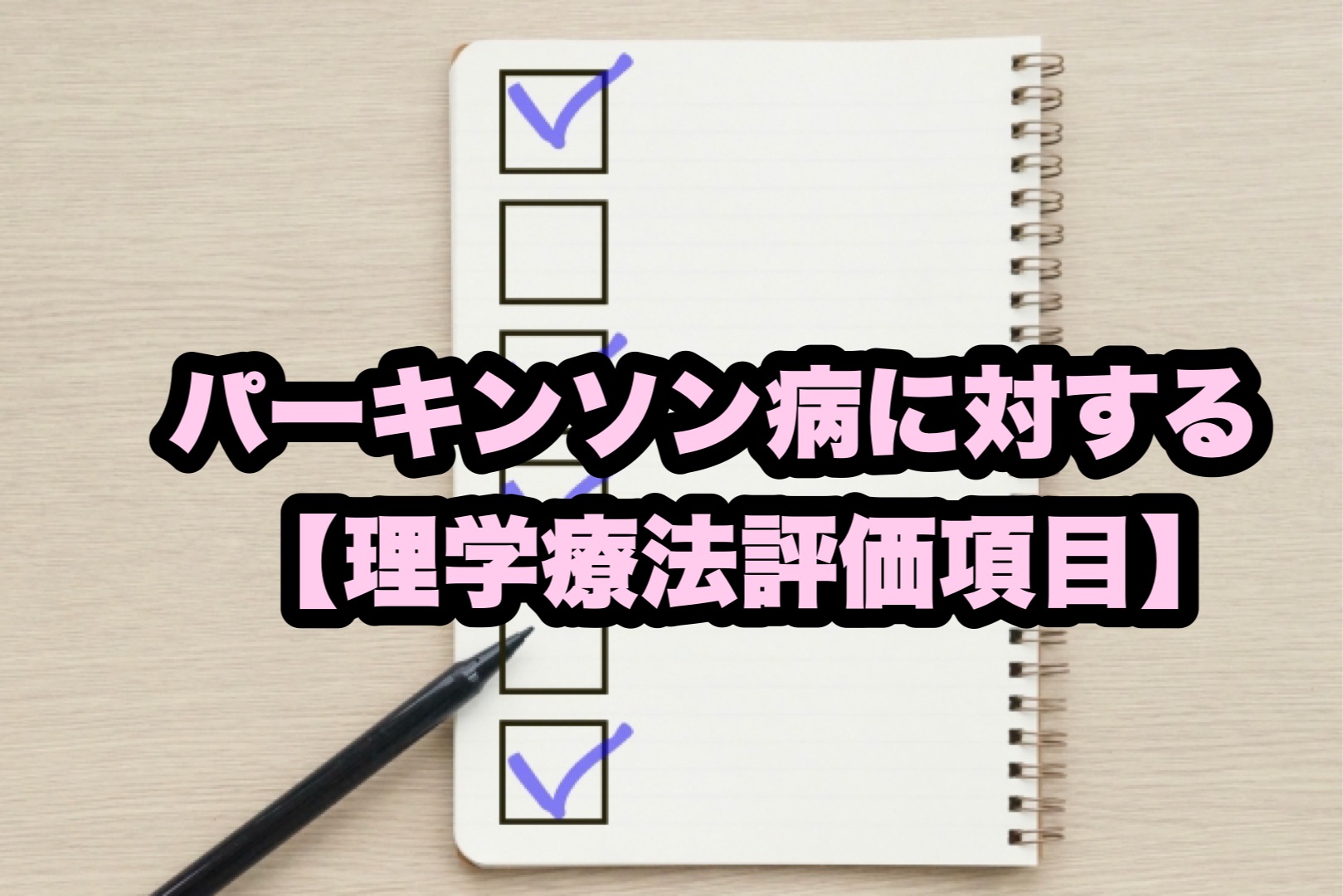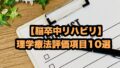パーキンソン病の理学療法評価:評価項目一覧と選び方(オン/オフ・HY・MDS-UPDRS)
本ページは「パーキンソン病 理学療法 評価項目」を最短導線で整理するために、評価項目の一覧と選び方、オン / オフ(薬効)別の評価タイミング、Hoehn & Yahr(HY)病期別の優先順位、MDS-UPDRS の位置づけを実務目線でまとめました。まずはチェックリストで “いま必要なカテゴリ” を絞り、同一条件で再評価を固定して経時比較につなげてください(外部リンクは新規タブ)。
評価の “順番” を固定すると、記録とチーム共有が一気に整います。 理学療法士の転職ガイド(準備〜流れ)を見る
評価項目一覧(チェックリストと使い分け)
最初に主訴/HY/オン・オフ状態/安全性でスクリーニングし、必要に応じて精査へ進みます。目的は “網羅” ではなく、疑い・変化の“兆し”を拾って再評価に耐える指標セットを決めることです。
| カテゴリ | 目的 | 代表評価 | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| 総合重症度(基軸) | 全体像の共有/経時追跡 | HY、MDS-UPDRS II / III | 内服時刻・オン / オフ・補助具・靴を固定 |
| 歩行・バランス | 転倒リスク/介入効果 | TUG、FBS(BBS)、FRT、Mini-BESTest | ピーク時間帯を避け、同一環境で再評価 |
| 凍結歩行(FOG) | 誘発条件の特定/対策 | FOG-Q / NFOG-Q(名称で運用) | 狭所・回転・二重課題の “出やすさ” を併記 |
| ADL / IADL | 介護量/生活再建 | FIM、Barthel Index、Lawton IADL | 「している」か「できる」かを混ぜない |
| 嚥下 | 誤嚥リスク/栄養 | EAT-10、RSST、MWST(必要時 VE / VF) | むせ・湿性嗄声・食事場面をセットで記録 |
| 非運動症状 | QOL/安全管理 | 起立性低血圧、睡眠・気分・便秘、疼痛 | 悪化の時間帯(オン / オフ)と誘因を聴取 |
| 認知 | 運動学習/安全配慮 | MMSE、HDS-R ほか | 注意・遂行機能(手順保持)を行動で観察 |
※ スマホでは横スクロールできます。
現場の詰まりどころ(よくある失敗と立て直し)
| 詰まりどころ | NG(やりがち) | OK(立て直し) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| オンで数値が安定しない | ピークで測ってジスキネジアに巻き込まれる | オンの “安定帯” で測定、必要ならオン / オフを分けて併記 | 内服時刻、測定時刻、オン / オフ自己申告 |
| オフ測定が怖い | 単独で実施、環境が普段どおり | 監視者追加、歩行路の整理、安全ベルト、最小課題に絞る | 介助者の有無、見守りレベル、転倒リスク要因 |
| FOG が再現できない | 直線歩行だけで “出なかった” で終える | 狭所・回転・二重課題を段階的に、危険なら中止 | 誘発条件(場所 / 課題)、出現頻度、対処法の反応 |
| HY だけで判断する | 病期は書いたが、介入の指標が固定されていない | HY+最小セット(例:TUG+ADL)で “再評価の軸” を決める | 最小セット名、次回も同条件で測る宣言 |
| 非運動を見落とす | 運動だけで終了、離床の安全域が曖昧 | 起立性低血圧・睡眠・疼痛を “最低限” で拾い上げる | 血圧変化、めまい、転倒の時間帯、疼痛部位 |
※ スマホでは横スクロールできます。
オン / オフを踏まえた評価タイミング
同一患者でも内服オン / オフで所見は変動します。目的に応じて評価タイミングを固定し、経時比較の再現性を担保します(例:初回はオンとオフを別日に測定)。
| 目的 | 推奨タイミング | 代表評価 | 安全・備考 |
|---|---|---|---|
| 日常機能の代表値 | 内服オンの至適時間帯 | TUG/FBS/FRT/FIM | ピーク回避(過可動・ジスキネジア) |
| 変動の把握 | オフとオンの両条件 | MDS-UPDRS Part III/歩行速度 | オフ時は転倒・起立性低血圧に注意 |
| 転倒・凍結対策 | 患者が “悪い” と感じる時間帯 | Mini-BESTest/FOG-Q(名称で運用) | 監視者追加・環境整備を徹底 |
※ スマホでは横スクロールできます。
病期別(HY)での優先評価
HY は「病期の共有言語」です。病期 × 目的で指標の優先度を切り替え、フォロー間隔と再評価指標を固定化します。
| HY | 歩行・バランス | ADL / IADL | 嚥下 | 非運動 |
|---|---|---|---|---|
| I | 歩行速度/FRT | BI(更衣・移動) | スクリーニング(EAT-10) | 非運動の初期拾い上げ |
| II | TUG/FBS | FIM(移乗・トイレ) | RSST/MWST | 起立性低血圧チェック |
| III | Mini-BESTest/転倒歴 | FIM 全体/Lawton | VE / VF 連携を検討 | 睡眠・気分・便秘の介入 |
| IV–V | 介助下の座位・立位保持 | 介護量評価/ポジショニング | 嚥下安全性・栄養管理 | 疼痛・せん妄・自律神経 |
※ 施設基準・多職種体制に合わせて調整してください。
MDS-UPDRS の使いどころ(運用)
MDS-UPDRS は総合評価の基軸です。スコア表の全文転載は行わず、公式配布ページを参照のうえ、施設内で入手・運用してください。理学療法では Part II / III を中心に、変動(オン / オフ)や転倒歴と併記して経時追跡すると意思決定に強い軸になります。
非運動症状と起立性低血圧
PD では非運動症状が QOL を規定します。睡眠(RBD 等)・気分・便秘・頻尿・嗅覚低下・疼痛を系統的に聴取し、起立性低血圧は段階離床/弾性ストッキング・腹帯/水分・塩分調整/内服調整の連携まで含めてプロトコル化すると安全です。
凍結歩行(FOG)の評価
すくみ足・突進現象の自覚がある場合は FOG-Q / NFOG-Q(名称で運用)を導入します。歩行課題では狭所・方向転換・二重課題で誘発しやすく、環境調整(床目印・メトロノーム等)と身体戦略(大きい一歩・体幹伸展)の併用を介入へつなげます。
よくある質問(PD 評価編)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
初回は何から測れば良いですか?
安全確保 → HY と MDS-UPDRS(Part II / III)で全体像 → 歩行・バランス(TUG / FBS) → ADL(FIM / BI) → 必要時に嚥下(RSST / MWST)・非運動、の順が実務的です。以降は目的に応じた最小セットを同条件で再評価に固定します。
オン / オフはどちらで評価するべき?
「日常の代表値」はオン、「変動の把握」はオン+オフです。オフ測定時は転倒・低血圧に注意し、介助者・環境を整えます。
病期が進んだら何を優先しますか?
HY III 以降は転倒予防と介護量の把握に軸足を移し、Mini-BESTest/FIM/嚥下安全性の比重を上げます。ポジショニングや栄養・排泄など多職種連携が鍵です。
おわりに
実地では「安全の確保 → オン / オフ確認 → スクリーニング → 目的別の再評価固定」というリズムが肝心です。病期・非運動症状・嚥下を含めて指標を束ねると、介入設計とチーム共有が一段と精密になります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック(A4・5 分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。配布物のダウンロードはこちら
参考文献
- Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR, et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results. Mov Disord. 2008;23(15):2129-2170. doi: 10.1002/mds.22340 / PubMed
- Osborne JA, Botkin R, Colon-Semenza C, et al. Physical Therapist Management of Parkinson Disease: A Clinical Practice Guideline From the American Physical Therapy Association. Phys Ther. 2022;102(4):pzab302. doi: 10.1093/ptj/pzab302 / PubMed
- 日本神経学会監修 「パーキンソン病診療ガイドライン」作成委員会 編. パーキンソン病診療ガイドライン 2018. 医学書院; 2018. ISBN: 978-4-260-03596-5. 公開ページ
- 中西 亮二ほか. パーキンソン病の障害評価とリハビリテーション. Jpn J Rehabil Med. 2013;50:658-670. 本文
- 中馬 孝容. パーキンソン病に対するリハビリテーション. Jpn J Rehabil Med. 2016;53:524-528. 本文
- MDS-UPDRS 日本語版(最終版 PDF). International Parkinson and Movement Disorder Society. PDF
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下